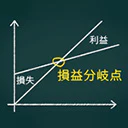経費を効率的に削減するには?経費削減の効果や方法、注意点を解説
更新

経営改善や利益率向上を図るための手段としてよくあげられるのが、経費削減です。例えば、同じ売上でも、不要な経費を削減できれば利益は多くなります。反対に、いくら売上が増えても、それより多くの経費がかかっていては、利益はマイナスとなり赤字です。そのため、経営課題として、経費削減に取り組みたいと考えている企業は少なくありません。
とはいえ、事業を行ううえで、経費は必要不可欠なものです。利益率を上げたいからといって、ただ闇雲に経費を削減すればいいというわけではありません。では、経費を効率的に削減するには、どのようなことに気を付ければいいのでしょうか。
ここでは、経費削減の目的や効果、実践しやすい経費削減の方法、経費削減を行う際の注意点などについて解説します。
今なら「弥生会計 Next」スタート応援キャンペーン実施中!

会計・経費・請求、誰でもカンタンまとめて効率化!法人向けクラウド会計ソフト「弥生会計 Next」
経費削減を行う目的
企業が経費削減に取り組む目的は、利益を増加させるためです。利益とは売上高から経費などを引いた、いわゆる儲けです。
そもそも経費とは、事業者が事業を営むために支出したお金のことを指します。経費を削減し、売上に対する経費の割合を少なくするほど、結果的に利益率が高くなるということになります。しかし、売上を上げるために必要な経費まで削ってしまうと、かえって企業の成長をストップさせることにもなりかねません。設備投資のように、将来の事業拡大を見越してかける経費もあるでしょう。経費削減を行ううえでは、自社にとって必要なコストと無駄な支出を、しっかりと見極めることが大切です。
なお、経費と混同されやすいものに、費用があります。費用とは、事業を営むうえで発生するお金のことで、経費とほぼ同義です。ただし、費用は企業の経営活動におけるすべての支出であるのに対して、経費は主に売上につながるような販売目的の支出や管理目的の支出を指します。
経費削減は広義では企業のコストを抑えるということを指すため、経費と費用を厳密に区別する必要はないかもしれませんが、会計上の考え方においては、費用の中に経費が含まれます。
経費の計上については、以下の記事で詳しく解説していますので参考にしてください。
会計・経費・請求、誰でもカンタンまとめて効率化!法人向けクラウド会計ソフト「弥生会計 Next」
経費は固定費と変動費の2つに分けられる
企業の経費は、「固定費」と「変動費」の2つに分けられます。効果的な経費削減を目指すためには、固定費と変動費をきちんと区別して扱うことが大切です。
ここでは、固定費と変動費について、それぞれ詳しく説明します。
固定費とは、売上に関係なく、常に一定の期間で発生する費用
固定費とは、売上高や販売数量にかかわらず、常に一定の期間で発生する経費のことです。例えば、正社員の給与や賞与、福利厚生費、設備の減価償却費、オフィスや店舗の家賃、光熱費などが固定費に該当します。これらの費用は、売上や販売数量の大小にかかわらず支払う額がほぼ固定なので、固定費と呼ばれます。
経費を削減しようとしたとき、まず固定費を減らそうと考える企業は多いかもしれません。しかし実は、固定費はなかなか減らしにくいものです。たとえ売上が落ちても、正社員の給与やオフィスの家賃などの支払いは変わらず発生します。そのため、「そもそも固定費を増やしすぎない」「固定費を増やす場合は、売上や粗利とのバランスを考えて慎重に判断する」ということが大切です。
変動費とは、売上や生産量、販売数に比例して増減する経費
変動費とは、売上や生産量、販売数に比例して増減する経費のことです。変動費に該当するのは、原材料費や仕入原価、販売手数料、外注費、支払運賃、パート・アルバイトの給与などです。
これらの費用が変動費に区分されるのは、売上高や販売数量などの条件によって金額が変動するからです。例えば原材料費の場合、製品を100個生産する場合と1,000個生産する場合を比べると、単純計算で、後者は前者の10倍の金額がかかることになります。また、販売量が増える繁忙期のみ派遣社員を雇う場合などは、派遣会社への支払いが「販売量の増加に合わせて増えた経費」と見なされ、変動費になります。
固定費と変動費については、以下の記事で詳しく解説していますので参考にしてください。
会計・経費・請求、誰でもカンタンまとめて効率化!法人向けクラウド会計ソフト「弥生会計 Next」
経費削減で期待できる効果
経費を削減すると、企業の利益向上に役立ちます。さらに、経費削減の効果はそれだけではありません。
経費削減によって、利益向上に加えて、下記のような効果が期待できます。
従業員の生産性が上がる
業務プロセスを見直して効率化し、従業員の生産性を上げることも、人的コストを減らす経費削減の1つです。
例えば、既存の業務フローから不要な作業をカットしたり、それまで人の手で行っていたことをシステムで自動化したりすることも、経費削減につながるでしょう。このような取り組みによって業務がスムーズに進むようになれば、業務効率化や生産性向上といった効果が期待できます。
さらに、業務の無駄をなくすことで働きやすい職場環境が整備され、結果的に従業員のモチベーションアップにもつながるはずです。
企業価値が上がる
経費削減によって生まれた資金を、新規事業などに投資することで、企業価値の向上につなげられる可能性があります。
新規事業の立ち上げ以外にも、商品や製品の改良、社内の人材育成などに資金を投入するのもいいでしょう。削減した経費を事業や人材の成長のために活用し、より大きな利益を生み出せば、企業価値を向上させる好循環を目指すことができます。
顧客満足度が上がる
経費削減は、顧客満足度の向上にも効果が期待できます。例えば、削減した経費を、顧客ニーズに応じた商品開発やサービス改善に役立てる方法もあるでしょう。経費削減によって資金的な余裕が生まれれば、それを商品や製品の価格に反映することも可能かもしれません。継続的な経費削減を意識することによって、顧客満足度の向上や顧客層の拡大につながる可能性があります。
会計・経費・請求、誰でもカンタンまとめて効率化!法人向けクラウド会計ソフト「弥生会計 Next」
今すぐに実践できる経費削減の方法は?
経費を削減するには、さまざまな方法があります。ここからは、その中でも、中小企業がすぐに取り組みやすい経費削減の具体的な方法を紹介します。
働き方を見直す
従業員の働き方を見直すことで、経費削減につながる場合があります。近年では、働き方の多様化が進み、ワークライフバランスが重視されるようにもなっています。
例えば、働き方改革を進めることによって残業が減れば、残業代やオフィスの光熱費の削減が可能です。部署や業務内容によっては、在宅勤務を取り入れることも可能でしょう。従業員の働き方を見直すことで、経費削減だけではなく、従業員満足度を向上させる効果も期待できます。
業務をペーパーレス化する
業務のペーパーレス化は、経費削減の第一歩ともいえます。紙の書類をできるだけ電子化すれば、用紙代、印刷のためのインク代、郵送費、書類を保管するためのコストなど、さまざまな経費の削減が可能です。さらに、電子化された情報は、紙の書類に比べて共有や検索がスムーズになるため、業務効率化にも役立ちます。
オフィスを見直す
働き方改革やペーパーレス化に伴い、オフィス環境を見直すのも経費削減に効果的です。例えば、テレワークの従業員が増えると、広いオフィスは不要になるかもしれません。また、業務のペーパーレス化が進むことによって、紙の書類を保管するためのスペースが不要になります。状況に合わせてオフィスの縮小や移転ができれば、賃料や光熱費の削減につながります。
人件費を見直す
経費削減の方法の1つとして、人件費の見直しもあげられます。人件費は、企業の経費の中でも大きな割合を占めます。新たに従業員を雇用しようと考えている場合は、「本当に人員が必要か」「システムの導入などで対応できないか」などをよく検討しましょう。
特に、正社員を雇用すると、給与や賞与はもちろん、福利厚生費や社会保険料の負担なども発生します。場合によっては、繁忙期だけ短期アルバイトを雇ったり、自社で対応できない業務のみ外注したりするなどの方法をとってもいいかもしれません。
通勤手当の見直し
通勤手当を見直すことで、経費削減につながる場合があります。従業員の通勤手当は、本人の申告に従って支給されることが一般的です。従業員から通勤ルートの申告を受けた際には、そのルートが最適かどうかしっかり確認しましょう。
公共交通機関による通勤費を非課税の通勤手当とするためには、支給する金額が、合理的な運賃等に該当しなければなりません。合理的な運賃とは、最も通勤時間が早い経路や、最も金額が安い経路、最も乗り換えが少ない経路による運賃のことです。ただし、金額の安いルートにすると大幅に通勤時間が増えてしまうような場合は、従業員の負担につながるため、柔軟な対応が求められます。
また、テレワークの導入などにより出社回数が少なくなった従業員に対しては、定期券相当額を通勤手当として支給するのは合理的ではありません。その場合、出社日数に応じて、個別に通勤手当を計算する方がいいでしょう。なお、通勤手当については、トラブル防止のためにも、就業規則や賃金規程で支給ルールを明確に定めておくことが大切です。
通信費・光熱費の節約
オフィスや店舗で契約している電話や通信回線を見直し、もし使っていない回線があったら解約やグレードダウンを検討しましょう。
例えば、従業員のテレワーク化が進んだ場合、不要になった電話回線を解約すると経費削減につながります。また、照明をLEDに変更したり、空調の温度設定を見直したりすることも、経費節減に効果的です。より支出を抑えられるように、電力会社や通信会社の変更を検討するのもおすすめです。
事務経費・消耗品代の節約
事務用品をはじめとする消耗品代も、見直しを行うことで、大きな経費削減につながる可能性があります。
ペーパーレス化で用紙代やインク代を削減するだけではなく、文房具や梱包資材などの消耗品についても、無駄のないように管理しましょう。ストックが多すぎると使い切る前に劣化してしまうこともあるため、必要な分だけを購入することが大切です。
会計ソフトを導入する
表計算ソフトや手書きで帳簿付けを行っている場合は、会計ソフトの導入も経費削減に役立ちます。会計ソフトの導入によって日々の仕訳を自動化できれば、業務負担の大幅な軽減につながります。紙の帳簿類を用意したり、保管したりするコストもかかりません。日々の記帳はもちろん、決算にかかわる作業もスムーズになり、業務効率化につながります。
会計ソフトについては、以下の記事で詳しく解説していますので参考にしてください。
会計・経費・請求、誰でもカンタンまとめて効率化!法人向けクラウド会計ソフト「弥生会計 Next」
経費を削減しすぎるとどうなる?経費削減のデメリットは?
経費削減は企業にとって重要な課題ですが、闇雲に経費を削減すると、かえって逆効果になってしまうことがあります。
行きすぎた経費削減は、下記のようなデメリットを招く可能性があるため、注意が必要です。
従業員のモチベーションが低下したり、離職率が上がったりするリスクがある
従業員の不利益に直結する経費削減を行うと、企業への不満や不信感が増し、モチベーション低下につながる恐れがあります。従業員の不利益になる経費削減の例としては、給与や賞与のカット、リストラ、手当の廃止、福利厚生の縮小などがあげられます。
従業員のモチベーションは、労働生産性と比例する場合が少なくありません。例えば、給与カットやリストラによって一時的に経費を削減できたとしても、職場全体のモチベーションが下がって生産性が低下すれば、将来的な業績悪化を招きかねません。さらに、企業への不信感から退職者が増えるなど、離職率が上がってしまうリスクもあります。
顧客が離れてしまう可能性がある
経費削減によって商品やサービスの質を低下させてしまうと、顧客離れを引き起こす要因になります。特に飲食店や製造業などの場合、原材料費の極端な削減は品質低下を招く可能性があります。また、それまで実施してきた顧客サービスの終了なども、顧客満足度の低下につながってしまうでしょう。顧客の減少は売上に直結するのはもちろん、企業やブランドのイメージにも悪影響を与えかねません。
機会損失のリスクがある
経費を削減して業務に影響するシステムやツールのグレードを下げた場合、社内における情報共有や意思決定のプロセスに遅延が生じてしまう恐れがあります。一時的なコストダウンを優先して情報共有や意思決定プロセスが遅れた結果、せっかくのビジネスチャンスを逃してしまう可能性があるため、注意しましょう。
会計・経費・請求、誰でもカンタンまとめて効率化!法人向けクラウド会計ソフト「弥生会計 Next」
会計ソフトなら日々の帳簿付けや決算書作成もかんたん
「弥生会計 Next」は、使いやすさを追求した中小企業向けクラウド会計ソフトです。帳簿・決算書の作成、請求書発行や経費精算もこれひとつで効率化できます。
画面を見れば操作方法がすぐにわかるので、経理初心者でも安心してすぐに使い始められます。
だれでもかんたんに経理業務がはじめられる!
「弥生会計 Next」では、利用開始の初期設定などは、対話的に質問に答えるだけで、会計知識がない方でも自分に合った設定を行うことができます。
取引入力も連携した銀行口座などから明細を取得して仕訳を登録できますので、入力の手間を大幅に削減できます。勘定科目はAIが自動で推測して設定するため、会計業務に慣れていない方でも仕訳を登録できます。
仕訳を登録するたびにAIが学習するので、徐々に仕訳の精度が向上します。

会計業務はもちろん、請求書発行、経費精算、証憑管理業務もできる!
「弥生会計 Next」では、請求書作成ソフト・経費精算ソフト・証憑管理ソフトがセットで利用できます。自動的にデータが連携されるため、バックオフィス業務を幅広く効率化できます。

自動集計されるレポートで経営状態をリアルタイムに把握!
例えば、見たい数字をすぐに見られる残高試算表では、自社の財務状況を確認できます。集計期間や金額の累計・推移の切りかえもかんたんです。
会社全体だけでなく、部門別会計もできるので、経営の意思決定に役立ちます。

「弥生会計 Next」で、会計業務を「できるだけやりたくないもの」から「事業を成長させるうえで欠かせないもの」へ。まずは、「弥生会計 Next」をぜひお試しください。
会計・経費・請求、誰でもカンタンまとめて効率化!法人向けクラウド会計ソフト「弥生会計 Next」
不要な経費を削減して企業の成長につなげよう
経費削減は、企業の利益向上のための重要な課題です。ただし、行きすぎた経費削減は、従業員のモチベーションや企業の信用力を低下させる恐れがあります。まずは現在の業務の進め方を見直し、無駄な経費が発生していないか、改善できる部分はないかを検討することが大切です。
効果的な経費削減のためにおすすめなのが、会計ソフトの導入です。会計ソフトを活用することによって業務効率が上がると、残業も減り、結果的に人件費や光熱費などの削減につながります。さらに、会計ソフトを使って、経費の内訳などを詳しく分析することも可能です。
会計業務にかかる手間と時間が大幅に軽減されれば、従業員にとって働きやすい環境をつくることにもつながります。会計ソフトなどの便利なツールを上手に利用して、無理なく効果的な経費削減に努めましょう。
会計・経費・請求、誰でもカンタンまとめて効率化!法人向けクラウド会計ソフト「弥生会計 Next」
【無料】お役立ち資料ダウンロード
「弥生会計 Next」がよくわかる資料
「弥生会計 Next」のメリットや機能、サポート内容やプラン等を解説!導入を検討している方におすすめ

この記事の監修者渋田貴正(税理士、司法書士、行政書士、社会保険労務士)
税理士、司法書士、社会保険労務士、行政書士、起業コンサルタント®。
1984年富山県生まれ。東京大学経済学部卒。
大学卒業後、大手食品メーカーや外資系専門商社にて財務・経理担当として勤務。
在職中に税理士、司法書士、社会保険労務士の資格を取得。2012年独立し、司法書士事務所開設。
2013年にV-Spiritsグループに合流し税理士登録。現在は、税理士・司法書士・社会保険労務士として、税務・人事労務全般の業務を行う。