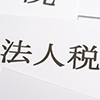固定資産税とは?納付先や計算方法、特例措置などを解説
更新
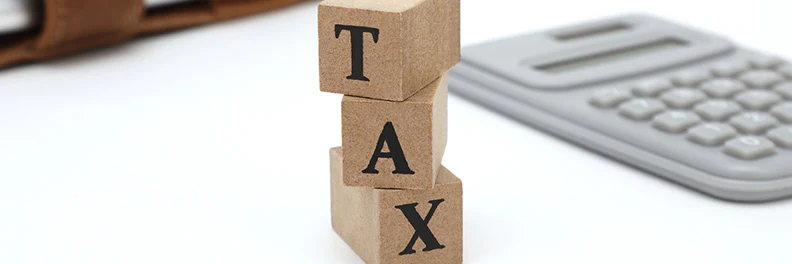
土地や建物などにかかる固定資産税は、経費として認められる税金です。そのため、法人の経営者や個人事業主は、その仕訳方法や各種軽減措置について正しく理解し、会計業務にも役立てていく必要があるでしょう。
本記事では、固定資産税の納付方法や計算方法、仕訳方法、特例措置などについて解説します。
今なら「弥生会計 Next」スタート応援キャンペーン実施中!

会計・経費・請求、誰でもカンタンまとめて効率化!法人向けクラウド会計ソフト「弥生会計 Next」
固定資産税とは、固定資産に対して課せられる税金のこと
固定資産税とは地方税の一種で、個人や法人が所有する固定資産に対して課せられる税金です。土地や家屋などのほとんどすべての不動産が、税金を課せられる固定資産に該当します。その他にも、事業用として使われる機械や機器類なども固定資産税の対象という扱いになります。(自動車税の対象になる車両など一定の固定資産を除く。)
また、固定資産の1つである償却資産とは、土地や家屋以外の事業用に使う資産のことです。長期間にわたって使用される償却資産の取得にかかった支出を、その資産を使用できる期間にわたり配分することを、減価償却と呼びます。
償却資産のほかにも、さまざまな固定資産があります。固定資産の種類と具体例は、それぞれ下記のとおりです。
| 固定資産の種類 | 具体例 |
|---|---|
| 土地 | 田んぼ、畑、住宅地、池沼、山林、鉱泉地(温泉など)、牧場、原野などの土地 |
| 家屋 | 住宅、お店、工場(発電所や変電所を含む)、倉庫などの建物 |
| 償却資産 | 会社等(事業者)が所有する構築物(広告塔やフェンスなど)、運搬具、備品(パソコンや工具など)など |
- ※総務省「固定資産税」
会計・経費・請求、誰でもカンタンまとめて効率化!法人向けクラウド会計ソフト「弥生会計 Next」
固定資産税の納付先
固定資産税の納付先は、固定資産のある市町村となります。ただし、東京23区内については東京都が納付先となる点に注意が必要です。
固定資産税として納められた税金は、学校や公園、道路などの日常生活で利用する公共施設の整備や、介護や福祉などの行政サービスに使用されることとなります。
会計・経費・請求、誰でもカンタンまとめて効率化!法人向けクラウド会計ソフト「弥生会計 Next」
固定資産税の納付時期・納付方法
市町村によって納付時期は異なりますが、4月・7月・12月・翌年2月の年4回に分けて納付するのが一般的です。また、一括で納付することもできます。
具体的には、以下の納付方法があります。
固定資産税の主な納付方法
- スマートフォン決済
- クレジットカード
- 地方税の納税システム(eLTAX)を利用する
- 口座振替
- 金融機関、税事務所の窓口
- コンビニエンスストア
-
※東京都主税局「都税の支払い方法について
」
納付方法の選択肢は自治体によるため、希望する方法で納付できるかどうかは確認が必要となります。
会計・経費・請求、誰でもカンタンまとめて効率化!法人向けクラウド会計ソフト「弥生会計 Next」
固定資産税の計算方法
固定資産税は、どのように計算すればよいのでしょうか。ここでは、固定資産税の計算方法と評価方法について説明します。
固定資産税の計算式
固定資産税は、土地や家屋、償却資産などの固定資産の資産価値を示した評価額に応じて決まり、税額は評価額と標準税率を使って算出します。
固定資産税を求める計算式は、以下のとおりです。
固定資産税の計算式
固定資産税=固定資産の評価額×1.4%(固定資産税の標準税率)
標準税率は1.4%ですが、自治体によって異なる税率を適用する場合があるため、各自治体のウェブサイトや窓口で確認することをおすすめします。
また、固定資産の評価額は、納税通知書に添付されている課税明細書の価格欄に記載されています。家屋などの建物については、この評価額が課税標準額となることも押さえておきましょう。
固定資産税の評価方法
固定資産は、各自治体が固定資産一つひとつについて総務大臣の定めた基準の下、評価される資産です。また、土地や家屋などの固定資産は、そのときの市場価格により変動する場合があり、この評価方法のことを再建築価格方式といいます。
再建築価格方式の場合、固定資産の評価見直しは、3年間隔で行われます。なお、償却資産については、毎年1月1日時点における評価内容を1月31日に申告することとなるため、償却資産評価は毎年変動します。
主な固定資産の種類とそれぞれの評価方法については、以下のとおりです。
| 固定資産の種類 | 評価方法 |
|---|---|
| 土地 | 宅地・畑・田など地目ごとに売買価格を基本に価格を評価される(宅地の場合は地価公示価格の7割を目処に評価される) |
| 家屋 | 再建築価格方式で評価される |
| 償却資産 | 償却資産の取得価格を基に経過年数を考慮して評価される |
固定資産税の評価額の確認方法
固定資産税の評価額は、以下のいずれかの方法で確認することができます。
固定資産税の評価額の確認方法
- 納税通知書に記載されている課税明細書から確認する
- 固定資産課税台帳を閲覧申請して確認する
- 固定資産評価証明書を入手して確認する
納税通知書は、原則、毎年4月から6月に郵送で届きます。なお、固定資産評価額は各市町村や都税事務所が決めますが、その計算方法は全国で統一されています。
家屋と売却資産の評価方法
家屋の評価には、再建築価格方式という方法が用いられます。これは、評価する家屋と同じものを再び建築したと仮定して、一般的に必要となる建築費に経過年数や損耗具合も加味して評価額を算出する方法です。
また、償却資産については、取得年月と取得価額、耐用年数に基づいて、毎年1月1日時点での評価額を算出することとなります。
会計・経費・請求、誰でもカンタンまとめて効率化!法人向けクラウド会計ソフト「弥生会計 Next」
固定資産税の仕訳例
事業用の土地や建物、自動車、器具備品などにかかる固定資産税は、経費計上することが認められています。ここでは、固定資産税の仕訳方法について、法人と個人事業主それぞれのケースに分けて見ていきましょう。
法人の場合の仕訳例
法人が固定資産税の仕訳を行う場合は、租税公課という勘定科目で処理するのが一般的です。ここでは、固定資産税を納期開始日や賦課決定日に経費処理する場合と、固定資産税を納付した際に経費処理する場合の2つのパターンに分けて仕訳例を見ていきましょう。
固定資産税を納期開始日や賦課決定日に経費処理する場合の仕訳
固定資産税を納期開始日や賦課決定日に経費処理する場合は、固定資産税の金額が確定した日に、未払金として貸方へ計上します。この時点では、未払いのお金(負債)が増加したという処理になります。
例えば、10万円の固定資産税を租税公課の勘定科目にした場合の仕訳例は、以下のとおりです。
| 借方 | 貸方 | ||
|---|---|---|---|
| 租税公課 | 100,000 | 未払金 | 100,000 |
また、実際に固定資産税を納付した日に未払金の消込処理を行った場合の仕訳例は、以下のとおりです。
| 借方 | 貸方 | ||
|---|---|---|---|
| 未払金 | 100,000 | 現金 | 100,000 |
固定資産税を納付した際に経費処理する場合の仕訳
固定資産税を実際に支払ったタイミングで仕訳処理する方法も見ていきましょう。この場合は、納期開始日や賦課期日における仕訳は行わず、納付した日にのみ対応して処理します。固定資産税は、原則として年4回に分けて納付していくため、金額を間違えないように注意して計上しなければなりません。
例えば、20万円の固定資産税の4分の1を現金で支払った日の仕訳例は、以下のとおりです。
| 借方 | 貸方 | ||
|---|---|---|---|
| 租税公課 | 50,000 | 現金 | 50,000 |
個人事業主の場合の仕訳例
個人事業主の場合、家賃や水道光熱費などのプライベートの費用と、事業で使用した費用との区別があいまいになってしまうことがあります。その際、納税すべき固定資産税を家事按分することが所得税法によって認められています。家事按分とは、プライベートと業務を兼ねた支出に関して、業務利用分を計算し、その分の費用を経費として計上することです。
ただし、個人事業主の場合、固定資産の用途が私用と業務用で混在しているケースがあります。兼用している場合は、業務用の費用のみが経費として認められるため、業務用に使用している割合を算出する必要があります。自宅の一部を業務用スペースとして使用している場合、その面積の割合を算出したうえで固定資産税を家事按分しなければなりません。個人事業主が経費を家事按分する場合、私用部分の費用は、事業主貸として処理します。
例えば、自宅の敷地全体の50%を業務用スペースとして使用している個人事業主が、10万円の固定資産税を納付したタイミングで計上する場合の仕訳例は、以下のとおりです。
| 借方 | 貸方 | ||
|---|---|---|---|
| 租税公課 | 50,000 | 現金 | 100,000 |
| 事業主貸 | 50,000 | ||
また、納付時に全額を租税公課で処理することによって、期末の決算整理で家事按分した場合の仕訳例は、以下のとおりです。
| 借方 | 貸方 | ||
|---|---|---|---|
| 事業主貸 | 50,000 | 租税公課 | 50,000 |
また、家事按分は、どのような条件でも適用できるわけではないため注意が必要です。白色申告の場合、原則として全体に対して業務用の割合が50%を超える場合にのみ、家事按分して費用として計上することができます。
ただし、事業用とプライベート用を明らかに区別できる場合についてのみ業務用割合が50%以下の場合でも必要経費に算入できます。それに対し、青色申告の場合は制限がありません。業務上かかった経費は、割合を問わず家事按分することができます。
このように、個人事業主が確定申告を行ううえでは、青色申告と白色申告のどちらで申告するのかによって家事按分で計上できる条件が異なるため、十分に注意しましょう。
会計・経費・請求、誰でもカンタンまとめて効率化!法人向けクラウド会計ソフト「弥生会計 Next」
固定資産税の特例措置
固定資産税は、固定資産の種類ごとにさまざまな特例措置が設けられています。そのため、所有している固定資産に適用できる特例がないか、あらかじめ確認しておくことが大切です。
ここでは、さまざまな固定資産税の特例措置について、それぞれ説明します。
新築住宅に係る税額の減額措置
新築住宅に係る税額の減額措置は、2024年3月31日までに新しく建てた住宅に適用される特例措置です。この特例措置が適用されることによって、新築住宅の居住部分の床面積120㎡までの税額が2分の1に減額されます。
特例期間については、一般住宅と長期優良住宅に分けて以下のように定められています。
| 住宅の種類 | 期間 | 減額の割合 | 対象床面積 |
|---|---|---|---|
| (1)一般の住宅 ※(2)以外 |
3年度分 | 2分の1 | 居住部分に係る床面積で、120㎡が限度(120㎡を超えるものは120㎡相当分まで) |
| (2)3階建て以上で耐火構造の住宅 | 5年度分 |
| 住宅の種類 | 期間 | 減額の割合 | 対象床面積 |
|---|---|---|---|
| (3)一般の長期優良住宅 ※(4)以外 |
5年度分 | 2分の1 | 居住部分に係る床面積で、120㎡が限度(120㎡を超えるものは120㎡相当分まで) |
| (4)3階建て以上で耐火構造の長期優良住宅 | 7年度分 |
-
※国土交通省「新築住宅に係る税額の減額措置
」
住宅用地特例
住宅用地特例は、住宅用地に対する固定資産税の課税標準額を減額する特例です。減額分の課税標準額は、住宅用地の価格に特例率を乗じることによって算出します。
| 区分 | 固定資産税の課税標準額 |
|---|---|
| 小規模住宅用地(住宅用地のうち200㎡以下の部分) | 住宅用地の価格の6分の1 |
| 一般住宅用地(住宅用地の200㎡を超える部分) | 住宅用地の価格の3分の1 |
-
※総務省「固定資産税制度について
」
住宅耐震改修特別控除
住宅耐震改修特別控除とは、家屋の耐震改修に伴う減税特例で1982年1月1日以前に建築された住宅を、現行の耐震基準(1981年6月1日以降の耐震基準)に適合する耐震改修を行った場合に、翌年度分の固定資産税が2分の1に減額される制度です。
この控除の適用を受けるための主な条件は、以下のとおりです。
住宅耐震改修特別控除を受けるための主な条件
- 昭和56年5月31日以前に建築された家屋であって、自己の居住の用に供する家屋であること
- ※耐震改修(地震に対する安全性の向上を目的とした増築、改築、修繕または模様替えのこと)をした家屋が、現行の耐震基準に適合するものであること
- 2つ以上の住宅を所有している場合には、主として居住の用に供すると認められる住宅であること
- ※申請により登録住宅性能評価機関、指定確認検査機関、建築士または住宅瑕疵担保責任保険法人から「増改築等工事証明書」(平成29年3月31日以前に控除の対象となる改修工事を行った場合は「住宅耐震改修証明書」)が発行される。なお、地方公共団体の長に申請を行った場合は、「住宅耐震改修証明書」が発行される。
-
※国税庁「No.1222 耐震改修工事をした場合(住宅耐震改修特別控除)
」
バリアフリー改修に関する特例措置
バリアフリー改修に関する特例措置とは、新築後10年以上を経過した住宅に対して、一定のバリアフリー改修工事を行った場合に、翌年度分の固定資産税から3分の1が減額される制度のことです。一定のバリアフリー改修工事とは規定の条件に該当する工事のことを指します。
この制度が適用されるための主な条件は、以下のとおりです。
バリアフリー改修に関する特例措置の適用を受けるための主な条件
- 自己が所有する家屋についてバリアフリー改修工事をして、平成26年4月1日から令和5年12月31日までの間に自己の居住の用に供していること
- バリアフリー改修工事の日から6か月以内に居住の用に供していること
- この特別控除を受ける年分の合計所得金額が、3,000万円以下であること
- 工事をした後の住宅の床面積が50平方メートル以上であり、かつ、床面積の2分の1以上を専ら自己の居住の用に供していること
- 2以上の住宅を所有している場合には、主として居住の用に供すると認められる住宅であること
- バリアフリー改修工事に係る標準的な費用の額(その工事等の費用に関し補助金等の交付を受ける場合はその額を控除した額)が50万円を超えるものであること
- 工事費用の2分の1以上の額が自己の居住用部分の工事費用であること
会計・経費・請求、誰でもカンタンまとめて効率化!法人向けクラウド会計ソフト「弥生会計 Next」
固定資産税の納付に関する注意点
固定資産税を納付するうえでは、どのようなことに注意すればよいのでしょうか。ここでは、固定資産税の納付に関する主な2つの注意点について、それぞれ解説します。
滞納した場合には延滞金が生じる
固定資産税は、未払いのまま納付期限を1日でも過ぎると延滞金が生じます。本来の税額に、期限の翌日から納付する日までの日数に応じた延滞金を加えて納付しなければなりません。ただし、税額が2,000円未満の場合は、延滞金は生じません。
2024年1月1日からの延滞金の割合は、以下のとおりです。
固定資産税の延滞金の割合
- 期限の翌日から1か月を経過するまで に納付する場合:年2.4%
- 期限の翌日から1か月以上を経過して納付する場合:年8.7%
減額・減免措置を受けるためには申告が必要
固定資産税の特例措置を受けるには、申告や届出が必要な点も覚えておく必要があります。
例えば、家屋の耐震改修に伴う減税やバリアフリー改修に関する特例措置の適用を受けるためには、工事完了日から3か月以内に固定資産税減額申告書や増改築等工事証明書などの書類を、当該家屋の所在する市区町村の窓口へ提出しなければなりません。
固定資産税の減額・減免措置を受ける条件や申告の仕方については、各自治体のウェブサイトや窓口で確認しましょう。
会計・経費・請求、誰でもカンタンまとめて効率化!法人向けクラウド会計ソフト「弥生会計 Next」
会計ソフトなら日々の帳簿付けや決算書作成もかんたん
「弥生会計 Next」は、使いやすさを追求した中小企業向けクラウド会計ソフトです。帳簿・決算書の作成、請求書発行や経費精算もこれひとつで効率化できます。
画面を見れば操作方法がすぐにわかるので、経理初心者でも安心してすぐに使い始められます。
だれでもかんたんに経理業務がはじめられる!
「弥生会計 Next」では、利用開始の初期設定などは、対話的に質問に答えるだけで、会計知識がない方でも自分に合った設定を行うことができます。
取引入力も連携した銀行口座などから明細を取得して仕訳を登録できますので、入力の手間を大幅に削減できます。勘定科目はAIが自動で推測して設定するため、会計業務に慣れていない方でも仕訳を登録できます。
仕訳を登録するたびにAIが学習するので、徐々に仕訳の精度が向上します。

会計業務はもちろん、請求書発行、経費精算、証憑管理業務もできる!
「弥生会計 Next」では、請求書作成ソフト・経費精算ソフト・証憑管理ソフトがセットで利用できます。自動的にデータが連携されるため、バックオフィス業務を幅広く効率化できます。

自動集計されるレポートで経営状態をリアルタイムに把握!
例えば、見たい数字をすぐに見られる残高試算表では、自社の財務状況を確認できます。集計期間や金額の累計・推移の切りかえもかんたんです。
会社全体だけでなく、部門別会計もできるので、経営の意思決定に役立ちます。

「弥生会計 Next」で、会計業務を「できるだけやりたくないもの」から「事業を成長させるうえで欠かせないもの」へ。まずは、「弥生会計 Next」をぜひお試しください。
会計・経費・請求、誰でもカンタンまとめて効率化!法人向けクラウド会計ソフト「弥生会計 Next」
固定資産税を理解して正しく会計処理や納付をしましょう
法人や個人事業主にとっても重要な固定資産税に関する基礎知識を解説しました。事業用資産にかかる固定資産税は経費計上が認められるため、固定資産の評価方法や納税額の計算方法を正しく理解し、納税額の特例措置についても把握することで負担を軽減できる可能性があります。
固定資産税に関する知識を身に付け、日々の帳簿付けを行うようにしましょう。弥生のクラウド会計ソフト「弥生会計 Next」などの自社に合った会計ソフトを活用することで、会計業務を効率化しましょう。
会計・経費・請求、誰でもカンタンまとめて効率化!法人向けクラウド会計ソフト「弥生会計 Next」
【無料】お役立ち資料ダウンロード
「弥生会計 Next」がよくわかる資料
「弥生会計 Next」のメリットや機能、サポート内容やプラン等を解説!導入を検討している方におすすめ

この記事の監修者渋田貴正(税理士、司法書士、行政書士、社会保険労務士)
税理士、司法書士、社会保険労務士、行政書士、起業コンサルタント®。
1984年富山県生まれ。東京大学経済学部卒。
大学卒業後、大手食品メーカーや外資系専門商社にて財務・経理担当として勤務。
在職中に税理士、司法書士、社会保険労務士の資格を取得。2012年独立し、司法書士事務所開設。
2013年にV-Spiritsグループに合流し税理士登録。現在は、税理士・司法書士・社会保険労務士として、税務・人事労務全般の業務を行う。