交通費精算とは?精算のやり方やチェックポイント、効率化の方法を解説
更新
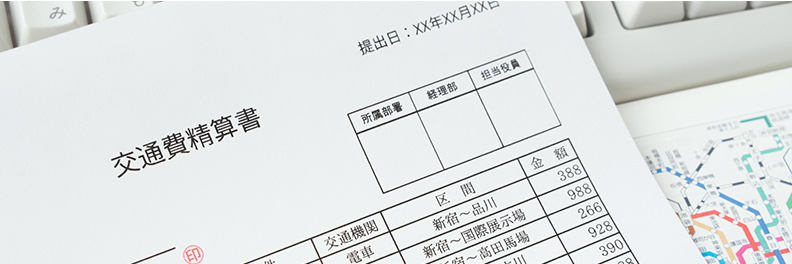
経理業務の1つに経費精算がありますが、中でも交通費精算は件数の多い業務でしょう。交通費精算は頻繁に行う作業だからこそ、効率化すれば、時間と手間の大幅な削減につながる可能性があります。
本記事では、交通費精算の流れや精算時の注意点と共に、交通費精算を効率化する方法について解説します。
今なら「弥生会計 Next」スタート応援キャンペーン実施中!

会計・経費・請求、誰でもカンタンまとめて効率化!法人向けクラウド会計ソフト「弥生会計 Next」
交通費精算とは、従業員が立て替えた交通費を会社が精算・支給する手続きのこと
交通費精算は、経理業務である経費精算の1つです。営業活動のために従業員が一時的に立て替えた交通費を、後日会社が精算・支給するまでの一連の手続きを指します。
会社の営業活動の中では、取引先への訪問をはじめとするさまざまな移動が必要になり、そのたびに交通費が発生します。特に外回りが多い営業担当者などは、電車やバス、タクシーなど、頻繁に交通費を支払うことになるでしょう。
しかし、これらの交通費は金額が細かいうえ、いつ、いくら必要になるかを正確に予測できず、前もって従業員に渡すことは現実的ではありません。そのため、多くの場合は従業員が一時的に立て替えて支払い、後日、従業員からの申請を会社が承認し、支払うことで精算を行います。
会計・経費・請求、誰でもカンタンまとめて効率化!法人向けクラウド会計ソフト「弥生会計 Next」
交通費と似た費用との違い
交通費と似た費用に、旅費交通費や通勤費があります。それぞれどのような違いがあるのかを確認しておきましょう。
交通費と旅費交通費の違い
交通費とは、一般的に、通勤以外で業務のために交通機関を利用した場合にかかった費用を指します。
顧客や取引先への訪問、仕入れ、納品、外注先との打ち合わせ、業務に関わる情報収集・取材、経理担当者の銀行訪問など、仕事での移動にかかる費用は交通費です。基本的には、日常の業務に関わる近場への移動の際に発生した費用を、交通費と考えて問題ないでしょう。
交通費に含まれるもの
- 電車代やバス代、タクシー代
- 車で移動する際の有料道路通行料金(ETC料金含む)
- 駐車場代
それに対して、旅費交通費は、出張のように遠方への移動や宿泊を伴う移動をした際にかかった費用のことです。会社によっては、旅費交通費の上限を定めている場合もあります。
旅費交通費に含まれるもの
- 飛行機や新幹線などを含めた出張先へ向かう(または出張先から戻る)ための交通費
- 出張先での移動にかかった交通費
- 出張による宿泊費、日当など
旅費交通費については、こちらの記事で詳しく解説していますので参考にしてください。
交通費と通勤費の違い
交通費は業務に関わる移動に伴う費用ですが、通勤費は会社に通勤する際に発生する費用です。電車代やバス代などの他、車で通勤することが認められている従業員のガソリン代も通勤費に含まれる費用です。全額支給や上限を設けた一部支給など、通勤費のルールは会社によって異なります。
なお、従業員に支払う通勤費は、給与とは違い、一定額までは所得税が非課税となります。ただし、社会保険料の基となる標準報酬月額は、通勤費を含めることに注意しましょう。
それに対して交通費は、あくまで会社の経費を従業員が立て替えたものです。従業員個人の所得には関係がないため、たとえ精算する交通費が高額になっても、従業員の所得税が増額されたり、社会保険料が上がったりすることはありません。
交通費・通勤手当の課税と非課税のルールについてはこちらの記事で解説していますので、参考にしてください。
会計・経費・請求、誰でもカンタンまとめて効率化!法人向けクラウド会計ソフト「弥生会計 Next」
交通費精算処理のやり方
交通費精算は、従業員の立て替え払いが発生するたびに行うこともあれば、1ヵ月に1度など期間を決めてまとめて行うこともあります。会社によってルールが異なるため、定められたタイミングで精算手続きを行いましょう。一般的な交通費精算の流れは、次のとおりです。
1. 従業員が交通費精算書を作成
まずは、従業員に交通費精算書を作成してもらいます。基本的に経費精算では領収書が必要とされますが、電車やバスなどの公共交通機関では、領収書が発行されないこともあります。特に最近では交通系ICカードの利用が一般化しており、移動手段ごとに領収書をもらうのは難しいでしょう。
そのため多くの会社では、交通費の精算にあたり、領収書を添付する代わりに交通費精算書を作成しています。交通費精算書には、申請者の氏名や日付、訪問先、目的、使用した交通機関、経路、運賃などを記載します。
有料道路通行料金の立て替え精算では、従業員が所有するETCカードの利用証明書を証憑として申請することも可能です。なお、利用証明書はETC利用照会サービスのWebページでダウンロードできます。
会社がETCカードを貸与している場合は、個人立て替えではなく、経費として直接処理することができます。
2. 従業員の上長がチェック・承認
従業員が交通費精算書を作成したら、直属の上長に提出することが一般的です。上長は、従業員から提出された交通費精算書を確認し、その移動が業務上必要なものか、訪問先や訪問目的に不自然な点はないかなどをチェックします。このような作成者と上長のダブルチェック体制によって、経費精算がよりスムーズになるでしょう。
上長は、確認して問題がなければ交通費精算書を承認し、経理担当者に提出します。
3. 経理担当者がチェック
経理担当者は、提出された交通費精算書を確認し、承認作業を行います。もし経理担当者が漏れやミスを見つけた場合は、差し戻さなければいけません。主なチェックポイントは以下のとおりです。
最安経路で申請されているか
交通費が最安経路で申請されているかを確認します。目的地までの経路が複数存在する場合は、最も運賃が安いルートで申請されているかのチェックが必要です。
ただし、アポイントの時間に間に合わせるために、移動時間を短縮できる経路を選んだといった、正当な理由があれば最安運賃でなくても問題ないと考えられます。交通費精算書の備考などに理由を記載してもらうといいでしょう。
必要な領収書が添付されているか
交通費精算書には、交通費の領収書の添付が必要な場合と添付不要な場合があり、提出されたものがいずれに該当するかを確認することが重要です。
近郊へ電車やバスで移動した場合の運賃は領収書の受領が難しいため、添付がなくても問題ありません。消費税法上も、3万円未満の交通費については適格請求書等に該当する領収書の保管義務が免除されています。
ただし、飛行機や新幹線などに関しては、3万円未満であったとしても交通費精算書と併せて領収書の提出を求めるのがよいでしょう。一般的に領収書が発行されるタクシー代についても同様です。
また、2023年10月から開始されたインボイス制度に対応するため、添付した領収書が適格簡易請求書として使用できる書類かどうか確認する必要がある点にも注意しましょう。
インボイス制度開始によるレシートの扱いにおける変更点についてはこちらの記事で解説していますので、参考にしてください。
社内ルールに沿っているか
交通費の上限や、タクシー利用が可能な基準など、社内ルールに沿った申請となっているかをチェックします。ETCカードで支払った高速道路の通行料を申請する場合は、ETC利用証明書を添付するルールとし、走行区間や目的地が申請内容と一致しているか確認しましょう。会社貸与のETCカードの場合、私的利用との区別がつくよう運用ルールを明確にする必要があります。
4. 経理担当者が精算金を支給
従業員の申請を承認したあと、経理担当者は従業員に精算金を支給する手続きをとります。精算方法は、現金での支払いや銀行振込、翌月の給与と合算しての支払いなど、会社によってさまざまです。
会計・経費・請求、誰でもカンタンまとめて効率化!法人向けクラウド会計ソフト「弥生会計 Next」
交通費精算の期限を設定する重要性
交通費精算の期限設定は、企業全体の経理処理や勤怠管理をスムーズに進めるうえで重要なポイントです。
毎月決まったタイミングで交通費精算を行うことで、月次決算や会計処理のスケジュールが安定し、業務全体の流れがスムーズになるでしょう。
多くの企業では「毎月〇日までに提出」もしくは「月末締め・翌月〇日払い」など、具体的な期限を設けています。例えば、「交通費の申請は毎月25日まで」といったルールを定め、必ずその日までに申請してもらうことが重要です。期限を設定することにより、交通費の支払いが遅れることなく行われ、従業員の不満や混乱を防ぐ効果も期待できます。
万が一、交通費精算が期限を過ぎてしまうと、精算処理が翌月にずれ込み、支払いが遅延する可能性もあります。さらに、経理部門に余計な確認作業が発生するため、業務負荷が高まることにもなりかねません。期限を明確に設定し、必ず期限内に申請してもらうよう周知することが重要です。
会計・経費・請求、誰でもカンタンまとめて効率化!法人向けクラウド会計ソフト「弥生会計 Next」
手作業による交通費精算チェックの主な課題
交通費精算時のチェック作業は、経理担当者にとって重要な業務の1つです。その一方で、一連の業務を手作業で進めている場合、さまざまな課題も発生します。手作業による交通費精算チェックにおいて、主な課題と考えられるのは以下の2点です。
ヒューマンエラーが起きやすい
交通費の申請が集中しやすい月末や月初などの繁忙期には、経理担当者の作業負担が大きくなりがちです。業務量が一時的に急増することから、1件あたりのチェックにかけられる時間が減り、金額の入力ミスや経路の確認漏れなどが発生するリスクが高まります。たとえ意図的ではなかったとしても、こうしたミスの積み重ねが不正な経費の計上と見なされる可能性も否定できません。
ミスを防ぐためにダブルチェックを実施している企業もありますが、ダブルチェックの工程が追加されたことによって、確認作業の負荷がかえって増大している可能性もあります。特に人的リソースの確保が困難な中小企業においては、十分なチェック体制を整えるのが現実的ではないケースも多々あるでしょう。このように、ヒューマンエラーの抑制に向けた抜本的な対策を講じるのは簡単ではありません。
申請・確認作業に時間と労力がかかる
申請・確認作業には時間と労力がかかることも課題の1つです。経理担当者は、申請内容に対して経路検索を行い、金額やルートが適切であることを確認したうえで、社内規定との整合性もチェックする必要があります。社員数の多い企業であれば、毎月の申請件数は膨大な量にのぼるでしょう。1件1件の申請に対してこうしたチェック作業を要するのは、経理担当者にとって大きな負担になりかねません。
さらに、申請内容に不備が見つかれば差し戻し作業が発生します。差し戻しが頻発すると処理の遅延につながるだけでなく、担当者のストレス増大にもつながりやすいことが懸念点です。結果的に作業効率が低下すれば、企業全体の経費管理に悪影響を及ぼす可能性があります。このように、1件あたりの交通費精算に費やす時間と労力は限られているように感じられたとしても、積もり積もっていくことで業務効率化を妨げる要因にもなりえるのが実情です。
会計・経費・請求、誰でもカンタンまとめて効率化!法人向けクラウド会計ソフト「弥生会計 Next」
交通費精算を効率化する方法
交通費精算は細かい作業が多く、申請者と経理担当者の双方にとって、手間がかかりがちです。交通費精算を効率化するためには、次のような方法があります。
ICカード対応の経費精算システムを導入する
交通費精算の効率化に役立つのが、経費システムや経費精算アプリです。スマートフォンからも入力可能なシステムやアプリを使うと、移動中の隙間時間などに交通費を入力することが可能です。中には、交通系ICカードの情報を自動読み取りできる機能を備えたシステムやアプリもあります。業務用の交通系ICカードを従業員に支給したうえで、そのようなシステムを使えば、これまで手書きや手入力していた精算作業の負荷を軽減し、作業時間を短縮できるでしょう。さらに、会計ソフトと連携が可能なシステムなら、交通費精算以外の経理業務も格段に効率化できます。
例えば、弥生が提供する「スマート取引取込」は、レシートをスマートフォンのカメラで撮影し、画像データとして対象製品に取り込むことができるアプリです。取り込まれた画像データは、経費精算アプリなどの連携サービスで仕訳データに自動で変換した後、対応する弥生の会計ソフトの帳簿に自動的に反映され、確定申告や決算に利用できます。
明確に経費精算ルールを決める
従業員から提出される交通費精算書に抜け漏れがあったり、社内ルールから外れたりしていると、差し戻しに余計な手間と時間がかかってしまいます。そのような無駄を削減するために、経費精算に関するルールをしっかりと決めておくことが大切です。
例えば、交通費精算書の記載項目、交通費として認められる範囲、領収書の添付が必要なケースなど、明確なルールを定めて社内に周知することで、単純ミスの減少につながるでしょう。もしミスがあったとしても、経理担当者に提出される前に、上長のチェックの段階で修正が可能になります。
領収書を電子化する
経費精算システムの導入と併せて、領収書を電子化するのも1つの方法です。交通系ICカードやクレジットカードの取引データを、電子帳簿保存法に則った形式できちんと保存・管理しておけば、紙の領収書を保存する必要がありません。また、会計ソフトの中には、スキャンや撮影した領収書のデータを取り込み、自動で仕訳が可能なものもあります。
そのような機能を活用すれば、紙の領収書をファイリングしたり保管スペースを確保したりする手間もなくなるうえ、仕訳作業も自動化できます。
不正があった際の処遇を共有・社内周知する
経費精算にあたって避けなければならないのが、従業員による交通費の不正請求です。交通費は従業員からの自己申告になるため、不正のリスクは避けられません。交通費精算のルールと共に、不正請求があった場合の処遇も明確に定め、社内にしっかりと周知させましょう。同時に、直属の上長と経理担当者のダブルチェックなど、不正が起こりにくい体制を整えることも大切です。
会計・経費・請求、誰でもカンタンまとめて効率化!法人向けクラウド会計ソフト「弥生会計 Next」
交通費精算をする際の6つの注意点
交通費精算は、頻繁に繰り返し発生する経理業務です。また、従業員の数が増えると、交通費精算の件数も多くなります。ミスや見落としのないように、以下の点に注意を払いましょう。
旅費交通費と出張費の区別を徹底する
前述したように、日常的な近場への移動にかかる交通費と出張など遠方への移動にかかる旅費交通費は、内容にやや違いがあります。ただし会計処理上は、いずれの勘定科目も「旅費交通費」です。会社によっては、出張の際に、出張手当のような日当を支給しているケースもあるでしょう。また、交通費の上限なども、近場の移動と出張時では異なるルールを設けている場合があるかもしれません。
ただし、精算時に近場の移動と宿泊を伴う出張を同じ旅費交通費として処理してしまうと、確認や管理がしにくくなります。そのため、旅費交通費の勘定科目のうち、出張にかかった費用は出張費として区別して精算するのがおすすめです。
利用経路と運賃を確認する
交通費精算を行う際は、出発地・目的地・交通手段・金額を明確に確認してもらうことが重要です。これらの事項は、交通費精算書にも必ず記載されていなければなりません。最安ルートでの精算とする場合は、その旨を社内ルールとして明文化し、従業員に周知しましょう。暗黙の了解として曖昧なままにすると、後々トラブルを招きかねません。
定期区間控除や区間などの申請ルールを確認する
会社から従業員に通勤定期代が支給されている場合は、申請された交通費に通勤定期の区間が含まれていないか確認が必要です。通勤定期を使って移動しても、交通費はかかりません。交通費精算は、実際に支払った分のみが対象となります。
領収書のない公共交通機関の費用の申請漏れには注意する
一般的な経費精算は、領収書の提出が必須となります。しかし、領収書のない公共交通機関の運賃は、日々の業務に追われているうちに、つい申請を忘れてしまいがちです。申請の漏れや遅れがあると、精算ができずに従業員の不利益になるうえ、経理担当者の負担も増大します。そのため交通費精算は、あらかじめ申請期限を定めて社内に周知し、期限前には再度アナウンスを行うといいでしょう。例えば、「申請期限〇日前に社内へアナウンスする」「申請期限の前日に再度アナウンスする」といった業務フローを定め、着実に実行していくことが大切です。
交通費として認められる限度額に注意する
会社によっては社内ルールとして交通費の上限を定めていることがあり、その場合は、申請された金額が、認められる限度額を超えていないかを確認する必要があります。また、通勤費についても、所得税が非課税となる限度額が定められています。例えば、公共交通機関を使って通勤する場合は、非課税となる限度額は1ヵ月15万円までです。車通勤の場合は距離によって非課税となる限度額が変わるので注意しましょう。
領収書が適格請求書か否かを確認する
2023年10月からインボイス制度が開始され、課税事業者は適格請求書(インボイス)がないと仕入税額控除が受けられません。そのため、交通費精算を行う際には、それぞれの公共交通機関で発行された領収書が適格請求書として有効かどうかを確認しましょう。従業員には、できるだけ提出前に適格請求書であるか否かを確認してもらうよう依頼することをおすすめします。
会計・経費・請求、誰でもカンタンまとめて効率化!法人向けクラウド会計ソフト「弥生会計 Next」
会計ソフトなら日々の帳簿付けや決算書作成もかんたん
「弥生会計 Next」は、使いやすさを追求した中小企業向けクラウド会計ソフトです。帳簿・決算書の作成、請求書発行や経費精算もこれひとつで効率化できます。
画面を見れば操作方法がすぐにわかるので、経理初心者でも安心してすぐに使い始められます。
だれでもかんたんに経理業務がはじめられる!
「弥生会計 Next」では、利用開始の初期設定などは、対話的に質問に答えるだけで、会計知識がない方でも自分に合った設定を行うことができます。
取引入力も連携した銀行口座などから明細を取得して仕訳を登録できますので、入力の手間を大幅に削減できます。勘定科目はAIが自動で推測して設定するため、会計業務に慣れていない方でも仕訳を登録できます。
仕訳を登録するたびにAIが学習するので、徐々に仕訳の精度が向上します。

会計業務はもちろん、請求書発行、経費精算、証憑管理業務もできる!
「弥生会計 Next」では、請求書作成ソフト・経費精算ソフト・証憑管理ソフトがセットで利用できます。自動的にデータが連携されるため、バックオフィス業務を幅広く効率化できます。

自動集計されるレポートで経営状態をリアルタイムに把握!
例えば、見たい数字をすぐに見られる残高試算表では、自社の財務状況を確認できます。集計期間や金額の累計・推移の切りかえもかんたんです。
会社全体だけでなく、部門別会計もできるので、経営の意思決定に役立ちます。

「弥生会計 Next」で、会計業務を「できるだけやりたくないもの」から「事業を成長させるうえで欠かせないもの」へ。まずは、「弥生会計 Next」をぜひお試しください。
会計・経費・請求、誰でもカンタンまとめて効率化!法人向けクラウド会計ソフト「弥生会計 Next」
会計ソフトを活用して交通費精算を効率よく進めよう
交通費精算は多くの企業で日常的に発生する経理業務である一方で、煩雑な作業が多くヒューマンエラーを招きやすい面もあります。交通費精算が適切に行われていない状況が常態化すれば、不正な経費の計上を疑われることにもなりかねません。
交通費精算は正確性を求められる業務である一方で、経理担当者にとって多くの時間と労力を費やす必要がある作業の1つといえます。細かい経路や金額の確認も必要なため、できるだけ効率良く進めたいと考えている経理担当者も多いでしょう。交通費をはじめとする経費精算を効率化するには、使いやすい会計ソフトを活用するのがおすすめです。交通費精算をはじめとする経費精算をスムーズに進め、経理業務の効率化を図りたい事業者様は、ぜひ「弥生会計 Next」の導入をご検討ください。
会計・経費・請求、誰でもカンタンまとめて効率化!法人向けクラウド会計ソフト「弥生会計 Next」
【無料】お役立ち資料ダウンロード
「弥生会計 Next」がよくわかる資料
「弥生会計 Next」のメリットや機能、サポート内容やプラン等を解説!導入を検討している方におすすめ

この記事の監修者渋田貴正(税理士、司法書士、行政書士、社会保険労務士)
税理士、司法書士、社会保険労務士、行政書士、起業コンサルタント®。
1984年富山県生まれ。東京大学経済学部卒。
大学卒業後、大手食品メーカーや外資系専門商社にて財務・経理担当として勤務。
在職中に税理士、司法書士、社会保険労務士の資格を取得。2012年独立し、司法書士事務所開設。
2013年にV-Spiritsグループに合流し税理士登録。現在は、税理士・司法書士・社会保険労務士として、税務・人事労務全般の業務を行う。









