売上債権とは?種類や管理方法、回収方法などを解説
更新
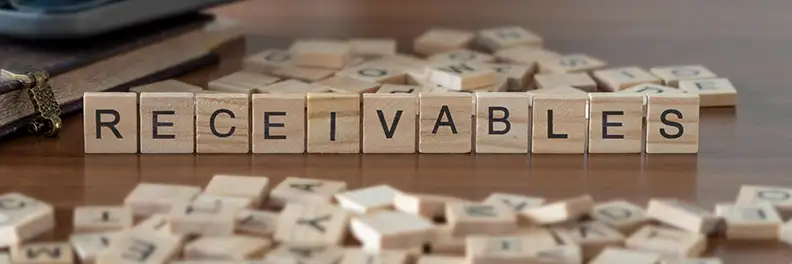
企業間取引では、営業上の債権である売上債権が頻繁に発生します。売上債権は企業の資金繰りと深くかかわっているため、適切に管理し、可能な限り早期に回収することが重要です。
本記事では、売上債権の種類や管理方法、回収方法について解説します。併せて、経営状態を把握するための指標である売上債権回転率・売上債権回転期間についてもまとめていますので、ぜひ参考にしてください。
今なら「弥生会計 Next」スタート応援キャンペーン実施中!

会計・経費・請求、誰でもカンタンまとめて効率化!法人向けクラウド会計ソフト「弥生会計 Next」
売上債権とは取引先との間で生じた営業上の債権のこと
売上債権とは、商品の販売やサービスの提供に伴い、後日代金を受け取る権利やその金額のことを指します。債権とは、特定の人に特定の行為や給付を請求できる権利のことです。一般的に、企業間の取引においては、業務を効率良く進めるために商品やサービスを先立って提供し、代金を後日請求する掛取引(信用取引)が行われています。このような、お互いの信頼関係に基づく掛取引に伴って発生するのが売上債権です。
掛取引には、現金を持ち歩くリスクを回避できる他、資金繰りの改善や事務処理負担の軽減といったメリットがあります。よって、売上債権の存在自体をネガティブに捉える必要はありません。その一方で、売上債権の数や金額が増加することは、自社が立て替えている代金が増えていることを意味する点に注意しましょう。
会計・経費・請求、誰でもカンタンまとめて効率化!法人向けクラウド会計ソフト「弥生会計 Next」
売上債権の種類
売上債権には、大きく分けて「売掛金」「受取手形」「電子債権」の3種類があります。資金繰りを適切に行うには、これらの売上債権を注視していくことが必要です。それぞれの売上債権の特徴について詳しく見ていきましょう。
売掛金:商品やサービスの売上代金を後日受け取る権利
売掛金とは、商品やサービスの売上代金を後日受け取る権利のことです。
一般的に、企業間取引においては現金取引が行われるケースは少なく、掛取引が多く見られます。月単位など一定期間内の取引をまとめて処理することにより、請求や入金確認の事務処理を効率化できるためです。
その一方で、売掛金が存在することは、商品やサービスの代金が未回収の状態であることを意味します。よって、売掛金は迅速に回収しなければなりません。なお、掛取引を行う際は、取引先の信用調査を実施し、取引限度額を設定します。売掛金の回収に想定よりも時間を要したり、代金を回収できなくなったりするリスクを回避することが、信用調査を実施する主な目的です。
こちらの記事でも解説していますので、参考にしてください。
受取手形:売買取引に際して決済手段として振り出される手形
受取手形とは、商品やサービスの売買取引に際して、決済手段として振り出される手形のことです。
受取手形は、手形割引を利用することで、期日前に資金化できます。また、裏書譲渡により第三者への支払に利用することも可能です。受取手形は、手形法に基づいて発行されることから、売掛金と比べて法的効力が強いという特徴があります。
なお、受取手形には、約束手形と為替手形の2種類があります。約束手形は、当事者が2人の取引、為替手形は、当事者が3人の取引に用いられる受取手形です。企業間取引においては、約束手形が用いられるケースが多く見られます。
電子記録債権:電子的に発行された手形
電子記録債権とは、電子的に発行された手形のことを指します。
電子記録債権は、発行から受け取り、決済までの管理を金融機関に担ってもらえる点が大きな特徴です。また、電子記録債権は電子データによってやりとりが完結するため、管理コストが抑えられる点がメリットとしてあげられます。なお、物理的な受取手形には盗難や改ざんのリスクがありますが、電子記録債権であればこうしたリスクを回避できます。
会計・経費・請求、誰でもカンタンまとめて効率化!法人向けクラウド会計ソフト「弥生会計 Next」
売上債権から経営状態を把握するための指標
売上高が順調に伸びていたとしても、売上債権を適切に回収できなければ現金は入ってきません。したがって、売上債権の回収状況は経営状態を把握するための重要な手掛かりとなります。売上債権の回収状況を示す指標は、「売上債権回転率」と「売上債権回転期間」の2つです。それぞれ詳しく見ていきましょう。
売上債権回転率:売上債権がどれほど回収できているかを示す指標
売上債権回転率とは、売上債権がどれほど回収できているかを示す指標のことです。売上債権回転率は、売上高を売上債権の金額で割ることで算出されます。
売上債権回転率の計算式
売上債権回転率=売上高÷売上債権額
売上債権回転率が高いほど、効率的に売上債権を回収できていることを表し、キャッシュ・フローが良好な状態に保たれています。反対に、売上債権回転率が低い場合は、売上債権が回収されるまでに時間を要していることが懸念されます。売上債権の回収の遅れをできるだけ解消すると共に、未回収のままにならないよう何らかの対策を講じなくてはなりません。
ただし、売上債権回転率の目安は業種によって異なる点に注意しましょう。一般的に、売上債権回転率は小売業や飲食業といった現金取引が多い業種では高く、製造業・建設業など売掛金による取引が多く発生する業種では低くなる傾向があります。
売上債権回転期間:売上債権の回収期間を示す指標
売上債権回転期間とは、売上債権の回収期間を示す指標です。売上債権回転期間は、以下の計算式によって算出されます。
売上債権回転期間の計算式
売上債権回転月数=売上債権÷(売上高÷12か月)
売上債権回転日数=売上債権÷(売上高÷365日)
例えば、売上高6,000万円に対して売上債権が800万円の場合、売上債権回転月数・日数はそれぞれ以下のように算出できます。
売上債権回転月数=800万円÷(6,000万円÷12か月)=1.6か月
売上債権回転日数=800万円÷(6,000万円÷365日)=48.67日
よって、売上債権の回収までの平均月数は1.6か月、平均日数は48.67日とわかります。
売上債権回転期間が短いほど、短期間で債権が回収できていることを表しています。ただし、売上債権回転率と同様、業種によって売上債権回転期間の目安は異なる点に注意しましょう。一般的に、売上債権回転期間は、小売業や飲食業といった現金取引が多くを占める業種では短く、製造業・卸売業のように掛取引が多い業種では長くなる傾向があります。
会計・経費・請求、誰でもカンタンまとめて効率化!法人向けクラウド会計ソフト「弥生会計 Next」
売上債権の管理方法
売上債権はどのように管理していくのがよいのでしょうか。いずれの売上債権にも共通するポイントとして、取引先の信用調査を実施し、与信管理を行うことが重要です。取引を開始する際はもちろん、すでに長期にわたる取引実績のある取引先であっても、与信の状況は変化する可能性があります。そのため、決算情報をはじめ、取引先へのヒアリングや業界関係者を通じて情報収集を行い、貸倒れリスクを抑制していくことが大切です。売上債権の種類ごとに、適切な管理方法を見ていきましょう。
売掛金の管理方法
売掛金を管理する際の基本は、請求書などに記載した期日どおりに入金されているかを確認することです。取引先ごとに「いつまでに」「いくら」入金されていればよいのかを正確に把握し、間違いなく入金されているか注視していくことが大切になります。期日を過ぎても入金が確認できない場合は、取引先へ状況の確認や督促など、しかるべき対策を講じる必要があります。
なお、取引先の件数が限られているようなら、売掛金を売上台帳や売掛帳などに手書きで記入することで管理できるでしょう。その一方で、取引先の件数が増えていくにつれて、こうした手書きでの管理は煩雑になる可能性が高いと考えられます。こうした場合は、売掛金の管理に特化した会計ソフトを導入し、売掛台帳や売掛帳の自動集計機能を活用するのがおすすめです。また、会計ソフトを活用することで、請求書や納品書の生成機能を活用でき、売掛金を抜け・漏れなく管理できるだけでなく、業務効率化にもつながることも大きなメリットといえます。
受取手形の管理方法
受取手形の管理に関しては、決済日があらかじめ決められているため、期日が到来したら銀行に取り立て依頼をする必要があります。その際、銀行の営業日が決済日から3営業日超過した場合は、取り立てが不可能になってしまう点に注意しましょう。そのため、受取手形ごとに手形決済の日付を正確に把握しておかなくてはなりません。
具体的には、手形決済の日付をまとめた受取手形帳を作成して管理する方法がおすすめです。受取手形の期日は、一般的に30日・60日・90日・120日といった単位で設定されます。特に、90日や120日といった期日が長く設定されている受取手形に関しては、決済日に取り立ての依頼を失念することのないよう十分に注意しなければなりません。
電子記録債権の管理方法
電子記録債権で管理すると、債権を譲り受けた金融機関が受取から決済までの手続きを行うため、取り立てを失念することはありません。決済日が到来すると、自動的に銀行口座に決済代金が振り込まれます。したがって、電子記録債権の管理の目的は回収ではなく、現金化の状況を正確に把握することにあります。
電子記録債権の現金化の状況を適切に把握するには、決済日や金額を管理台帳にまとめておくことがおすすめです。現金化が可能な電子記録債権の状況を把握することにより、今後の資金繰りに問題が生じるおそれがないか確認しやすくなります。
会計・経費・請求、誰でもカンタンまとめて効率化!法人向けクラウド会計ソフト「弥生会計 Next」
売上債権の回収方法
売上債権の回収は資金繰りに直結します。したがって、可能な限り早期に現金化することが重要です。売上債権の基本的な回収方法を確認しておきましょう。
実施方法を決める
まずは、売上債権を具体的にどのように回収するのか、実施方法を明確にする必要があります。一般的な回収方法としてあげられるのは以下の3つです。
売上債権の回収方法
- 現金による回収
- 銀行口座への振込による回収
- 受取手形や電子記録債権による回収
なお、上の他に、買掛金や未払金を相殺する売上債権の回収方法もあります。どの回収方法を選択するかは、取引先の要望も考慮して決めなければなりません。自社にとって都合のよい方法で回収できるとは限らない点に注意しましょう。企業間取引においては、取引開始時に取り決めた条件がその後の取引においても適用されるケースが多く見られることから、事前に双方で協議のうえ売上債権の回収方法を慎重に設定する必要があります。
支払期日を決める
次に、売上債権の支払期日に関しても、事前に明確な取り決めをすることが売上債権の回収方法において重要になります。売掛金の場合、翌月末払、翌々月末払といった支払期日が設定されるケースが多く見られます。そのため、受取手形や電子記録債権に関しては、120日後決済、150日後決済などの決済日を事前に定めなければなりません。決済日が到来すると、受取手形は銀行へ取り立てを依頼して現金化されます。電子記録債権に関しては、あらかじめ登録した銀行口座に振り込まれるため、自社で取り立てを行う必要はありません。
支払期日についても、取引先との合意に基づいて決定することが求められます。ただし、支払期日はいくらでも引き延ばせるわけではありません。取適法(下請法)によって、自社や取引先の資本金の金額によっては支払期日は商品の受領やサービス提供を受けた日から60日以内に設定する必要があります。期日を超過していないか確認したうえで、支払期日を決めましょう。
※下請法(下請代金支払遅延等防止法)は、2026年1月1日から「製造委託等に係る中小受託事業者に対する代金の支払の遅延等の防止に関する法律(通称:取適法・略称:中小受託取引適正化法)」に改正
会計・経費・請求、誰でもカンタンまとめて効率化!法人向けクラウド会計ソフト「弥生会計 Next」
会計ソフトなら日々の帳簿付けや決算書作成もかんたん
「弥生会計 Next」は、使いやすさを追求した中小企業向けクラウド会計ソフトです。帳簿・決算書の作成、請求書発行や経費精算もこれひとつで効率化できます。
画面を見れば操作方法がすぐにわかるので、経理初心者でも安心してすぐに使い始められます。
だれでもかんたんに経理業務がはじめられる!
「弥生会計 Next」では、利用開始の初期設定などは、対話的に質問に答えるだけで、会計知識がない方でも自分に合った設定を行うことができます。
取引入力も連携した銀行口座などから明細を取得して仕訳を登録できますので、入力の手間を大幅に削減できます。勘定科目はAIが自動で推測して設定するため、会計業務に慣れていない方でも仕訳を登録できます。
仕訳を登録するたびにAIが学習するので、徐々に仕訳の精度が向上します。

会計業務はもちろん、請求書発行、経費精算、証憑管理業務もできる!
「弥生会計 Next」では、請求書作成ソフト・経費精算ソフト・証憑管理ソフトがセットで利用できます。自動的にデータが連携されるため、バックオフィス業務を幅広く効率化できます。

自動集計されるレポートで経営状態をリアルタイムに把握!
例えば、見たい数字をすぐに見られる残高試算表では、自社の財務状況を確認できます。集計期間や金額の累計・推移の切りかえもかんたんです。
会社全体だけでなく、部門別会計もできるので、経営の意思決定に役立ちます。

「弥生会計 Next」で、会計業務を「できるだけやりたくないもの」から「事業を成長させるうえで欠かせないもの」へ。まずは、「弥生会計 Next」をぜひお試しください。
会計・経費・請求、誰でもカンタンまとめて効率化!法人向けクラウド会計ソフト「弥生会計 Next」
売上債権を適切に管理して健全な経営状態を維持しよう
売上債権とは、商品の販売やサービスの提供に伴い、代金を後日受け取る権利のことです。売上債権には売掛金・受取手形・電子記録債権の3種類があり、それぞれ回収方法が異なります。売上債権を適切に管理し、期日までに回収することは、資金繰りを安定させ、健全な経営を維持するために不可欠です。売掛金の管理が可能な会計ソフトを活用すると共に、受取手形帳を別途作成するなどして、着実に売上債権を回収していくことが求められます。今回紹介した売上債権の管理方法や回収方法を参考に、企業の健全な経営状態を維持しましょう。
会計・経費・請求、誰でもカンタンまとめて効率化!法人向けクラウド会計ソフト「弥生会計 Next」
【無料】お役立ち資料ダウンロード
「弥生会計 Next」がよくわかる資料
「弥生会計 Next」のメリットや機能、サポート内容やプラン等を解説!導入を検討している方におすすめ

この記事の監修者渋田貴正(税理士、司法書士、行政書士、社会保険労務士)
税理士、司法書士、社会保険労務士、行政書士、起業コンサルタント®。
1984年富山県生まれ。東京大学経済学部卒。
大学卒業後、大手食品メーカーや外資系専門商社にて財務・経理担当として勤務。
在職中に税理士、司法書士、社会保険労務士の資格を取得。2012年独立し、司法書士事務所開設。
2013年にV-Spiritsグループに合流し税理士登録。現在は、税理士・司法書士・社会保険労務士として、税務・人事労務全般の業務を行う。








