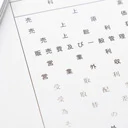予実管理とは?予算管理との違いや手順、成功させるポイントを解説
監修者: 小林祐士(税理士法人フォース)
更新

予実管理とは、企業における予算と実績を比較・管理する手法のことです。しっかり予実管理ができれば、予算と実績を比較して事業活動の実態を把握し、経営目標に向けて適切に進捗しているかを確認できます。では、予実管理を経営目標の達成に役立てるには、どのような手順で行えばよいのでしょうか。
本記事では、予実管理と予算管理との違いや目的や重要性、具体的な手順、成功のポイントなどについて解説します。
今なら「弥生会計 Next」スタート応援キャンペーン実施中!

会計・経費・請求、誰でもカンタンまとめて効率化!法人向けクラウド会計ソフト「弥生会計 Next」
予実管理とは、企業の予算と実績を管理すること
予実管理とは、企業の予算と実績を管理することであり、「予算実績管理」とも呼ばれます。具体的には、あらかじめ設定しておいた具体的な数値目標(予算)と、一定期間における実際の業績(実績)との乖離を分析し、改善に活かす経営手法です。
企業が経営目標を達成するためには、予算と実績を比較して分析を行う必要があります。経営目標を設定しても、途中経過を確認する機会がなければ、進捗状況や課題を把握できません。このとき、目標達成までの状況を可視化するための手段の1つが、予実管理です。
予実管理を行うと、予算に対してどの程度の実績を上げているのかをタイムリーに把握でき、自社の業績を定量的に分析することが可能になります。予算どおりに実績が推移していない場合は、課題を明確化して具体的な改善策を講じることも可能です。また、目標に対して好調な実績が得られた場合にも、要因を分析して今後に活かすことができます。
予実管理においては、売上予算、利益予算、原価予算、経費予算といった各種予算に対して、実際の業績がどの程度達成されているかを定期的に確認・分析します。一般的には、週ごとや月ごとに状況をチェックし、月次決算を活用することでより精度の高い確認が可能になります。予実管理は自己流ではなく、税理士など専門家の助言を得ながら進めることがおすすめです。
会計・経費・請求、誰でもカンタンまとめて効率化!法人向けクラウド会計ソフト「弥生会計 Next」
予実管理と予算管理の違い
業務の中でよく用いられる「予算管理」は、予実管理と混同されやすい用語の1つです。両者は似たような意味で用いられることもありますが、実際にはそれぞれ異なる役割を担っています。
予算管理とは、一般的に、「事業年度ごとに策定する企業の予算計画の管理」を指す言葉です。予算管理においては、過去の売上や市場の動向などに基づき予算計画を立て、その計画と期末の実績を比較・分析します。
それに対して、予実管理は多くの場合、1週間や1か月単位の短いサイクルで予算と実績を比較・分析します。予算管理に比べて分析のサイクルが短いため、予実管理は予算管理の一部として捉えられることもあるでしょう。
また、予算管理が予算の策定から実績の把握、改善まで、予算にかかわる管理活動全般を指すのに対して、予実管理は、特に予算と実績の比較・分析に重点を置いている点が特徴です。
会計・経費・請求、誰でもカンタンまとめて効率化!法人向けクラウド会計ソフト「弥生会計 Next」
予実管理の目的と重要性
予実管理の大きな目的は、経営目標の進捗状況を可視化し、課題を早期に発見して適切な改善策を講じることです。予実管理を行っていないと、「経営目標を達成できるかが決算までわからない」ということになり、経営課題への対応が遅れてしまう可能性があります。
予実管理を行い、定期的に予算と実績の差異をチェックしていれば、期中であってもタイムリーに進捗度を把握できます。目標に対する達成度が低ければ、原因を分析し、迅速な軌道修正を図ることも可能です。予算と実績の差を意識することで、未達成の要因を特定しやすくなり、営業戦略の再検討や修正にも役立ちます。
その他にも、予実管理には企業経営の健全性を保つ働きもあります。予算と実績の差異を定期的に確認し、問題点を早期に発見して改善につなげていくことで、経営の透明性が高まるでしょう。
また、明確な数値目標として予算を設定することで、企業全体に目標意識が浸透し、結果として商品やサービスの品質改善に向けた取り組みが促される、といった可能性もあります。このように、予実管理は企業にとって非常に重要なものだといえます。
会計・経費・請求、誰でもカンタンまとめて効率化!法人向けクラウド会計ソフト「弥生会計 Next」
予実管理の進め方と具体的な手順
ここからは、予実管理を実施する具体的な手順について解説していきます。予実管理の進め方は企業ごとに異なりますが、一般的な流れは次のとおりです。
1. 予算目標を立てて予算を設定する
前述したように、予実管理の目的は、「目標に向かって進む過程を可視化し、実績を予算目標に照らして管理していくこと」です。予算目標が設定されていなければ、予実管理は実施できません。そのため、予実管理は、まず予算目標を立てることからスタートします。
予算目標を立てるタイミングは、一般的に期首までに設定することが多いため、事業計画に基づき、まず企業全体の予算目標を設定し、その後、各部門・プロジェクトごとに展開します。このとき大切なのは、企業としての成長を目指しつつも、現実的に達成可能な目標を立てることです。現実離れした高すぎる目標は達成が難しく、予実管理の意味を失う可能性があります。
反対に、あまりに低すぎる目標でも企業としての成長が望めないため、予算を設定する際には、努力すれば達成できると思えるような、現実的に実現可能な予算目標を意識することがポイントです。企業の経営目標や経営戦略をしっかりと理解したうえで、予算目標の方向性を定めるようにしましょう。
2. 月次決算を行う
次に、予算と実績の差異を定期的にチェックするために、月次決算を行います。月次決算とは、1か月単位で行う決算業務のことで、月末ごとに会計を締め、年次決算とほぼ同じ決算作業を行います。月次決算を行うことで予算と実績の差異を把握しやすくなり、予実管理の精度を高めることが可能です。
財務状況をタイムリーに把握できるようになるので、課題の分析や対策、軌道修正なども行いやすくなります。なお、月次決算の結果は可能な限り関係者に共有し、目標意識と進捗認識の向上を図りましょう。
月次決算については、こちらの記事で解説していますので、参考にしてください。
3. 予算と実績を比較して分析する
月次決算の後は、設定した予算と実績の比較をします。目標とする営業利益と実際の利益に差がある場合は、その差が生まれた要因を分析し、改善策を検討する必要があります。
分析の際は、売上額ではなく、営業利益(売上高-売上原価-販売管理費)に注目して差異を確認しましょう。定量的なデータに基づき、売れていない商品やサービスがあればその理由を探って改善につなげ、売れている商品やサービスなどはさらに売れるような工夫を行います。
4. 改善策を立案して実行する
予算と実績の差を比較し、現状を把握したら、その差を埋めるための改善策を立案します。立案した改善策は、優先順位を明確にし、段階的に実行しましょう。「Plan(計画)、Do(実行)、Check(評価)、Action(改善)」のPDCAサイクルを繰り返すことで、より精度の高い予算設定が可能になり、課題の早期解決にもつながります。
具体的には、設定した予算に向けて行動に移し、予算と実績の数値を比較し、達成度を定量的に評価します。そして、分析結果とそこから明らかになった課題をフィードバックして、改善策を実施することが大切です。解決策を実施した後も継続的に分析とフィードバックを行い、継続的な改善を図ります。
会計・経費・請求、誰でもカンタンまとめて効率化!法人向けクラウド会計ソフト「弥生会計 Next」
予実管理を成功させるポイント
予実管理を成功させるには、押さえておきたいポイントがあります。予実管理を行う際は、次のポイントを意識しましょう。
適切な予算を設定する
予実管理を成功させるうえでポイントになるのが、適切な予算の設定です。
予算目標は、高すぎても低すぎても効果的とはいえません。例えば、あまりに高すぎる予算目標を設定してしまうと、従業員のモチベーションが下がる可能性があります。反対に、低すぎる目標では、努力しなくても容易に達成できてしまい、従業員の向上意欲が失われかねません。
そのため、予算目標は、「容易に達成できないものの、努力すれば実現可能」というラインに設定することが大切です。適度に高い予算目標を設定することで、従業員の意欲や能力が引き出され、企業の成長にも寄与します。
定期的に課題を発見・対策する
予実管理を成功させるポイントは、課題を定期的に把握し、迅速に対策を講じることです。
こまめに現状分析を行うほど、課題が小さいうちに発見しやすくなり、対策も容易になります。予算と実績に乖離が起こった場合は、できるだけその差が小さいうちに発見し、いち早く改善策を講じる必要があります。予算と実績の差が広がってから問題が見つかった場合、軌道修正が難しくなるため、早期に有効な対策を講じることが大切です。
そのため、予実管理は月次でチェックすることが一般的ですが、可能であれば週単位など、より頻繁に現状分析を行うのが望ましいです。月次での確認を基本とし、チェックのタイミングを事前に設定すると効果的でしょう。
部門ごとにKPIを設定する
予実管理を成功させるポイントの1つが、部門ごとのKPI(Key Performance Indicator)を設定することです。
KPIとは、「企業や組織が目標を達成するための、各プロセスにおける具体的な行動指標」を指します。KPIの設定により、目標達成のためにとるべき行動や上げるべき成果の目安を明確にできます。例えば、営業部門の場合は、売上を達成するための具体的な行動と数値目標がKPIです。製造部門の場合は、生産量や品質目標の達成に向けた作業内容および数値がKPIに該当します。
会計・経費・請求、誰でもカンタンまとめて効率化!法人向けクラウド会計ソフト「弥生会計 Next」
予実管理における注意点
予実管理は、企業が経営目標の達成を目指すうえで効果的な手段ですが、方法を間違えると効果をうまく発揮させることができません。効果的に予実管理を行うためには、以下の注意点を把握しておきましょう。
必要に応じて予算の見直しを行う
予実管理における注意点の1つは、必要に応じて予算の見直しを行うことです。
予算と実績が大きく乖離している場合、設定した予算自体が現実的でない可能性があります。例えば、「取引先の状況が急変し、継続的に受けていた注文が途絶えた」「近隣に競合店がオープンして客足が流れた」「競合他社が新商品を開発したことにより、自社の既存商品が陳腐化した」「原材料の高騰により、製品原価が想定より高くなってきた」「営業所の移転により、地代家賃が大きく増えた」など、予算の前提となる情報に変化が起きているケースもあります。
予算と実績に差異が生じた場合は、その原因を丁寧に分析し、必要に応じて予算の見直しを検討することが大切です。
非現実的な目標の達成を強いると、従業員の疲弊やモチベーション低下を引き起こす可能性があります。そればかりか、非現実的な目標を達成するために実績をごまかそうとして、売上の水増しなど、不正行為に発展するリスクも懸念されます。予実管理において予算目標の達成は重要ですが、当初の予算にこだわり過ぎないように注意しましょう。
細かい差異にこだわり過ぎない
予算と実績の細かい差異にこだわり過ぎないことも、予実管理における注意点です。
予実管理を行っていると、どうしても「予算と実績の差を小さくしなければ」ということを重視しやすくなります。しかし、予算と実績の細かい差異ばかりに注目していると、予実管理の本質を見失ってしまうおそれがあります。
予実管理の目的は、現状を把握し、経営改善の対策を立てて実行していくことで、差異の分析は、あくまでそのための手段です。本来、手段である予算と実績の比較・差異分析に過度に重点を置いてしまうと、いつの間にか手段が目的になってしまう可能性があります。予実管理を行う際には、細部の数値にとらわれすぎず、大きな差異から優先的に分析することが効果的です。
会計・経費・請求、誰でもカンタンまとめて効率化!法人向けクラウド会計ソフト「弥生会計 Next」
会計ソフトなら日々の帳簿付けや決算書作成もかんたん
「弥生会計 Next」は、使いやすさを追求した中小企業向けクラウド会計ソフトです。帳簿・決算書の作成、請求書発行や経費精算もこれひとつで効率化できます。
画面を見れば操作方法がすぐにわかるので、経理初心者でも安心してすぐに使い始められます。
だれでもかんたんに経理業務がはじめられる!
「弥生会計 Next」では、利用開始の初期設定などは、対話的に質問に答えるだけで、会計知識がない方でも自分に合った設定を行うことができます。
取引入力も連携した銀行口座などから明細を取得して仕訳を登録できますので、入力の手間を大幅に削減できます。勘定科目はAIが自動で推測して設定するため、会計業務に慣れていない方でも仕訳を登録できます。
仕訳を登録するたびにAIが学習するので、徐々に仕訳の精度が向上します。

会計業務はもちろん、請求書発行、経費精算、証憑管理業務もできる!
「弥生会計 Next」では、請求書作成ソフト・経費精算ソフト・証憑管理ソフトがセットで利用できます。自動的にデータが連携されるため、バックオフィス業務を幅広く効率化できます。

自動集計されるレポートで経営状態をリアルタイムに把握!
例えば、見たい数字をすぐに見られる残高試算表では、自社の財務状況を確認できます。集計期間や金額の累計・推移の切りかえもかんたんです。
会社全体だけでなく、部門別会計もできるので、経営の意思決定に役立ちます。

「弥生会計 Next」で、会計業務を「できるだけやりたくないもの」から「事業を成長させるうえで欠かせないもの」へ。まずは、「弥生会計 Next」をぜひお試しください。
会計・経費・請求、誰でもカンタンまとめて効率化!法人向けクラウド会計ソフト「弥生会計 Next」
しっかり予実管理をして経営目標達成につなげよう
予実管理は、迅速な経営判断や改善に欠かせない重要なプロセスです。定期的かつ継続的に予実管理を行うことで、目標達成に向けた具体的な対策が立てやすくなります。
予実管理を行うには、設定した予算に対して、実績がどの程度なのかをタイムリーに把握する必要があります。そのようなとき、日々の取引を記録・管理する会計ソフトの活用が効果的です。会計ソフトで帳簿をつけていれば、売上や費用の状況をその都度確認できるようになります。「弥生会計 Next」などの会計ソフトを導入して予実管理に活用し、経営目標の達成に役立てましょう。
会計・経費・請求、誰でもカンタンまとめて効率化!法人向けクラウド会計ソフト「弥生会計 Next」
よくあるご質問
予実管理とは?
予実管理とは企業の予算と実績を管理することで、予算実績管理とも呼ばれます。予実管理を行うと予算に対してどの程度の実績を上げているのかを把握でき、自社の状況を定量的に分析できるようになります。詳しくはこちらをご確認ください。
予実管理と予算管理の違いとは?
予実管理は、予算管理のプロセスに含まれる業務の1つです。予算管理とは、一般的に「年度ごとに策定する企業の予算計画」を指す言葉です。過去の売上や市場の動向などにもとづき予算計画を立て、その計画と期末の実績を比較・分析します。詳しくはこちらをご確認ください。
予実管理の手順は?
まず予算目標を立て、月次決算を行います。月次決算を行うことで予算と実績の乖離が発見しやすくなり、予実管理の精度を高めることができます。その上で予算と実績を比較し、目標とする営業利益と実際の利益に差がある場合は要因を分析し、軌道修正をします。詳しくはこちらをご確認ください。
会計・経費・請求、誰でもカンタンまとめて効率化!法人向けクラウド会計ソフト「弥生会計 Next」
【無料】お役立ち資料ダウンロード
「弥生会計 Next」がよくわかる資料
「弥生会計 Next」のメリットや機能、サポート内容やプラン等を解説!導入を検討している方におすすめ

この記事の監修者小林祐士(税理士法人フォース)
東京都町田市にある東京税理士会法人登録NO.1
税理士法人フォース 代表社員
お客様にとって必要な税理士とはどのようなものか。私たちは、事業者様のちょっとした疑問点や困りごと、相談事などに真剣に耳を傾け、AIなどの機械化では生み出せない安心感と信頼感を生み出し、関与させていただく事業者様の事業発展の「ちから=フォース」になる。これが私たちの法人が追い求める姿です。