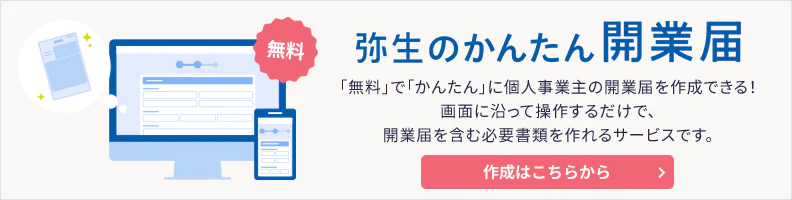個人事業主・自営業・フリーランスの違いは?定義や税金について解説
監修者: 森 健太郎(税理士)
更新
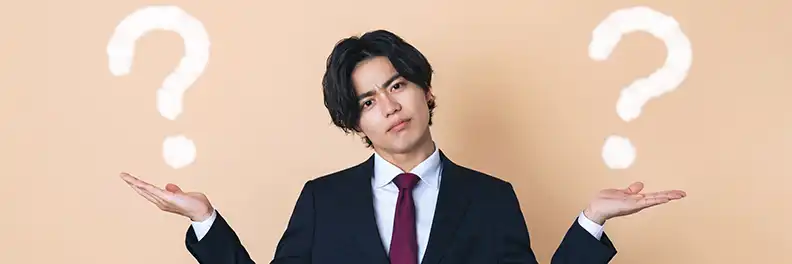
企業や公共団体などに所属せず、自分で事業を行う人を指す言葉には、「個人事業主」「自営業」「フリーランス」と、いくつかの種類があります。独立して自分で事業をしたいと考えたとき、それぞれの言葉にどのような違いがあるか、はっきりとはわからない方も多いのではないでしょうか。
また、事業を始めるには、個人で開業するだけでなく、自分で会社を設立して起業する方法もあります。起業する際には、それぞれのスタイルの違いや、メリット・デメリットをしっかりと把握しておくことが大切です。
本記事では、個人事業主・自営業・フリーランスの違いや、それぞれのメリット・デメリット、開業に必要な手続きなどについて解説します。
【利用料0円】はじめてでもカンタン・安心な「開業届」の作成はこちらをクリック
個人事業主・自営業・フリーランスの違い
個人事業主や自営業、フリーランスとは、いずれも自分で事業を行う人のことを指す言葉ではありますが、それぞれの定義として、以下のような違いがあります。
- 個人事業主・自営業・フリーランスの定義
-
- 個人事業主:独立して事業を行う個人を指す税法上の区分
- 自営業:独立して事業を行う人を指す一般的な名称。個人だけでなく、法人を設立している経営者も含む
- フリーランス:組織に所属せず個人で仕事をする働き方
個人事業主と自営業では、独立して事業を営んでいるという点では同じです。しかし、個人事業主はその名のとおり個人事業を行う人のみを指すのに対して、自営業は個人以外に法人を設立した会社経営者も含まれる点が異なります。
その一方で、個人事業主とフリーランスでは、個人で仕事を請け負うという点では同じです。しかし、個人事業主は税法上の区分であるのに対し、フリーランスは組織に所属しないという働き方である点に違いがあります。
それぞれの関係性を整理すると、大きく自営業とフリーランスに分けられ、そのうち個人事業で開業している人が個人事業主、ということになります。
それでは、個人事業主と自営業、フリーランスという属性や、それぞれのメリット・デメリットについて詳しく見ていきましょう。
【利用料0円】はじめてでもカンタン・安心な「開業届」の作成はこちらをクリック
個人事業主は個人で事業を行う税法上の区分
個人事業主とは個人で事業を行っている人を指す税法上の区分のことで、個人で事業を行うために「個人事業の開業・廃業等届出書(以下、開業届)」を提出している人を、税法上「個人事業主」と言います。自分1人だけで事業を行う場合をはじめ、家族や従業員などと複数人で事業を行う場合も、法人でなければ個人事業主です。
個人事業主の例としては、「1人で作品を制作するイラストレーター」「店員を雇ったり、家族で経営している飲食店の事業主」「顧問先の会計処理を代行したり、税務相談や決算処理のほか、確定申告書を作成したりする税理士」などがあげられます。
個人事業主のメリット
個人事業主には、以下のようなメリットがあります。
- 個人事業主のメリット
-
- 節税効果の高い青色申告を選択できる
- 事業に関連する費用を経費に計上できる
個人事業主は、開業届に加えて、「所得税の青色申告承認申請書(以下、青色申告承認申請書)」も提出すると、確定申告で青色申告を選べることがメリットです。青色申告には、所定の要件を満たせば最大65万円の青色申告特別控除を適用できる、赤字を3年間繰り越せるなど、さまざまな節税対策ができます。
また、個人事業主は、売上から必要経費を引いた所得を基に税金を計算されるため、公私で兼用していれば、自宅の家賃や光熱費、携帯電話代なども、按分(事業で使用した割合を計算して配分すること)して経費計上できることも個人事業主のメリットです。
個人事業主のデメリット
個人事業主には、以下のようなデメリットもあります。
- 個人事業主のデメリット
-
- 自分で会計処理や確定申告を行う必要がある
- 社会保険料を全額負担しなければならない
個人事業主になると、1年間の所得から納めるべき所得税額を計算し、自分で確定申告をしなければならないことがデメリットです。さらに、前述した青色申告特別控除などのメリットを得るためには、複雑な記帳方法である複式簿記で記帳しなければなりません。
会社員であれば、会社が税金を計算して、給与からの天引きや年末調整をしてくれますが、個人事業主は会計処理・確定申告をすべて自分で行うことになります。
また、会社員のような社会保険(健康保険・厚生年金保険)ではなく、国民健康保険や国民年金に加入しなければならないことも個人事業主のデメリットです。社会保険は会社が保険料の半額を負担してくれますが、国民健康保険や国民年金の保険料は、全額を自分で支払わなければなりません。
【利用料0円】はじめてでもカンタン・安心な「開業届」の作成はこちらをクリック
自営業とは独立して自分で事業を営む個人や小規模法人
自営業とは、独立して自分で事業を営んでいる人のことです。また、個人だけでなく、自分で設立して経営している小規模法人も自営業の中に入ります。
ただし、会社経営者で自営業と呼ばれるのは、基本的に、自ら会社を設立した人のことです。会社内で昇進して社長になったような場合は自営業とは呼ばず、「会社役員」などと言われることが一般的と言えます。
例えば、店舗を運営している人の場合、個人経営であっても法人化していても、自営業と呼ばれるケースが多いでしょう。
自営業のメリット
自営業として、以下のようなメリットがあげられます。
- 自営業のメリット
-
- 自分の好きなことやアイデアを仕事にできる
- 収入や年齢の上限がない
自営業のメリットは、何よりも自分の好きなことやアイデアをそのまま事業にできる点にあります。会社員のように組織の方針に縛られることなく、自分が本当にやりたいことを仕事として形にできるため、働くこと自体が大きなやりがいにつながるでしょう。
また、働くうえで収入や年齢に上限が設けられていないことも自営業のメリットです。業績を上げればその分だけ収入を伸ばすことが可能で、定年退職という概念もなく、自分のペースで長く働き続けられます。
自営業のデメリット
自営業のデメリットには、以下のようなことが考えられます。
- 自営業のデメリット
-
- 病気やケガなどで働けなくなったときの保障がない
- 事業に関する責任を負う
自営業の場合、病気やケガなどで働けなくなったときに、会社員のような休業補償や傷病手当金といった制度的な保障がほとんどないことがデメリットです。仕事ができず収入が途絶えると、生活や事業の継続に直結するため、常に健康管理やリスクへの備えに注意を払う必要があります。
さらに、自営業は、事業に関わるすべての責任を自ら負うこともデメリットの1つです。売上や資金繰りの不調はもちろん、顧客や取引先とのトラブルも、すべて自己責任で解決しなければなりません。
【利用料0円】はじめてでもカンタン・安心な「開業届」の作成はこちらをクリック
フリーランスとは企業に所属せず個人で仕事を請け負う働き方
フリーランスとは、企業や特定の団体に所属せず、個人で仕事を請け負う働き方のことです。一般的に、フリーランスは、単発の仕事ごとに契約を結び、案件ごとに業務を行います。
ただ、フリーランスという呼び方に法的な根拠がないため、定義もさまざまと言えるでしょう。
例えば、政府が策定した「フリーランスとして安心して働ける環境を整備するためのガイドライン」では、フリーランスを「実店舗がなく、雇人もいない自営業主や一人社長であって、自身の経験や知識、スキルを活用して収入を得る者」と定義しています。
例えば、フリーランスとして働いている人が開業届を提出すれば、税法上は個人事業主です。
また、開業届を提出していなくても、スキルを活用して1人で仕事をしている人はフリーランスと呼ばれます。なお、会社員であっても、副業が許可されている企業に勤務していれば、副業でフリーランスとして働くことは可能です。
フリーランスのメリット
フリーランスのメリットには、以下があげられます。
- フリーランスのメリット
-
- 働き方の自由度が高い
- スキル次第で高収入を目指せる
フリーランスは、働く場所や時間、休日、ペース配分などを、自分でコントロールできることがメリットです。就労場所や勤務時間などが定められている会社員とは違い、依頼された業務さえやり遂げれば、どのように仕事を進めても問題ありません。そもそも仕事を受けるかどうかも自由です。
また、自分のスキル次第で高収入を目指せることも、フリーランスのメリットです。会社員の場合は月々の給与額がある程度決まっていますが、フリーランスは自分の行動が収入に直結します。スキルを磨き、高い成果を上げれば、その分収入を増やすことも可能です。
フリーランスのデメリット
フリーランスは、以下がデメリットと言えるでしょう。
- フリーランスのデメリット
-
- 収入が不安定になりやすい
- 事業規模や社会的な信用力が小さい
成果にかかわらず一定額の給与が支給される会社員とは異なり、フリーランスは仕事をしなければ収入を得られないことがデメリットです。案件ごとに報酬額が決まるため、収入の波が大きくなりやすくなります。
また、個人で仕事を請け負うフリーランスは、法人や会社員に比べて社会的な信用度が低いこともデメリットです。さらに、フリーランスは個人で対応できる範囲しか仕事を受けられないため、おのずと事業規模も小さくなってしまいます。
【利用料0円】はじめてでもカンタン・安心な「開業届」の作成はこちらをクリック
フリーランスから個人事業主に切り替えるタイミングは?
フリーランスとして事業を始めるなら、事業の開始1年目から、個人事業主に切り替えたほうがよいと言えます。
前述のように、フリーランスとして働いている人は、開業届を提出することで、税法上は個人事業主となります。個人事業主になって青色申告承認申請書も併せて提出すると、確定申告をする際に青色申告ができるようになります。
確定申告をする個人事業主のうち、青色申告承認申請書の提出や複式簿記での記帳といった所定の要件を満たしている場合には、青色申告が可能です。それ以外の所定の要件を満たしていない個人事業主は、白色申告しか選択できません。フリーランスで事業所得が少なかったり赤字だったりする場合、青色申告できなくても白色申告でよいと考える方もいるかもしれません。
しかし、最大65万円の特別控除を受けられたり、赤字を3年間繰り越せたりするなど、青色申告にはさまざまな節税メリットがあります。知識がないと難しそうな複式簿記による記帳も、確定申告ソフトなどを使えば簡単です。
そのため、フリーランスとして個人で事業を行うのであれば、事業所得の金額にかかわらず、青色申告をすることをおすすめします。フリーランスで個人事業を始める際は、青色申告するためには必須となる、開業届と青色承認申請書を提出して、個人事業主になっておくとよいでしょう。
フリーランスが開業届を提出すべきかどうかについては以下の記事を併せてご覧ください。
【利用料0円】はじめてでもカンタン・安心な「開業届」の作成はこちらをクリック
個人事業主・自営業・フリーランスに課せられる税金
個人事業主や自営業、フリーランスとして働く方の税金は、個人で行う事業の所得などを基に計算されます。個人事業主や自営業、フリーランスに課せられる主な税金は、以下のとおりです。
- 個人事業主・自営業・フリーランスに課される主な税金
-
- 所得税
- 個人住民税
- 個人事業税
- 消費税
所得税
所得税とは、個人が事業で得た所得にかかる国税です。1月1日から12月31日までの1年間の収入から、必要経費を引いた所得に対して、所定の税率を掛けて算出されます。
個人住民税
個人住民税とは、暮らしている地方自治体に納める地方税です。大きく分けると、自治体ごとに定められている均等割と、所得に応じて課税される所得割から構成されています。
個人事業税
個人事業税とは、法律で定められた業種(法定業種)の人が、事務所や事業所のある都道府県に納付する地方税です。課税の有無や税率は業種によって決まります。なお、法定業種に該当しても、所得が290万円以下である場合は課税されません。
消費税
消費税は、商品やサービスなどの取引に対して課税される税金です。国税である「消費税」と地方税である「地方消費税」の2つを総称して、消費税(税法上は消費税等)と呼びます。
基準期間(前々年)や特定期間(前年の1月1日~6月30日)の課税売上高が1,000万円を超えるなど、所定の要件を満たした場合は課税事業者となり、消費税の納付義務が生じます。
なお、適格請求書等保存方式(インボイス制度)に対応するために適格請求書発行事業者の登録を受けた場合には、課税売上高にかかわらず課税事業者となる点に注意しましょう。
【利用料0円】はじめてでもカンタン・安心な「開業届」の作成はこちらをクリック
個人事業主・自営業・フリーランスが加入できる社会保障
個人事業主や自営業、フリーランスとして働く方には、会社員・公務員とは適用される社会保障制度が異なります。そのため、会社員や公務員を辞めて個人事業主となる場合には、それまで加入していた社会保険(健康保険・厚生年金保険)から、国民健康保険と国民年金への切り替え手続きが必要です。
個人事業主でも常時5人以上の従業員を雇用する場合には、事業所として社会保険へ加入しなければならない場合が多いですが、事業主本人は加入できません。なお、国民年金は、厚生年金に比べて、将来的に受け取る年金受給額が少ないため、iDeco(個人型確定拠出年金)や国民年金基金、小規模企業共済など、年金の受給額不足を補う方法を検討するとよいでしょう。
ただし、自営業であっても法人を設立した方は、事業主自身も社会保険に加入できます。
【利用料0円】はじめてでもカンタン・安心な「開業届」の作成はこちらをクリック
個人事業主として開業するために必要なもの
個人事業主として開業する際には、以下が必要になります。
- 開業のために必要なもの
-
- 開業届や青色申告承認申請書などの提出書類
- マイナンバーカードまたは本人確認書類
個人事業主の開業にあたって、開業届などの提出書類やマイナンバーがわかる本人確認書類が必要です。マイナンバーカードがない場合には、通知カードやマイナンバーの記載がある住民票などの「番号確認書類」と、運転免許証、パスポートなどの「身元確認書類」の両方が必要です。
また、個人事業の開業後は、自分で帳簿を付け、毎年確定申告を行わなければなりません。事業を開始してから慌てずに済むように、開業のタイミングで確定申告ソフトを導入しておくと安心です。
開業届の提出に必要なものについては以下の記事を併せてご覧ください。
【利用料0円】はじめてでもカンタン・安心な「開業届」の作成はこちらをクリック
個人事業主として開業する際に必要な手続き
個人事業主として開業するには、所定の手続きを行わなければなりません。ここからは、個人事業主として開業する際に必要な手続きを、ステップに沿って紹介します。
- 個人事業主が開業する際に必要な手続き
-
-
STEP1.開業届と事業開始等申告書の提出
-
STEP2.開業届と併せて提出するほうがよい書類がある場合には提出する
-
STEP3.国民健康保険・国民年金に切り替える
-
STEP1. 開業届と事業開始等申告書の提出
個人事業主として開業する場合は、開業届を、所轄の税務署へ提出する必要があります。提出期限は、開業から1か月以内です。
また、併せて、「事業開始等申告書」も各自治体に提出しなければなりません。事業開始等申告書は、都道府県に個人事業の開始を知らせる書類で、自治体によって、「個人事業開業届出書」や「事業開始届」などと呼ばれることもあります。提出先は基本的に都道府県税事務所ですが、市区町村への提出が必要な場合もあるので、提出期限と提出先を各自治体のWebページで確認してください。
そのほか、業種によっては、開業にあたって許認可申請も必要です。許認可の手続き窓口は種類によって異なるため、事前に確認しておきましょう。
開業届や許認可については以下の記事を併せてご覧ください。
STEP2. 開業届と併せて提出するほうがよい書類も提出する
開業する際には、開業届と併せて提出しておいた方がよい書類があります。何度も税務署へ足を運んだり郵送したりするのは手間がかかるため、以下の表を確認し、どのような場合に提出が必要になるのかも把握しておきましょう。
開業届と併せて提出しておくとよい書類
| 書類名 | 必要なケース | 提出期限 | 提出先 |
|---|---|---|---|
|
所得税の青色申告承認申請書 |
確定申告で青色申告を行う場合 | 青色申告をしようとする年の3月15日まで(その年の1月16日以後に開業した場合は開業日から2か月以内) | 税務署 |
| 青色事業専従者給与に関する届出・変更届出書 |
青色事業専従者の要件を満たす家族従業員への給与を経費にしたい場合 | 青色事業専従者給与額を必要経費に算入しようとする年の3月15日まで(その年の1月16日以後に開業した場合や、新たに専従者を雇用することになった場合は、開業または雇用した日から2か月以内) | 税務署 |
| 給与支払事務所等の開設・移転・廃止届出書 |
従業員を雇う場合 | 事務所の開設日から1か月以内 | 税務署 |
| 適格請求書発行事業者の登録申請書 |
インボイス制度に対応するために適格請求書発行事業者になりたい場合 | 登録希望日の15日前まで | 税務署 |
| 源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請書 |
従業員数が10名未満で、源泉所得税の納付を年2回にまとめたい場合 | 期限の定めなし(原則として、提出した日の翌月に支払う給与等から適用) | 税務署 |
STEP3. 国民健康保険・国民年金に切り替える
会社を退職して個人事業主になる場合は、社会保険(健康保険・厚生年金保険)から、国民健康保険・国民年金への切り替え手続きが必要です。退職日の翌日から14日以内に、居住地の市区町村役場で手続きをしましょう。
なお、健康保険については、所定の要件を満たせば最長2年間の任意継続が可能です。任意継続を希望する場合は、退職日の翌日から20日以内に加入する健康保険(協会けんぽや健康保険組合)で手続きをしてください。
個人事業主の社会保険や開業時にやることについては以下の記事・動画を併せてご覧ください。
【利用料0円】はじめてでもカンタン・安心な「開業届」の作成はこちらをクリック
個人事業主の開業や青色申告を手軽にする方法
個人事業主として開業するには、開業届の提出をはじめ、さまざまな手続きが必要です。開業準備で忙しい中、必要書類をすべて自分で準備するのは大変です。個人事業主の開業手続きを手軽に行いたい場合は「弥生のかんたん開業届」がおすすめです。
「弥生のかんたん開業届」は、画面の案内に沿って必要事項を入力するだけで、個人事業主の開業時に必要な書類を自動生成できる無料のクラウドサービスです。パソコンでもスマホでも利用でき、開業届や青色申告承認申請書など、開業時に提出が必要な書類をスムーズに作成することができます。
また、開業後は、日々の帳簿付けや毎年の確定申告が必要になります。事業が本格的に動き出してから慌てることのないよう、開業のタイミングで会計ソフトや確定申告ソフトを導入しておきましょう。クラウド確定申告ソフト「やよいの青色申告 オンライン」なら、簿記や会計の知識がなくても、最大65万円の青色申告特別控除の要件を満たした、青色申告に必要な書類がかんたんに作成できます。
【利用料0円】はじめてでもカンタン・安心な「開業届」の作成はこちらをクリック
独立するなら開業形態をよく検討しよう
個人事業主や自営業、フリーランスは、いずれも自分で事業を行う人を指す言葉ですが、事業を営む主体や働き方などに違いがあります。中でも、開業手続きや税金のしくみなどに影響するのは、個人事業主か法人を設立するかという点です。
自営業やフリーランスといった言葉に惑わされず、個人事業主としてスタートするか、それとも法人を設立するかをよく検討するようにしてください。会社員の場合は、まず副業で個人事業主になり、事業が軌道に乗ってから独立するのも1つの方法です。
また、個人事業主の開業手続きをスムーズにすすめるには、「弥生のかんたん開業届」の利用がおすすめです。さらに、開業後に確定申告を行う際は、「やよいの青色申告 オンライン」を使えば、簿記や経理の知識がなくてもスムーズに青色申告できます。独立すると会計処理の手間が増えるので、開業準備の段階から会計ソフトの導入も進めておきましょう。
【利用料0円】はじめてでもカンタン・安心な「開業届」の作成はこちらをクリック
よくあるご質問
個人事業主と自営業の違いは?
個人事業主とは、独立して継続的に事業を行っている個人を指す税法上の区分です。個人で事業を行うために開業届を提出している人のことを、税法上、個人事業主と言います。
それに対して、自営業は、独立して自分で事業を営んでいる個人だけでなく、自分で設立して経営している小規模法人も自営業に含まれる点が個人事業主とは異なります。
個人事業主・自営業・フリーランスの違いについては、詳しくはこちらをご確認ください。
個人事業主のメリット・デメリットは?
個人事業主の大きなメリットは、確定申告をする際に、節税効果の高い青色申告を選択できることです。青色申告には、所定の要件を満たせば最大65万円の青色申告特別控除を適用できる、赤字を3年間繰り越せるなど、さまざまな節税メリットがあります。
その一方で、個人事業主になると自分で会計処理や確定申告を行わなければならず、経理作業の手間がかかります。加えて、会社員のような労使折半の社会保険に加入できず、国民健康保険や国民年金の保険料を全額自分で負担しなければならないというデメリットもあります。
個人事業主のメリット・デメリットについては、詳しくはこちらをご確認ください。
個人事業主として開業する際に必要な手続きは?
個人事業主として開業するためには、開業届と事業開始等申告書を税務署へ提出する必要があります。その際に、青色申告承認申請書などの書類についても、必要に応じて提出します。
さらに、会社を退職して個人事業主になる場合は、社会保険から、国民健康保険・国民年金への切り替え手続きも必要です。
個人事業主として開業する際に必要な手続きについては、詳しくはこちらをご確認ください。
【利用料0円】はじめてでもカンタン・安心な「開業届」の作成はこちらをクリック
この記事の監修者森 健太郎(税理士)
ベンチャーサポート税理士法人 代表税理士。
毎年1,000件超、累計23,000社超の会社設立をサポートする、日本最大級の起業家支援士業グループ「ベンチャーサポートグループ」に所属。
起業相談から会社設立、許認可、融資、助成金、会計、労務まであらゆる起業の相談にワンストップで対応します。起業・会社設立に役立つYouTubeチャンネル会社設立サポートチャンネルを運営。