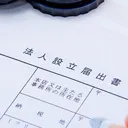新設法人はインボイスを発行できる?課税業者のなり方や消費税免除要件も解説
監修者: 森 健太郎(税理士)
更新
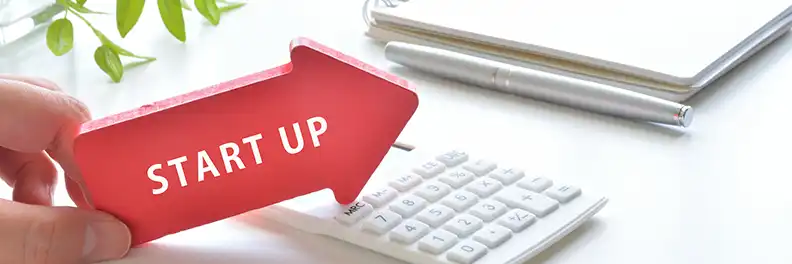
新設法人とは、言葉どおりに捉えれば、新たに設立された法人という意味です。しかし、消費税法における新設法人は定義が異なるため、注意が必要です。
会社を設立したとき、消費税の申告・納付義務が生じるかどうかは、消費税法上の新設法人に該当するかどうか、また、1期目から適格請求書等保存形式(インボイス制度)に対応するかどうかによって異なります。さらに、会社設立時から適格請求書(インボイス)を発行するためには、所定の手続きを行わなければなりません。
では、どのような場合に消費税法上の新設法人に該当し、会社設立時からインボイス制度に対応するにはどのような手続きが必要なのでしょうか。
本記事では、一般的な新設法人と消費税法上の新設法人の違い、会社設立時からインボイスを発行するために必要な手続きのほか、会社設立と同時に適格請求書発行事業者として登録するメリットや注意点についても解説します。
法人設立ワンストップサービスを利用して、オンラインで登記申請も可能。
個人事業主から法人成りを予定している方にもおすすめです。

【無料】はじめてでもカンタン・安心な「会社設立」の書類作成はこちらをクリック
新設法人は会社設立時からインボイス(適格請求書)を発行できる
新設法人は、会社設立時からインボイスを発行することが可能です。
ただし、設立1期目からインボイスを発行するためには、所定の手続きをする必要があります。さらに、新たに設立した会社が消費税法上の新設法人に該当するかによって、インボイスを発行するために必要な手続きが変わってきます。
インボイスの発行にあたっては、消費税法上の新設法人やインボイス制度について正しく知っておくことが重要です。
消費税法上の新設法人とは、基準期間がなく資本金や出資金が1,000万円以上の法人のこと
消費税法上の新設法人とは、消費税法によって定められた「基準期間がない事業年度の開始の日における、資本金の額または出資の金額が1,000万円以上である法人」のことです。
法人の基準期間とは、前々事業年度を指します。新たに設立された法人は前々事業年度が存在しないため、設立時点の資本金または出資金の額が1,000万円以上の場合は、消費税法上の新設法人に該当するということになります。
消費税法により、基準期間の課税売上高が1,000万円以下の事業者は、原則として、消費税の納税義務が免除されます。つまり、新しく会社を設立した場合は、設立2期目まで消費税の納税義務が免除されるということです。
しかし、資本金または出資金の額が1,000万円以上の消費税法上の新設法人は、この免税が適用されず、設立1期目から消費税の納税義務が生じます。
このように消費税法上の新設法人には要件があり、一般的な新設法人と混同してしまう可能性があるため、本記事では、日本語の意味としての新設法人を「新設法人」、消費税法における新設法人を「消費税法上の新設法人」として解説しています。
インボイス制度とは事業者が消費税を適正に納める制度
インボイス制度とは、2023年10月1日より開始された、事業者が消費税を正しく納めるための制度です。正式名称を「適格請求書等保存方式」といいます。インボイス制度によって、課税事業者(消費税の申告・納付義務のある事業者)が仕入税額控除を適用するためには、原則としてインボイスの保存が必要になります。
仕入税額控除とは、課税事業者が消費税の納税額を計算するときに、売上にかかった消費税額から、仕入や経費にかかる消費税額を差し引くことです。課税事業者は商品やサービスを販売するにあたり、消費者から預かった消費税を国に納めますが、事業者自身も仕入などの際には消費税を支払っています。預かった消費税額から既に支払った消費税額を控除し、二重課税を防ぐしくみが仕入税額控除です。
この仕入税額控除の適用要件の1つが、売手(仕入先)が発行したインボイスの保存です。インボイスには記載項目の定めがあり、登録番号を持つ適格請求書発行事業者しか発行できません。そして、適格請求書発行事業者に登録できるのは、消費税の課税事業者だけです。
仕入先や経費の支払先が免税事業者だったり、適格請求書発行事業者の登録をしていなかったりすると、インボイスが発行されないため、原則として、仕入税額控除を適用できません。そのため、新たに設立した会社でインボイスを発行できないと、取引先が課税事業者だった場合、取引先の税負担を増加させてしまう可能性があります。
【無料】はじめてでもカンタン・安心な「会社設立」の書類作成はこちらをクリック
会社設立時からインボイスを発行するための手続き
会社設立時からインボイスを発行できるようにするためには、所定の手続きが必要です。具体的な手続き内容は、設立した会社が、消費税法上の新設法人に該当するかどうかによって異なります。
消費税法上の新設法人(資本金などの金額が1,000万円以上)に該当し、課税事業者になる場合
設立した会社の資本金または出資金の額が1,000万円以上で、消費税法上の新設法人に該当する場合は、設立初年度から課税事業者となります。
消費税法上の新設法人に該当する場合は、インボイス発行の有無にかかわらず、速やかに「消費税の新設法人に該当する旨の届出書」を管轄の税務署へ提出しなければなりません。
ただし、設立日から2か月以内に税務署へ提出する「法人設立届出書」の、「消費税の新設法人に該当することとなった事業年度開始の日」の欄に設立年月日を記載しておけば、「消費税の新設法人に該当する旨の届出書
」の提出は省略できます。
会社設立時からインボイスを発行したい場合は、さらに、適格請求書発行事業者の登録手続きも必要です。適格請求書発行事業者の登録をするには、設立した事業年度中に、「適格請求書発行事業者の登録申請書」を管轄のインボイス登録センターに郵送するか、e-Taxで提出します。
消費税法上の新設法人に該当せず(資本金などの金額が1,000万円未満)、免税事業者になる場合
資本金または出資金の額が1,000万円未満で、消費税法上の新設法人に該当しない会社は、設立時点では免税事業者です。
この場合は、まず課税事業者にならなければ、適格請求書発行事業者の登録ができません。そのため、基本的には、設立事業年度中に「消費税課税事業者選択届出書」を管轄の税務署へ提出して課税事業者になり、そのうえで「適格請求書発行事業者の登録申請書
」を提出する必要があります。
ただし、2029年9月30日までに限り、免税事業者は「適格請求書発行事業者の登録申請書」を提出すれば自動的に課税事業者となるため、「消費税課税事業者選択届出書
」を別途提出する必要はありません。
【無料】はじめてでもカンタン・安心な「会社設立」の書類作成はこちらをクリック
インボイスを発行できる課税事業者になるメリット
前述したように、適格請求書発行事業者の登録ができるのは、課税事業者のみです。そのため、消費税法上の新設法人に該当せず、会社設立時点では免税事業者であっても、インボイスを発行するためには課税事業者にならなければなりません。
インボイスを発行できる課税事業者になると、買い手(取引先)が仕入税額控除を利用できるため、取引継続において有利に働く可能性があります。
課税事業者にとって、インボイスを発行できない免税事業者との取引は、仕入税額控除が適用されないため税負担が増えてしまいます。インボイスを発行できれば、既存の取引の維持に役立つだけでなく、新たな取引先の獲得や、大手企業とのビジネスチャンスにもつながるかもしれません。
また、インボイスには消費税率ごとの消費税額や、商品ごとの消費税率などを明記するため、自社の取引にかかる消費税額を正確に把握しやすいというメリットもあります。会計処理の透明性が高まり、税務申告業務の精度も向上するでしょう。
さらに、課税事業者になると、状況によっては消費税の還付を受けられる場合があります。例えば、輸出取引のように売上は免税であるにもかかわらず、仕入や経費には消費税がかかるケースでは、その差額について還付を受けることが可能です。
【無料】はじめてでもカンタン・安心な「会社設立」の書類作成はこちらをクリック
インボイスを発行できる課税事業者になるデメリット
メリットがある一方で、インボイス発行できる課税事業者となることには、いくつかのデメリットも存在します。
中でも大きなデメリットといえるのが、消費税の納税義務が発生することです。インボイスを発行するために免税事業者が課税事業者になると、それまで免除されていた消費税の納税義務が課せられ、税負担が大きくなります。
また、課税事業者になった場合、消費税の計算・申告・納付を行う必要があり、経理処理が煩雑になります。例えば、売上や仕入にかかる消費税額、税率ごとの区分、インボイスの保存、帳簿の整備など、事務作業の負担は免税事業者に比べて格段に増加するでしょう。
【無料】はじめてでもカンタン・安心な「会社設立」の書類作成はこちらをクリック
法人の設立後2期目まで消費税が免除となる要件
原則として、基準期間の課税売上高が1,000万円以下の新設法人は、消費税の納税義務が免除されます。
法人の基準期間は前々事業年度を指すため、新設法人は設立2期目まで基準期間が存在しません。そのため、会社を設立すると、原則として2期目まで消費税が免税となるしくみです。
ただし、新設法人が設立2期目まで消費税免除となるには、以下のような要件を満たす必要があります。
設立1期目の消費税が免除となる要件
設立初年度に免税事業者になるのは、以下の2つの要件を満たした場合です。
資本金または出資金が1,000万円未満
消費税の納税義務が免除される要件の1つが、資本金または出資金が1,000万円未満、つまり消費税法上の新設法人ではないことです。この出資金または資本金の額は、事業年度の開始の日を基準として判断されます。
例えば、会社設立日(1期目の開始日)の資本金が1,000万円未満であれば、1期目の消費税は免除です。
なお、3期目以降は、基準期間(前々事業年度)または特定期間(前事業年度開始の日以後6か月の期間)における課税売上高によって、消費税の納税義務の有無が決まります。
特定新規設立法人に該当しない
特定新規設立法人に該当しない法人であることも、消費税が免除になる要件の1つです。たとえ資本金または出資金の額が1,000万円未満でも、新設法人が特定新規設立法人に該当する場合には、設立1期目から消費税の納税義務が発生します。
特定新規設立法人と判定される要件は、以下のとおりです。
特定新規設立法人と判定される要件
- 他の者が株式等の50%超を直接または間接に保有しているなど、その新しく設立された法人が支配される一定の条件に該当する
- 上記の他の者および他の者と一定の特殊な関係にある法人(特殊関係法人)のどちらかが、新規に設立する法人の基準期間に相当する期間における課税売上高が5億円を超えている
設立後2期目まで消費税が免除となる要件
上記2つの要件に加えて、以下のいずれかの要件を満たした場合、新設法人は設立後2期目まで消費税が免除されます。
特定期間の課税売上高が1,000万円以下
設立後2期目まで消費税が免除されるには、特定期間、つまり設立1期目が開始してから6か月間の課税売上高が1,000万円以下である必要があります。
消費税の納税義務があるのは、基準期間または特定期間の課税売上高が1,000万円を超える事業者です。
設立1期目は、基準期間も特定期間も存在しないので、前述した2つの要件を満たせば売上高にかかわらず免税となります。しかし、1期目開始から6か月間の課税売上高が1,000万円を超えた場合には、2期目から消費税の納税義務が生じます。
特定期間の給与等支払額の合計額が1,000万円以下
特定期間における「1,000万円以下」の要件は、課税売上高に代えて、給与等支払額の合計額によって判定することもできます。例えば、特定期間の課税売上高が1,000万円を超えても、給与等支払額の合計額が1,000万円以下であれば、1期目に引き続き2期目も消費税の免税が可能です。
消費税の免除要件については以下の記事も併せてご覧ください。
【無料】はじめてでもカンタン・安心な「会社設立」の書類作成はこちらをクリック
会社設立時にインボイス制度に対応する際に注意すべき点
自社の業種や取引先の状況などから、会社設立時に適格請求書発行事業者になろうと考えている方も多いかもしれません。適格請求書発行事業者に登録するということは、必然的に課税事業者になるということです。
会社設立と同時にインボイス制度に対応する場合は、以下の点に注意が必要です。
インボイス制度に対応する際の注意点
- 免税事業者から課税事業者に変更する場合は2割特例を利用できる
- インボイスの登録番号は個人から法人に引き継がれない
- 課税事業者となる場合のメリットとデメリットをよく検討する
免税事業者から課税事業者に変更する場合は2割特例を利用できる
「2割特例(インボイス発行事業者となる小規模事業者に対する負担軽減措置)」とは、納める消費税額を売上税額の2割分に負担を軽減させる措置のことで、インボイス制度を機に課税事業者になる免税事業者のみに適用できます。
新設法人は、資本金または出資金が1,000万円以上にならなければ、ほとんどが免税事業者としてのスタートです。そのため、新設法人が課税事業者になるために登録をすると、「インボイス制度を機に免税事業者から課税事業者になった」と税務署に見なされるため、2割特例の適用が可能です。
なお、2割特例の適用にあたっては、事前の届出は必要なく、消費税の申告時に消費税の確定申告書に2割特例の適用を受ける旨を記載しておくことで適用を受けることができます。
ただし、この2割特例を適用できるのは、2026年9月30日までの課税期間となります。
インボイスの登録番号は個人から法人に引き継がれない
課税事業者の判定やインボイス番号の登録は事業者単位で行われるため、適格請求書発行事業者だった個人事業主が法人成りしても、新設法人にインボイスの登録番号が引き継がれることはありません。
同様に、課税事業者である個人事業主が法人成りした場合も、資本金などの金額が1,000万円未満であれば、新規設立の法人は免税事業者となります。
法人成り後も引き続きインボイス制度に対応したい場合は、会社設立後に、改めて適格請求書発行事業者の登録手続きを行う必要があります。
課税事業者となる場合のメリットとデメリットをよく検討する
課税事業者になるか、免税事業者のままでいるかは、自社の事業や取引先の状況などによって異なるため、よく検討したほうがよいでしょう。
会社設立時から適格請求書発行事業者になると、設立1期目から消費税の納税義務が生じます。その一方で、適格請求書発行事業者の登録をしなければ、新設法人は原則として設立2期目まで消費税が免税可能です。
免税事業者のままでは、取引先が課税事業者であれば取引の継続が難しくなる可能性もありますが、インボイスの発行を求められない一般消費者相手の業種であれば、大きな問題はないかもしれません。
インボイス制度が今後の取引にどのような影響があるかをよく検討したうえで、会社設立時から課税事業者になるかどうかを決めるようにしてください。
【無料】はじめてでもカンタン・安心な「会社設立」の書類作成はこちらをクリック
会社設立時インボイス制度に対応する場合はタイミングも考慮しよう
会社設立時、インボイス制度に対応して適格請求書発行事業者になると、取引の継続などの面でメリットが得られる可能性がありますが、税負担や作業の手間は増加します。
新設法人は、資本金が1,000万円未満であれば基本的には免税事業者となるため、インボイス制度に対応するかどうかは、タイミングも含め慎重に検討しましょう。もし、判断に迷う場合は、税の専門家である税理士に相談するのもよいでしょう。
【無料】はじめてでもカンタン・安心な「会社設立」の書類作成はこちらをクリック
この記事の監修者森 健太郎(税理士)
ベンチャーサポート税理士法人 代表税理士。
毎年1,000件超、累計23,000社超の会社設立をサポートする、日本最大級の起業家支援士業グループ「ベンチャーサポートグループ」に所属。
起業相談から会社設立、許認可、融資、助成金、会計、労務まであらゆる起業の相談にワンストップで対応します。起業・会社設立に役立つYouTubeチャンネル会社設立サポートチャンネルを運営。