基礎控除とは?制度の意義や適用させる方法をわかりやすく解説
更新
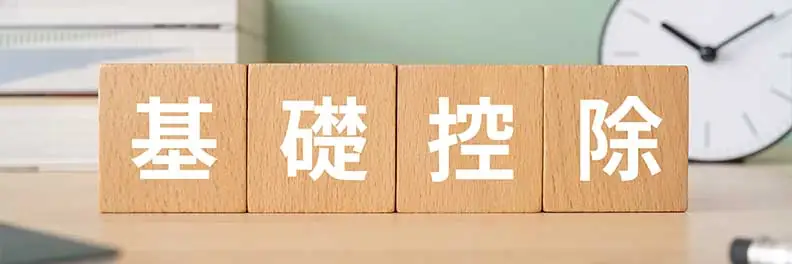
基礎控除は、原則としてすべての納税者に適用される所得控除です。所得控除とは、所得金額から一定額を差し引くことで課税対象となる所得額(課税所得)を減額し、税負担を軽減するしくみのことです。
基礎控除を始めとする各種控除のルールは税制改正によって変更されることがあり、令和7年度税制改正では、所得税の基礎控除の見直しなどが行われました。これに伴い、年末調整や確定申告では最新情報を反映させたうえで控除額の判定や申告書の記入を行います。
本記事では、基礎控除の基本的なしくみや控除額をわかりやすく整理すると共に、給与所得者と個人事業主それぞれの適用方法について解説します。さらに、令和7年度税制改正による具体的な変更点や、申告書の書き方についても触れています。基礎控除を正しく理解し、適切に手続きを行うための参考にしてください。
※本記事は「給与計算担当、会社員・パート・アルバイトの方の年末調整」向けの記事です。
フリーランスなどの個人事業主や副業で確定申告を行う方の基礎控除については、2025年分(2026年提出)に対応した以下の記事をご覧ください。
【無料で資料ダウンロード】「弥生給与 Next」でバックオフィス業務をスムーズに
無料お役立ち資料【「弥生給与 Next」がよくわかる資料】をダウンロードする
基礎控除とは所得金額から引かれる所得控除の1つ
基礎控除は、年末調整や確定申告で所得税を計算する際に、所得金額から差し引きができる所得控除の1つです。控除額が大きくなるほど、最終的に納付する税額が減少するため、税額計算の際に重要な項目となります。
所得控除には基礎控除の他にも、社会保険料控除や医療費控除、生命保険料控除、配偶者控除など、さまざまな種類が存在します。各控除には適用要件が定められており、それらの要件を満たした場合にのみ、税額の計算時に控除額として差し引き可能です。
基礎控除は、納税者の合計所得金額が2,500万円以下の場合に適用され、所得金額に応じた控除額が定められています。所得税は、1年分の給与などの総所得金額から控除額を差し引いた課税所得に税率を適用して算出します。給与所得から差し引く控除額が変わると課税所得金額が変動するため、その結果が税額にも影響します。計算の際には、税額に大きく影響する控除額などは慎重に取り扱いましょう。所得税計算について以下で詳しく解説します。
合計所得金額ごとの控除額
物価上昇に伴う税負担や就業調整への対応として、令和7年度税制改正により2025年から所得税の「基礎控除」と「給与所得控除」の金額が変更され、「特定親族特別控除」の制度も新設されました。
基礎控除の額は所得金額に応じて定められており、合計所得金額132万円以下の場合は控除額95万円(恒久措置)が新設されています。また、時限措置も含めて段階的に控除額が減少し、合計所得金額が2,500万円を超えると控除額は0円となります。
なお、今回の改正は所得税の基礎控除のみで、住民税の基礎控除に変更はありません。
| 合計所得⾦額 | 控除額 |
|---|---|
| 132万円以下 | 95万円 |
| 336万円以下 | 88万円 |
| 489万円以下 | 68万円 |
| 665万円以下 | 63万円 |
| 2,350万円以下 | 58万円 |
| 2,350万円超~2,400万円 | 48万円 |
| 2,400万円超~2,450万円 | 32万円 |
| 2,450万円超~2,500万円 | 16万円 |
| 2,500万円超 | なし |
所得税の求め方

所得税は、1年分の収入額と、業務上発生した経費や所得控除の合計額を基に算出します。1月から12月までの1年分の収入額から、同期間に発生した必要経費、基礎控除などの所得控除額を差し引き、課税所得金額を算出します。さらに課税所得に税率を掛けることで所得税額が計算されます。
2013年から2037年までの期間には復興特別所得税(税率2.1%)も徴収されるため、基準所得税額に復興特別所得税額を足した額が、最終的な所得税額になります。
所得税率は課税所得金額を7つの区分に分けた区分ごとに設定しています。課税所得金額が1,000円~194万9,000円の税率は5%、195万円~329万9,000円の部分については10%などと定められており、詳細は国税庁の公式サイトで確認できます。
【所得税の計算手順】
-
1.1年の収入額 - 収入から差し引かれる金額(必要経費など) = 所得金額
-
2.所得金額 - 所得控除額 = 課税所得金額
-
3.課税所得金額 × 税率 − (速算表による)控除額 = 所得税額
-
4.所得税額 - 所得税から差し引かれる金額(例:住宅ローン控除など) = 基準所得税額
-
5.基準所得税額 + 復興特別所得税額 = 最終的な所得税額
-
参照:国税庁「所得税のしくみ
」
-
参照:国税庁「No.2260 所得税の税率
」
所得控除の種類
所得控除は16種類あり、控除を受けるには、年末調整または確定申告の手続きをします。
| 控除の種類 | 内容 | 申告方法 | |
|---|---|---|---|
| 1 | 基礎控除 | 本人の合計所得金額が132万円以下の場合、控除額95万円(恒久措置)が新設された他、時限措置を含め段階的に控除額が減少する。合計所得金額が2,500万円を超えると控除額は0円となる | 年末調整で対応可能 |
| 2 | 配偶者控除 | 本人の合計所得金額が1,000万円以下で、税法上の控除対象配偶者がいる場合に適用される。控除額は本人の所得や配偶者の年齢に応じて変わる | 年末調整で対応可能 |
| 3 | 配偶者特別控除 | 本人の合計所得金額が1,000万円以下で、かつ配偶者(生計一親族など要件あり)の合計所得金額が58万円超133万円以下の場合に適用される。控除額は本人および配偶者の合計所得金額に応じて変わる | 年末調整で対応可能 |
| 4 | 扶養控除 | 税法上の控除対象扶養親族がいる場合に適用される。控除額は扶養親族の年齢や同居の有無に応じて38万~58万円 | 年末調整で対応可能 |
| 5 | 特定親族特別控除 | 令和7年度税制改正により新設。要件を満たす特定親族がいる場合、特定親族の合計所得金額に応じて3万円~63万円が控除される | 年末調整で対応可能 |
| 6 | 障害者控除 | 本人や、生計を一にする配偶者または扶養親族が、税法上の障害者に該当する場合に適用される。控除額は区分により27万~75万円 | 年末調整で対応可能 |
| 7 | 寡婦控除 | 夫と離婚または死別した女性が所定の要件に該当する場合、27万円が控除される | 年末調整で対応可能 |
| 8 | ひとり親控除 | 離婚、死別、未婚など独身で子どもを育てている人が、所定の要件に該当する場合、35万円が控除される | 年末調整で対応可能 |
| 9 | 勤労学生控除 | 本人が税法上の勤労学生に該当する場合、27万円が控除される | 年末調整で対応可能 |
| 10 | 生命保険料控除 | 生命保険料、介護医療保険料、個人年金保険料を支払った場合に受けられる控除。控除額は、支払った保険料等の金額や、新制度か旧制度かなどによって異なり、合計で12万円が上限となる | 年末調整で対応可能 |
| 11 | 地震保険料控除 | 地震保険にかかる保険料または掛金を支払った場合に受けられる控除。控除額は支払保険料の金額によって変わり、最高5万円 | 年末調整で対応可能 |
| 12 | 社会保険料控除 | 健康保険料(健康保険、国民健康保険)、年金保険料(国民年金、厚生年金保険)、介護保険料などの社会保険料について、支払った、または給与などから天引きされた全額が控除される | 年末調整で対応可能 |
| 13 | 小規模企業共済等掛金控除 | 小規模企業共済・iDeCo(個人型確定拠出年金)・心身障害者扶養共済制度の掛金を支払った場合、掛金の全額が控除される | 年末調整で対応可能 |
| 14 | 医療費控除 | 1年間に支払った医療費が一定額を超えた場合、最大200万円までの医療費控除か、最大8万8,000円までのセルフメディケーション税制(医療費控除の特例)のいずれかを適用できる(生計を一にする家庭単位) | 確定申告の手続きをする |
| 15 | 寄附金控除 | 国や地方公共団体などに対して特定寄附金を支出した場合以下のうち低い方の金額−2,000円が控除される ・特定寄附金の合計額 ・その年の総所得金額等の40%相当額。 |
確定申告の手続きをする (ふるさと納税はワンストップ特例を利用した場合は確定申告不要) |
| 16 | 雑損控除 | 災害や盗難、横領によって、対象の資産に損害を受けた場合に以下のうち多い方の金額が控除される ・(損失金額+災害等関連支出の金額-保険金等の額)-総所得金額など×10% ・(災害関連支出の金額-保険金等の額)-5万円 |
確定申告の手続きをする |
16種類のうち、年末調整では生命保険料控除や地震保険料控除など13種類の所得控除の申告ができます。会社員の場合は年末調整の際に勤務先に必要事項を記入した書類を提出し、勤務先が年末調整の手続きを行います。なお、年の途中で転職した人の場合は、1年分の所得税計算に前職の給与や賞与、給与等から控除された社会保険料や源泉徴収された所得税額も含めます。そのため、年末調整時に前職の源泉徴収票を提出してもらいましょう。
所得控除の受け方
会社は、「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」「給与所得者の保険料控除申告書」などの書類を従業員に配布して、記入後に回収します。生命保険料控除の「保険料控除証明書」、住宅ローン控除(住宅ローン控除は上記所得控除ではなく税額から直接控除する税額控除)の「住宅借入金等特別控除申告書」など、各控除を申告する際は、保険会社や金融機関が発行した書類の提出が求められます。
医療費控除、寄附金控除、雑損控除の3種類に加え、初年度の住宅ローン控除は年末調整では申告できないため、留意しましょう。会社員の場合には勤務先の年末調整でほとんどの所得控除の申告が可能ですが、上記3種類の所得控除と初年度の住宅ローン控除の申告は、年末調整とは別に自分で確定申告をします。
【無料で資料ダウンロード】「弥生給与 Next」でバックオフィス業務をスムーズに
基礎控除を適用させる方法
基礎控除を適用させるには、年末調整や確定申告が求められます。会社員の場合は年末調整で処理され、個人事業主は確定申告で手続きを行います。
給与所得者は年末調整で基礎控除を受ける
会社員、パート、アルバイトなどの給与所得者は、年末調整を行うことで基礎控除が適用されます。勤務先の給与計算担当者が従業員の1年間の給与に基づく所得税額を計算して年末調整を行い、納税額を調整します。年末調整の際には、従業員は「給与所得者の基礎控除申告書」を提出します。
この申告書には、基礎控除の適用に求められる項目だけでなく、配偶者控除、所得金額調整控除を受けるための情報も記載します。漏れなく記載して、正しく控除を受けるようにしましょう。
給与計算担当者は、従業員の年間給与や申告書を基に、最終的な所得税額を算出します。税額が決定すると、これまで源泉徴収していた額との差額を還付または徴収で調整します。年末調整の精算は、主に12月または翌年1月の給与で行われます。申告書の提出は、一般的には例年11月~12月初旬ごろまで提出が遅れると控除を受けられない可能性があるため、提出期限を周知することが望まれます。
年末調整についてはこちらの記事もご覧ください。
個人事業主の基礎控除は確定申告で受ける
1月1日から12月31日までの所得や税額、源泉徴収額を税務署に報告し、納税を行う手続きが「確定申告」です。個人事業主が基礎控除を受けるためには、所得を得た年の翌年に自ら確定申告を行います。確定申告の期間は、毎年その翌年の2月16日から3月15日までです。3月15日が土日に重なる場合は、次の月曜日が最終期限になります。
なお、令和7年分(2025年分)の確定申告期間は、2026年2月16日(月)から3月16日(月)までです。確定申告書の基礎控除額を記入する欄に、申告者の所得に基づく控除額を適用します。e-Taxを利用したオンライン申告も可能です。
【無料で資料ダウンロード】「弥生給与 Next」でバックオフィス業務をスムーズに
基礎控除制度の意義と税制改正による変更点
基礎控除制度は、納税者本人や配偶者・扶養親族の生活維持のために、最低限の収入を守ることを目的に設けられた制度です。令和7年度税制改正によって基礎控除額の拡大などの変更があり、今後さらに所得税額の軽減が期待されています。
基礎控除制度の意義
所得税は個人の所得に課される税金ですが、生活に必要な最低限の収入まで課税すると、納税者の負担が過度に大きくなってしまいます。そこで、納税者の生活の安定を考慮し、課税負担を軽減するために控除制度が設けられました。
基礎控除は、憲法25条の「健康で文化的な最低限度の生活を営む権利」に基づき1947年に創設された制度です。所得が2,500万円以下の個人に適用され、所得額に応じて税率が軽減されることで、所得税の負担を抑えることができます。
これまで「103万円の壁」と呼ばれていたものは、2024年までの給与所得における基礎控除額48万円と給与所得控除55万円の合算額を意味します。この給与所得控除とは、給与所得などの収入から差し引かれる控除額を指します。2024年までの給与所得控除には給与額に応じて6つの給与区分があり、最も低い区分の162万5,000円以下が55万円、最も高い区分の850万円超には195万円(上限)と、それぞれ控除額が設定されていました。
給与所得控除の最低額55万円と基礎控除48万円を合わせると103万円となり、年収103万円までであれば、所得税は課税されません。ただし103万円を超えると、その超過分に対して所得税が課されます。これがいわゆる年収103万円の壁と言われるものです。なお、令和7年度税制改正により基礎控除額・給与所得控除が引き上げられ、課税されない範囲も拡大しています。
-
参照:国税庁「所得控除の今日的意義(要約)
」
令和7年度税制改正による変更点
これまでの基礎控除は所得額に応じた4つの区分が設けられており、2,400万円以下の所得区分では控除額が48万円とされていました。「令和7年度税制改正」により、合計所得金額132万円以下の控除額95万円(恒久措置)が新設されました。また時限措置も含めて段階的に控除額が減少し、合計所得金額が2,500万円を超えると控除額が0円となります。この改正は2025年から適用されます。
さらに、給与所得控除の最低保障額も55万円から65万円に引き上げられたことで、従来「103万円の壁」とされていた基準が「160万円の壁」へと変更されます。
これにより、パートタイムやアルバイトなどの勤務形態で働く人が、所得税を回避するための年収上限は、基礎控除48万円+給与所得控除55万円の合算103万円から、基礎控除95万円+給与所得控除65万円の合算160万円に引き上げられます。この改正により、より多くの収入を得ても課税されない範囲が広がります。
【無料で資料ダウンロード】「弥生給与 Next」でバックオフィス業務をスムーズに
基礎控除申告書の書き方

基礎控除を受けるためには、年末調整で提出する「給与所得者の基礎控除申告書 兼 給与所得者の配偶者控除等申告書 兼 給与所得者の特定親族特別控除申告書 兼 所得金額調整控除申告書」に必要事項を記載します。これらの書類は、毎年10月下旬から11月ごろにかけて勤務先が従業員に配布し、従業員本人が記入後に回収します。
この申告書は、以下の4つの申告書が一式にまとめられたものです。
-
- 給与所得者の基礎控除申告書
- 給与所得者の配偶者控除等申告書
- 給与所得者の特定親族特別控除申告書
- 所得金額調整控除申告書
なお、詳細な書き方や計算手順については、以下の関連記事もご覧ください。
本年中の合計所得金額の見積額を算出する
まず、「本年中の合計所得金額の見積額」を記載します。これは、基礎控除の適用額を決めるうえで重要な項目です。記入の流れは次のとおりです。
-
1.給与収入を記入
給与所得の「収入金額」の欄に、会社から交付された前年の源泉徴収票や、現時点までの給与支給額を基に見積もった収入金額を記入します。年末調整前に当年分の源泉徴収票は交付されないため、あくまで見積額で差し支えありません。
-
2.給与所得を記入
給与所得の「所得金額」の欄に、給与収入から給与所得控除を差し引いた給与所得額を記入します。
-
3.給与所得以外の所得の合計額を記入
給与所得以外の所得の合計額を「所得金額」の欄に、事業所得や不動産所得、雑所得など、給与以外で得た所得の合計額(売上から経費を引いた額)を記載します。この場合も、年内に正確な数値を把握することは難しいため、概算額(見積額)で差し支えありません。
-
4.合計所得金額を計算
給与所得と給与所得以外の所得を合算し、「本年中の合計所得金額の見積額」として欄に記入します。
基礎控除の額を記載する
算出した「本年中の合計所得金額の見積額」を基に、基礎控除の額を判定しましょう。
-
1.控除額を確認
「控除額の計算」の表に合計所得金額の見積額を当てはめ、基礎控除額を判定します。
-
2.該当欄にチェック
該当する行のチェックボックスにチェックを入れます。
-
3.「基礎控除の額」欄に記入
導き出した基礎控除額を「基礎控除の額」欄に転記し、最終的に適用される控除額として申告します。
ここまでの手順を踏むことで、基礎控除が正しく適用され、年末調整による所得税計算に反映されます。
【無料で資料ダウンロード】「弥生給与 Next」でバックオフィス業務をスムーズに
税制改正による業務負担は「弥生給与 Next」で軽減しよう
基礎控除はすべての納税者にかかわる重要な所得控除であり、年末調整や確定申告の際に正しく適用することが大切です。税制度は改正されることがあるため、その年の最新情報に基づいた手続きを行いましょう。税制改正が行われると申告書の仕様も変更されるため、年末調整担当者は対応が求められます。
そのような場合の業務効率化に役立つのが、「弥生給与 Next」です。最新の税制や法令に自動対応し、給与額や控除額などは自動計算が可能です。年末調整の申告書はWeb上での配布・回収が可能で、作業を大幅に削減できます。給与計算や年末調整をスムーズに行い、正確な処理を実現するためにも、「弥生給与 Next」の導入を検討してみてはいかがでしょうか。
- ※ご契約のプランによって利用できる機能が異なります。
【無料で資料ダウンロード】「弥生給与 Next」でバックオフィス業務をスムーズに
「弥生給与 Next」で給与・勤怠・労務をまとめてサクッとデジタル化
弥生給与 Nextは、複雑な人事労務業務をシームレスに連携し、効率化するクラウド給与サービスです。
従業員情報の管理から給与計算・年末調整、勤怠管理、保険や入社の手続きといった労務管理まで、これひとつで完結します。
今なら、すべての機能を最大2か月間無料で利用できます!
この機会にぜひお試しください。
この記事の監修者税理士法人古田土会計
社会保険労務士法人古田土人事労務
中小企業を経営する上で代表的なお悩みを「魅せる会計事務所グループ」として自ら実践してきた経験と、約3,000社の指導実績で培ったノウハウでお手伝いさせて頂いております。
「日本で一番喜ばれる数の多い会計事務所グループになる」
この夢の実現に向けて、全力でご支援しております。
解決できない経営課題がありましたら、ぜひ私たちにお声掛けください。必ず力になります。








