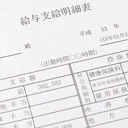アルバイトにも給与明細の発行は必要?作り方や必要な項目を解説
更新

アルバイト等の給与形態は正社員と異なることから、「給与明細の発行は必要か」や「どのように給与計算するか」で悩む担当者が少なくありません。近年はスポットワーカーも増加しており、労務管理が多様化しています。
本記事では、時給制のアルバイトに焦点を当て、給与明細の作成方法や給与計算を行う際の注意点を紹介します。給与明細の誤りが発覚した場合の対処法や、近年増加しているスポットワーカーの取り扱いについても解説します。
【無料で資料ダウンロード】「弥生給与 Next」でバックオフィス業務をスムーズに
今なら「弥生給与 Next」スタート応援キャンペーン実施中!

無料お役立ち資料【「弥生給与 Next」がよくわかる資料】をダウンロードする
アルバイトにも給与明細の発行が必要
正社員と同様にアルバイトにも給与明細の発行が必要です。そもそも給与明細とは、従業員の勤怠情報や給与の総支給額と内訳、控除額などが明記された書類を指します。企業の給与支払者は・労働基準法、所得税法等に沿って、すべての従業員に対し支払明細書を交付しなければなりません。給与明細書はこの「支払明細書」に該当し、アルバイト・正社員といった雇用形態を問わず、給与を支払う企業には交付する義務があります。
アルバイトとは、パートタイム労働法の対象になるパートタイム労働者(短時間労働者)を指し、正社員と比較して1週間の所定労働時間が短い従業員です。これは、パートタイム労働法上はパートタイムとアルバイトの区別がなく、いずれも「パートタイム労働者」に区分されるためです。
【無料で資料ダウンロード】「弥生給与 Next」でバックオフィス業務をスムーズに
アルバイトの給与明細に必要な項目
アルバイトの給与明細に記載が必要な項目は主に「勤怠」「支給」「控除」で、それぞれに記載する内容の詳細は、以下のとおりです。
勤怠
1か月当たりの勤怠状況を記載します。具体的には出勤日数、遅刻早退時間、欠勤日数、労働時間、時間外労働時間、深夜労働時間 有休消化などです。
記載する時間は、支給や控除など給与計算の元情報として機能するため、適切な勤怠管理を行い正確に把握することが重要です。2019年4月から施行された「働き方改革関連法」により、自己申告による勤怠管理は原則禁止され、企業はタイムカードやパソコンのログなど、客観的な記録に基づいて労働時間を管理することが義務付けられました。
支給
以下の事項を個別に記載し、それらの合計に該当する「総支給額」を明示します。
-
- 基本給
- 諸手当(交通費、資格手当、住居手当など)
- 割増賃金(深夜労働、休日労働、休日深夜労働など)
時給制のアルバイトの基本給は、時給×労働時間で計算します。なお、諸手当や割増賃金は内訳ごとに欄を作成し、金額を確認しやすいよう配慮しましょう。
控除
控除の項目には、給与から差し引く税金(所得税 住民税)や社会保険料(健康保険・介護保険・厚生年金保険・雇用保険)、欠勤・遅刻・早退での控除(時給者であれば、未支給となります)の金額、その他控除の金額を記載し、合計の控除額も算出します。
勤務先に「給与所得者の扶養控除等の(異動)申告書」を提出していない方が月の給与が8万8,000円以上になった場合、アルバイトであっても所得税の源泉徴収が必要です。
また、企業には所定の給与や労働時間を超えたアルバイトを社会保険や雇用保険へ加入させる義務があります。
【無料で資料ダウンロード】「弥生給与 Next」でバックオフィス業務をスムーズに
社会保険の対象となるアルバイトの要件
社会保険の適用対象は段階的に拡大されており、2024年10月からは、社会保険に加入している被保険者数が51〜100人の企業で働くアルバイトも、一定の条件を満たせば適用対象となりました。
-
- 契約上の所定労働時間が週20時間以上
- 所定内賃金が月額8.8万円以上
- 雇用期間の見込みが2か月を超える
- 学生ではない
所定内賃金(雇用契約によって定められた所定労働時間内の労働に対して支払われる賃金)の月額は、時間外手当や賞与といった瞬時的に発生する賃金を除外して計算します。通勤手当のように最低賃金に算入しないことが決められている賃金も除外が可能です。
-
参照:政府広報オンライン「社会保険の適用が拡大!従業員数51人以上の企業は要チェック」
参照:厚生労働省「社会保険適用対象となる加入条件」
【無料で資料ダウンロード】「弥生給与 Next」でバックオフィス業務をスムーズに
アルバイトの給与明細作成に必要なもの
時給制のアルバイトの基本給与は、基本時給に労働時間を乗じるシンプルな方法で計算できます。ただし、実際の給与計算や給与明細の作成を行う際には注意点があることから、手元に以下の資料を用意し、確認しながら給与計算を進めましょう。
就業規則
給与計算業務を行う際には就業規則や給与規程を用意して、事前に内容を確認する必要があります。就業規則には始業および終業時刻、休憩時間、休日、休暇といった労働条件が記載されており、それらの計算方法は給与規程に定められておりますので、これらの内容に従って給与計算しなければなりません。
なお、従業員を常時10人以上雇用している企業には、就業規則の作成および労働基準監督署への届出義務があります。10人未満の企業には義務がないとは言え、トラブルを防止するため、用意しておくと安心です。
就業規則については、こちらの記事で詳しく紹介しています。
給与規程
給与規程には、給与計算の基準や計算方法の他、給与の締め日や支払いの時期、支払方法など、給与業務に関係する内容が詳細に定められています。確認漏れがないように注意しなければなりません。
タイムカードなど勤怠管理の書類
出勤日数・欠勤日数・労働時間などを確認するため、タイムカードなどの書類が必要です。従業員の勤怠情報を正しく反映していれば、タイムカード以外の方法でも問題ありません。例えば、勤怠管理システムのデータも、手元資料として活用が可能です。
タイムカードについて詳しくはこちらの記事をご覧ください。
また、税金や社会保険料の控除に関する書類の確認も必要です。
-
- 被保険者標準報酬決定通知書
- 住民税課税決定通知書
- 保険料額表
- 保険料率表
- 源泉徴収税額表
なお、健康保険の保険料額表、雇用保険の保険料率表、源泉徴収税額表は定期的に変更されることから、最新版を確認してください。
【無料で資料ダウンロード】「弥生給与 Next」でバックオフィス業務をスムーズに
アルバイトの給与計算時には割増賃金に注意
アルバイトを含む従業員に時間外労働、深夜労働、休日労働させる場合に企業は、割増賃金を支払わなければなりません。
割増賃金は種類によって割増率が異なり、以下の記事で詳しく解説しています。
また、学生や専門学校生、高校生をアルバイトとして雇用している場合には、年少者保護の観点から労働基準法で規定されている条件を確認することも重要です。18歳未満の高校生は年少者として扱われ、労働時間や深夜労働に制限があります。
規定の詳細は、以下を参照してください。
参照:厚生労働省「高校生等を使用する事業主の皆さんへ」
時間外労働の場合
労働基準法では特例を除き、1日8時間、1週間40時間を法定労働時間と定めています。法定労働時間を超過して働いた分が時間外労働となり、割増賃金の支払いが必要です。時給制のアルバイトが時間外労働した場合、法定労働時間を超過した時間分に対して基本時給の1.25倍を支払うように給与計算してください。
深夜労働の場合
深夜労働とは、22時から翌朝5時までの時間帯に労働させることで、労働基準法で定められています。時給制のアルバイトに深夜労働をさせた場合は、通常の基本時給+基本時給の0.25倍以上の割増賃金を支払う必要があります。例えば、アルバイトの基本時給が1,200円の企業では、300円以上の割増賃金を支払うことになります。
休日労働の場合
労働基準法では法定休日が定められており、週1日もしくは曜日を問わずに4週間を通じて4日以上の休日を与えるとされています。法定休日にアルバイトを労働させる場合は、基本時給の0.35倍分以上の割増賃金を支払うことになります。
ただし、シフト制でもともと休みだった日に出勤した場合、その日が法定休日に該当せず、一日8時間、週40時間を下回っていれば、割増賃金を支払う義務は発生しません。
割増賃金が重複した場合
時間外労働もしくは休日労働と深夜労働のように、重複して割増賃金が発生するケースもあり、このような場合には、合算して支払わなければいけません。例えば、時間外労働が22時以降まで及んだ場合、時間外労働の割増率1.25倍以上と深夜労働の割増率0.25倍以上の合計で割増率1.5倍となります。
なお、法定休日には法定労働時間の概念が存在しません。休日労働に対しては時間外労働の割増賃金が発生しないため、重複することはありません。
-
参照:厚生労働省「法定労働時間と割増賃金について教えてください。」
【無料で資料ダウンロード】「弥生給与 Next」でバックオフィス業務をスムーズに
時給制のアルバイトの給与計算の流れ
時給制のアルバイトの給与は、次の流れで計算します。
-
- 労働時間を集計する
- 支給額を計算する
- 控除額を計算する
各ステップで行う作業の概要や注意点を説明していきます。また、以下の記事でも詳しく解説しているので、参考にしてください。
1. 労働時間を集計する
まず、勤怠記録を活用し、給与を支払う対象期間の労働時間を集計します。労働時間は、通常の労働時間・時間外労働・休日労働・深夜労働に分け、それぞれ分けて正しく算出してください。
アルバイトの労働時間は、他の従業員と同様に1分単位で計算します。10分や15分単位で切り捨てることはできません。切り捨てた場合、労働基準法「賃金全額払いの原則」に違反する恐れがあるので注意が必要です。
また、たとえ未成年であっても、給与は本人に全額現金で支払うことが義務付けられており、親や親権者などに代わりに支払うことはできません。原則は現金による支払いですが、本人の同意があれば本人名義の口座に給与を振り込むことは可能です。
なお、労働時間の端数処理の例外として、1か月単位で各労働時間を集計し端数が発生した場合に30分未満を切り捨て、それ以上は1時間切り上げる方法が認められています。切り捨てと切り上げは必ず併用が必要なので注意が必要です。
-
参照:厚生労働省「労働時間を適正に把握し正しく賃金を支払いましょう」
2. 支給額を計算する
集計した労働時間に時給の単価を乗じ、支給額を計算します。通常の労働時間に対する給与は「基本時給×労働時間」で計算します。時間外労働時間・深夜労働時間・休日労働時間に対する給与は、「基本時給×割増率×割増に該当する労働時間」で計算してください。それぞれの計算結果を合計すると、総支給額が算出できます。
3. 控除額を計算する
アルバイトでも勤務状況や収入によって、雇用保険料や社会保険料(健康保険・介護保険・厚生年金)、税金(所得税・住民税)などの控除が必要な場合があります。控除の計算は種類によって方法が異なるため、必要書類を参照しながら計算してください。各控除額を合計し、総支給額から差し引くと、実際に支給する給与の金額が確定できます。
【無料で資料ダウンロード】「弥生給与 Next」でバックオフィス業務をスムーズに
アルバイトの給与明細の作り方
アルバイトの給与明細作成には、主に3つの作成方法があります。
-
- 手書き
- ExcelやWord
- 給与計算ソフト
手間をかけず効率的に作成したい場合には、給与計算ソフトの活用がおすすめです。
手書きの給与明細に記載する
給与明細は、手書きでも作成可能です。市販されている大半の給与支払明細書には必須項目が印刷されているので、テンプレートに沿って記入すれば容易に給与明細が作成できます。
なお、手書きで作成する場合は、複写式の「給与支払明細書」を利用し、本人交付用と会社の控えとして2部用意してください。控えがあることで、給与トラブルが発生した場合にもすぐに見返せ、迅速に対処できます。複写式を使用しない場合には作成した原本をコピーして、社内に保管してください。
ExcelやWordで作成する
ExcelやWordで給与明細書を作成することも可能です。インターネットで配布されている無料テンプレートをダウンロードするのがおすすめです。項目ごとに入力するだけで作成できるので、レイアウトする手間が省けます。
ただし、ExcelやWordを使用して給与明細を作成する場合には、関係法規が改定されるたびに計算式をアップデートしなければなりません。また、データが破損したり、誤ってデータを消去したりするリスクを考慮し、バックアップを取っておく必要があります。
給与計算ソフトを使う
給与明細作成機能が搭載された給与計算ソフトを活用すると便利です。給与業務の手作業で発生しやすいミスを回避し、ペーパーレス化も行うことができます。
勤怠情報の集計や給与計算、計算結果を元にした給与明細作成まですべて自動でしてくれるソフトが多く、給与計算担当者の負担の大幅な軽減が可能です。
給与計算ソフトによっては、作成した給与明細をオンラインで従業員のコンピューターやスマートフォンへ配信できます。給与明細をペーパーレス化すれば印刷や封入れなどの作業を削減し、コストカットが実現します。
【無料で資料ダウンロード】「弥生給与 Next」でバックオフィス業務をスムーズに
アルバイトの給与明細で注意すべき点
アルバイトに限らず、給与明細は遅滞なく用意しなければなりません。また従業員との信頼関係を維持・構築するためには、給与明細のミスが発覚した場合の対応にも注意が必要です。
給与の支払日までに給与明細を交付する
給与明細は雇用形態を問わず、給与を支払っているすべての従業員に対して交付しなければならない書類です。給与明細を交付しなかった場合には、所得税法違反として1年以下の懲役もしくは50万円以下の罰金の対象となります。
また、給与明細は給与の支払日までに交付することが必要です。給与明細の交付遅延に罰則はないものの、企業の責任として期限内に交付できるよう作成体制を整備しておかなければなりません。
誤りがあったら迅速に対応する
給与計算や給与明細の誤りが発覚した場合には、対象の従業員へ迅速に謝罪し、どのように対応するか説明してください。給与が不足していた場合には「全額支払いの原則」に基づき、その月のうちに調整を行い給与明細を差し替えることが理想的です。過払いした場合には従業員の了承を得て、翌月に調整を行う方法も検討されます。ただし、給与計算の誤りは極力早急に解消することが望ましく、過払いがあった場合もその月のうちに対処すると安心です。
また、税金や社会保険料などの控除額も間違っている可能性があります。税金や社会保険料の誤りは年末調整に影響するため、遅くとも当年の12月31日までに対処が必要です。
【無料で資料ダウンロード】「弥生給与 Next」でバックオフィス業務をスムーズに
スポットワーカーも給与明細が必要
スポットワーカーとは、アプリやウェブサービスを活用して短時間かつ単発の仕事を受け、現場の指示の下で働くことです。近年、副業解禁の流れも受け、スポットワーカーとして働く人は増加しています。
当然ながらスポットワーカーも労働基準法の対象です。給料を支払う際には給与明細を作成し、交付する必要があります。給与を正しく計算するためには、仕事の開始時間と終了時間を適切に把握、管理することも重要です。
スポットワーカーの社会保険はどうなる?
継続性のない、その日限りのようなスポットワーカーは労働時間や給与の基準を満たさないことが多いため、健康保険や雇用保険の事務手続きは基本的に不要です。一部のアプリやウェブサービスでは事務手続きを発生させないための配慮として、リピーターの就業時間に一定の制限を付加しています。
その一方で、業務上の怪我や事故に備える労災保険は、スポットワーカーも強制加入となっております。したがって労災保険に未加入の状態でスポットワーカーが怪我をした場合、企業としてしかるべき補償を行わなければなりません。万が一のトラブルによる金銭的な負担を軽減するためにも、労災保険への加入をおすすめします。
スポットワーカーの源泉徴収はどうなる?
スポットワーカーの場合、給与の日額によって源泉徴収の有無が変わります。給与の日額が9,300円未満の場合、原則として源泉徴収が不要です。それに対して、給与の日額が9,300円以上は源泉徴収の対象となり、国税庁の源泉徴収税額表の丙欄を参照して日給額に対する源泉徴収額を計算します。
なお、2か月を超えて日々雇用し、継続的に給与を支払った場合は丙欄を参照した源泉徴収の計算が行えません。同じ人がスポットワーカーとして繰り返し働いた場合にも該当する可能性があるため、直接雇用する等の対応が必要です。
-
参照:国税庁 「給与所得の源泉徴収税額表(令和7年分)日額表」
スポットワーカーを継続して雇用する際の手続きは?
スポットワーカーを単発で雇用する際にも、労働契約の締結は必要です。単発の仕事から継続雇用に切り替えたい場合には、労働契約を変更するための事前準備として本人の同意を得てください。本人の同意を得られたら労働条件通知書や雇用契約書を交付して取り交わしをします。します。
労働契約の切り替えに際して不利な労働条件への変更は労働契約法の禁止事項です。スポットワーカーを継続して雇用する場合に提示する労働条件は、当初の内容を加味したうえで相手の不利益にならないように配慮する必要があります。
-
参照:厚生労働省「労働契約(契約の締結、労働条件の変更、解雇等)に関する法令・ルール」
【無料で資料ダウンロード】「弥生給与 Next」でバックオフィス業務をスムーズに
アルバイトの給与明細作成には給与計算ソフトを活用しよう
企業は法令を遵守し、時給制のアルバイトやスポットワーカーに対しても、適切な給与処理を行う責任があります。
給与計算や明細書の作成は手作業でも行えますが、計算ミスや記入漏れを起こしやすいので、給与計算ソフトの導入がおすすめです。「弥生給与 Next」は、給与計算や明細書の作成を自動化でき、大幅な効率化が可能です。勤怠管理や労務管理機能も利用できるプランもあり、労務業務をシームレスにつないで効率化を狙える点もメリットです。自社に合ったサービスを活用して業務の効率化を目指しましょう。
【無料で資料ダウンロード】「弥生給与 Next」でバックオフィス業務をスムーズに
「弥生給与 Next」で給与・勤怠・労務をまとめてサクッとデジタル化
弥生給与 Nextは、複雑な人事労務業務をシームレスに連携し、効率化するクラウド給与サービスです。
従業員情報の管理から給与計算・年末調整、勤怠管理、保険や入社の手続きといった労務管理まで、これひとつで完結します。
今なら「弥生給与 Next」 スタート応援キャンペーン実施中です!
この機会にぜひお試しください。
この記事の監修者税理士法人古田土会計
社会保険労務士法人古田土人事労務
中小企業を経営する上で代表的なお悩みを「魅せる会計事務所グループ」として自ら実践してきた経験と、約3,000社の指導実績で培ったノウハウでお手伝いさせて頂いております。
「日本で一番喜ばれる数の多い会計事務所グループになる」
この夢の実現に向けて、全力でご支援しております。
解決できない経営課題がありましたら、ぜひ私たちにお声掛けください。必ず力になります。