納品書の用紙サイズに決まりはある?用紙の選び方や送付時のマナーを解説
監修者: 市川 裕子(ビジネスマナー監修)
更新
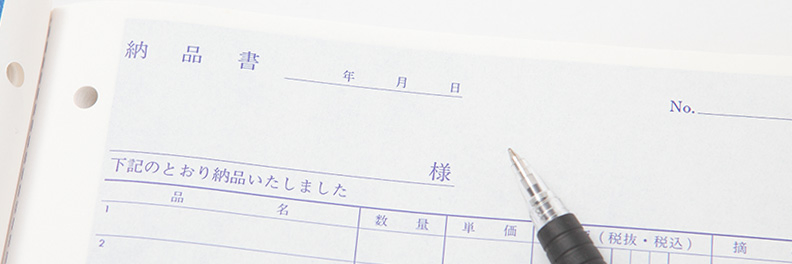
納品書の書式は、会社で定型フォーマットが作られていることも多いですが、自分で一から作成するケースもあります。その際に、納品書をどのサイズで作ればよいのか悩む人もいるでしょう。本記事では、納品書にふさわしいサイズや用紙の種類、送る際の注意点などに焦点をあてて、わかりやすく解説します。
無料【クラウド請求書作成ソフト「Misoca」がよくわかる資料】をダウンロードする
納品書に適した用紙のサイズ
納品書は、取引先に納品物の明細や数量、金額などを明示するために作成する重要な書類です。取引が正しく行われたことを証明する証憑書類となるため、適切に作成する必要があります。
納品書を作成する場合、どの程度の大きさで作成すればよいか迷うケースもあるため、納品書に適したサイズについて解説します。
基本はA4サイズが一般的
納品書のサイズは法律で決められているわけではありません。納品日や納品先、数量や単価、合計金額などの必要な基本情報が正しく記載されていれば、どのようなサイズの納品書にするのかは自由です。
会社によっては小さめの伝票タイプの納品書を使っているところもありますが、近年、官公庁の届出用紙やビジネス文書で使われている基本サイズはA4サイズです。
一般的な帳簿やビジネス文書、行政文書などに使われるサイズと同じA4サイズにしておけば、作成する側も送られる側も管理がしやすいでしょう。
A5やB5でも問題はない
納品書をはじめとした帳簿や書類のサイズは法律で定められたルールはありません。帳簿や書類には手書きの伝票やドットプリンターで打ち出した複写式の帳票など、多くの種類が存在しておりサイズもさまざまです。
A5やB5などの規格の判型でも、それ以外の大きさでも自由ですが、送られた相手方の管理を考えると、一般的に使われているA4サイズが無難といえるでしょう。
また、クリアファイルやレターケースなど多くの事務用品にA4が多いことからも、整理整頓や保管に適しているといえます。
【1年間無料】フリーランスの見積・請求・申告は「Misoca×やよいの青色申告 オンライン」セットがお得!
納品書の用紙の選び方
納品書のサイズに規定はないものの、A4が適切であると説明しました。では、用紙は何を使えばよいのでしょうか。用紙の紙質について解説します。
印刷用紙は長期保管を前提として選ぶとよい
納品書は証憑書類となる書類のひとつであり、取引先と納品状況について相互に確認するためだけに作られる書類ではありません。会社法や法人税法に大きく関与するため、保存が義務付けられている書類であるとの認識が必要です。
会社は、会計帳簿類とともに取引に関する書類を、事業年度の確定申告の期限の翌日から、最低7年間は保存する義務があります。これは法人税法の定めで、会社法では10年間の保存義務が定められています。
納品書は、法人だけではなく、個人事業主にとっても重要な意味を持つ書類です。年に一度の確定申告で必要になるだけでなく、法律で定められた期間の保存義務があります。個人事業主が青色申告や白色申告する場合、納品書等の書類は5年ないし7年の保存義務が課せられています。
それらの年数や保管状態を考慮すると、納品書は少なくとも10年程度の長期保管にも耐えられる紙質の用紙を選ぶことが大切です。
納品書の保存についてはこちらもご参照ください。
コストが気になる場合はコピー用紙でもOK
プリンター印刷で使われる用紙は、主に普通紙、上質紙、再生紙の3種類です。一般的にコピー用紙として使われるのは普通紙で、PPC用紙とも呼ばれています。
上質紙は、文字やグラフなどの文書の印刷に向いている用紙で、インクジェットやレーザープリンターの印刷用紙としてはもちろん、筆記具の手書きにも向いています。
再生紙は、古紙をリサイクルした紙で若干グレーがかって見えます。リサイクルコストから新しい紙よりも割高になるケースもありますが、近年はSDGsの取り組みとして積極的に使用する動きもあるようです。紙質は普通紙に近い質感です。
また、紙の厚さによっても印象は異なります。一般的にコピー用紙として使われる普通紙は、中厚口と呼ばれる70 kgから73kgのものです。Kg(キログラム)で表す数字は、紙を裁断する前の原紙サイズを1,000枚まとめた重量を指し、小さければ紙厚は薄く、数字が大きいほど厚くなります。
厚手でしっかりした紙を何枚も重ねて保管する場合、厚みによるボリュームがあり重量も重くなってしまいます。文書を長期間保存する際、保管スペースが広く必要になり重くなるため取り扱いにくいのが難点です。
しかし、薄くペラペラな用紙では裏から透けて見えることがあり、耐久性にも劣るためふさわしくありません。紙質や厚さが気になる場合は、他社から届いている書類の紙質を参考にするとよいでしょう。
【1年間無料】フリーランスの見積・請求・申告は「Misoca×やよいの青色申告 オンライン」セットがお得!
発行枚数が多い場合はプリンターにもこだわりましょう
プリンターの中でも広く普及しているのがレーザープリンターとインクジェットプリンターです。レーザープリンターは高速で大量に印刷できるため、企業で多く使用されています。
小規模オフィスなどでよく使われているインクジェットプリンターは、導入コストが低く、カラー印刷が高品質に仕上がるため、図やグラフを多用した資料作りや報告書などの作成に適しています。ただし、印刷スピードが遅めでインクのコストが割高になります。
レーザープリンターは、ランニングコストを考えれば長期的な使用でのコストパフォーマンスに優れていますが、インクジェットプリンターと比べると解像度が低めで、繊細な色のグラデーションの効果が難しくなります。しかし、文字や表が主体のビジネス文書で品質の善し悪しは、そこまで気にならないことがほとんどです。
【1年間無料】フリーランスの見積・請求・申告は「Misoca×やよいの青色申告 オンライン」セットがお得!
納品書を送付する際の基本的なマナー
納品書の受け渡し方には、注文された商品への同梱、商品とは別に郵送、持参、メール添付やWEB発行と、ケースはさまざまです。
送付する場合は、基本的なビジネスマナーに沿った適切な方法で届けましょう。以下で、納品書の送付方法のマナーを解説します。
納品書には送付状を付ける
納品書だけを単独で封筒に入れて送っても、納品書のタイトルを見れば相手には納品書であることが伝わります。しかし、それだけではあまりに簡略化したという印象を持たれかねません。
商品を購入してくれた取引先へは、送付状を付すことによって発注のお礼を伝えることができます。
また、納品書と同時に請求書を送る際にも同封物を記した添え状を付けることで、見落としなどを避けられます。
送付状のテンプレートについては、こちらの記事も参考にしてください。
納品書は長形3号の封筒に三つ折りに入れるのが一般的
納品書をA4サイズで印刷した場合、長形3号の封筒を使いましょう。長形3号は、横120mm×縦235mmで、A4サイズを横向きに三つ折りしてちょうどよく収まるサイズです。
郵送する場合、定形郵便物で送れる最大のサイズの封筒で厚さ1cmまで、重量は25g以内なら84円(2024年10月1日の価格改定後は、50gまで110円)で送れます。納品書は、送付状と一緒にずれないように重ね、表面を内側に横に三つ折りになるように書類の下を先に折り上げ、上から下に被せるように折りましょう。
なお、折ると厚みが出てかさばる場合や、どうしても折りたくない場合などは、角形2号サイズの封筒がジャストサイズです。角形2号は定形外郵便物となりますが、厚さ3cmまで、重量50g以内なら120円(2024年10月1日の価格改定後は、140円)で送ることができます。
封筒には「納品書在中」と記す
会社には毎日多数の郵便物が届きます。納品書が担当部署まで間違いなく届き、確実に開封してもらうには、封筒の表面に「納品書在中」と記載しておきましょう。
縦書きの場合は表面の左下に、横書きの場合は表面の宛名のやや右下に書いて定規を使用し四角で囲みます。手書きに限らずゴム印のスタンプを利用して封筒に印字しても構いません。
【1年間無料】フリーランスの見積・請求・申告は「Misoca×やよいの青色申告 オンライン」セットがお得!
納品書用紙は送付相手のことも考えて選びましょう
納品書は長期保管が義務付けられている重要な書類です。証憑書類にあたるため、必要事項を漏れなく記載して、正しい書式と適切な用紙のサイズで作成しましょう。
一般的にはA4サイズで作成します。納品書を作成して郵送する業務は、印刷や郵送のコストはもちろん、手間もかかります。手作業では封筒と納品書の宛名間違いなどの人的ミスが起こらないとも限りません。
このようなトラブルを避け、業務負担を軽減するためには「Misoca」のようなクラウド作成サービスの導入が有効的です。法改正などにもすぐに応できるため、誤った書類を作成する不安もありません。ぜひご検討ください。
【1年間無料】フリーランスの見積・請求・申告は「Misoca×やよいの青色申告 オンライン」セットがお得!
クラウド見積・納品・請求書サービスなら、請求業務をラクにできる
クラウド請求書作成ソフトを使うことで、毎月発生する請求業務をラクにできます。
今すぐに始められて、初心者でも簡単に使えるクラウド見積・納品・請求書サービス「Misoca」の主な機能をご紹介します。
「Misoca」は月10枚までの請求書作成ならずっと無料、月11枚以上の請求書作成の有償プランも1年間0円で使用できるため、気軽にお試しすることができます。
見積書・納品書・請求書をテンプレートでキレイに作成

Misocaは見積書 ・納品書・請求書・領収書・検収書の作成が可能です。取引先・品目・税率などをテンプレートの入力フォームに記入・選択するだけで、かんたんにキレイな帳票ができます。
各種帳票の変換・請求書の自動作成で入力の手間を削減

見積書から納品書・請求書への変換や、請求書から領収書・検収書の作成もクリック操作でスムーズにできます。固定の取引は、請求書の自動作成・自動メール機能を使えば、作成から送付までの手間を省くことが可能です。
インボイス制度(発行・保存)・電子帳簿保存法に対応だから”あんしん”

Misocaは、インボイス制度に必要な適格請求書の発行に対応しています。さらに発行した請求書は「スマート証憑管理」との連携で、インボイス制度・電子帳簿保存法の要件を満たす形で電子保存・管理することが可能です。
確定申告ソフトとの連携で請求業務から記帳までを効率化

Misocaで作成した請求書データは、弥生の確定申告ソフト「やよいの青色申告 オンライン」に連携することが可能です。請求データを申告ソフトへ自動取込・自動仕訳できるため、取引データの2重入力や入力ミスを削減し、効率的な業務を実現できます。
会計業務はもちろん、請求書発行、経費精算、証憑管理業務もできる!
法人向けクラウド会計ソフト「弥生会計 Next」では、請求書作成ソフト・経費精算ソフト・証憑管理ソフトがセットで利用できます。自動的にデータが連携されるため、バックオフィス業務を幅広く効率化できます。

「弥生会計 Next」で、会計業務を「できるだけやりたくないもの」から「事業を成長させるうえで欠かせないもの」へ。まずは、「弥生会計 Next」をぜひお試しください。
無料【クラウド請求書作成ソフト「Misoca」がよくわかる資料】をダウンロードする
この記事の監修者市川 裕子(ビジネスマナー監修)
マナーアドバイザー上級、秘書検定1級、ビジネス実務マナー、硬筆書写検定3級、毛筆書写検定2級、収納アドバイザー1級、など。 出版社や人材サービス会社での業務を経験。秘書業務経験よりビジネスマナーとコミュニケーションの重要性に着目し、資格・スキルを活かし、ビジネスマナーをはじめとする各種マナー研修や収納アドバイザー講師として活動。











