概算見積書とは?必要性や正式見積書との違い、書き方を解説
監修者: 高崎文秀(税理士)
更新
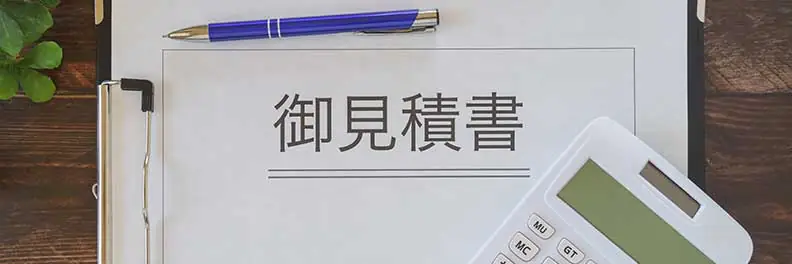
概算見積書とは、正式な契約を結ぶ前の検討段階で、おおよその費用を提示するための見積書です。取引の初期段階でよく使用されますが、「概算と正式、どちらを出すべきか迷う」「概算見積書の書き方がわからない」と悩む方も少なくありません。
そこで本記事では、概算見積書の役割や正式見積書との違い、書き方のポイントについてわかりやすく解説します。併せて、概算見積書を活用するメリットや、トラブルを防ぐために注意すべき点も紹介しています。
無料【クラウド請求書作成ソフト「Misoca」がよくわかる資料】をダウンロードする
概算見積書とは
概算見積書とは、正式な契約前に提示される「おおよその金額」を示した見積書です。主に商談中など契約が決まる前の初期段階や、買手側の希望がまだはっきりとは固まっていない段階で使用します。記載される金額はあくまで目安であり、最終的な請求金額とは異なる場合があります。
一般的に、概算見積書における金額の精度は「−25%から+50%」程度とされており、ある程度の誤差を前提としています。概算見積書は、買手側との初期のコミュニケーションにおいて、おおよその費用を早めに共有し、費用や納期などをすり合わせるために重要な書類です。
概算見積書の必要性
概算見積書が必要とされる主なシーンの1つが、買手側が相見積もりを行う場合です。複数の業者から見積もりを取り寄せて比較検討する際、まずはおおよその費用感を把握する手段として、概算見積書が活用されます。
また、買手側が社内で予算を確保する目的で概算見積書を求めるケースもあります。概算見積書は、事前に大まかな金額を把握し、それを基に予算承認プロセスを進めるための資料とする場合や、経営層が新規プロジェクトへの投資を判断する際の検討材料として使用するケースも少なくありません。
概算見積書と正式見積書の違い
概算見積書と正式見積書の違いは、主に以下の3つの点になります。
-
- 金額の精度
- 発行のタイミング
- 法的拘束力
概算見積書は、あくまでおおよその金額を示すものです。それに対して、正式見積書では、詳細な打ち合わせを基に正確な金額が記載され、一般的な精度は「−5%から+10%」です。どちらの見積書も金額が変更される可能性はありますが、正式見積書の方が信頼性は高いです。
また、概算見積書は、プロジェクトや取引の初期段階で発行されるのが一般的です。買手側の希望がまだ固まっていない場合や、予算の目安を知りたい場合に使われることが多いです。正式見積書は、詳細な仕様や条件が明確になった段階で発行され、契約締結や正式発注の直前に提示されることが多いです。
そして、概算見積書には法的な拘束力はなく、参考資料としての性質が強いです。そのため、後から金額や条件が変更されることもよくあります。それに対して、正式見積書は契約の基礎となるものであり、発注書などと合わせて双方の合意が確認されれば、法的に契約が成立したとみなされます。このような背景から、正式見積書に有効期限を設けるなど法的な効力に制限を設けて、期間を明確にしておくことが一般的です。
見積書の書き方についての詳細は以下の記事で解説していますので、参考にしてください。
【無料でお試し!】クラウド見積書作成ソフト「Misoca」で見積書がかんたんきれいに完成
概算見積書を作成するメリット
概算見積書は、買手側とのコミュニケーションを円滑にし、商談を有利に進めるうえでも大きな役割を果たします。ここでは、概算見積書を作成することで得られる主なメリットについて解説します。
商談を有利に進められる可能性がある
見積もりの際に求められることが多い概算見積書は、内容によっては商談を有利に進める材料になります。買手側は複数の企業から提出された概算見積書を比較し、条件の良い提案を選びます。費用や納期、材料、仕様などの面で他社よりも有利な内容を提示できれば、自社の強みを効果的にアピールできます。
ただし、実際の内容とかけ離れた金額を提示すると、正式な見積書を発行する段階でトラブルに発展する可能性があるため注意が必要です。後述する概算見積書の書き方などを参考にしてください。
予算化の働きかけを行える
商談時に買手側がまだ予算を確保していない場合は、概算見積書を発行することで予算の準備を促すことができます。特に法人の場合は、概算見積書があることで、決裁者から出費の承認を得やすくなり、社内での予算確保を後押しできます。
予算が確保されている場合でも、概算見積書に対する買手側の反応を確認することで、必要に応じた内容の調整が可能です。見積もりを基に具体的なコミュニケーションを重ねることで、買手側の要望に柔軟に対応でき、取引成立の可能性も高まります。
【無料でお試し!】クラウド見積書作成ソフト「Misoca」で見積書がかんたんきれいに完成
概算見積書の書き方
概算見積書は、あくまで「おおよその金額」を伝える資料であるため、伝え方を誤ると後々トラブルにつながる可能性があります。そうしたリスクを避けるためにも、作成時にはいくつかのポイントをしっかり押さえておくことが重要です。
タイトルに「概算見積書」と明記する
まず、冒頭にタイトルとして「概算見積書」と明確に記載しましょう。単に「見積書」とだけ記載すると、買手側に確定金額と誤解される可能性があります。その結果、後になって記載金額での対応を求められるなど、トラブルに発展することもあるため注意が必要です。
「概算見積書」と明示しておくことで、あくまで暫定的な見積もりであると伝えられ、不要な誤解や混乱を避けられます。
見積番号や日付を付与する
概算見積書にも、正式見積書と同様に見積番号と発行した日付を必ず記載します。見積番号は、重複しないように規則性を持たせた採番ルールを自社・自事業所内で設けておくのがおすすめです。例えば、取引先のコードと請求月の組み合わせで採番する場合、A社は「001」B社は「002」と取引先のコードを設定します。これに、請求月を採番すると以下のようになります。
-
- A社に対して2025年7月締めの請求書を作成する場合 → 001-202507
- B社に対して2025年8月締めの請求書を作成する場合 → 002-202508
また、日付も「いつの時点の情報か」を把握するうえで不可欠な項目です。これらを明記しておけば、見積書の検索や再発行がしやすくなり、自社・自事業所での管理が容易になります。さらに、買手側からの問い合わせにも迅速に対応できます。
取引先企業名などを記載する
正式見積書と同様に、概算見積書にも取引先の企業名や担当者情報を明記しましょう。どの企業に向けた見積もりかを明確にするために、企業名の他、部署名や担当者名も正確に記載することが大切です。企業名には「御中」、担当者名には「様」を付けるなど、宛名の書き方にも注意しましょう。
取引先の情報に加え、自社の情報も必ず記載します。会社名、住所、電話番号、メールアドレスなど、買手側がいつでも連絡できるよう、連絡先ははっきりと記載しておくことが重要です。
概算見積書の金額は「約●円」などと記載する
概算見積書には、正式見積書と同様に数量・単位・金額を記載します。ただし、あくまで目安として提示する見積もりであるため、金額は「約●円」などの表記でも構いません。また、価格の変動が想定される場合には、「約●円~約●円」と幅を持たせた金額表示も可能です。このように記載することで、誤解を未然に防げるだけでなく、後の調整もしやすくなります。
概算見積書の有効期限や支払条件を明記する
概算見積書には、有効期限や支払条件も記しておきます。有効期限を記載することで、物価や為替レートなどの変動による予期せぬ損失を防げます。設定期間は業界や商材によって異なりますが、一般的には2週間〜6か月程度が目安とされています。
支払条件は、支払いの遅延や未払いといったトラブルを防ぐためにも重要な項目です。例えば、「納品後●日以内」や「●年●月●日までに支払い」といった期限を明確にし、「支払方法:銀行振込」などと併せて、振込手数料の負担をお願いする旨を記載しておくことで、トラブルを防ぎやすくなります。
ただし、概算見積書を発行する段階では、支払条件が未確定であるケースもあります。その場合は、「別途打ち合わせ」などと記載しておくと、柔軟な対応が可能になります。
概算見積書であることを摘要欄で示す
摘要欄(備考欄)には、概算見積書である旨を改めて示しておきます。これにより、正式な見積書とは異なることを買手側に再確認してもらえます。
その他、概算時と正式見積時で金額が変動する可能性がある点など、懸念事項についても摘要欄に記載しておくと安心です。例えば近年であれば、原材料費の高騰や為替変動などにより価格が上昇する可能性があるため、その旨を明記しておけば後のトラブルを防げます。
【無料でお試し!】クラウド見積書作成ソフト「Misoca」で見積書がかんたんきれいに完成
概算見積書を発行する際の注意点
概算見積書は正式な見積書とは異なり、ある程度の幅を持たせた金額を提示できる反面、内容によっては後々トラブルにつながる可能性もあります。信頼性の高い見積書として活用するために注意すべきポイントを解説します。
金額のブレ幅に注意する
概算見積書で提示する金額はあくまで目安であり、後の詳細な打ち合わせや実作業の進行にともない、金額が変動する可能性があることをあらかじめ明確に伝えておきましょう。
例えば、「約●円〜約●円」といった形で金額の幅を持たせることで、変動の可能性を自然に伝えることができます。ただし、幅を広げすぎると買手側に不信感を与える恐れがある一方、狭すぎると実際の費用と差が生じた際にトラブルの原因となるため、バランスが重要です。
一般的に、概算見積書の金額の精度は「−25%から+50%」の範囲内に収めるのが目安とされています。この範囲に基づいて見積もることで、後からのトラブルを未然に防げ、買手側との信頼関係の維持にもつながります。
金額の根拠を準備する
「概算」とは言っても、見積書の内容をあいまいにして良いわけではありません。金額を提示する以上、その根拠をしっかりと用意しておくことが重要です。
例えば、過去に同様の規模・条件で実施したプロジェクトがあれば、その実績データを基に金額を算出するのが有効です。買手側から金額について質問を受けた際に、明確な根拠を以て説明できれば、見積もりに対する信頼性が高まり、買手側との関係構築にもつながります。
提示までに時間をかけない
概算見積書が相見積もりに使われる場合、買手側はまだ発注先を検討している段階です。このタイミングで対応が遅れると、せっかくの受注チャンスを逃してしまう可能性があります。
買手側は、すばやく見積書を提示してくれた売手に信頼感やスピード感を覚え、そのまま正式な依頼を決めてしまうことも少なくありません。ある程度の精度を保つためには、金額の算出や根拠の整理に時間がかかることもありますが、時間をかけすぎないように注意しましょう。
【無料でお試し!】クラウド見積書作成ソフト「Misoca」で見積書がかんたんきれいに完成
概算見積書は可能な限り正確・迅速に提示しよう
概算見積書は、商談初期における信頼構築の第一歩となるツールです。金額の精度や根拠を意識しつつ、スピーディーに提示することで、受注の可能性を高められます。その一方で、対応が遅れたりあいまいな内容を示したりすると、機会損失や信頼低下のリスクもあるため注意しましょう。
見積書作成には、クラウド請求書作成ソフト「Misoca」の活用がおすすめです。見積書から請求書まで一括管理でき、正確で効率的な業務運用を実現します。「Misoca」では、スマホでも見積書作成ができるので、訪問先や外出先での作成や修正も可能です。迅速な提案をサポートいたします。
【無料でお試し!】クラウド見積書作成ソフト「Misoca」で見積書がかんたんきれいに完成
クラウド見積・納品・請求書サービスなら、請求業務をラクにできる
クラウド請求書作成ソフトを使うことで、毎月発生する請求業務をラクにできます。
今すぐに始められて、初心者でも簡単に使えるクラウド見積・納品・請求書サービス「Misoca」の主な機能をご紹介します。
「Misoca」は月10枚までの請求書作成ならずっと無料、月11枚以上の請求書作成の有償プランも1年間0円で使用できるため、気軽にお試しすることができます。
見積書・納品書・請求書をテンプレートでキレイに作成

Misocaは見積書 ・納品書・請求書・領収書・検収書の作成が可能です。取引先・品目・税率などをテンプレートの入力フォームに記入・選択するだけで、かんたんにキレイな帳票ができます。
各種帳票の変換・請求書の自動作成で入力の手間を削減

見積書から納品書・請求書への変換や、請求書から領収書・検収書の作成もクリック操作でスムーズにできます。固定の取引は、請求書の自動作成・自動メール機能を使えば、作成から送付までの手間を省くことが可能です。
インボイス制度(発行・保存)・電子帳簿保存法に対応だから”あんしん”

Misocaは、インボイス制度に必要な適格請求書の発行に対応しています。さらに発行した請求書は「スマート証憑管理」との連携で、インボイス制度・電子帳簿保存法の要件を満たす形で電子保存・管理することが可能です。
確定申告ソフトとの連携で請求業務から記帳までを効率化

Misocaで作成した請求書データは、弥生の確定申告ソフト「やよいの青色申告 オンライン」に連携することが可能です。請求データを申告ソフトへ自動取込・自動仕訳できるため、取引データの2重入力や入力ミスを削減し、効率的な業務を実現できます。
会計業務はもちろん、請求書発行、経費精算、証憑管理業務もできる!
法人向けクラウド会計ソフト「弥生会計 Next」では、請求書作成ソフト・経費精算ソフト・証憑管理ソフトがセットで利用できます。自動的にデータが連携されるため、バックオフィス業務を幅広く効率化できます。

「弥生会計 Next」で、会計業務を「できるだけやりたくないもの」から「事業を成長させるうえで欠かせないもの」へ。まずは、「弥生会計 Next」をぜひお試しください。
無料【クラウド請求書作成ソフト「Misoca」がよくわかる資料】をダウンロードする
この記事の監修者高崎文秀(税理士)
高崎文秀税理士事務所 代表税理士/株式会社マネーリンク 代表取締役
早稲田大学理工学部応用化学科卒
都内税理士事務所に税理士として勤務し、さまざまな規模の法人・個人のお客様を幅広く担当。2019年に独立開業し、現在は法人・個人事業者の税務顧問・節税サポート、個人の税務相談・サポート、企業買収支援、税務記事の監修など幅広く活動中。また通常の税理士業務の他、一般社団法人CSVOICE協会の認定経営支援責任者として、業績に悩む顧問先の経営改善を積極的に行っている。











