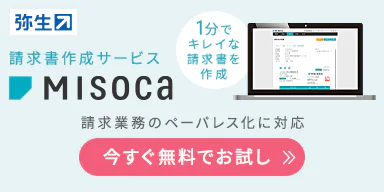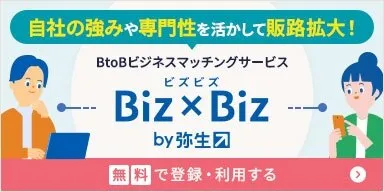納品書兼請求書とは?発行するケースや書き方、作成時の注意点を解説
監修者: 高崎文秀(税理士)
更新
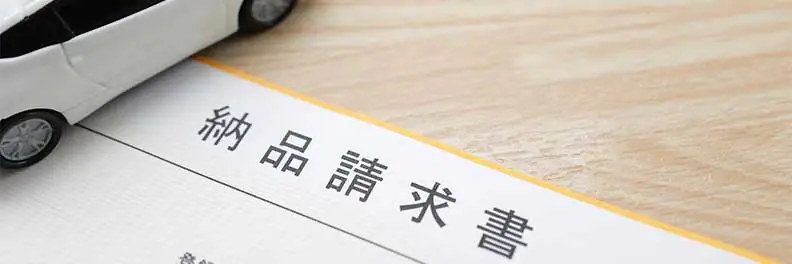
納品書兼請求書は、納品書と請求書が一緒になっている書類です。主に注文を受けてから商品やサービスの提供を行う際に発行します。納品書兼請求書を取り入れて適切に作成することによって、書類作成に関連するコストの削減や業務効率化などのメリットも実現します。本記事では、納品書兼請求書の概要や、作成に適した取引の特徴、書類の作成方法、作成時の注意点などを解説します。
納品書兼請求書とは
企業が商品やサービスの売買取引を行う場合に作成する書類には、納品書や請求書があります。どちらも取引の内容を記載する書類ではあるものの、それぞれ発行する時期や詳細な記載内容などは異なります。納品書兼請求書は、この2種類の書類と同じ役割を持つ書類です。
納品書の役割
納品書とは、商品やサービスなどを提供する際に、一緒に渡す書類です。商品・サービスの種類や数量、単価、合計金額などが書かれているため、品物の種類や数量などに間違いがないかチェックするために使用します。納品書は法律で発行が義務付けられているものではありません。ただし、発行した場合には、受領した側も含めて、控えや原本を一定期間保管する義務が生じます。
納品書があると、発注した側は届いた品物の品名や数量などの内訳を確認できます。これにより、注文とは異なる品物や不良品などが届いた場合にも早急な対応を依頼できます。また、請求書が届いた際に請求金額が合っているかといった確認も可能です。その一方で、発行側には品物の誤発送といったトラブルを防ぐ目的があります。そのため、多くの事業者が商品・サービスを発送する際に納品書を作っています。
請求書の役割
請求書は、商品やサービスの売上金額を請求する際に作成する書類です。受注側が発注側に宛てた請求書を作り、発注側は受け取った請求書に書かれている請求金額を支払います。請求書も法的な発行義務がある書類ではありません。しかし、発注側に対して正しい金額を知らせる目的やトラブルを防止する効果があるため、ほとんどの事業者が請求書を作って送付しています。請求書は債権の一種でもあることから、発行後5年の間は売上金額の請求も可能です。
また、請求書の形式は法律で定められていないため、比較的自由な形式で作成が可能です。ただし記載が必要な項目はあるため、書き方には注意しなければなりません。記載が必要な項目は、請求者の名称、取引先の名称、取引年月日、取引内容、税込みの金額などです。必要な項目が書かれている場合には、形式に関わらず請求書として認められます。
請求書を作成する時期は、必ずしも納品書と同じとは限りません。注文があった品物を納品して取引が完了した際に作成・請求するケースと、複数回の取引が完了してから売り上げの合計額をまとめて請求するケースがあります。
納品書兼請求書の役割
納品書兼請求書とは、納品書と請求書、両方の機能を持つ書類のことです。複数回の取引金額を月の締め日にまとめて請求している場合には、納品と請求の時期が異なるため、納品書と請求書を同時に渡すことはありません。
その一方で、1回の取引ごとに代金の請求を行う「都度方式」や単発の取引の場合には、納品書と請求書を同時に渡します。そこで、2種類の書類の代わりにできるのが納品書兼請求書です。納品書兼請求書があると、納品書と請求書の両方を作ってから送付する必要がなくなり、やり取りの簡略化や、書類の管理業務の効率化などにもつながります。
納品書兼請求書を発行する主なケース
前述のとおり、納品書兼請求書は都度方式の取引や単発の取引などで使用されます。しかし、何度も取引を行っており信頼関係ができている相手先との取引は、多くの場合「掛売方式」で行われるため、請求書は、相手先の締め日に合わせて発行します。また、納品日と請求日が違うため「掛売方式」では、基本的に納品書兼請求書は使用できません。なお、プログラムやデザインなど、実際に品物を発送する必要がない取引の場合も、納品書兼請求書が使用されます。
納品書兼請求書にも法律上の保存義務がある
納品書兼請求書は取引内容が書かれている証憑書類のため、発行後または受領後には一定期間保存しなければなりません。保存期間は、法人税法では事業年度の確定申告書の提出期限翌日から7年間と定められています。発行した側は書類の控えを、受領した側は原本を一定期間保存します。
紙で作った書類を受領した場合には紙のまま保存する他に、スキャナ保存も認められています。その一方で、PDFで発行した納品書兼請求書を電子メールで受領した場合のように、電子データでやり取りした場合は発行側も受領側も電子データで保存しなければならないため、保存方法にも注意が必要です。法律で定められた方法と期間を守り、保存する必要があります。
出典:国税庁「No.5930 帳簿書類等の保存期間」
納品書兼請求書として発行するメリット
納品書兼請求書の発行には、作成や発送時のコストや手間の削減など、さまざまなメリットがあります。
コストを削減できる
書類を作る際、郵送する際には、用紙代やインク代、封筒代、切手代などのコストがかかります。納品書と請求書をそれぞれ別で作っていると、納品時と請求時に各コストがかかります。その一方で、納品書兼請求書を使用する場合には、書類枚数の削減が可能です。納品時、請求時に2種類の書類をそれぞれ発行する必要がなくなるため、コスト削減につながります。取引社数や取引件数が多い企業ほど書類の発行や発送にコストがかかっているため、納品書兼請求書を活用するとコスト削減が期待できます。
かかる手間や時間を削減できる
納品書と請求書の両方を発行している場合は手間や時間がかかります。納品書や請求書は正確に作成しなければなりません。作成時には、取引内容や数量、金額などを十分に確認する必要があり、作成後にも封筒に入れて郵送するなどの手間がかかります。納品書兼請求書を発行する場合、納品書と請求書をまとめて1つの書類として作れるため、それまで各書類の作成にかかっていた手間や時間を削減できます。納品書や請求書の発行数が多い企業ほど削減効果が高く、業務効率化が可能です。効率的に書類を作成できるため、繁忙期にもスムーズに仕事ができてミスの発生も防げます。書類作成にかかっていた時間が軽減できると、他に取り組むべき業務や企業の利益に直結する業務に時間を割けることから、売り上げの向上にもつながります。
書類の管理が楽になる
納品書と請求書の両方の機能を備えた納品書兼請求書を使用すると、書類を確認する際や、保存の際に管理がしやすくなります。例えば経理業務では、納品書と請求書が一緒になっているため、取引内容や売上金額などの確認をスムーズに行えます。
保管スペースをスリム化できるというメリットもあります。紙の納品書と請求書を保存する場合は長期間保管するためのスペースが必要です。納品書兼請求書を使用すれば、これまで保存が必要だった書類の枚数が単純に半分になります。
納品書兼請求書の書き方・作成方法
納品書兼請求書は、発行義務自体はありません。ただし記載すべき項目は決まっているため、必要事項を漏らさずに記載することが大切です。
納品書兼請求書に記載する項目
納品書兼請求書に記載が必要な項目は以下のとおりです。
- 作成する人の氏名・名称:納品書兼請求書を発行する事業者の名称、住所、連絡先など
- 取引年月日:納品書兼請求書には納品書の役割もあるため、納品日を記載
- 取引内容:販売した商品やサービスの品名、数量など
- 請求金額:販売した商品やサービスの単価、消費税、小計、消費税込みの合計額など
- 領者の氏名・名称:商品やサービスを依頼した事業者の氏名や企業名、住所、部署名、必要に応じて担当者名も記載
なお、納品書とよく似ている書類ですが、あくまでも請求書も兼ねる書類なので、タイトルには「納品書兼請求書」と記載します。
インボイスとして発行する場合に必要な項目
納品書兼請求書は、「インボイス(適格請求書)」として用いられる場合もあります。インボイス(適格請求書)に用いる場合には、法律で定められた一定の項目の記載が必要です。国税庁によると、記載すべき項目は、以下のとおりです。
- 作成する人の氏名・名称および登録番号
- 取引年月日
- 取引内容(軽減税率の対象となる品目である旨)
- 適用になる税率別に区分し算出した税込み金額合計
- 適用になる税率別に区分し算出した消費税額等合計
- 受領者の氏名・名称
出典:国税庁「No.6625 適格請求書等の記載事項」
納品書兼請求書を作成する際の注意点
納品書兼請求書は、取引年月日、送付先、送付のタイミングなどに注意して作ります。取引先によって、記載すべき日付や送付先などが異なる場合もあるため、事前に確認することが大切です。
取引年月日を確認する
取引年月日に書き込む日付は、納品日が基本です。実際の納品日の他には、出荷日や到着予定日、検収日などがあります。自社が基準にしている日付を書き込んだ場合、後から取引先に到着日や検収日にして欲しいといわれるケースもあるため、注意しなければなりません。実際に納品書兼請求書を発行する前に、相手先に日付の希望があるかどうかを確認しておくことが大切です。
送付先を確認する
送付する際には、どこに送るべきかにも注意します。例えば営業所や店舗と、本社の住所が異なるケースがあります。このようなケースでは、納品書兼請求書を本社の経理担当部門に送り、品物を営業所や店舗に送る場合も少なくありません。
その一方で、商品の納品先と同じ営業所や店舗に送るケースや他の営業所に送るケースなどもあります。誤った住所に送るリスクをなくすためには、事前に取引先に確認しておくことが大切です。納品書兼請求書の送付先と指定された納品先が異なる場合は、送り先の間違いにも注意が必要です。
送付するタイミングを確認する
多くの場合、納品書兼請求書は品物の納品時に送付する、または直接渡します。これは、相手先が届いた品物の品名や数量をチェックする際や、請求時に代金を確認する際などに納品書兼請求書を用いるためです。送付のタイミングが納品よりも早い場合や遅い場合には、取引先がスムーズに確認できず業務に支障をきたす原因になるため注意が必要です。事情があって送付するタイミングがずれこむ場合には、相手先にあらかじめ連絡しておきましょう。
担当者不在時は指示を仰ぐ
品物の納入時に納品書兼請求書を渡す際には、取引先の担当者に渡します。納品先に担当者がいなかった場合、そのまま別の人に品物を渡して済ませてしまうのではなく、担当者に連絡をすることが大切です。担当者に確認を取った際に、品物と納品書兼請求書を届ける旨を伝えられた際には納品を完了します。また、品物と一緒に納品書兼請求書を届けるよう指示があった場合には、封筒に入れて書類が外から見えない状態にしておきます。ただし、納品書兼請求書は信書に該当するため、納入口は閉じないようにしましょう。
納品書兼請求書もPDFでのやり取りが可能
電子帳簿保存法には、保存が義務付けられている各種書類に関して、電子データでの保存方法や要件などが定められています。電子帳簿保存法の改正によって、2024年1月1日以降に電子データで受け取った書類の電子保存が義務化されました。納品書兼請求書は、電子帳簿等保存、スキャナ保存、電子取引のデータ保存のいずれかの方法で保存が可能です。
国税関係帳簿書類の電磁的記録による保存の場合
国税関係帳簿書類の電磁的記録による保存とは、会計システムやパソコンなどで作成した帳簿や書類などのデータを、印刷しないでデータのまま保存する方法のことです。データは、クラウド上での保存が可能です。
この方法は任意なので、会計システムやパソコンなどで作成した納品書兼請求書を、プリントアウトして保存することもできます。
スキャンして保存する場合
スキャンして保存する方法は、受け取った紙の書類を紙のまま保存する代わりに、スキャナやスマートフォンのカメラなどで読み取った電子データとして保存する方法です。発行側が納品書兼請求書を紙で作成して送付した場合でも、受領側はそれをスキャンしてPDFデータにしてから保存できます。この方法も任意なので、紙で受け取った納品書兼請求書を、紙のまま保存すること自体は可能です。
電子取引のデータで保存する場合
電子取引のデータで保存する方法は、電子データでやり取りした書類を、その電子データのまま保存する方法です。例えば、電子メールにPDFデータを添付して送付する方法や、クラウド請求書発行システムに記載したURLから受領してもらう方法などがあります。
電子帳簿等で保存する場合とスキャンして保存する場合とは異なり、この方法は義務です。受領側が受け取った電子データをデータのまま保存する必要があるのはもちろん、発行側も電子データで作成・送付した場合には電子データで保存します。保存するファイルの形式は問いません。PDF化したデータの他にスクリーンショットをデータで保存することも可能です。
納品書兼請求書は日付と送付日に注意しよう
納品書兼請求書とは、納品書と請求書両方の機能を備えた書類です。納品された商品のチェックや、請求金額の確認などに用いられます。作成時には、記載する日付や送付するタイミングなどに注意しましょう。また、必要な項目を記載している場合には、インボイス(適格請求書)としての使用も可能です。
納品書兼請求書の作成や送付を効率的に行うには、クラウド請求書作成ソフトの使用が適しています。クラウド請求書作成ソフト「Misoca」ならテンプレートで簡単に作成可能です。PDFの発行や送付はワンクリックで完了できるため、業務効率化が実現します。
クラウド見積・納品・請求書サービスなら、請求業務をラクにできる
クラウド請求書作成ソフトを使うことで、毎月発生する請求業務をラクにできます。
今すぐに始められて、初心者でも簡単に使えるクラウド見積・納品・請求書サービス「Misoca」の主な機能をご紹介します。
「Misoca」は月10枚までの請求書作成ならずっと無料、月11枚以上の請求書作成の有償プランも1年間0円で使用できるため、気軽にお試しすることができます。
見積書・納品書・請求書をテンプレートでキレイに作成

Misocaは見積書 ・納品書・請求書・領収書・検収書の作成が可能です。取引先・品目・税率などをテンプレートの入力フォームに記入・選択するだけで、かんたんにキレイな帳票ができます。
各種帳票の変換・請求書の自動作成で入力の手間を削減

見積書から納品書・請求書への変換や、請求書から領収書・検収書の作成もクリック操作でスムーズにできます。固定の取引は、請求書の自動作成・自動メール機能を使えば、作成から送付までの手間を省くことが可能です。
インボイス制度(発行・保存)・電子帳簿保存法に対応だから”あんしん”

Misocaは、インボイス制度に必要な適格請求書の発行に対応しています。さらに発行した請求書は「スマート証憑管理」との連携で、インボイス制度・電子帳簿保存法の要件を満たす形で電子保存・管理することが可能です。
確定申告ソフトとの連携で請求業務から記帳までを効率化

Misocaで作成した請求書データは、弥生の確定申告ソフト「やよいの青色申告 オンライン」に連携することが可能です。請求データを申告ソフトへ自動取込・自動仕訳できるため、取引データの2重入力や入力ミスを削減し、効率的な業務を実現できます。
会計業務はもちろん、請求書発行、経費精算、証憑管理業務もできる!
法人向けクラウド会計ソフト「弥生会計 Next」では、請求書作成ソフト・経費精算ソフト・証憑管理ソフトがセットで利用できます。自動的にデータが連携されるため、バックオフィス業務を幅広く効率化できます。

「弥生会計 Next」で、会計業務を「できるだけやりたくないもの」から「事業を成長させるうえで欠かせないもの」へ。まずは、「弥生会計 Next」をぜひお試しください。
この記事の監修者高崎文秀(税理士)
高崎文秀税理士事務所 代表税理士/株式会社マネーリンク 代表取締役
早稲田大学理工学部応用化学科卒
都内税理士事務所に税理士として勤務し、さまざまな規模の法人・個人のお客様を幅広く担当。2019年に独立開業し、現在は法人・個人事業者の税務顧問・節税サポート、個人の税務相談・サポート、企業買収支援、税務記事の監修など幅広く活動中。また通常の税理士業務の他、一般社団法人CSVOICE協会の認定経営支援責任者として、業績に悩む顧問先の経営改善を積極的に行っている。