納品書と請求書の違いとは?役割・記載項目の違いや似ている書類も解説!
監修者: 中川 美佐子(税理士)
更新
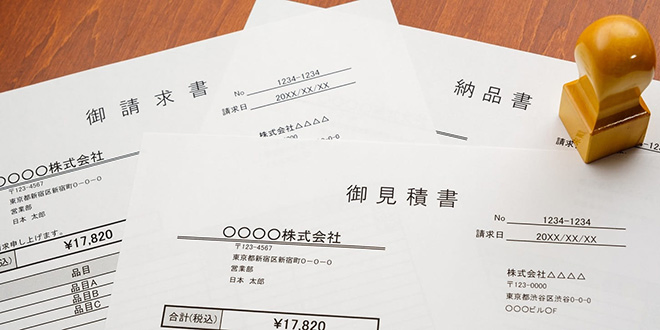
商取引における証憑書類は、納品書、請求書、見積書、注文書、請書(注文請書)、検収書、請求書など多種多様です。取引をスムーズに成立させるためには、これらの書類の違いを把握したうえで、適切な書類を発行しなければなりません。また、インボイス制度や改正電子帳簿保存法など、最新の法律への対応も不可欠です。そこで本記事では納品書と請求書を中心に、それぞれの証憑書類の概要や記載項目、発行時の注意点などをわかりやすく解説します。本記事を読むことで、納品書・請求書などの発行のために必要な基本知識を得ることができます。
納品書と請求書の違いは?それぞれの役割や発行のタイミング
納品書と請求書は役割や発行のタイミングが似ていることもあり、混同しがちです。しかし両者には以下のような違いがあります。
納品書とは
納品書は、商品・サービスを提供したことを証明する書類です。納品書には納品物の内容や数量、納品日などが記載されており、発注通りに取引が行われたか確認するために用いられます。納品書は商品・サービスを納品するごとに、納品と同時に発行されるのが一般的です。商品と同梱されていることもよくあります。
請求書とは
請求書は、提供した商品・サービスの代金の支払いを発注者に求めるための書類です。請求対象の品目や金額、支払方法、支払期限などが記載されており、発注者はこれらの情報を基に支払処理を行います。
請求書の発行タイミングは、「商品・サービスの納品時」か「事前に取り決めた締め日」です。単発の取引の場合は納品ごとに、継続的な取引の場合は締め日にこれまでの取引内容をまとめて請求することが一般的です。
納品書に記載する主な項目
納品書の記載事項は、厳密には明確なルールは存在しません。しかし、消費税法に基づく仕入税額控除を適用するためには、以下の項目を最低限含めることが求められます。
- 発行者の氏名または名称
- 宛名(受取側の氏名または名称)
- 取引年月日
- 納品内容(品名、数量、軽減税率の対象である旨など)
- 合計金額(税率ごとに区分された消費税込み合計金額)
なお、小売業・飲食店業・タクシーなどの一部事業者は宛名を省略することが認められています。
請求書に記載する主な項目
2023年10月からインボイス制度が開始されました。この制度によって、請求書に記載すべき項目は、発行するのが適格請求書(インボイス)なのか、簡易適格請求書(簡易インボイス)なのか、それとも自社がインボイスを発行できない免税事業者なのかによって、以下のように変わります。
適格請求書(インボイス)の場合
適格請求書発行事業者は、適格請求書(インボイス)を発行できます。適格請求書には、以下の項目を記載することが必要です。
-
①書類作成者の氏名または名称および登録番号
-
②取引年月日
-
③取引内容(軽減税率の対象品目である旨)
-
④税率ごとに区分して合計した税込対価(又は税抜対価)の額及び適用税率
-
⑤税率ごとに区分した消費税額等
-
⑥書類の交付を受ける事業者の氏名または名称
引用:国税庁「No.6625 適格請求書等の記載事項」
適格簡易請求書(簡易インボイス)の場合
適格請求書発行事業者のうち、小売業や飲食店業などの一部の業種は適格簡易請求書(簡易インボイス)の発行が可能です。簡易インボイスの場合、インボイスで必要な記載事項のうち、上記④の適用税率か⑤のどちらか、そして⑥の記載を省略できます。
免税事業者の請求書の場合
消費税の免税事業者は、適格請求書発行事業者には登録できないため、インボイスの発行ができません。そのため、免税事業者は以下のように、従来の区分記載請求書と同じ項目を請求書に記載します。
- 発行者の氏名または名称
- 取引年月日
- 取引内容(軽減税率の対象品目である旨)
- 税率ごとに区分して合計した請求額
- 宛名(請求先の氏名または名称)
納品書・請求書と類似する書類の種類と役割
納品書・請求書以外にも、証憑書類には以下のような種類があります。
見積書
見積書は、発注・契約前に発注者がその発注内容の見積額を確認するために、受注者が発行する書類です。発注者は見積書を基に取引内容と単価などを事前確認したり、他社の商品・サービスと比較検討したりします。発注者と受注者の間で費用や納期などの認識を事前に共有し、認識のずれを防ぐためにも見積書は重要です。
注文書
買手側が発注をするために作成するのが「注文書」です。発注書と呼ばれることもあります。注文書には、希望する商品・サービスの内容や納期、納品方法などの事項を明確に記載することが大切です。
また、継続的な取引の場合や、見積書の内容をそのまま採用して発注することが多い場合は、「見積書兼発注書」という形で、同じ書面を使ってやり取りすることもあります。
請書(注文請書)
受注者(売手側)は注文書を受け取ったら、注文を確かに受けたことを相手に知らせるために「請書(注文請書)」を発行します。これにより発注者(買手側)も安心できます。商取引上は、注文書と注文請書が取り交わされたこの段階で契約が成立したとみなされます。
検収書
受け取った商品やサービスに欠陥や不具合がないのかを確認した後、買手側が発行するのが検収書です。検収書を発行するとその取引は終了し、売手側から請求書が発行されることになります。
納品書や請求書などの書類はすべて発行が必要?
納品書や請求書をはじめとする証憑書類は、必ずしも顧客や取引先に提出しなければならないものではありません。実際、個人事業主や中小企業の場合、こうした書類を介さず、口頭でのやり取りだけで取引を行うこともあります。
ただし、これらの書類がないと、万が一取引先とトラブルが発生したときに、取引の事実関係を証明することが非常に困難です。例えば売掛金が発生した場合は、注文書や発注書、検収書などの証憑書類がないと、取引があった事実を証明できず、代金を請求できなくなることもあります。そのため、証憑書類はこうしたトラブルの予防や対応をするために不可欠な書類です。
インボイスは発行側も受領側も保存義務がある
適格請求書発行事業者の場合、インボイスにあたる書類を受け取った側(買手側)は一定期間インボイスを保存する必要があります。また、発行した側(売手側)は控えを保存しなければなりません。具体的には、売手側・買手側共に、「受領した日の属する課税期間の末日の翌日から2か月を経過した日から7年間」が保存義務期間です。
引用:国税庁「No.6625 適格請求書等の記載事項」
特に買手側としてインボイスに該当する書類を受け取った場合、決められた保存期間の間はインボイスを保管しないと、仕入税額控除を受けることができません(消費税の簡易課税を選択している場合を除く)。
インボイスの保存形式は紙でも電子データでも構いません。ただし、電子帳簿保存法に従い、請求書も含めて電子データ形式で受け取った証憑書類は原則的に電子データのまま保存する必要があります。保存方法についても、電子帳簿保存法の要件に則って処理するようにしましょう。
納品書や請求書などの発行を省略するには?
証憑書類は工夫次第で省略可能です。例えば特定の会社と商品・サービスの取引を定期的に行う場合は、その都度書類を発行するのではなく、別途取引契約書を作成した方が効率的です。その契約書に毎月の発注量や支払方法、金額、検収方法などを明記することで、その都度書類をやり取りする手間が省けます。とはいうものの、納品・検収作業自体は、その都度適切に行い、取引の安全性を確保することが重要です。
また、納品書・請求書は発行のタイミングを同時にできるので、「納品書兼請求書」という形でひとつにまとめられます。インボイスに関しても、すべての書類をインボイス対応にする必要はありません。インボイス対応にする書類を絞りこむことで、作業負担を軽減できます。
納品書や請求書などの役割を知って適切に発行・保存しよう
納品書・請求書などの証憑書類は、それぞれ異なった役割や発行するタイミングがあります。取引をスムーズに成立させるためには、これらの違いを理解し、適切に発行・保存することが大切です。証憑書類は工夫次第で省略できるほか、Misocaなどの請求書作成ソフトを活用することで作業負担を軽減できます。インボイス制度や電子帳簿保存法などへの法対応も含め、証憑書類の管理業務に課題を感じている方は、ぜひ活用してください。
クラウド見積・納品・請求書サービスなら、請求業務をラクにできる
クラウド請求書作成ソフトを使うことで、毎月発生する請求業務をラクにできます。
今すぐに始められて、初心者でも簡単に使えるクラウド見積・納品・請求書サービス「Misoca」の主な機能をご紹介します。
「Misoca」は月10枚までの請求書作成ならずっと無料、月11枚以上の請求書作成の有償プランも1年間0円で使用できるため、気軽にお試しすることができます。
見積書・納品書・請求書をテンプレートでキレイに作成

Misocaは見積書 ・納品書・請求書・領収書・検収書の作成が可能です。取引先・品目・税率などをテンプレートの入力フォームに記入・選択するだけで、かんたんにキレイな帳票ができます。
各種帳票の変換・請求書の自動作成で入力の手間を削減

見積書から納品書・請求書への変換や、請求書から領収書・検収書の作成もクリック操作でスムーズにできます。固定の取引は、請求書の自動作成・自動メール機能を使えば、作成から送付までの手間を省くことが可能です。
インボイス制度(発行・保存)・電子帳簿保存法に対応だから”あんしん”

Misocaは、インボイス制度に必要な適格請求書の発行に対応しています。さらに発行した請求書は「スマート証憑管理」との連携で、インボイス制度・電子帳簿保存法の要件を満たす形で電子保存・管理することが可能です。
確定申告ソフトとの連携で請求業務から記帳までを効率化

Misocaで作成した請求書データは、弥生の確定申告ソフト「やよいの青色申告 オンライン」に連携することが可能です。請求データを申告ソフトへ自動取込・自動仕訳できるため、取引データの2重入力や入力ミスを削減し、効率的な業務を実現できます。
会計業務はもちろん、請求書発行、経費精算、証憑管理業務もできる!
法人向けクラウド会計ソフト「弥生会計 Next」では、請求書作成ソフト・経費精算ソフト・証憑管理ソフトがセットで利用できます。自動的にデータが連携されるため、バックオフィス業務を幅広く効率化できます。

「弥生会計 Next」で、会計業務を「できるだけやりたくないもの」から「事業を成長させるうえで欠かせないもの」へ。まずは、「弥生会計 Next」をぜひお試しください。
この記事の監修者中川 美佐子(税理士)
税務署の法人税の税務調査・申告内容の監査に29年勤務後、令和3年「
たまらん坂税理士法人」の社員税理士(役員)に就任。法人の暗号資産取引を含め、法人業務を総括している。










