領収書の日付の正しい書き方は?訂正方法や日付なしの場合の対処法を解説
監修者: 高崎文秀(税理士)
更新
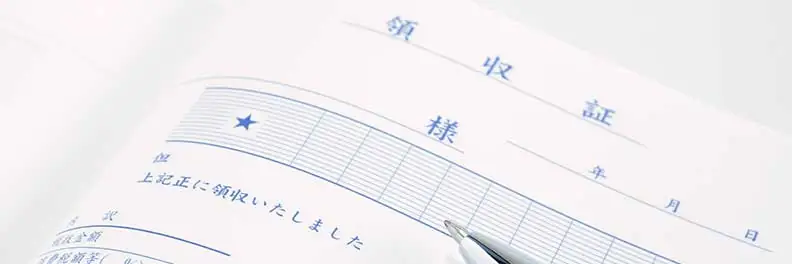
領収書には、経理処理や税務上の正確性を保つため、正しく日付を記載しなければなりません。日付の記載を誤ると不正を疑われる恐れがあり、正しい記載方法と対応が求められます。本記事では、領収書の発行者・受領者に向けて、領収書の日付の正しい書き方や日付の誤りに対処する方法について詳しく解説します。
領収書の日付の正しい書き方
領収書は取引の証明として発行される重要な書類です。そのため、日付の記載は必須であり、適切に記載しなければなりません。以下では、領収書の日付に関する正しい書き方について解説します。
実際の支払日の日付を記載する
領収書の日付欄には、実際に金銭の授受を行った日を記載します。売買契約が成立した日や商品の引き渡し日などと混同しないように注意が必要です。税務会計上、いつ金銭のやり取りが発生したのかを正確に記録することが重要だからです。誤った日付を記載してしまうと、税務調査時に指摘を受ける原因になります。カレンダーなどで確認し、正確な日付を記載することを心がけましょう。
また、改ざんが疑われないように、消せないボールペンを使用してはっきりと書くのが基本です。特に「1」と「7」、「4」と「9」、「0」と「9」など、数字の誤読を防ぐためにていねいに書くことが求められます。
和暦・西暦は略して記載しない
領収書の日付の欄には、和暦または西暦を省略せずに正しく記載する必要があります。
例えば、「2024/1/1」と記載すると、「2024年1月1日」であることが明白です。しかし、省略して「24/1/1」と記載した場合、「平成24年1月1日」と混同されることがあります。このため、「2024年1月1日」や「令和6年1月1日」といった表記が推奨されます。
また、日常的に「令和」を「R」と略して記載することがあります。しかし、領収書の日付欄に省略した表記は適していません。特に、アルファベット1文字表記は読み違えの原因になりやすく、税務署が不正を疑う要因にもなりかねません。和暦でも西暦でも、略さずに年月日を正確に記載することを徹底してください。
領収書に日付の記載が必要な理由
領収書に日付を記載することは、正確な経理処理において欠かせません。日付を正しく書く習慣が社内に浸透していれば、経理上の不正が生じにくくなります。また、万が一発生した場合でも、迅速に発見できる可能性が高まります。
金銭のやり取りが発生した証拠になるため
経理処理において、金銭を授受した正確な日付が重要です。日付入りの領収書は、「いつ代金を確かに受け取ったか」を示す証拠になります。また、日付入りの領収書には売買を証明する「証憑書類(しょうひょうしょるい)」としての役割を果たします。そのため、金銭のやり取りについて確認や照会が必要になった際に、日付は不可欠な要素です。
仮に領収書に日付がなければ、売上の多い月に支出を操作するなどして納税額を抑えるといった不正行為を行える余地が生まれます。このような不正を防ぐためにも、領収書には正確な日付を記載し、金銭のやり取りが発生したタイミングを明確に残す必要があります。
社内の不正を発見するため
領収書の日付記載には、経費における不正防止の効果があります。日付などの記載を厳守する習慣が社内にあれば、不正な改ざんや二重発行など不自然な領収書を発見しやすくなります。また、日付の確認によって発見できる不正もあります。例えば、土・日や祝日などの所定休日にもかかわらず、接待用の飲食店領収書が発行されているようなケースは、業務外での使用が疑われます。そのため、プライベート利用ではないかという指摘が可能です。
領収書の日付が間違っている場合の対処法
領収書の日付は正確に記載することが重要ですが、誤って記載してしまう場合もあります。また、受け取った領収書の日付が間違っていることに気付く場合もあるかもしれません。そうした場合には、焦らずに対処することが大切です。以下では、発行者側と受領者側のそれぞれの対応方法について解説します。
発行者側
発行者が日付の誤りに気付いた場合、誤った領収書を破棄し、新しいものを再発行するのが基本です。発行前であれば、訂正した領収書を発行してください。ただし、再発行が難しい事情がある場合は、定められた方法で訂正処理を行います。
訂正の際は、誤って記載した部分に二重線を引き、訂正印を押したうえで正しい日付を加筆します。訂正印には会社の印鑑や担当者の印鑑を使用し、さらに会社の角印を添えることで、より正式な対応となり信頼性が高まります。ただし、訂正された領収書は、税務署の確認対象になる可能性があるため、再発行が可能であれば再発行を優先するのが望ましいです。
受領者側
受領者が自ら領収書の日付を修正することはできません。領収書は、金銭を受け取った発行者が正式に記載する書類であるためです。受領した領収書に日付の誤りがある場合は、速やかに発行者に連絡し、再発行を依頼してください。この際、発行者が元の領収書の破棄を求めることがあります。そのため、新しい領収書を受け取る際には、元の領収書を持参しましょう。
領収書が日付なしになっている場合の対処法
日付が記載されていない領収書を発行・受領してしまう場合があります。その場合も慌てずに、正しい方法で対処することが重要です。
発行者側は後日日付を記入する
発行者が日付の記載を忘れてしまった場合、後日追記することが可能です。時間が経過して支払日がわからない場合、売上データや支払確認書などの記録と照合し、正確な日付を確認したうえで記載しましょう。
受領者側は日付を別紙にメモして保管する
受領者が日付なしの領収書を受け取った場合、日付を直接加筆してはいけません。領収書偽造などの不正を疑われる原因になります。発行者に連絡できる場合は、再発行を依頼し、正しい日付を記載してもらうのが望ましいです。連絡が難しい場合は、日付を別紙にメモし、日付の証拠となる他の帳票と併せて保管してください。
領収書を過去の日付で発行するケースについて
上述のとおり、領収書は金銭の授受が発生した当日に記載することが基本です。しかし、状況によっては過去の日付での発行が必要となる場合や、顧客からそのような要望を受ける場合もあります。
後日発行する際の注意点
領収書は後日発行することが可能です。例えば、レシートから領収書への差し替えを依頼される場合などが考えられます。領収書の後日発行を依頼された場合、必ずレシート等の取引の証拠となる書類を確認してください。取引の証拠がないまま対応することは、脱税を目的とした架空取引に加担する可能性があるため、慎重な対応が求められます。なお、レシート等は回収してください。
再発行を求められた場合
領収書の再発行を求められた場合、発行者は安易に応じないのが賢明です。原則として再発行の要求に応じる義務はありません。発行者・受領者双方が、二重発行による不正の疑いを受けるリスクを伴います。どうしても再発行に応じる場合は、「再発行」とはっきり領収書に明示し、前の領収書と再発行された領収書の両方の控えを一緒に保管してください。また、トラブルを未然に防ぐため、「領収書の再発行はしない」という方針を事前に取引先に通知することも有効です。
領収書の日付は正しく記載しよう
領収書の日付は、正しく記載する必要があります。金銭の授受があった日を、和暦・西暦を省略することなく、正確に記載してください。日付に誤りがあった場合、再発行をするなど、税務署から不正を疑われることがないよう、正しい対処を心がけましょう。
クラウド請求書作成ソフトを用いて領収書を作成すると、日付の記載漏れといった基本的なミスがなくなり、請求業務が簡単かつ正確になります。特にクラウド請求書作成ソフト「Misoca」は、初心者でも簡単に領収書が作成可能です。スマートフォンやタブレットからでも作成・発行ができますので、ぜひ活用してください。
クラウド見積・納品・請求書サービスなら、請求業務をラクにできる
クラウド請求書作成ソフトを使うことで、毎月発生する請求業務をラクにできます。
今すぐに始められて、初心者でも簡単に使えるクラウド見積・納品・請求書サービス「Misoca」の主な機能をご紹介します。
「Misoca」は月10枚までの請求書作成ならずっと無料、月11枚以上の請求書作成の有償プランも1年間0円で使用できるため、気軽にお試しすることができます。
見積書・納品書・請求書をテンプレートでキレイに作成

Misocaは見積書 ・納品書・請求書・領収書・検収書の作成が可能です。取引先・品目・税率などをテンプレートの入力フォームに記入・選択するだけで、かんたんにキレイな帳票ができます。
各種帳票の変換・請求書の自動作成で入力の手間を削減

見積書から納品書・請求書への変換や、請求書から領収書・検収書の作成もクリック操作でスムーズにできます。固定の取引は、請求書の自動作成・自動メール機能を使えば、作成から送付までの手間を省くことが可能です。
インボイス制度(発行・保存)・電子帳簿保存法に対応だから”あんしん”

Misocaは、インボイス制度に必要な適格請求書の発行に対応しています。さらに発行した請求書は「スマート証憑管理」との連携で、インボイス制度・電子帳簿保存法の要件を満たす形で電子保存・管理することが可能です。
確定申告ソフトとの連携で請求業務から記帳までを効率化

Misocaで作成した請求書データは、弥生の確定申告ソフト「やよいの青色申告 オンライン」に連携することが可能です。請求データを申告ソフトへ自動取込・自動仕訳できるため、取引データの2重入力や入力ミスを削減し、効率的な業務を実現できます。
会計業務はもちろん、請求書発行、経費精算、証憑管理業務もできる!
法人向けクラウド会計ソフト「弥生会計 Next」では、請求書作成ソフト・経費精算ソフト・証憑管理ソフトがセットで利用できます。自動的にデータが連携されるため、バックオフィス業務を幅広く効率化できます。

「弥生会計 Next」で、会計業務を「できるだけやりたくないもの」から「事業を成長させるうえで欠かせないもの」へ。まずは、「弥生会計 Next」をぜひお試しください。
この記事の監修者高崎文秀(税理士)
高崎文秀税理士事務所 代表税理士/株式会社マネーリンク 代表取締役
早稲田大学理工学部応用化学科卒
都内税理士事務所に税理士として勤務し、さまざまな規模の法人・個人のお客様を幅広く担当。2019年に独立開業し、現在は法人・個人事業者の税務顧問・節税サポート、個人の税務相談・サポート、企業買収支援、税務記事の監修など幅広く活動中。また通常の税理士業務の他、一般社団法人CSVOICE協会の認定経営支援責任者として、業績に悩む顧問先の経営改善を積極的に行っている。











