請求書の締め日とは?支払日や必着日との違い、どちらが決めるかを解説
監修者: 高崎文秀(税理士)
更新
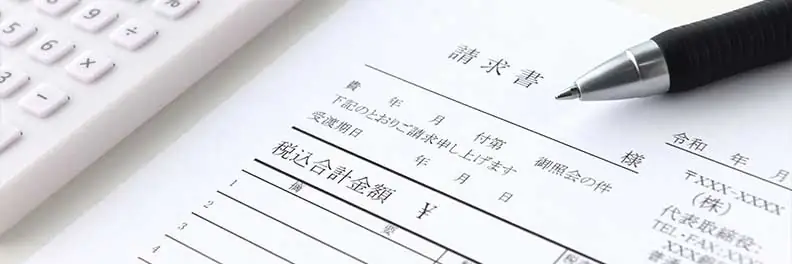
請求担当者は、締め日を基準に期間内の取引を集計し、請求書を発行・送付します。したがって、請求業務を円滑に進めるためには、請求書の締め日について正確に把握しておくことが求められます。
本記事では請求日の締め日の概要や決め方、支払日との違い、取引先との調整方法、決算時の注意点など、実務で知っておきたいポイントをわかりやすく解説します。締め日は買手側と売手側のどちらが決めるのかなど、現場でよくある質問にも答えていますので、ぜひ参考にしてください。
無料【クラウド請求書作成ソフト「Misoca」がよくわかる資料】をダウンロードする
請求書の締め日とは?
請求書の締め日とは、請求対象となる取引の期間を区切る最終日、つまり「どこまでの取引分をまとめて請求書に記載するか」を決める基準となる日付です。
そもそも、企業間取引における請求方式には、「都度請求」と「掛売方式(締め請求)」の2種類があります。都度請求とは、取引が発生するごとに、その都度請求書を発行する形式です。この場合、締め日は設定されません。
これに対して、掛売方式(締め請求)とは、1か月ごとなど事前に定めた期間内の取引分を一括して請求する方式です。この際、それぞれの取引期間を区切るための境目となるのが締め日です。つまり、請求書の締め日が設定されるのは、請求方式が掛売方式(締め請求)の場合です。
締め日は、各企業がそれぞれの事情に合わせて決めます。一般的には、「月末締め」を筆頭に、「20日締め」「25日締め」などがよく使われる例です。例えば月末締めの場合、4月分の請求は、4月1日から4月30日までの期間の取引が請求対象になります。20日締めの場合は、3月21日から4月20日までの取り引きが請求対象です。
請求書に締め日が必要な理由
請求書に締め日を設ける最大の理由は、売手側と買手側の双方が円滑に事務処理を遂行できるようにするためです。
例えば、月に何度も取引がある取引先に対して「都度請求」の対応をしようとすると、取引のたびに何度も請求書や入金確認の処理が必要になってしまいます。これは売手側と買手が双方にとって非常に煩雑です。事務処理が頻繁に発生するために、二重請求(二重払い)や請求漏れなどのミスが発生する可能性もあるでしょう。
その一方で、締め日(掛売方式(締め請求))にすれば、その期間内の取引をまとめて一括請求できるため、頻繁に発生する事務処理から解放されます。請求金額や入金確認業務なども、決まったタイミングで確認するだけでよくなるため、非常に効率的です。
請求書の締め日・支払日の例
締め日は企業ごとに異なりますが、特に多いのは「10日締め」「20日締め」「月末締め」などです。支払日は、買手側と売手側双方の事務処理に要する期間を考慮したうえで期日を調整します。締め日と支払日の組み合わせとして多いのは、以下のような例です。
-
- 月末締め/翌月15日払い
- 月末締め/翌月末払い
- 月末締め/翌々月末払い
- 20日締め/翌月末払い
例えば、「月末締め/翌月15日払い」の場合、売手側は当月1日から末日までの取引を集計して請求書を発行・送付します。買手側はその請求書を確認して、翌月15日までに支払処理をすることになります。
なお、支払日が金融機関の休業日である土・日・祝日に該当するケースもあるため、「支払日が土・日・祝日に当たる場合は、翌営業日を期限とする」などの補足ルールを事前に決めておくのも一般的です。
また、締め日は1か月単位で設定されることが多いですが、事業者によっては「週末締め」「2週間締め」「10日ごと締め」など、細かく締め日を刻む場合もあります。締め日や支払日の決め方は基本的に当事者である事業者に委ねられており、各事業者の事情に合わせて調整する形です。
【無料でお試し】クラウド請求書作成ソフト「Misoca」でかんたんキレイに請求書作成!
請求の締め日と必着日や支払日の違い
請求業務では、締め日以外にも「必着日」「支払日」などの言葉が使われます。それぞれの言葉の意味はまったく異なるため、混同しないように注意しましょう。
それぞれの言葉の意味を誤解していると、「締め日に請求書を送付する」「必着日に入金確認をする」など、無駄な動きをしてしまうかもしれません。以下では、それぞれの言葉の意味と違いを解説します。
支払日との違い
支払日とは、売手側が請求した代金を、買手側が実際に支払う期日を指します。買手側は請求書を受け取ったら、この支払日までに請求金額を振り込まなければなりません。売手側からすると、この支払日に合わせて請求金額がきちんと入金されているか確認し、必要に応じて未回収金の催促を行うことになります。
支払日は一般的に、締め日の翌月または翌々月に設定されることが多いです。つまり、「締め日」は売手側が請求金額を確定する基準日、「支払日」は買手側が支払処理を完了する期限という違いがあります。
なお、2024年施行の「中小受託取引適正化法(旧下請法)」やフリーランス新法の規定に伴い、中小受託事業者(旧下請け)およびフリーランスに仕事を発注する際は、原則として成果物やサービスの受領日から60日以内に支払いを完了することが必要になりました。こうした法整備により、支払日を不当に遅らせることはできなくなっています。
-
参照:内閣官房・公正取引委員会・中小企業庁・厚生労働省「ここからはじめるフリーランス・事業者間取引適正化等法
」p.10
フリーランス新法について詳しくは、以下の関連記事を参考にしてください。
必着日との違い
必着日とは、買手側の元に請求書が必ず到着していなければならない期限日を指します。買手側の経理担当者が社内で請求書を確認し、支払処理を進めるためには一定の準備期間が必要です。支払日の直前に請求書が届いても、期限までに支払いをすることはできません。
例えば「翌月10日必着」と定められている場合、その日までに請求書が買手側に到着していなければ、当月の支払いに間に合わなくなります。そこで、必着日を買手側の担当者と事前に確認しておくことが重要です。
必着日は、通常「締め日」と「支払日」の間に設定されます。売手側は、締め日を過ぎたら請求書を発行し、必着日までに必ず買手側の元に届くように速やかに送付することが大切です。特に郵送の場合は配達日数分を考慮し、余裕をもって送付することが求められます。
必着日については、以下の記事で詳しく解説しています。
【無料でお試し】クラウド請求書作成ソフト「Misoca」でかんたんキレイに請求書作成!
締め日と支払日を設定する際のポイント
締め日や支払日をいつにするかは、業務フローや資金繰りに深くかかわります。したがって、それらの期日の設定は、諸々の事情を考慮したうえで判断するのが大切です。その際、特に留意しておくべきポイントとしては以下が挙げられます。
法的なルールはなく、合意と慣習がベース
前提として、締め日や支払日の決め方に関して法的な定めは特にありません。したがって、締め日は多くの場合、買手側と売手側双方の合意や商慣習に則って設定されます。
その際、売手側と買手側どちらが主体となって締め日を決めるかについては、一般的には買手側が締め日を指定することが多いです。多くの場合、月末締めや20日締めなどが選択されます。
支払日に関しては、締め日の1か月ほど先に設定されることが多いです。実際、「月末締め・翌月末払い」という期間設定を数多くの企業が採用しています。
資金繰りや業務負担に配慮する
締め日や支払日を決める際に留意したいのが、資金繰りや業務負担との兼ね合いです。例えば、自社・自事業の資金繰りの予定に合わせて締め日・支払日を調整することで、特定の時期に極端にキャッシュが少なくなる事態を防げます。
また、締め日から支払日までの期間に余裕をもたせるなら、売手側・買手側双方が落ち着いて事務処理を進めやすくなり、トラブルやミスの防止につながります。業務負担の軽減という点では、繁忙期や給与の支払日と時期が重ならないようにするのも効果的です。
【無料でお試し】クラウド請求書作成ソフト「Misoca」でかんたんキレイに請求書作成!
一般的な請求書の発行スケジュール
請求業務は一般的に、「請求金額の確定→請求書の発行・送付→入金確認」という流れで行われます。締め日や必着日などの期日を守りながら各工程を円滑に進めることが重要です。以下では、各工程で行う具体的な仕事内容を解説します。
1.締め日に請求金額を確定させる
請求書を発行するためには、まず請求金額を確定することが必要です。都度請求の場合は、取引ごとに金額を算定するので、この作業は比較的シンプルに済みます。
それに対して、掛売方式(締め請求)の場合は、締め日が来た時点で所定の期間内の取引を集計し、請求金額を計算します。取引数が多くなると、記入漏れや集計ミスが生じやすくなるので、ていねいな確認が重要です。
2.請求書を発行・送付する
金額が確定したら、速やかに請求書を発行します。請求書には「請求先」「取引内容」「請求金額」「支払期限」など、必要な項目を漏れなく記載しましょう。とりわけ発行するのが適格請求書(インボイス)の場合は、インボイス制度に則って所定の項目をきちんと記載する必要があります。
請求書を発行したら、必着日に間に合うように送付します。その際に注意したいのが、請求書の控えを自社側で保存しておくことです。特に適格請求書発行事業者はインボイス制度に従い、控えを作成・保存することが必要です。これを怠ると、原則として買手側が仕入税額控除を受けられなくなります。買手側の迷惑になることを避けるため、忘れないようにしましょう。
適格請求書について詳しくは、以下の記事を参考にしてください。
また、メールやWebなど、請求書を電子的に交付する場合は、電子帳簿保存法の「電子取引」に該当しますので、所定の仕方でデータ保存する必要があります。
このデータ保存の方法については、以下の記事で詳しく解説しています。
3.支払日に入金を確認する
支払日を迎えたら、まずは入金の有無を確認します。入金が確認できた場合は、入金額と請求額が一致しているかも同時にチェックしましょう。もしも入金額に誤りがあった場合は、速やかに買手側へ確認の連絡を入れ、必要に応じて不足分の入金を促すか、過払い分の返金対応を行います。
入金に問題がなければ、帳簿上で「消込処理」を行います。これは、売掛金(請求残高)をゼロにして、入金を受けたことを帳簿上で確認できるようにする作業です。消込処理を怠ると、未回収金の見落としや二重請求などのミスが生じやすくなるので、忘れずに行いましょう。
【無料でお試し】クラウド請求書作成ソフト「Misoca」でかんたんキレイに請求書作成!
請求の締め日は変更できる
請求業務を行う中で、買手側から「締め日を変更してほしい」と要望を受けることがあります。締め日の変更自体は可能ですが、安易に応じると、自社の資金繰りや業務フローに支障をきたすリスクがあるため、慎重な判断が必要です。
ここでは、締め日変更の希望があった際の確認ポイントや、実際の対応パターンについて解説します。
請求書の締め日変更を希望されたときに確認する内容
買手側から締め日の変更を求められた場合、まず確認すべきなのは「今回だけなのか」「今後すべての取引が対象なのか」といった変更範囲です。加えて、新たな締め日や支払日、変更を希望する理由もしっかりヒアリングしましょう。
変更希望の理由まで確認すべきなのは、未回収金を回避するためです。もしもその理由が「資金繰りが厳しくて、請求締め切り日を延ばすことで支払いを遅らせたい」といった内容であれば、売掛金が回収できなくなるリスクもあります。買手側の支払能力に疑いが生じた場合は、必要に応じて信用調査や与信管理の実施も検討しましょう。
請求書の締め日変更を希望されたときの対応パターン
上記の確認内容を踏まえて、締め日の変更要望に対しては、大きく分けて以下の3パターンで対応します。
1. 要望どおり変更に対応する
締め日変更に特に問題がなければ、要望どおりに承諾することも可能です。あるいは、たとえ変更によって多少の負担が生じる場合でも、先方が重要な顧客であれば、関係維持を優先して要望を受け入れることも選択肢となります。ただし、自社の資金繰りや業務フローに無理が生じないか十分に注意しましょう。
2. 条件を交渉する
締め日変更に応じる場合でも、そのまま受け入れるのではなく、なんらかの条件を提示して交渉する方法もあります。
例えば、「締め日を変更する代わりに発注量を増やしてもらう」「変更時期を自社の資金繰りに影響しないタイミングに調整してもらう」などです。多少調整すれば変更に対応できる場合は、交渉を通じて双方にとって納得できる着地点を探りましょう。
3. 変更を拒否する
締め日の変更が自社にとって不都合が大きく、どうしても対応が難しい場合は、変更を拒否する判断も必要です。
その場合は、なぜ変更できないのか理由をていねいに伝え、希望に添えないことを真摯にお詫びしましょう。場合によっては今後の取引継続が難しくなる可能性もありますが、一方的に相手に譲るのではなく、毅然とした対応をとることも時には重要です。
【無料でお試し】クラウド請求書作成ソフト「Misoca」でかんたんキレイに請求書作成!
自社が請求書の締め日変更を希望する場合の対応方法
自社の都合で請求書の締め日を変更したい場合は、先方が社内で十分に調整できるように、2~3か月前には通知しましょう。通知文には、「いつから」「どのように」「なぜ」締め日が変わるのか、具体的な変更内容とその理由を明記することが大切です。締め日の変更によって支払日やその他の取引条件も変更となる場合は、その旨も正確に記載してください。
締め日の変更は、取引先の事務処理やキャッシュフローにも少なからず影響を及ぼします。変更を快く受け入れてもらえるように、文面はていねいかつ謙虚な表現を心がけ、先方の理解と協力を得る姿勢を示すことが大切です。
【無料でお試し】クラウド請求書作成ソフト「Misoca」でかんたんキレイに請求書作成!
【Q&A】請求書の締め日に関するよくある質問
最後に、請求書の締め日に関連したよくある質問にお答えします。
締め日は請求書への記載が必要?
締め日の記載は必須ではありません。記載されていた方がわかりやすい面もありますが、一般的な請求書には締め日が記載されていないことも多いです。
ただし、支払日の記載は必須です。支払日の記載がなければ、買手側がいつまでに代金を支払えばいいのかがあいまいになってしまいます。締め日も記載する場合は、支払日と混同されないように、きちんと項目を分けて示しましょう。
請求書の締め日はどちらが決める?
法的な規定はありませんが、一般的には請求書を受け取る側(買手側)が締め日を指定することが多いです。これは、買手側が支払処理をしやすいように配慮するためです。例えば、買手側が複数の企業との取引を抱えている場合は、締め日を共通にしておいた方が、支払業務が効率的になります。
締め日後に請求書を送るタイミングは?
請求書の送付タイミングは、締め日の後から必着日までの間です。締め日を過ぎたら、速やかに請求金額を確定して請求書を発行し、必着日までに確実に買手側へ届くように送付しましょう。郵送の場合は到着までに時間がかかるため、配達に要する時間も計算して早めに送付することが大切です。
決算月に請求締め日が決算日と重ならない場合は?
決算月の最終日(決算日)と請求書の締め日が異なる場合は、特別な経理処理をすることが必要です。仮に、締め日が毎月20日で決算日が月末(31日)の場合、締め日から決算日までの売上については、請求書を発行していなくても「売掛金」として計上します。
例えば12月決算の事業者で「12月20日締め」の場合、12月21日~12月31日までの売上分は、翌年1月20日締めの請求書で請求します。しかし、税務や会計上は、この期間(12月21日~12月31日)の売上も12月分の売上に含めて計上しなければなりません。
なぜなら、売上の計上タイミングは「商品やサービスの引き渡し時」が原則であり、請求書の発行日や締め日ではないからです。この「締め日と決算日のずれ」を正しく把握しないと、実際の売上や費用が計上すべき期ではない事業年度に記録される「期ずれ」が発生します。期ずれは税務調査でもチェックされやすいポイントなので、締め日と決算期がずれる場合は注意しましょう。
【無料でお試し】クラウド請求書作成ソフト「Misoca」でかんたんキレイに請求書作成!
締め日を理解して正しく請求書を発行しよう
請求日の締め日とは、掛売方式(締め請求)において、請求対象となる取引期間を区切るための基準日です。一般的には月末締めや20日締めなどが多く採用されます。請求担当者は締め日がきたら該当期間の取引を集計して請求書を発行し、必着日までに買手側へ送付しなければなりません。
こうした請求業務を効率化するには、弥生のクラウド請求書作成ソフト「Misoca」を利用するのがおすすめです。Misocaを使えば、請求書の発行・送付作業を自動化し、請求業務を効率化できます。電子帳簿保存法やインボイス制度に対応しているのもポイントです。ぜひ導入をご検討ください。
【無料でお試し】クラウド請求書作成ソフト「Misoca」でかんたんキレイに請求書作成!
クラウド見積・納品・請求書サービスなら、請求業務をラクにできる
クラウド請求書作成ソフトを使うことで、毎月発生する請求業務をラクにできます。
今すぐに始められて、初心者でも簡単に使えるクラウド見積・納品・請求書サービス「Misoca」の主な機能をご紹介します。
「Misoca」は月10枚までの請求書作成ならずっと無料、月11枚以上の請求書作成の有償プランも1年間0円で使用できるため、気軽にお試しすることができます。
見積書・納品書・請求書をテンプレートでキレイに作成

Misocaは見積書 ・納品書・請求書・領収書・検収書の作成が可能です。取引先・品目・税率などをテンプレートの入力フォームに記入・選択するだけで、かんたんにキレイな帳票ができます。
各種帳票の変換・請求書の自動作成で入力の手間を削減

見積書から納品書・請求書への変換や、請求書から領収書・検収書の作成もクリック操作でスムーズにできます。固定の取引は、請求書の自動作成・自動メール機能を使えば、作成から送付までの手間を省くことが可能です。
インボイス制度(発行・保存)・電子帳簿保存法に対応だから”あんしん”

Misocaは、インボイス制度に必要な適格請求書の発行に対応しています。さらに発行した請求書は「スマート証憑管理」との連携で、インボイス制度・電子帳簿保存法の要件を満たす形で電子保存・管理することが可能です。
確定申告ソフトとの連携で請求業務から記帳までを効率化

Misocaで作成した請求書データは、弥生の確定申告ソフト「やよいの青色申告 オンライン」に連携することが可能です。請求データを申告ソフトへ自動取込・自動仕訳できるため、取引データの2重入力や入力ミスを削減し、効率的な業務を実現できます。
会計業務はもちろん、請求書発行、経費精算、証憑管理業務もできる!
法人向けクラウド会計ソフト「弥生会計 Next」では、請求書作成ソフト・経費精算ソフト・証憑管理ソフトがセットで利用できます。自動的にデータが連携されるため、バックオフィス業務を幅広く効率化できます。

「弥生会計 Next」で、会計業務を「できるだけやりたくないもの」から「事業を成長させるうえで欠かせないもの」へ。まずは、「弥生会計 Next」をぜひお試しください。
無料【クラウド請求書作成ソフト「Misoca」がよくわかる資料】をダウンロードする
この記事の監修者高崎文秀(税理士)
高崎文秀税理士事務所 代表税理士/株式会社マネーリンク 代表取締役
早稲田大学理工学部応用化学科卒
都内税理士事務所に税理士として勤務し、さまざまな規模の法人・個人のお客様を幅広く担当。2019年に独立開業し、現在は法人・個人事業者の税務顧問・節税サポート、個人の税務相談・サポート、企業買収支援、税務記事の監修など幅広く活動中。また通常の税理士業務の他、一般社団法人CSVOICE協会の認定経営支援責任者として、業績に悩む顧問先の経営改善を積極的に行っている。









