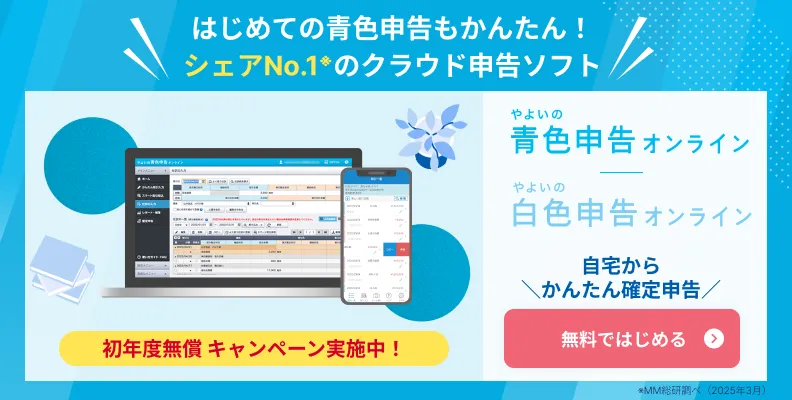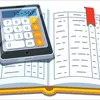クレジットカードの帳簿の付け方は?個人事業主の仕訳方法を解説
監修者: 齋藤一生(税理士)
更新

個人事業主がクレジットカードで必要経費の支払いをした場合は、帳簿の付け方に注意しなければなりません。とはいえ、どのように帳簿を付ければいいのかわからないといった方も多いのではないでしょうか。利用したクレジットカードが、プライベート用か事業用かによって仕訳方法が変わることもあるため、考え方を理解しておきましょう。
ここでは、個人事業主がクレジットカードを使った際の仕訳方法や、クレジットカード取引での注意点について解説します。
日付や金額などを入力するだけで、確定申告に必要な帳簿や申告書類が完成します
初年度無料ですべての機能が使用できます。e-Taxも製品から直接できるので、自宅からかんたんに確定申告が可能です

確定申告の方法によって個人事業主の帳簿の付け方は変わる
個人事業主がクレジットカードを利用した際の帳簿の付け方は、青色申告・白色申告といった確定申告の方法や、青色申告で適用を受ける青色申告特別控除の金額によって異なります。個人事業主の確定申告の方法と帳簿の付け方との関係は、以下のとおりです。
個人事業主における確定申告の方法と帳簿の付け方の関係
| 確定申告の方法 | 帳簿の付け方 | |
|---|---|---|
| 青色申告 | 65万円または55万円の青色申告特別控除を利用 | 複式簿記 |
| 10万円の青色申告特別控除を利用 | 単式簿記でも可 | |
| 白色申告 | 単式簿記でも可 | |
複式簿記とは、1つの取引を原因と結果の両面から記録していく記帳方法です。単式簿記よりも複雑ですが、より正確な記録が可能です。
例えば、クレジットカードで支払った必要経費を複式簿記で記帳する際は、商品を購入した際と代金が引き落とされた際の2回記帳します。また、プライベート用のカードを使ったか、事業用のカードを使ったかによっても処理方法が異なります。詳しくは、後で解説する「クレジットカードで取引した場合の仕訳」の項目をご確認ください。
一方の単式簿記は、お小遣い帳のようなシンプルな記帳方法です。クレジットカードで必要経費を支払った際も、決済日に「消耗品(ボールペン):100円」といった形の記録を残すだけで記帳が完了します。
なお、65万円または55万円の青色申告特別控除の適用を受けるためには、複式簿記で記帳したうえで、貸借対照表と損益計算書を作成し、確定申告書に添付しなければなりません。
貸借対照表とは、ある特定の時点(通常は決算日)での資産、負債、純資産の額と内訳を示す書類で、バランスシートとも呼ばれます。損益計算書は、ある一定期間(通常は決算期)の収益、支出、利益を示す書類です。
また、10万円の青色申告特別控除を利用する事業者は損益計算書のみ、白色申告者は損益計算書と同様の内容を記載する収支内訳書を確定申告書に添付します。
複式簿記と単式簿記については以下の記事で詳しく解説していますので参考にしてください。
仕訳とは、取引内容を借方と貸方の両面に分けて記帳すること
仕訳とは、取引内容を借方(かりかた)と貸方(かしかた)の両面に分けて仕訳帳に記録することです。複式簿記で記帳する際に行わなければならない作業で、記帳時には勘定科目による分類を行います。
例えば、1,000円の文房具を現金で購入したとしましょう。文房具は消耗品に当たるため、消耗品費という勘定科目を使います。また、仕訳ではひとつの取引を原因と結果に分けて記載しますが、この例の場合、原因は「1,000円の消耗品を買ったこと」で、結果は「現金が1,000円減ったこと」です。そのため、以下のように仕訳をします。
1,000円の文房具を現金で購入した際の仕訳例
| 借方 | 貸方 | ||
|---|---|---|---|
| 消耗品費 | 1,000 | 現金 | 1,000 |
仕訳では、左側を借方、右側を貸方と呼び、双方の合計額は一致します。原因と結果を借方と貸方のどちらに記載するのかは、以下のように、取引によって何が増えて何が減ったのかといった観点で考えるのが一般的です。
借方・貸方の主な分け方
| 分類 | 借方に記載する事項 | 貸方に記載する事項 |
|---|---|---|
| 資産 | 資産の増加 | 資産の減少 |
| 負債 | 負債の減少 | 負債の増加 |
| 純資産(自己資本) | 純資産の減少 | 純資産の増加 |
| 費用 | 費用の増加 | 費用の減少 |
| 収益 | 収益の減少 | 収益の増加 |
仕訳については以下の記事で詳しく解説していますので参考にしてください。
個人事業主がクレジットカードの取引で使う勘定科目
個人事業主がクレジットカードの取引を複式簿記で記帳する際は、以下の勘定科目を使用します。
個人事業主がクレジットカードの取引で使う勘定科目
- 事業主借・事業主貸
- 未払金・買掛金
仕訳方法を理解するためには、それぞれの勘定科目が何を表していて、どのようなときに使用するのかを確認しておかなければなりません。
なお、上記のほかに購入した商品やサービスに応じた勘定科目も使用します。例えば、文房具を購入したのであれば消耗品費、手土産品を購入したのであれば接待交際費といった勘定科目が用いられます。
事業主借・事業主貸
事業主借と事業主貸は、個人事業主特有の勘定科目です。事業資金をプライベートのために使用した場合は事業主貸、個人事業主のプライベートの資金を事業に使用した場合は事業主借を利用します。
例えば、事業の売上が入金された口座から10万円を引き出して生活費に充てる場合は、以下のように仕訳します。
事業用資金を口座から下ろして個人の生活費に充てた場合の仕訳例
| 借方 | 貸方 | ||
|---|---|---|---|
| 事業主貸 | 100,000 | 普通預金 | 100,000 |
反対に、個人の貯金から事業用の資金を使った場合は事業主借を使って仕訳します。生活費用の口座から仕入代金3万円の支払いをした際の仕訳は以下のとおりです。
個人の貯金から仕入代金を支払った場合の仕訳例
| 借方 | 貸方 | ||
|---|---|---|---|
| 仕入高 | 30,000 | 事業主借 | 30,000 |
クレジットカードの仕訳でも同様で、事業用のクレジットカードでプライベートの支払いをした場合は事業主貸、プライベート用のクレジットカードで事業用の支払いをした場合は事業主借を利用します。
クレジットカードを事業用とプライベート用で分けていないと、必要経費とプライベートの支出が混同する可能性もあります。「プライベートのカードを事業にも利用していて、事業専用のカードは所持していない」といった方は、事業用のカードを別に用意するのがおすすめです。
国税庁の資料「帳簿の記帳のしかた(事業所得者用)」にも、クレジットカードを事業用と私用で分けるように記載されています。
未払金・買掛金
未払金は、事業用の必要経費を後払いで購入した際に使用する勘定科目です。ただし、仕入用の商品の購入については使用しません。例えば、事務用品や消耗品などを購入したケースのような、営業活動以外の取引で使用します。
仕入用の商品を後払いで購入した際は、買掛金という勘定科目を使用しましょう。掛取引で仕入れた商品や原材料などについては買掛金に該当します。
例えば、事業用のクレジットカードで業務に使用する書籍を購入した場合は未払金、販売用の商品を購入した場合は買掛金を使って仕訳します。
買掛金と未払金を分けた方が原価と販売管理費等のいずれの費用に係る負債残高が残っているのかがわかりやすいのですが、一方で会計上は複雑になり負債の消込が面倒になるため、実務上は未払金にまとめているケースも多いと言えます。
クレジットカードで取引した場合の仕訳
個人事業主がクレジットカードで支払いをした際の仕訳方法は、利用したクレジットカードの種類などに応じて変わります。
通常は、商品を購入したタイミングと購入代金が引き落とされるタイミングの2回仕訳をすることになりますが、状況によっては、1回しか仕訳をしないこともあります。どのカードを使い、どのような支払いを行ったのかに着目して、正しい仕訳ができるようにしておきましょう。
以下では、クレジットカードの種類と支払方法に応じた仕訳例に加えて、ポイントを使った場合の仕訳例についても確認していきます。
事業用のクレジットカードで事業の必要経費を一括払いで支払った場合
事業用のクレジットカードで必要経費を一括払いした場合の勘定科目は、将来支払う債務を意味する未払金を使用します。購入時に未払金を計上し、利用代金の引き落とし時には債権・債務の残高を消す作業である「消込」を行いましょう。
事業用のクレジットカードで、1,000円の消耗品を一括払いで購入した場合の仕訳例は以下のとおりです。
購入時の仕訳
| 借方 | 貸方 | ||
|---|---|---|---|
| 消耗品費 | 1,000 | 未払金 | 1,000 |
クレジットカード利用代金の引き落とし時の仕訳(消込)
| 借方 | 貸方 | ||
|---|---|---|---|
| 未払金 | 1,000 | 普通預金 | 1,000 |
事業用のクレジットカードでプライベートの支出を一括払いで支払った場合
事業用のクレジットカードでプライベートの支出を一括払いで支払った場合は、事業資金をプライベートで使用しているため、事業主貸の勘定科目で仕訳をしましょう。
プライベートで事業用のクレジットカードを一括払いで利用した場合、商品を購入した時点では事業に関する取引が発生していないため、仕訳は必要ありません。例えば、プライベートの食事代5,000円を事業用のクレジットカードを利用して一括払いで支払った場合、利用代金の引き落とし時に以下のように仕訳を行います。
クレジットカード利用代金の引き落とし時の仕訳
| 借方 | 貸方 | ||
|---|---|---|---|
| 事業主貸 | 5,000 | 普通預金 | 5,000 |
プライベート用のクレジットカードで事業の必要経費を一括払いで支払った場合
プライベート用のクレジットカードを使って事業の必要経費を一括払いで支払った場合は、個人の資金を事業に使用しているため、事業主借の勘定科目を使って仕訳をします。
ただし、仕訳が必要なのは購入時だけです。クレジットカードの利用代金が個人の口座から引き落とされることは、事業上の取引には該当しません。そのため、クレジットカード代金の引き落とし時の仕訳は不要です。
プライベート用のクレジットカードで会議室の利用代金3,000円を一括払いで支払った場合は、以下のように仕訳を行いましょう。
購入時の仕訳
| 借方 | 貸方 | ||
|---|---|---|---|
| 会議費 | 3,000 | 事業主借 | 3,000 |
事業用のクレジットカードで事業の必要経費を分割払いで支払った場合
事業用のクレジットカードで必要経費を分割払いすると、実際の購入金額のほかに手数料も支払わなければならないため、手数料を考慮に入れた仕訳が必要です。手数料については、支払利息と呼ばれる勘定科目で仕訳を行います。支払利息は、全額を経費計上できます。
以下は、5万円のソフトウェアを5回払いで購入した場合の仕訳例です。なお、ソフトウェアの購入費用は消耗品費に該当します。
購入時の仕訳
| 借方 | 貸方 | ||
|---|---|---|---|
| 消耗品費 | 50,000 | 未払金 | 50,000 |
クレジットカード利用代金の引き落とし時の仕訳(消込)
| 借方 | 貸方 | ||
|---|---|---|---|
| 未払金 | 10,000 | 普通預金 | 10,340 |
| 支払利息 | 340 | ||
利用代金の引き落とし時の仕訳については、5回の分割払いが終わるまで繰り返し発生します。
事業用のクレジットカードのポイントでキャッシュバックを受けた場合
クレジットカードのポイントは、キャッシュバックや金券への交換などの用途で利用できます。事業用のクレジットカードのポイントを利用する場合も、仕訳が必要です。
キャッシュバックは収入と同等と見なされるため、キャッシュバックを受けたタイミングで雑収入の勘定科目を使って仕訳を行います。以下は、普通預金口座にキャッシュバックとして1万円が振り込まれた場合の仕訳例です。
普通預金口座にキャッシュバックの金額が振り込まれた際の仕訳例
| 借方 | 貸方 | ||
|---|---|---|---|
| 普通預金 | 10,000 | 雑収入 | 10,000 |
なお、確定申告でも、ポイント収入は雑収入(雑所得)として申告します。また、金券交換の場合、借方の勘定科目は前払金または貯蔵品を用います。
クレジットカードを事業で利用する場合の注意点
事業の支払いにクレジットカードを利用した際は、領収書や利用明細書の取り扱いに注意しなければなりません。
個人事業主は、領収書を一定期間保存しなければならないと所得税法で定められています。保存期間は、青色申告者が7年間、白色申告者が5年間です。ただし、課税事業者で領収書が適格請求書に該当する場合、白色申告者でも7年間の保存が必要です。
なお、クレジットカードの利用明細書はクレジットカードの利用内訳を示すもので、厳密には領収書ではありませんが、一定の条件のもとで領収書に代わり購入を証明できることがあります。
また、領収書や利用明細書を電子データとして受け取った場合は、書類をデータのまま保存しなければなりません。これは、電子帳簿保存法に定められた義務です。
Web上で明細などを閲覧できるサービスもありますが、閲覧できる期限が定められている場合も少なくありません。保存期間中に閲覧期限を迎える場合は、個別にダウンロードして保管しておく必要があります。
電子帳簿保存法での領収書やクレジットカードの領収書の扱いについては以下の記事で詳しく解説していますので参考にしてください。
個人事業主でクレジットカードを利用する場合は、正しい仕訳で帳簿を付けよう
個人事業主がクレジットカードを利用する場合は、仕訳方法に注意しましょう。状況に応じて、適切な仕訳を行わなければいけません。
手間をかけずに正確な記帳を行うなら「やよいの青色申告 オンライン」や「やよいの白色申告 オンライン」が便利です。弥生の確定申告ソフトには、クレジットカードと連携して利用データを読み込み、自動で仕訳を行う機能が搭載されています。いちいち手作業で仕訳をする必要がないため、効率良く記帳を進められます。日々の記帳や確定申告をスムーズに進めるために、ぜひご活用ください。
確定申告ソフトなら、簿記や会計の知識がなくても確定申告が可能
確定申告ソフトを使うことで、簿記や会計の知識がなくても確定申告ができます。
今すぐに始められて、初心者でも簡単に使える弥生のクラウド確定申告ソフト「やよいの白色申告 オンライン」とクラウド青色申告ソフト「やよいの青色申告 オンライン」から主な機能をご紹介します。
「やよいの白色申告 オンライン」は、ずっと無料、「やよいの青色申告 オンライン」は初年度無料です。両製品とも無料期間中もすべての機能が使用できますので、気軽にお試しいただけます。もちろん、確定申告もe-Taxでの申告が可能です!
【無料・税額シミュレーター】売上と経費を入力して青色と白色の税額を比較してみよう!
初心者にもわかりやすいシンプルなデザイン

弥生のクラウド確定申告ソフトは、初心者にもわかりやすいシンプルなデザインで、迷うことなく操作できます。日付や金額などを入力するだけで、確定申告に必要な帳簿や必要書類が作成できます。
取引データの自動取込・自動仕訳で入力の手間を大幅に削減

弥生のクラウド確定申告ソフトは、銀行・クレジットカードなどの金融機関の明細や電子マネー、POSレジ、請求書、経費精算等のサービスと連携すると日々の取り引きデータを自動で取得します。
自動取得した取引データはAIが自動で仕訳して帳簿に反映します。学習機能があるので、使えば使うほど仕訳の精度がアップします。紙のレシートは、スマホやスキャンで取り込めば、文字を認識してデータに変換し、自動で仕訳します。これにより入力の手間と時間が大幅に削減できます。
確定申告書類を自動作成。e-Tax対応で最大65万円の青色申告特別控除もスムーズに

弥生のクラウド確定申告ソフトは、画面の案内に沿って入力していくだけで、収支内訳書や青色申告決算書、所得税の確定申告書、消費税の確定申告書等の提出用書類が自動作成されます。
「やよいの青色申告 オンライン」なら、青色申告特別控除の最高65万円/55万円の要件を満たした資料の用意も簡単です。インターネットを使って直接申告するe-Tax(電子申告)にも対応し、最大65万円の青色申告特別控除もスムーズに受けられます。
自動集計されるレポートで経営状態がリアルタイムに把握できる

弥生のクラウド確定申告ソフトに日々の取引データを入力しておくだけで、レポートが自動で集計されます。経営状況やお金の流れをリアルタイムで確認できます。最新の経営状況を正確に把握することで、早めの判断ができるようになります。