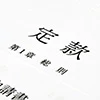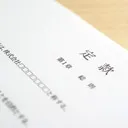株式・発行可能株式総数とは?発行株式数から決める方法も解説
監修者: 森 健太郎(税理士)
更新

株式会社を設立する際には、株式を発行し、発行可能株式総数を決める必要があります。会社設立にあたり、「発行可能株式総数はどうやって決めればいいのだろう」「そもそも株式とは?」と、疑問に思う方もいるかもしれません。
本記事では、株式の意味や発行可能株式総数を定款で定める理由、決め方のほか、発行可能株式総数を決める際の注意点について解説します。
法人設立ワンストップサービスを利用して、オンラインで登記申請も可能。
個人事業主から法人成りを予定している方にもおすすめです。

【無料】はじめてでもカンタン・安心な「会社設立」の書類作成はこちらをクリック
株式とは、出資者である株主に発行する証券のこと
株式とは、株式会社が出資者である株主に発行する証券のことです。株式会社は、事業を始めたり拡大したりする目的で株式を発行し、出資者から事業に必要な資金を集め、出資の対価として株式を交付します。
出資して株式を取得した人は、株主と呼ばれます。株主は、例えば保有する株式の割合に応じた株主総会での議決権行使や、利益が出た際の配当金の受け取りなどが可能です。また、株式は売却することもできます。
会社設立を行いたい場合、出資者を募らずに株式会社を設立することも可能で、その場合は会社を設立したい人が出資してすべての株式を取得することになります。株式を第三者に譲った場合、第三者が株主総会での議決権行使によって経営に参画してくる可能性もあるため、会社を設立する際は株式の意味や株主の権利の内容を押さえておきましょう。
※株式については以下の記事を併せてご覧ください
【無料】はじめてでもカンタン・安心な「会社設立」の書類作成はこちらをクリック
株主は自益権と共益権と呼ばれる2つの権利を持つ
株主は、大きく分けて自益権、共益権と呼ばれる2つの権利を持ちます。株式を発行する際に、複数の株主で会社を構成する場合は、株主にどのような権利があり、何ができるのかを把握しておきましょう。
自益権とは、出資した会社から経済的なメリットを受けられる権利
自益権とは、株主としての権利のうち、出資した会社から経済的なメリットを受けられる権利のことです。自益権は、行使した株主自身の利害にしか関係しないため、自益権と呼ばれています。
自益権の例としては、会社から配当金を受け取る権利(剰余金配当請求権)や、会社が解散をしたときに最後に残った財産の分配を受ける権利(残余財産分配請求権)などがあげられ、持っている株数が多ければ多いほど利益も大きくなります。
共益権とは、株主が会社の経営への参加や監督ができる権利
共益権とは、株主が会社の経営への参加や監督ができる権利です。共益権を行使すると、株主全体の利害に影響するため、共益権と呼ばれています。共益権のうち、代表的な権利として、株主総会における議決権や、株主総会の招集請求権などがあげられます。
※株主の権利については以下の記事を併せてご覧ください
【無料】はじめてでもカンタン・安心な「会社設立」の書類作成はこちらをクリック
1株当たりの株式の金額を1万円または5万円に設定する傾向がある
株式の発行にあたって、1株当たりの株式の金額を1万円か5万円に設定する傾向があります。株式会社を設立する際には1株当たりの株式の金額を決める必要がありますが、その決定方法にルールはないため、わかりやすさを考慮して1株1万円とする会社も少なくありません。また、旧商法で1株の額面が5万円以上と定められていたため、現在でも1株5万円と設定する会社があります。
1株当たりの株式の金額に上限はないため、例えば、1株100万円に設定することも可能です。ただし、もし第三者からの出資を募る場合は、1株当たりの株式の金額を高く設定すると、出資者を集めづらくなります。
【無料】はじめてでもカンタン・安心な「会社設立」の書類作成はこちらをクリック
発行可能株式総数とは、会社が発行できる株式の上限のこと
発行可能株式総数とは、会社が発行できる株式の上限のことです。会社は、発行可能株式総数を超えて株式を発行することはできません。また、株式会社は、発行可能株式総数について定款で定める必要があります。例えば、「当会社の発行可能株式総数は、1万株とする」といった形で定款に記載します。
発行可能株式総数を超えて株式を発行したい場合は、株主総会の特別決議によって定款を変更しなければなりません。普通決議では出席株主の議決権の過半数で決議できますが、特別決議では出席株主の議決権のうち3分の2以上が賛成しなければならないため、ハードルが上がります。
さらに、発行可能株式総数は登記事項にあたるため、変更する場合は変更登記手続きと登録免許税も必要になります。定款変更、変更登記の手間を避けるためにも、発行可能株式総数については、将来の資金調達なども十分に考慮して検討することが必要です。
なお、発行可能株式総数は定款への絶対的記載事項ではありませんが、登記事項となっていることから設立登記までには記載が必要な事項となっています。そのため発行可能株式総数は、定款を作成する時点で決定し、定款に記載しておきましょう。
※定款の絶対的記載事項については以下の記事を併せてご覧ください
【無料】はじめてでもカンタン・安心な「会社設立」の書類作成はこちらをクリック
発行可能株式総数を定款で定めなければならない理由がある
会社法が、定款に発行可能株式総数を記載するように義務付けていることには、理由があります。会社の基本ルールである定款に記載することで、発行可能株式総数の範囲内での新たな株式発行(新株発行)がしやすくなる一方、発行可能株式総数を超える株式発行がしづらくなるため、定款への記載を要求しています。
主に以下の2つの理由があることを押さえながら、慎重に発行可能株式総数をどの程度にするべきかを検討してみてはいかがでしょうか。
会社が速やかに資金調達を行えるようにする
定款に発行可能株式総数を定める理由の1つは、速やかな資金調達を可能にすることです。発行可能株式総数を定款に定めておけば、公開会社で有利発行でない場合などでは、取締役会の決議だけで、発行可能株式総数の範囲内で新株発行できるため、迅速に資金調達できます。
公開会社とは、株式の全部または一部の譲渡について、会社の承認を要求する規定を定款に設けていない会社のことです。また、有利発行とは、時価よりも低い価格で株式を発行することを指します。
新株発行は株主全体の利害にかかわるため、本来であれば株主総会で決議すべき事柄です。しかし、株主総会の開催には手間や時間がかかり、急を要する資金調達には間に合わないかもしれません。
例えば、株主総会を行うには、取締役会で株主総会の招集を決定し、招集通知と参考書類を発送し、株主総会を開くといったステップが必要です。これが取締役会だけで済ませられれば、迅速に資金調達ができるようになります。
発行可能株式総数を決める際は、資金調達の機動性についても考慮に入れておきましょう。
株主が不利益を被らないよう取締役会の権利濫用を防止する
定款に発行可能株式総数を定める理由の1つは、株主が不利益を被らないよう取締役会の権利濫用を防止することです。定款で発行可能株式総数を定めることで迅速な新株発行が可能になりますが、取締役会が際限なく株式を発行してしまうと既存の株主の不利益につながることもあるため、発行可能株式総数で上限を設けています。
例えば、株式を譲渡する際の制限を定款に定めていない公開会社では、特定の第三者に株式を発行することも取締役会決議で可能ですが、第三者への株式の発行数が多いほど、既存株主の議決権の割合が下がることになります。
第三者が取締役会に参加することを想定している場合は、発行可能株式総数を決める際に、取締役会の権限濫用と既存株主の不利益を避けるという観点も意識して、発行可能株式総数を決めてみてはいかがでしょうか。
※定款については以下の記事を併せてご覧ください
【無料】はじめてでもカンタン・安心な「会社設立」の書類作成はこちらをクリック
発行可能株式総数の上限は公開会社と非公開会社で異なる
公開会社と非公開会社では、発行可能株式総数の上限が異なります。非公開会社とは、株式譲渡について定款で制限している会社のことです。公開会社と非公開会社では新株発行に関する法律上の規定が異なるため、発行可能株式総数の上限にも違いが生じています。
公開会社と非公開会社のどちらを選択するかについては、将来株式市場からの資金調達も想定している場合は公開会社として、親族など関係者のみが出資して経営者が変わる予定がない場合は非公開会社とするのが一般的です。
発行可能株式数を決定する際は、以下のルールがあることを確認して、法律に違反しないようにしましょう。
公開会社は発行株式数の4倍が上限
公開会社の場合、発行可能株式総数の上限は設立時の株式数の4倍です。会社法では、「公開会社は設立時の発行株式の総数が発行可能株式総数の4分の1を下回ってはいけない」と定められています。つまり、発行可能株式総数は設立時の発行株式数の4倍以下にするよう規定されているため、この基準を超えて発行可能株式総数を設定することはできません。
公開会社では取締役会決議のみで新株発行ができるため、発行可能株式総数で取締役会の権限濫用を防止できますが、発行可能株式総数に上限がないと、その目的が実現できない可能性があります。例えば、発行可能株式総数が設立時の株式数の100倍になっていると、取締役会の決議だけで、既存株主の議決権の割合を100分の1程度に下げることも可能になります。
公開会社で発行可能株式総数を決める際は、法律上の基準を超えられないため、その範囲内に収まるように数値を設定しましょう。
非公開会社は発行可能株式総数に制限はない
非公開会社の場合は、発行可能株式総数の上限について、公開会社のような法律上の制限はありません。非公開会社であれば、基本的に新株発行については株主総会の決議が必要となるため、発行可能株式総数の上限を設けなくても、既存株主は自分で自分の権利を守ることができます。
例えば、発行可能株式総数は、設立時の株式数の10倍でも、100倍、1,000倍でも問題はありません。将来、増資や株式分割によって株式数が増えることも考えながら、株式数を設定しましょう。
【無料】はじめてでもカンタン・安心な「会社設立」の書類作成はこちらをクリック
発行可能株式総数を決める際には手順がある
発行可能株式総数については、一定の手順に沿って決めるのが一般的です。特に公開会社の場合は、手順を考えずに自由に発行可能株式総数を決定してしまうと、法律上の制限を超えることにもなりかねません。以下の流れに沿って、先に設立時に発行する株式数を決めてから、発行可能株式総数を決めましょう。
STEP1. 設立時の発行株式数を計算する
発行可能株式総数を決めるためには、最初に、資本金と1株当たりの株式の金額から以下の計算式で設立時に発行する株式数を計算します。
設立時の株式数の計算式
設立時の株式数=資本金÷1株当たりの株式の金額
例えば、資本金100万円、1株1万円だった場合、設立時の株式数は「100万円÷1万円=100株」となります。
STEP2. 発行可能株式総数を決定する
設立時の株式数を求めたら、その数値を基に、発行可能株式総数を決定します。公開会社の場合は、発行可能株式総数は設立時の株式数の4倍までと決められているため、設立時の株式数が100株なら、発行可能株式総数は「100株×4=400株」が上限です。
非公開会社であれば、発行可能株式総数の上限に定めはないため、何株に設定しても問題ありません。例えば、将来予定している増資の金額が明確なら、予定増資額を基準に決めることも可能です。
増資の予定が明確でないのであれば、以下のような数値を目安に決定してみてはいかがでしょうか。
設立時の株式数の10倍程度を目安にする
非公開会社の発行可能株式総数の決定方法として、設立時の株式数の10倍程度を目安にする方法があります。資金調達時の迅速さを重視して、公開会社に関する会社法の基準よりも多めの基準を採用した考え方です。例えば、設立時の株式数が100株であれば、「100株×10=1,000株」が発行可能株式総数となります。
発行可能株式総数に余裕を持たせたい場合は、10倍を目安に数値を検討してみましょう。
資本金1億円を目安にする
非公開会社の発行可能株式総数の決定方法として、資本金1億円を目安にする方法があります。資本金の額が1億円以下の会社には、法人税の軽減税率の適用や外形標準課税の不適用など、さまざまな税制上の優遇措置があるため、この基準で発行可能株式総数を決める会社もあります。例えば、1株1万円の例で計算すると、発行可能株式総数は「1億円÷1万円=1万株」です。
税制上の優遇措置を意識して、将来も優遇措置が受けられる範囲内での事業展開を想定している場合は、資本金1億円を目安に発行可能株式総数を決めてはいかがでしょうか。
【無料】はじめてでもカンタン・安心な「会社設立」の書類作成はこちらをクリック
発行可能株式総数を決める際には、さまざまな注意点がある
発行可能株式総数を適切に設定するには、さまざまな注意点があります。何も意識せずに発行可能株式総数を決めてしまうと、想定外のコストがかかったり、トラブルに遭遇したりする可能性があります。以下の点に注意して、リスクを回避しましょう。
発行可能株式総数の変更には手間がかかる
発行可能株式総数の変更には手間がかかることに、注意が必要です。発行可能株式総数を変更する場合は、定款や登記事項を変更することになるため、例えば、株主総会での特別決議や変更登記の手続きなどが必要になり、事務負担やコストがかかります。
最初に設定する発行可能株式総数に余裕がないと、その分、新たに発行できる株式数が少なくなり、新株発行の必要が出てきた際に煩雑な手続きが必要になる可能性があります。将来、迅速な増資が必要になった場合に、発行可能株式総数が足かせになることも想定しなければなりません。将来の増資の可能性も考慮して、手間を最小化するために、発行可能株式総数は余裕を持った数値に設定しておきましょう。
発行可能株式総数を増やすと1株の価値を下げられるようになる
発行可能株式総数を設定する際には、1株の価値を下げられるようになることにも注意が必要です。発行株式数に対して発行可能株式総数が多ければ多いほど、既存株主の持株比率を薄められるため、新株発行によって既存株主の利益を減少させることが可能になります。
例えば、第三者からの出資を募る場合、そのリスクが出資の判断に影響を与えるかもしれません。また、発行可能株式総数が多いことを理由に、会社設立後に既存の株式の価値を大きく下げるような新株発行を行った場合は、既存株主とのトラブルに発展する可能性もあります。
他に出資者を予定している場合は、その出資者の利益にも配慮して、発行可能株式総数を設定しましょう。
【無料】はじめてでもカンタン・安心な「会社設立」の書類作成はこちらをクリック
会社設立を手軽に行う方法
このように、定款の内容を定めるだけでも労力がかかります。少しでも会社設立手続きにかかる手間や時間を軽減するためにおすすめしたいのが、「弥生のかんたん会社設立」です。「弥生のかんたん会社設立」は、画面の案内に沿って必要事項を入力するだけで、定款をはじめとする会社設立時に必要な書類を自動生成できるクラウドサービスです。各官公庁への提出もしっかりガイドするため、事前知識は不要。さらに、入力内容はクラウドに保存され、パソコンでもスマホでも自由に切り替えながら書類作成ができます。
【無料】はじめてでもカンタン・安心な「会社設立」の書類作成はこちらをクリック
会社設立時は、余裕を持って発行可能株式総数を決めよう
株式会社を設立する際には、発行可能株式総数を決め、定款に定める必要があります。非公開会社であれば、発行可能株式総数の上限に定めはありません。会社を設立後、発行可能株式総数を変更する場合は、株主総会での特別決議による定款の変更と登記変更の手続きを行う必要があるため、将来できるだけ手間やコストをかけずに済むように、余裕を持たせて発行可能株式総数を設定しておきましょう。
また、定款の作成や登記など、煩雑な会社設立の手続きを効率化したい場合は、「弥生のかんたん会社設立」の利用をご検討ください。
【無料】はじめてでもカンタン・安心な「会社設立」の書類作成はこちらをクリック
この記事の監修者森 健太郎(税理士)
ベンチャーサポート税理士法人 代表税理士。
毎年1,000件超、累計23,000社超の会社設立をサポートする、日本最大級の起業家支援士業グループ「ベンチャーサポートグループ」に所属。
起業相談から会社設立、許認可、融資、助成金、会計、労務まであらゆる起業の相談にワンストップで対応します。起業・会社設立に役立つYouTubeチャンネル会社設立サポートチャンネルを運営。