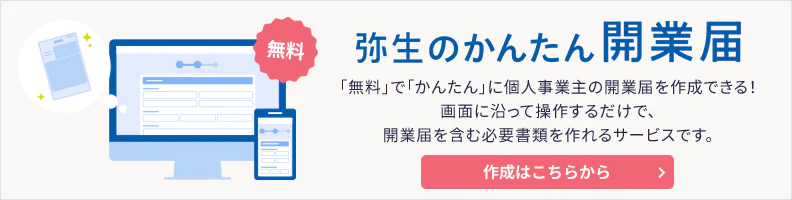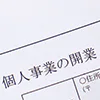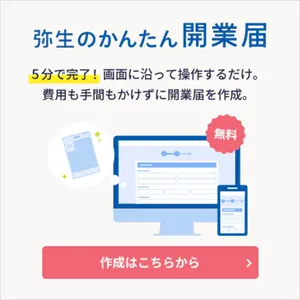開業届の提出に必要なものは?開業時の必要書類や出し方も解説
監修者: 森 健太郎(税理士)
更新

個人事業主として開業する際には、「個人事業の開業・廃業等届出書(以降、開業届)」の提出が必要です。開業届の提出方法には、窓口への提出、郵送での提出、e-Taxを利用した提出の3種類あり、提出時に必要なものは提出方法によって異なります。
提出に必要なものが足りず、「開業届を再提出しなければならない」といった事態にならないよう、あらかじめ提出に必要なものを確認しておきましょう。本記事では、方法別に開業届の提出に必要なものや開業届と併せて提出しておきたい書類と共に、開業届の作成・提出方法についても解説します。
【利用料0円】はじめてでもカンタン・安心な「開業届」の作成はこちらをクリック
開業時すべての方に提出が必要な書類
開業時には、個人事業主となるすべての方が以下の書類を提出する必要があります。期限内にスムーズに提出できるよう、提出期限や提出先も併せて確認しておきましょう。
開業時に提出が必要な書類
| 書類名 | 提出期限 | 提出先 |
|---|---|---|
|
個人事業の開業・廃業等届出書 |
事業開始日の属する年分の所得税確定申告期限まで(2025年12月31日までの開業については、開業等の事実のあった日から1か月以内) | 税務署 |
| 事業開始等申告書 | 都道府県により異なる(東京都は開業日より15日以内) | 都道府県税事務所 |
開業届
個人事業主として開業する際には、開業届の提出が必要です。事業を開始する事業主本人が所定の期限までに提出します。
なお、開業届は提出が遅れたり、提出しなかったりしても、特に罰則はありません。しかし、開業届を提出していないことで、屋号付きの銀行口座の開設や補助金・助成金の申請ができなくなるなどのリスクがあるため、開業したら期日までに提出するようにしましょう。
事業開始等申告書
開業時には、事業開始等申告書の提出も必要です。この事業開始等申告書も個人事業の開業を届け出るための書類ですが、開業届とは目的や提出先が異なります。開業届は所得税を納める意思を税務署に届け出る書類であるのに対し、事業開始等申告書は個人事業税を納める意思を都道府県に届け出る書類です。
また、この書類の正式名称は地域により異なり、東京都では「事業等開始申告書」ですが、他の地域では、「事業開始・変更・廃止申告書」や「個人の事業の開始等の報告書」などとも呼ばれています。
【利用料0円】はじめてでもカンタン・安心な「開業届」の作成はこちらをクリック
開業届を提出する際に必要なもの
開業届を提出する際に必要なものは、提出方法により異なります。以下の3つの方法ごとに、提出する際に必要なものを詳しく確認しておきましょう。
窓口で提出する際に必要なもの
開業届を管轄の税務署の窓口で直接提出する方法で必要なものは、開業届とマイナンバーカード、本人確認書類です。以下で、詳しくご説明します。
窓口で開業届を提出する際に必要なもの
- 開業届
- マイナンバーカード(ない場合には、通知カードやマイナンバーが記載された住民票などマイナンバーがわかるものが必要)
- 本人確認書類(マイナンバーカードがない場合には、運転免許証やパスポートなどの写真付きの身分証明書が必要)
窓口で開業届を提出すると、開業届を受領した日付や税務署名が記載されたリーフレットをもらうことができます。このリーフレットは、個人事業主が屋号付き口座を開設する際や小規模企業共済に加入する際などに開業の証明書として必要になる場合があるため、大切に保管しておきましょう。
開業届を窓口で直接提出する方法がおすすめなのは、開業届の書き方に不安がある方です。税務署の窓口では、記入内容に誤りがあればその場で指摘を受けて訂正できるほか、記入内容について質問や相談もできるため安心して提出できます。
なお、自分の管轄の税務署を調べたい場合には、国税庁のWebページ「税務署の所在地などを知りたい方」から検索が可能です。
郵送で提出する際に必要なもの
開業届を郵送で提出する方法で必要なものは、開業届、郵送用封筒、返信用封筒、切手、マイナンバーカードと本人確認書類のコピーです。以下で、詳しくご説明します。
郵送で開業届を提出する際に必要なもの
- 開業届
- 郵送用封筒、切手
- 返信用封筒、切手
- マイナンバーカードのコピー(ない場合には、通知カードやマイナンバーが記載された住民票などマイナンバーがわかるもののコピーが必要)
- 本人確認書類のコピー(マイナンバーカードがない場合には、運転免許証やパスポートなどの写真付きの身分証明書のコピーが必要)
郵送で提出する際には、返信用封筒を同封すれば、開業届の受領を証明するリーフレットを返送してもらえます。返信用封筒には、自分の住所・氏名を記載し切手を貼付するようにしてください。
開業届を直接提出しに行く暇がなかったり、e-Taxの操作に慣れず難しかったりする場合は、郵送で提出するようにしましょう。
e-Taxで提出する際に必要なもの
開業届はe-Taxを利用したオンラインでの提出も可能です。e-Taxでの提出時に必要なものは、本人確認書類または、マイナンバーカードとマイナンバーカードの読み取りに対応したスマホ、または、ICカードリーダー/ライターです。以下で、詳しくご説明します。
e-Taxで開業届を提出する際に必要なもの
税務署職員の対面による本人確認の場合
- 本人確認書類(運転免許証やパスポートなどの写真付きの身分証明書が必要)
マイナンバーカードを利用する場合
- マイナンバーカード
- マイナンバーカードの読み取りに対応したスマホ、または、ICカードリーダー/ライター
e-Taxを利用するためには、まず利用者識別番号を取得しなければなりません。利用者識別番号を取得するためには、マイナンバーカードとスマホ、または、ICカードリーダー/ライターを利用するか、税務署職員の対面による厳選な本人確認が必要になります。また、事前に、電子証明書の取得も必要です。
なお、開業届をe-Taxで提出した場合には、送信後データの受信通知がメッセージボックスに届きます。この受信通知では、提出された方の氏名または名称、受付番号、受付日時などを確認可能です。ただし、一定期間が経つとメッセージボックスから削除されてしまうため、必要であれば印刷しておくかスマートフォンで撮影し、データを保存しておくとよいでしょう。
e-Taxでの提出は、都合のよい時間帯に、自宅から提出したいという方に向いている方法です。
ただし、インターネットに接続された環境が必要であると共に、マイナンバーカードの読み取りに対応したスマホ、または、ICカードリーダー/ライターが必要になるうえ、事前に利用者識別番号や電子証明書の取得も必要となるため、オンラインやパソコンでの作業に抵抗のない方におすすめします。
開業届の提出については以下の記事を併せてご覧ください。
【利用料0円】はじめてでもカンタン・安心な「開業届」の作成はこちらをクリック
開業する際に業種によっては許認可が必要になる
事業の業種によっては、開業する際に許認可が必要な場合があります。許認可には、届出、登録、認可、許可、免許の5種類があり、業種により種類が異なります。開業時に許認可が必要となるのは、主に、以下のような業種です。
開業時に許認可が必要な主な業種
- 美容業(届出)
- 飲食業(許可)
- 建設業(許可)
- 運送業(許可)
- 不動産業(免許)
- 旅行業(登録)
許認可の中には、申請から許認可証の交付まで数か月程度かかる業種もあります。そのため、開業したい業種が決まったら、許認可が必要かどうかをあらかじめ調べておくようにしましょう。
開業時にやることや許認可については以下の記事をご覧ください。
【利用料0円】はじめてでもカンタン・安心な「開業届」の作成はこちらをクリック
【必要ケース別】開業届と併せて提出しておきたい書類
開業届を提出する際に、併せて提出しておいた方がよい書類は、「所得税の青色申告承認申請書」や「青色事業専従者給与に関する届出・変更届出書」、「給与支払事務所等の開設・移転・廃止届出書」、「適格請求書発行事業者の登録申請書」、「源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請書」です。
ただし、提出が必要な方はケースごとに異なります。提出が必要となるケース別に、以下に提出期限と提出先も併せて一覧でまとめました。それぞれどのような役割を持つ書類なのか、一覧表の下にも解説していますので、確認しておきましょう。
開業届と併せて提出しておくとよい書類一覧
| 必要となるケース | 書類名 | 提出期限 | 提出先 |
|---|---|---|---|
| 確定申告で青色申告を選択する | 所得税の青色申告承認申請書 |
青色申告をしようとする年の3月15日まで(その年の1月16日以後に開業した場合は、開業日から2か月以内) | 税務署 |
| 青色事業専従者の要件を満たす家族従業員への給与を必要経費にする | 青色事業専従者給与に関する届出・変更届出書 |
青色事業専従者給与額を必要経費として計上する年の3月15日まで(その年の1月16日以後に開業した場合や、新たに専従者を雇用することになった場合は、開業または雇用した日から2か月以内) | 税務署 |
| 従業員を雇う | 給与支払事務所等の開設・移転・廃止届出書 |
事務所の開設日から1か月以内 | 税務署 |
| 適格請求書等保存方式(インボイス制度)に対応するために適格請求書発行事業者になる | 適格請求書発行事業者の登録申請書 |
登録希望日の15日前まで | 税務署 |
| 従業員が10名未満の場合に、源泉所得税を年2回にまとめて納付する | 源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請書 |
期限の定めなし(原則として、提出した日の翌月に支払う給与等から適用) | 税務署 |
所得税の青色申告承認申請書
「所得税の青色申告承認申請書」は、青色申告をしたい場合に提出が必要な書類です。
個人事業主の確定申告には、青色申告と白色申告の2種類があり、それぞれ必要となる要件が異なります。
最大65万円の青色申告特別控除の適用を受けられる青色申告をするには、事前にこの「所得税の青色申告承認申請書」を提出しておかなければなりません。
青色事業専従者給与に関する届出書
「青色事業専従者給与に関する届出書」は、家族従業員に支払う給与を必要経費として計上したい場合に、提出が必要な書類です。税務署から青色事業専従者と認められるためには、以下の要件があります。
青色事業専従者の認定要件
- 青色申告者と生計が同一の配偶者または親族である
- 申告を行う年の12月31日時点で15歳以上である
- 申告を行う年の6か月を超える期間、青色申告者の事業に専従している
- 給与設定が事業に従事する対価として妥当な金額である
なお、この青色事業専従者給与の特例について適用を受けるためには、「所得税の青色申告承認申請書」も提出する必要があります。
給与支払事務所等の開設・移転・廃止届出書
「給与支払事務所等の開設・移転・廃止届出書」は、従業員を雇用する場合に提出が必要な書類です。従業員を雇用する事業者は、従業員の給与から源泉徴収をして、従業員の代わりに所得税を国へ納めています。「給与支払事務所等の開設・移転・廃止届出書」を税務署に提出することで、従業員の所得税の納付書が送付されます。
適格請求書発行事業者の登録申請書
「適格請求書発行事業者の登録申請書」は、開業当初から適格請求書等保存方式(インボイス制度)に対応し、適格請求書発行事業者になる場合に提出が必要な書類です。
新たに開業した個人事業主は、基準期間(前々年)の売上がないため、売上が1,000万円を超えていても、開業後2年間は消費税が免除されます。ただし、この「適格請求書発行事業者の登録申請書」を提出した場合には課税事業者として開業当初から消費税が課税され、適格請求書発行事業者となることが可能です。
取引先との関係性や消費税納税のための事務負担の増加など、課税事業者になることでのメリットとデメリットを考慮したうえで、書類の提出を判断しましょう。
源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請書
「源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請書」は、雇用している従業員が10名未満の場合に申請できる書類です。源泉所得税の納期の特例の適用を受けたい場合には、この書類を提出しなければなりません。
源泉所得税は原則として徴収した日の翌月10日が納期限ですが、この特例の適用を受けると、源泉徴収をした所得税と復興特別所得税について、年2回にまとめて納付できるようになります。
【利用料0円】はじめてでもカンタン・安心な「開業届」の作成はこちらをクリック
開業届を作成・提出する方法
開業費を作成して提出するための流れは、以下になります。開業届をスムーズに提出するために、あらかじめ手順を確認しておきましょう。
開業届を作成し提出する手順
-
STEP 1.開業届を入手する
-
STEP 2.必要項目を記入する
-
STEP 3.税務署に提出する
STEP 1. 開業届を入手する
開業届は、国税庁のWebページ「個人事業の開業届出・廃業届出等手続」からダウンロード、または、税務署で入手できます。そのほか、e-Taxを利用した提出であれば、オンライン上のe-Taxソフトの申請・申告等一覧から「個人事業の開業・廃業等届出書」を選択しましょう。
STEP 2. 必要項目を記入する
開業届を入手したら、必要事項に沿って記入していきます。
なお、開業日は事業の開始日やオープン日などにすることが一般的ですが、開業日はある程度柔軟に選べるため、開業前の準備している期間を開業日に設定しても問題ありません。
STEP 3. 税務署に提出する
作成した開業届を税務署に提出します。
税務署への提出は、窓口、郵送、e-Taxの3種類から選べるため、自分に合う方法を選んで提出しましょう。
開業届の提出方法については以下の記事や動画をご覧ください。
【利用料0円】はじめてでもカンタン・安心な「開業届」の作成はこちらをクリック
開業届を提出する際のメリット
開業届を提出する際には、メリットとデメリットがあります。それぞれを比較しながら、開業届の提出を検討しましょう。まずは、開業届を提出するメリットからご紹介します。
開業届を提出するメリット
- 節税効果の高い青色申告ができる
- 屋号名義で銀行口座を開設できる
- 補助金や助成金の申請が可能になる
- 小規模企業共済に加入できる
節税効果の高い青色申告ができる
開業届を提出するメリットは、青色申告ができることです。
青色申告をする際は煩雑な複式帳簿で記帳する必要はあるものの、青色申告特別控除が適用されれば、課税所得金額から最大65万円の控除を受けることができます。そのほか、青色申告をすることで、赤字を3年間繰り越すことや30万円未満の必要経費を一括計上できる少額減価償却資産の特例も受けられるなど、節税効果を高めることが可能です。
屋号名義で銀行口座を開設できる
屋号名義で銀行口座を開設できることも、開業届を提出するメリットの1つです。
屋号付き口座を開設する際は、屋号を使って事業をしていることを証明するための書類として、開業届の確認を求められます。開業届を提出した際にもらう、受領を証明するリーフレットや受信通知での証明が可能です。
なお、屋号名義の銀行口座を開設する際には、開業届以外に、納税証明書や確定申告書の控えなども提出書類として認められる場合があります。口座を開設する銀行によって異なるため、銀行のホームページなどで必要書類を確認しましょう。
補助金や助成金への申請が可能になる
開業届は事業を開始したばかりの個人事業主であるという証明になるため、補助金や助成金を申請する際の必要書類としても使用できます。この際も、開業届の提出時にもらうリーフレットや受信通知で問題ありません。
個人事業主は法人と比べて開業時に資金調達する手段が限られるため、補助金や助成金への申請が可能になることはメリットといえます。
小規模企業共済に加入できる
小規模企業共済に加入できることも、開業届を提出するメリットとしてあげられます。小規模企業共済とは、個人事業主や中小企業の経営者などが積み立てる退職金制度のことです。個人事業主は会社員のように退職金制度がないため、老後のための支えとなる制度といえます。
小規模企業共済に開業時から加入する場合には、個人事業主であるという証明書として開業届が必要です。開業届の提出を証明するリーフレットや受信通知を提示しましょう。
【利用料0円】はじめてでもカンタン・安心な「開業届」の作成はこちらをクリック
開業届を提出する際のデメリット
開業届を提出することでのデメリットもあります。主なデメリットは以下になります。
開業届を提出するデメリット
- 家族の健康保険の被扶養者から外れる
- 失業保険を受給できなくなる
家族の健康保険の被扶養者から外れる
開業届を提出すると、家族の健康保険の被扶養者から外れる可能性もあることがデメリットです。健康保険の被扶養者の認定要件は健康保険組合ごとに異なるため、不安な方は家族が加入する健康保険組合の規定を確認しておくようにしてください。
もし家族の健康保険の被扶養者から外れてしまった場合には、国民健康保険や国民年金保険料を自分で支払わなければなりません。
失業保険を受給できなくなる
退職し失業保険を受給している場合には、失業保険を受給できなくなることもデメリットにあげられます。開業届を提出すると、個人事業主として事業を開始し「再就職の意思がない」と見なされるため、失業保険の受給対象ではなくなってしまうのです。
開業届を提出する際は、提出するメリットやデメリットと共に、提出するタイミングについても考慮するようにしましょう。
開業届を提出するメリット・デメリットについては以下の記事をご覧ください。
【利用料0円】はじめてでもカンタン・安心な「開業届」の作成はこちらをクリック
開業の手続きや日々の作業を手軽にする方法
ここまで説明してきたように、個人事業主として開業する際には、さまざまな書類の作成や手続きをしなければなりません。そのような煩雑な開業手続きを手軽に進めたい場合には、「弥生のかんたん開業届」のご利用がおすすめです。
「弥生のかんたん開業届」は、画面の案内に沿って必要事項を入力していくだけで、個人事業主の開業時に必要な書類を自動生成できる無料のクラウドサービスです。パソコンでもスマホでも利用でき、開業届をはじめとする、「所得税の青色申告承認申請書」や「給与支払事務所等の開設届出書」などの書類もスムーズに作成できます。
また、個人事業主として開業後は、日々の帳簿付けや毎年の確定申告も必要になります。事業が開始する前に、会計や確定申告をサポートしてくれるソフトを導入しておくと安心です。クラウド確定申告ソフト「やよいの青色申告 オンライン」なら、簿記や会計の知識がなくても、最大65万円の青色申告特別控除の要件を満たす青色申告の必要書類を簡単に作成できます。銀行口座明細の自動取込や自動仕訳機能を使って、記帳にかかる時間を削減することも可能です。
【利用料0円】はじめてでもカンタン・安心な「開業届」の作成はこちらをクリック
必要なものを揃えてスムーズに開業手続きしよう
開業時には、すべての方が開業届と事業開始等申告書を提出しなければなりません。
開業届を提出する際に必要なものは、提出方法によって異なります。自分が提出しやすい方法に合わせて、必要なものを揃えるようにしましょう。
また、開業届を提出する際に、併せて提出しておきたい書類もあります。ケース別に提出すべき書類は異なるので、あらかじめチェックして漏らさず提出するようにしてください。
また、開業する際は、「弥生のかんたん開業届」を利用すれば、開業届だけでなく、開業に必要なさまざまな書類を手軽に作成できます。また、「やよいの青色申告 オンライン」であれば、簿記の知識がなくても複式簿記での記帳がかんたんにできます。開業にあたって、ぜひご利用をご検討ください。
【利用料0円】はじめてでもカンタン・安心な「開業届」の作成はこちらをクリック
「弥生のかんたん開業届」登録者様限定!開業お祝いキャンペーン実施中!
「弥生のかんたん開業届」は、画面に沿って操作するだけで、「無料」で「かんたん」に個人事業主の開業届を作成できるサービスです。開業届だけでなく、開業届を含む必要書類を作れます。
今なら、「弥生のかんたん開業届」で開業して、「やよいの青色申告 オンライン」をご契約いただいた方に開業お祝いキャンペーン実施中です!(キャンペーン期間内にエントリー要)
開業お祝いキャンペーン概要
以下の条件すべてを満たした方の中から、抽選で150名様にAmazonギフトカード(Eメールタイプ)をプレゼントします。
また、エントリーいただいた方全員に「確定申告の流れがよくわかる!確定申告ガイド」を進呈します。
キャンペーン期間:2026年2月9日(月)~2026年3月31日(火)
キャンペーン適用条件
- 「弥生のかんたん開業届」に登録いただいた方
- キャンペーン期間内にキャンペーン申し込みフォームからエントリーされた方
- キャンペーン期間内に「やよいの青色申告 オンライン」をご契約いただいた方
キャンペーンお申し込みの手順などの詳細は、以下のバナーからご確認ください。
【利用料0円】はじめてでもカンタン・安心な「開業届」の作成はこちらをクリック
この記事の監修者森 健太郎(税理士)
ベンチャーサポート税理士法人 代表税理士。
毎年1,000件超、累計23,000社超の会社設立をサポートする、日本最大級の起業家支援士業グループ「ベンチャーサポートグループ」に所属。
起業相談から会社設立、許認可、融資、助成金、会計、労務まであらゆる起業の相談にワンストップで対応します。起業・会社設立に役立つYouTubeチャンネル会社設立サポートチャンネルを運営。