会社設立の登記申請書は郵送で申請できる?方法や注意点も解説
監修者: 森 健太郎(税理士)
更新
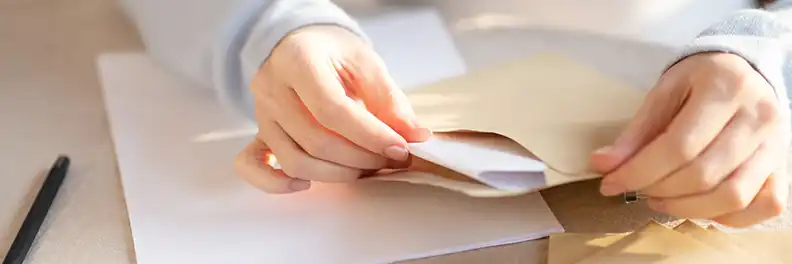
会社を設立する際の法人登記申請は、法務局の窓口に出向くほかに、オンラインでも手続きが可能です。
ただし、オンラインでの申請にはソフトのダウンロードなどの事前準備が必要になり、慣れていないとハードルが高いと考える方も多いかもしれません。
登記申請は、窓口やオンラインでの提出以外に、郵送でも可能です。本記事では、登記申請を郵送で行う方法や注意点などについて詳しく解説します。
法人設立ワンストップサービスを利用して、オンラインで登記申請も可能。
個人事業主から法人成りを予定している方にもおすすめです。

【無料】はじめてでもカンタン・安心な「会社設立」の書類作成はこちらをクリック
会社を設立する際の登記申請書類は郵送できる
設立登記申請書などの必要書類を管轄の法務局へ提出する法人登記(会社設立登記)の申請は、郵送で行うことができます。法務局のWebページ「商業・法人登記の郵送申請について」に郵送申請の方法が記載されているためです。
また、郵送での申請以外にも、窓口やオンラインで申請する方法もあります。この3つの申請方法のうち郵送申請やオンライン申請であれば、わざわざ法務局の窓口に足を運ぶ必要がなく、手間や時間を削減できます。
ただ、オンライン申請の場合は、専用ソフトのダウンロードや電子証明書の読み取りが必要になるため、慣れていない方にとってはハードルが高いと感じるかもしれません。さらに、データ化できない添付書類があると、申請後に別途窓口または郵送で提出しなければならず、二度手間になる可能性もあります。
そのようなときでも、郵送申請なら紙の書類で作成するので、専用ソフトなどの事前準備は不要です。また、設立登記申請書と添付書類を併せて郵送できるので、提出の手間も一度で済みます。法務局に行かずに登記申請をしたいけれどオンライン申請にはハードルを感じている場合や、申請書類を書面で作成したけれど法務局まで行くのに時間がかかるというような場合には、郵送申請を検討してみましょう。
【無料】はじめてでもカンタン・安心な「会社設立」の書類作成はこちらをクリック
郵送で登記申請する方法は他の方法と違う点がある
登記申請書を郵送で申請する場合は、窓口やオンラインでの申請方法とは違う点があります。スムーズに登記申請できるよう、以下のような登記申請書を郵送する際の具体的な流れをあらかじめ確認しておきましょう。
登記申請書を郵送で申請する方法
-
STEP1.登記申請に必要な書類を準備する
-
STEP2.管轄の法務局宛に必要書類一式を郵送する
-
STEP3.法務局に書類一式が届いて受理された後に登記申請が完了する
STEP1. 登記申請に必要な書類を準備する
まずは、法人登記申請に必要な書類を準備します。設立登記申請書は、法務局のWebページ「商業・法人登記の申請書様式」からダウンロードが可能です。株式会社と合同会社では記載する内容はほぼ同じですが、書式が異なるため間違えないように注意してください。
また、法人登記の申請をする際には、設立登記申請書以外にも、定款や取締役(代表社員)の印鑑登録証明書、出資金(資本金)の払込証明書など、さまざまな書類を提出する必要があります。株式会社と合同会社では提出書類が異なるため、用意する書類に不安のある方は管轄の法務局に必要書類を確認しておくと安心です。
なお、法人登記に必要な書類をかんたんに作成するには、クラウドサービス「弥生のかんたん会社設立」が便利です。「弥生のかんたん会社設立」を利用すれば、ステップに沿って必要情報の入力を進めるだけで株式会社や合同会社の設立に必要な書類を自動で生成できるため、書類作成に手間をかけたくない方は利用を検討してみましょう。
※会社設立に必要な書類については以下の記事を併せてご覧ください
※紙申請での登記申請書の作成方法については以下のよくある質問を併せてご覧ください
STEP2. 管轄の法務局宛てに必要書類一式を郵送する
続いて、必要書類一式を、本店所在地を管轄する法務局宛てに郵送します。封筒には、「登記申請書在中」と明記してください。
管轄の法務局の住所は、法務局のWebページ「管轄のご案内」から確認できます。このとき気を付けなければならないのが、郵送先の法務局を間違えないことです。管轄外の法務局に書類を郵送しても登記申請は却下となり、取り下げと再申請のために、手間と時間が余計にかかってしまいます。
なお、法務局には「不動産登記管轄区域」と「商業・法人登記管轄区域」があり、法人登記申請の郵送先は「商業・法人登記管轄区域」の法務局です。支局や出張所によっては商業・法人登記の申請を受け付けていないため、郵送先を確認するときには注意が必要です。
STEP3. 法務局に書類一式が届いて受理された後に登記申請が完了する
提出書類の内容に問題がなければ、法務局に書類が届いて受理されてから1週間~10日ほどで登記が完了します。書類に不備があれば法務局から連絡がありますが、不備がなければ法務局から登記完了の連絡はありません。
法人登記を郵送で申請した場合は、書類が到着して受理された日が会社設立日になります。書類を発送した日ではないので注意しましょう。なお、法務局の取扱い時間は土日祝日と年末年始を除く8時30分~17時15分までです。郵送した書類が業務時間外に到着した場合、受理されるのは翌業務日となります。
法人の登記申請については以下の動画を併せてご覧ください
【無料】はじめてでもカンタン・安心な「会社設立」の書類作成はこちらをクリック
登記申請書類を郵送する際には注意点がある
登記申請にミスやトラブルがあると、会社の設立が遅れたり、業務の開始時期にも影響を及ぼしたりする可能性があります。手続きをスムーズに終えられるよう、登記申請書類を郵送する際には以下のような点に注意しましょう。
会社設立の登記申請書類を郵送する際の注意点
- 申請書は追跡可能な郵送方法で送る
- 登録免許税分の収入印紙の貼り付けを忘れない
- 収入印紙に消印はしない
- 申請書に電話番号を付記しておく
- 不備があった際に申請の補正や取り下げが必要で時間や手間がかかる
申請書類は追跡可能な郵送方法で送る
会社設立の登記申請書類を郵送で送る際の注意点として、申請書類は追跡可能な郵送方法で送ることがあげられます。普通郵便で送ってしまうと郵便追跡サービスを利用できないため、法務局に到着したかどうかが確認できなくなるからです。
また、設立登記申請書などの提出書類は信書に該当し、宅配便で送付することはできません。登記申請書類一式を郵送するときには、レターパックや書留(簡易書留)、特定記録郵便といった追跡可能な方法で送付するようにしましょう。
登録免許税分の収入印紙の貼り付けを忘れない
会社設立の登記申請書類を郵送で送る際の注意点として、登録免許税分の収入印紙の貼り付けを忘れないこともあげられます。法人登記に当たっては、オンライン申請で電子納付をする場合を除き、登録免許税を収入印紙で納めなければならないからです。郵送で登記申請をする際には、「登録免許税納付用台紙」に登録免許税分の収入印紙を貼り付け、同封するのを忘れないよう注意してください。
登録免許税の金額は、株式会社は「資本金額×0.7%」または15万円のどちらか高い方、合同会社は「資本金額×0.7%」または6万円のどちらか高い方になります。
収入印紙は、法務局以外に全国の郵便局でも購入できるほか、例えば、コンビニなどの店舗でも収入印紙を取り扱っていることがあります。ただし、コンビニなどでは200円の収入印紙しか扱っていないことが多いため、法務局や郵便局で購入する方が必要な金額を揃えやすいといえるでしょう。
収入印紙に消印はしない
会社設立の登記申請書類を郵送で送る際の注意点として、収入印紙を台紙に貼付して送るときは、収入印紙に消印はしないこともあげられます。登録免許税を印紙で納品する場合は、法務局において収入印紙を確認した後に消印処理がされるためです。
消印とは、印紙と書類にまたがって押す印(または署名)のことで、収入印紙の再利用防止のために行うものです。例えば、申請者が印紙に消印をしたり汚したりしてしまったりすると、その印紙は使用できなくなってしまうため、取り扱いに注意しましょう。
申請書に電話番号を付記しておく
会社設立の登記申請書類を郵送で送る際の注意点として、申請書に電話番号を記載しておくこともあげられます。電話番号を記載しておくことで、例えば申請書類の内容に不備があったときには、法務局から速やかに連絡を受けられるためです。申請書の上部の余白部分などに電話番号を書き入れたり、メモを貼っておいたりするといいでしょう。
不備があった際に申請の補正や取り下げが必要で時間や手間がかかる
会社設立の登記申請書類を郵送で送る際の注意点として、不備があった際に申請の補正や取り下げが必要で時間や手間がかかることもあげられます。郵送申請に限りませんが、申請書類の内容に不備があったり、添付書類が不足していたりすると、新たに補正する手続きが必要になってしまいます。郵送で申請した場合は、法務局に直接再提出するほか、郵送で補正することも可能です。
また、例えば誤って管轄外の法務局に申請書類を送ってしまったなど、申請が却下された場合は、登記申請の取り下げを行う必要があります。書類の不備が多く、補正期限までに対応できない場合にも、いったん申請を取り下げてから再提出することになります。
補正や取り下げの手続きには時間や手間がかかり、その分会社の設立が遅れてしまいます。郵送する前に、提出書類に漏れはないか、収入印紙を貼り忘れていないか、宛先は管轄の法務局になっているかなどを、よく確認するようにしましょう。
【無料】はじめてでもカンタン・安心な「会社設立」の書類作成はこちらをクリック
会社設立の登記を申請するには郵送以外の方法もある
法人登記は、郵送以外に、法務局の窓口やオンラインでも申請が可能です。以下にあげるそれぞれの違いを把握したうえで、利用しやすい申請方法を選びましょう。
郵送以外に登記を申請する方法
- 法務局の窓口で直接申請する
- オンラインで申請する
法務局の窓口で直接申請する
郵送以外で会社設立の登記を申請するには、法務局の窓口で直接申請する方法があげられます。管轄の法務局の窓口に出向き、法人登記に必要な書類一式を直接提出する方法です。提出書類に不足がないかを窓口でチェックしてもらえるため、登記申請に不安がある方は心強いといえます。
ただし、書類の内容確認は提出の場では行われないため、不備があった際は法務局から連絡が入り、補正して再提出しなければなりません。
なお、窓口申請の場合は窓口で提出して受理された日が会社設立日となるため、設立日にこだわりがある方はこの方法を選ぶといいでしょう。
オンラインで申請する
郵送以外で会社設立の登記を申請するには、オンラインで申請する方法があげられます。
オンライン申請の場合には、法務省の「登記・供託オンライン申請システム 登記ねっと 供託ねっと」、またはマイナポータルの「法人設立ワンストップサービス
」を利用します。オンライン申請なら好きな時間に自宅から申請でき、登録免許税も電子納付が可能です。
ただし、登記・供託オンライン申請システム 登記ねっと 供託ねっとを利用するには、あらかじめ専用ソフトをダウンロードする必要があります。また、法人設立ワンストップサービスの利用に当たっては、代表者のマイナンバーカードや、ICカードリーダー/ライター、またはNFC対応のスマートフォン、マイナポータルアプリが必要です。申請時には電子署名の付与も必須となるため、デジタルツールを使ったやりとりに慣れていないと、かえって手間がかかるかもしれない点は考慮しておきましょう。
※設立登記をオンライン申請する方法については以下の記事を併せてご覧ください
【無料】はじめてでもカンタン・安心な「会社設立」の書類作成はこちらをクリック
会社設立に必要な手続きを手軽に行う方法
設立登記の申請といった会社設立の手続きを手軽に行いたい場合におすすめなのが、「弥生のかんたん会社設立」です。
「弥生のかんたん会社設立」は、画面の案内に沿って必要事項を入力するだけで、定款をはじめとする会社設立時に必要な書類を自動生成できるクラウドサービスです。各官公庁への提出もしっかりガイドするため、事前知識は要りません。さらに、入力内容はクラウドに自動保存され、パソコンでもスマホでも自由に切り替えながら書類作成ができます。
【無料】はじめてでもカンタン・安心な「会社設立」の書類作成はこちらをクリック
自社に合った方法でスムーズに法人登記申請を行おう
会社設立に必要な法人登記をするには、法務局の窓口や郵送のほか、オンラインを利用するといった申請方法があります。このうち郵送での申請なら、わざわざ法務局に足を運ぶ手間がかからず、専用ソフトのダウンロードなども必要ありません。
ただ、登記申請にはさまざまな提出書類があり、一からすべてを作成するのは大変な作業です。また、郵送する申請書類の内容に不備があると、補正のために余計な手間と時間がかかってしまいます。書類作成の手間を削減し、法人登記をスムーズに行うには、「弥生のかんたん会社設立」の利用がおすすめです。例えば、書類の作成に「弥生のかんたん会社設立」を利用し、郵送で申請するのも1つの方法です。会社設立準備で忙しい中、時間を効率よく使うためにも、便利なサービスを活用しましょう。
【無料】はじめてでもカンタン・安心な「会社設立」の書類作成はこちらをクリック
この記事の監修者森 健太郎(税理士)
ベンチャーサポート税理士法人 代表税理士。
毎年1,000件超、累計23,000社超の会社設立をサポートする、日本最大級の起業家支援士業グループ「ベンチャーサポートグループ」に所属。
起業相談から会社設立、許認可、融資、助成金、会計、労務まであらゆる起業の相談にワンストップで対応します。起業・会社設立に役立つYouTubeチャンネル会社設立サポートチャンネルを運営。









