社会保険の加入条件とは?適用範囲や手続き、提出書類を解説
更新
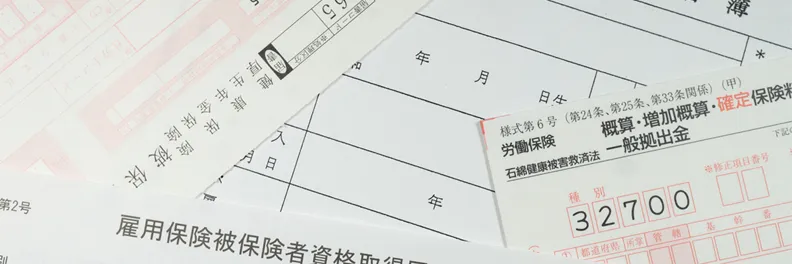
すべての企業は、社会保険の適用事業所となり、社会保険(健康保険・厚生年金保険・介護保険)の加入義務があります。さらに、条件を満たす従業員を雇用したときには、必ず社会保険に加入させなければなりません。社会保険のうち、健康保険と厚生年金保険については、法改正により2024年10月から加入適用範囲が拡大するため注意が必要です。
本記事では、社会保険の加入条件や適用範囲の他、加入手続きなどについて詳しく解説します。
【無料で資料ダウンロード】「弥生給与 Next」でバックオフィス業務をスムーズに
今なら「弥生給与 Next」スタート応援キャンペーン実施中!

無料お役立ち資料【「弥生給与 Next」がよくわかる資料】をダウンロードする
社会保険とは?
社会保険とは、病気やケガ、失職、老齢、労働災害など、働く人のさまざまなリスクに対する公的な保険制度で、「健康保険」「厚生年金保険」「介護保険」「雇用保険」「労災保険」の5つがあります。
社会保険は「広義の社会保険」と「狭義の社会保険」に分けて使われることがあり、広義の社会保険は前述の5つの保険を指し、狭義の社会保険は5つの保険のうち健康保険、厚生年金保険、介護保険の3つを指します。狭義の社会保険に含まれない雇用保険と労災保険は、まとめて「労働保険」と呼ばれます。
会社などに勤務する人にとっての社会保険とは、狭義の社会保険を指すことが多いでしょう。本記事でも社会保険は狭義の社会保険の意味として解説します。
健康保険
健康保険は、病気やケガで医療機関を受診する際の自己負担額を軽減するための保険です。健康保険はいくつか種類がありますが、企業で働く人が加入するのは協会けんぽ、または組合健保になります。
厚生年金保険
厚生年金保険は、企業などに雇用されて勤務している人が加入する公的年金制度です。被保険者が高齢になったときや、病気やケガが原因で障害が残ってしまったとき、死亡したときに、本人や遺族の生活を支えるための保険で、将来的に国民年金に上乗せする形で給付を受けることができます。
厚生年金保険についてはこちらの記事で解説していますので、参考にしてください。
介護保険
介護保険は、高齢によって介護が必要になった人などを社会全体で支えるために、2000年4月1日から施行された社会保険制度です。市区町村より要介護や要支援認定を受けた場合の介護費用の負担を軽減するための保険で、健康保険の加入者のうち、40歳以上の人は全員加入します。
介護保険についてはこちらの記事で解説していますので、参考にしてください。
広義の社会保険に含まれる雇用保険と労災保険
本記事では狭義の社会保険(健康保険、厚生年金保険、介護保険)を扱いますが、広義の社会保険は前述の3つに雇用保険と労災保険が加わります。雇用保険と労災保険をまとめて、労働保険と呼ぶこともあります。
雇用保険
雇用保険は、企業に雇用される従業員の生活や雇用の安定を目的とした保険です。失業した場合の求職者給付や教育訓練給付、育児休業・介護休業をした場合の育児休業給付や介護休業給付など、いざというときに状況に応じた給付を受け取ることができます。
雇用保険についてはこちらの記事で解説していますので、参考にしてください。
労災保険
労災保険は、労働災害のリスクに備えるための保険です。業務中や通勤中に発生した病気、ケガ、障害または死亡に対して、被保険者やその遺族へ必要な給付が行われます
労災保険についてはこちらの記事で解説していますので、参考にしてください。
【無料で資料ダウンロード】「弥生給与 Next」でバックオフィス業務をスムーズに
事業所の社会保険の加入条件
社会保険の加入条件は、事業所と従業員のそれぞれについて定められています。社会保険の適用を受ける事業所を「適用事業所」といい、適用事務所には「強制適用事業所」と「任意適用事業所」の2種類があります。
強制適用事業所
強制適用事業所とは、事業主や従業員の意思、従業員数、事業の規模、業種などに関係なく、社会保険への加入が義務付けられている事業所のことです。強制適用事業所に該当する条件は、以下のとおりです。
強制適用事業所の条件
- 国・地方公共団体または法人の事業所(事業主のみの場合を含む)
- 5人以上の従業員を常時雇用している個人の事業所(農林水産業、サービス業などの非適用業種を除く)
株式会社や合同会社などの法人は、従業員の人数を問わず強制適用事業所となります。たとえ社長1人のみの会社であっても、社会保険に加入しなければなりません。また、個人事業主でも、常時5人以上の従業員を雇用している場合は、社会保険への加入が必要です。
任意適用事業所
任意適用事業所とは、強制適用事業所とならない事業所のことで、厚生労働大臣(日本年金機構)の認可を事前に受けて、健康保険・厚生年金保険の適用となった事業所のことです。任意適用事業所になるために必要な条件は、従業員の半数以上が同意のうえ、事業主が申請して厚生労働大臣(日本年金機構)の認可を受けなければなりません。
【無料で資料ダウンロード】「弥生給与 Next」でバックオフィス業務をスムーズに
従業員の社会保険(健康保険・厚生年金保険)の加入条件と適用範囲
適用事業所で働いている従業員は、一定の条件を満たす場合、社会保険(健康保険・厚生年金保険)に加入する必要があります。従業員が社会保険に加入するための条件は、以下のとおりです。
社会保険の加入条件
- 適用事業所に常時雇用されている70歳未満(厚生年金)・75歳未満(健康保険)の従業員
- 1週間の所定労働時間および1か月の所定労働日数が常勤労働者の4分の3以上の従業員
なお、介護保険は、健康保険に加入している40歳以上の人が対象となります。
【無料で資料ダウンロード】「弥生給与 Next」でバックオフィス業務をスムーズに
パート・アルバイトの加入条件
所定労働時間や所定労働日数がフルタイム従業員の4分の3未満のパート・アルバイトであっても、以下の条件にすべて該当する場合は、社会保険の加入対象となります。
パート・アルバイトの社会保険の加入条件
- 従業員数(被保険者数)が101人以上の事業所に勤めている(2024年10月以降は常時51人以上)
- 週の所定労働時間が20時間以上30時間未満
- 所定内賃金が月額8万8,000円以上
- 2か月を超える雇用の見込みがある
- 学生ではない
なお、2024年10月以降は法改正により、社会保険の適用範囲が拡大されます。上に挙げたパート・アルバイトの社会保険の加入条件のうち、「従業員(被保険者数)が101人以上の事業所に勤めている」が、2024年10月以降は「従業員(被保険者数)が51人以上の事業所に勤めている」となります。
これまで社会保険に加入する必要がなかった従業員数51~100人の事業所で働くパート・アルバイト従業員も、2024年10月以降は、他の条件にも該当する場合、社会保険に加入しなければなりません。
2024年10月以降の適用範囲の変更点は、以下のとおりです。
| 対象 | 2022年10月~2024年9月 | 2024年10月~(改正) |
|---|---|---|
| 特定適用事業所 | 従業員数が101人以上 | 従業員数が常時51人以上 |
| 短時聞労働者 | 週の所定労働時間が20時間以上30時間未満 | 変更なし |
| 所定内賃金が月額8万8,000円以上 | 変更なし | |
| 2か月を超える雇用の見込みがある | 変更なし | |
| 学生でない | 変更なし |
-
※厚生労働省「社会保険適用拡大ガイドブック
」
企業は、条件を満たす従業員を社会保険に加入させなければならず、未加入のままだと後述する罰則が科せられる可能性があります。
ただし、2024年10月以降、社会保険の適用拡大の影響を受けるパートやアルバイト従業員の中には、「社会保険の扶養の範囲内で働きたい」「社会保険料を負担して手取りが減るのは避けたい」と考える人もいるかもしれません。企業は、該当する従業員と事前に面談などを行い、今後の労働時間や勤務形態の意向を話し合っておくことが大切です。
【無料で資料ダウンロード】「弥生給与 Next」でバックオフィス業務をスムーズに
事業所が新たに社会保険に加入するための手続きと提出書類
事業所が社会保険の適用を受けるためには、強制適用事業所か任意適用事業所かによって手続きの方法や提出書類などが異なります。特に、法人の場合はすべて強制適用事業所になるため、会社設立から5日以内に必要書類を提出しなければなりません。期限が短いので、遅れないように注意しましょう。
以下に紹介する提出書類を提出期日までに事務センターまたは管轄の年金事務所へ、窓口持参、郵送、電子申請のいずれかの方法で提出してください。
| 事業所 | 提出書類 | 提出期日 |
|---|---|---|
| 強制適用事業所 | 健康保険・厚生年金保険 新規適用届 健康保険・厚生年金保険 被保険者資格取得届 健康保険 被扶養者(異動)届 健康保険・厚生年金保険 保険料口座振替納付申出書 各種添付書類 |
事実発生から5日以内 |
| 任意適用事業所 | 健康保険・厚生年金保険 任意適用申請書・同意書 健康保険・厚生年金保険 被保険者資格取得届 健康保険 被扶養者(異動)届 健康保険・厚生年金保険 保険料口座振替納付申出書 各種添付書類 |
従業員の半数以上の同意を得たあと速やかに |
-
※日本年金機構「健康保険・厚生年金保険 新規加入に必要な書類一覧
」
【無料で資料ダウンロード】「弥生給与 Next」でバックオフィス業務をスムーズに
従業員の社会保険の加入・適用除外のための手続き
従業員の社会保険に関する手続きは、勤務先である事業所が行います。手続きが必要になるケースは、従業員の入社や退職など以下のような場合が多く、それぞれ手続きが異なります。
社会保険に関する手続きが発生する代表的な例
- 従業員が入社したとき
- 従業員が退職したとき
- 従業員が社会保険の加入条件を満たさなくなったとき
- 従業員が家族を被扶養者にするとき
従業員が入社したとき
社会保険の加入条件を満たす従業員が入社したときは、被保険者の資格取得手続きが必要です。従業員を雇用してから5日以内に、従業員の基礎年金番号またはマイナンバーが記載されている「被保険者資格取得届」を、所轄の年金事務所もしくは所轄の事務センターに提出します。
なお、会社が組合管掌健康保険(組合健保)に加入している場合は、健康保険組合での手続きを別途行う必要があります。
入社の手続きについてはこちらの記事で解説していますので、参考にしてください。
従業員が退職したとき
従業員が退職などによって被保険者の資格を失ったときは、被保険者の資格喪失手続きが必要です。従業員の退職から5日以内に、「被保険者資格喪失届」を所轄の年金事務所もしくは事務センターに提出します。また、健康保険が全国健康保険協会(協会けんぽ)の場合は、併せて健康保険証(扶養家族分を含む)を返却します。
なお、会社が組合管掌健康保険(組合健保)に加入している場合は、別途、健康保険組合での手続きを行います。
退職の手続きについてはこちらの記事で解説していますので、参考にしてください。
従業員が社会保険の加入条件を満たさなくなったとき
雇用契約の変更などにより、パートやアルバイト従業員の労働時間が減少することで、社会保険の加入条件を満たさなくなった場合は、従業員が退職したときと同じように「被保険者の資格喪失手続き」を行います。
ただし、この場合は本人への確認をせずに手続きを進めてしまうと、トラブルを招く可能性があるので注意が必要です。資格喪失手続きを行う前に、従業員本人が社会保険の加入条件を満たさなくなったことを認識しているか、さらには加入継続の意思があるかを、必ず確認してください。
従業員が家族を被扶養者にするとき
従業員が配偶者や親族を社会保険の扶養に入れる(被扶養者にする)場合、従業員に「健康保険 被扶養者(異動)届」と「国民年金第3号被保険者関係届」、被扶養者の戸籍謄(抄)本または住民票や収入要件確認のための書類などを提出してもらい、所轄の年金事務所または事務センターに届け出ます。
なお、家族を社会保険の被扶養者にできるのは、以下の2つの条件を満たしている場合です。
家族が社会保険の被扶養者になる条件
- その被扶養者(家族)の1年間の収入が130万円未満(60歳以上または一定の障害がある場合は180万円未満)
- その被扶養者(家族)の1年間の収入が被保険者の年間収入の2分の1未満
- ※健康保険組合の場合、一年間の定めが異なる場合がありますので必ず確認しましょう。
扶養についてはこちらの記事で解説していますので、参考にしてください。
【無料で資料ダウンロード】「弥生給与 Next」でバックオフィス業務をスムーズに
社会保険に加入しなかった場合は罰則がある
強制適用事業所であるにもかかわらず従業員を意図的に社会保険に加入させないなど、社会保険未加入の状態が続いた場合、悪質と判断されると以下のような罰則の対象となります。
強制適用事業所が社会保険に加入しなかった場合の罰則
- 6か月以下の懲役または50万円以下の罰金
- 過去2年前に遡及加入して未納分の社会保険料を納入
ただし、すぐに罰則の対象になるわけではなく、日本年金機構からの加入状況に関する調査や加入指導を経て、最終的には強制加入手続きや罰則が適応されます。
【無料で資料ダウンロード】「弥生給与 Next」でバックオフィス業務をスムーズに
社会保険や控除などの計算は給与計算ソフトが便利
社会保険の加入条件は法令で定められているため、従業員の雇用状況を把握したうえで適切な手続きが必要です。従業員の社会保険料は、給与や賞与から控除(天引き)して会社が納めます。また、給与や賞与からは社会保険料の他にも所得税などを控除しますが、控除額の計算方法や料率はそれぞれ異なります。このような煩雑な作業を効率化するには、給与計算ソフトの活用がおすすめです。
弥生の給与計算ソフト「弥生給与 Next」は、給与計算業務に必要な機能を網羅し、給与・賞与計算、年末調整を効率化します。自社に合った給与計算ソフトを活用して、給与計算業務を効率化しましょう。
【無料で資料ダウンロード】「弥生給与 Next」でバックオフィス業務をスムーズに
「弥生給与 Next」で給与・勤怠・労務をまとめてサクッとデジタル化
弥生給与 Nextは、複雑な人事労務業務をシームレスに連携し、効率化するクラウド給与サービスです。
従業員情報の管理から給与計算・年末調整、勤怠管理、保険や入社の手続きといった労務管理まで、これひとつで完結します。
今なら「弥生給与 Next」 スタート応援キャンペーン実施中です!
この機会にぜひお試しください。
この記事の監修者税理士法人古田土会計
社会保険労務士法人古田土人事労務
中小企業を経営する上で代表的なお悩みを「魅せる会計事務所グループ」として自ら実践してきた経験と、約3,000社の指導実績で培ったノウハウでお手伝いさせて頂いております。
「日本で一番喜ばれる数の多い会計事務所グループになる」
この夢の実現に向けて、全力でご支援しております。
解決できない経営課題がありましたら、ぜひ私たちにお声掛けください。必ず力になります。







