納品書の送り方|送るタイミングやポイントをわかりやすく解説
監修者: 市川 裕子(ビジネスマナー監修)
更新
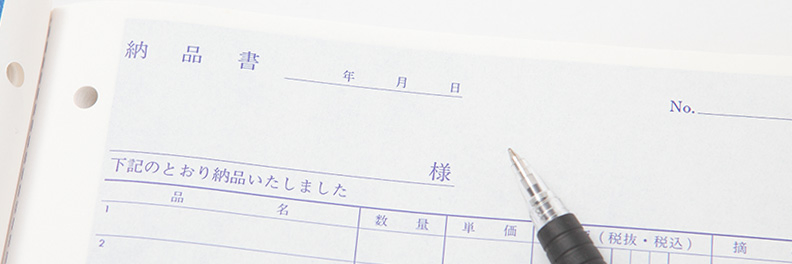
納品書はただ送付すればよいというわけではありません。取引先との信頼関係を築くためには、ビジネスマナーに従い適切なタイミングで送付する必要があります。本記事では、納品書をいつ送るのか、どのように送付するのか、そして送付時には何に注意すべきかを詳しく解説します。
無料【クラウド請求書作成ソフト「Misoca」がよくわかる資料】をダウンロードする
納品書の送付方法
納品書の送付方法には、以下の4つの方法があります。
- 郵送する
- 納品物と一緒に送る
- FAXで送る
- PDFにしてメールで送る
それぞれ詳しく見ていきましょう。
郵送する
納品書は信書に該当します。したがって、商品を納品後に日本郵便のサービスを利用して郵送するのが一般的です。日本郵便で信書が送れるサービスとしての主な方法は、以下の4つです。
- 第一種郵便
- 第二種郵便
- レターパック
- スマートレター
信書である納品書は通常の宅配便で送付することはできません。ただし、宅配業者の中には特定信書便事業者として信書を取り扱っている業者もあります。特定信書便事業者かどうかは、各宅配業者のウェブサイトや、以下の総務省のウェブサイトから確認できますので活用しましょう。
参照:総務省|信書便事業者一覧
納品物と一緒に送る
納品書は、無封の封筒やクリアファイルに収めて納品物と一緒に宅配で送ります。これにより、手軽に送付できますが、くれぐれも郵便法違反にならないように注意が必要です。
納品物に同梱する際の注意点
納品書は信書に該当するため、原則として納品物と一緒に宅配で送ることはできません。しかし、郵便法第4条第3項ただし書には以下の記載があります。
「ただし、貨物に添付する無封の添え状又は送り状は、この限りでない。」
引用:e-Gov|郵便法
これにより、無封の状態の納品書を納品物と一緒に送ることは許されています。総務省の見解によると、「無封の状態」とは以下のような状態を指します。
Q7 添え状・送り状の「無封」とはどういう状態のことですか?
「無封」とは、(1)封筒等に納めていない状態 (2)封筒等に納めて納入口を閉じていない状態 のことをいいます。また、封筒等に納めて納入口を閉じている場合であっても、(3)当該封筒等が透明であり容易に内容物を透視することができる状態 (4)当該封筒等の納入口付近に「開閉自由」等の表示(※)をするなど、運送営業者等が内容物の確認のために任意に開閉しても差し支えない状態であることが一見して判別できるようにしてある状態 も「無封」に含まれます。
※表示の例
- 「開閉自由」
- 「添え状・送り状につき開封可」
- 「添え状 ※本状は、郵便法により(内容を確認するため)開封する場合がございますので、予めご了承ください。」
(百貨店等でお客様がお持ちになった封をした添え状を贈答品に添付して送付する場合の表示例)
引用:総務省|信書に該当する文書に関する指針
FAXで送る
取引先がFAXで送付することを許可している場合は、FAXで送ることも可能です。事前に確認をして、送る直前に電話で連絡をすることで、より丁寧で確実な対応となります。
注意点として、誤送信にならぬよう十分に注意しなければなりません。電話番号とFAX番号が異なることは多いため、正しいFAX番号を確認してから送信するようにしましょう。また、納品物が届く前に送信しないように納品日の確認は忘れずに行いましょう。
さらに、取引先から納品書の原本を依頼される場合もあります。取引先の要望に対応できるように、原本は大切に保管しましょう。
PDFをメールで送る
納品書をPDFに変換して、メールに添付して送信することも可能です。件名に【納品書添付】などと記載し、メール本文に添付されている旨を記載することで、取引先が明確になり見落としが防げます。
注意点としてはPDFがきちんと開けるかを送付前に確認することです。また、メール送信時にPDFの添付を忘れることがよくあるため、メールの内容と併せて必ず事前に確認してください。
メール添付についてはこちらの記事で解説していますので、参考にしてください。
【1年間無料】フリーランスの見積・請求・申告は「Misoca×やよいの青色申告 オンライン」セットがお得!
納品書を送るタイミング
納品書の役割は注文どおりに商品を納めた事実を示すことです。したがって、取引先が納品書と照らし合わせながら納品物を確認できるように送付することが基本です。
納品書の送付は、納品物と同時か、納品後すぐに送付することが望ましいとされています。納品書のみを先に、単独で送付すると取引先が混乱しかねません。また、納品が完了してから時間が経過してしまうと、納品物と納品書を照らし合わせることが難しくなります。送る際には、早すぎることも遅すぎることもしないように心がけてください。
【1年間無料】フリーランスの見積・請求・申告は「Misoca×やよいの青色申告 オンライン」セットがお得!
納品書を送る際のポイント
納品書を送る際のポイントは、以下の4つです。
- 納品書は宅配便では送れない
- 納品書を送付する場合には送付状を付ける
- 長形3号の封筒に三つ折りで送る
- 納品書の誤記載は訂正ではなく再発行で対応する
それぞれ詳しく見ていきましょう。
納品書は宅配便では送れない
信書便法第2条第1項および郵便法第4条第2項によれば、「信書」とは「特定の受取人に対し、差出人の意思を表示し、又は事実を通知する文書」を指します。
引用:e-Gov|郵便法
納品書は、日本郵便のウェブサイトに例示されているとおり信書に該当します。
原則として、信書の送付手段は日本郵便に限られているため、宅配便で信書である納品書を送ることはできません。
納品書には送付状を付ける
送付状には、取引先へのあいさつと、納品書などの同封した書類を確認するための役割があります。納品書に送付状を付けることは慣例となっており、ビジネスマナーに反していると受け取られないためにも必ず付けるようにしましょう。
送付状に記載する基本の項目は以下のとおりです。
- 日付・宛先・差出人情報
- 表題:「書類送付のお知らせ」「納品書のご送付について」と記載
- 本文:頭語・あいさつ文・本文・結語の順番で記載
- 記書き:「記」と書いて、改行してから「納品書 一通」といった同封する書類の内容を記載
- 「以上」の文言
送付状の作成はテンプレートを参考にするのがおすすめです。以下の記事も参考にしてください。
長形3号の封筒に三つ折りで送る
納品書はA4サイズの用紙で作成するのが一般的です。そして、A4サイズの用紙を入れるために長形3号封筒が用いられ、納品書を三つ折りして入れるのがビジネスマナーです。
三つ折りの際、まず下から三分の一を折り畳み、次に上から三分の一を折り畳みます。こうすることで、開封した時に「納品書」の文字が真っ先に見え、取引先にとってわかりやすくなります。
納品書の誤記載は訂正ではなく再発行で対応する
記載されている商品が異なっていたり、数量や金額がズレているといったミスは起こりがちです。こうした誤記載があったとしても、納品書は法的な文書ではないため再発行の義務は課されません。
しかしながら、取引先との関係は今後も続きます。納品書を訂正するよりも再発行することで、丁寧な印象を与え、円滑な取引関係の維持が可能です。したがって、誤記載が発覚したら、すぐに取引先に連絡をしてお詫びした後に納品書を再発行しましょう。
封筒には「納品書在中」と記入する
納品書を入れる長形3号の封筒などに、「納品書在中」と記入することで、取引先が送付物の内容を一目で判断でき、郵便の仕分けも楽になります。義務ではないものの、ビジネスにおけるマナーとして記入するようにしましょう。
記入場所は、縦書きの場合なら表面の左下、横書きの場合なら表面の右下が基本の位置となります。百円ショップなどでは「納品書在中」と彫られたスタンプも売っているため、活用するのも1つの手段です。
【1年間無料】フリーランスの見積・請求・申告は「Misoca×やよいの青色申告 オンライン」セットがお得!
納品書の正しい送付方法を理解しましょう
納品書の送付方法として、郵送、納品物と一緒に送る、FAXで送る、PDFをメールで送る4つの方法を紹介しました。郵送する際には送付状を添え、「納品書在中」と記載された長形3号の封筒に三つ折りにして送付してください。いずれの方法でも、取引先に事前に確認し、商品の納品後に送付することが大切です。
納品書の作成・送付を効率的に行うには、弥生のクラウド請求書サービス「Misoca」が役立ちます。納品書のテンプレートも用意されており、簡単に・素早く・きれいな納品書が作成可能です。ぜひご検討ください。
【1年間無料】フリーランスの見積・請求・申告は「Misoca×やよいの青色申告 オンライン」セットがお得!
クラウド見積・納品・請求書サービスなら、請求業務をラクにできる
クラウド請求書作成ソフトを使うことで、毎月発生する請求業務をラクにできます。
今すぐに始められて、初心者でも簡単に使えるクラウド見積・納品・請求書サービス「Misoca」の主な機能をご紹介します。
「Misoca」は月10枚までの請求書作成ならずっと無料、月11枚以上の請求書作成の有償プランも1年間0円で使用できるため、気軽にお試しすることができます。
見積書・納品書・請求書をテンプレートでキレイに作成

Misocaは見積書 ・納品書・請求書・領収書・検収書の作成が可能です。取引先・品目・税率などをテンプレートの入力フォームに記入・選択するだけで、かんたんにキレイな帳票ができます。
各種帳票の変換・請求書の自動作成で入力の手間を削減

見積書から納品書・請求書への変換や、請求書から領収書・検収書の作成もクリック操作でスムーズにできます。固定の取引は、請求書の自動作成・自動メール機能を使えば、作成から送付までの手間を省くことが可能です。
インボイス制度(発行・保存)・電子帳簿保存法に対応だから”あんしん”

Misocaは、インボイス制度に必要な適格請求書の発行に対応しています。さらに発行した請求書は「スマート証憑管理」との連携で、インボイス制度・電子帳簿保存法の要件を満たす形で電子保存・管理することが可能です。
確定申告ソフトとの連携で請求業務から記帳までを効率化

Misocaで作成した請求書データは、弥生の確定申告ソフト「やよいの青色申告 オンライン」に連携することが可能です。請求データを申告ソフトへ自動取込・自動仕訳できるため、取引データの2重入力や入力ミスを削減し、効率的な業務を実現できます。
会計業務はもちろん、請求書発行、経費精算、証憑管理業務もできる!
法人向けクラウド会計ソフト「弥生会計 Next」では、請求書作成ソフト・経費精算ソフト・証憑管理ソフトがセットで利用できます。自動的にデータが連携されるため、バックオフィス業務を幅広く効率化できます。

「弥生会計 Next」で、会計業務を「できるだけやりたくないもの」から「事業を成長させるうえで欠かせないもの」へ。まずは、「弥生会計 Next」をぜひお試しください。
無料【クラウド請求書作成ソフト「Misoca」がよくわかる資料】をダウンロードする
この記事の監修者市川 裕子(ビジネスマナー監修)
マナーアドバイザー上級、秘書検定1級、ビジネス実務マナー、硬筆書写検定3級、毛筆書写検定2級、収納アドバイザー1級、など。 出版社や人材サービス会社での業務を経験。秘書業務経験よりビジネスマナーとコミュニケーションの重要性に着目し、資格・スキルを活かし、ビジネスマナーをはじめとする各種マナー研修や収納アドバイザー講師として活動。










