領収書と領収証の違いは?レシートや預かり証との違いも解説
監修者: 高崎文秀(税理士)
更新
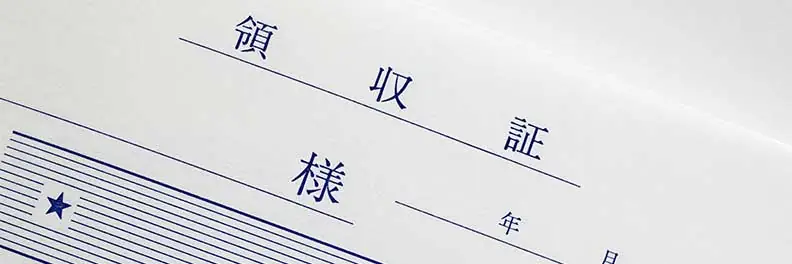
領収書と領収証の違いや、どちらを使うべきかお悩みの方に向けて、領収書と領収証の違いを中心に、レシートや預かり証の違い、インボイスに対応するための注意点などを解説します。また、領収書や領収証をもらう意味についても取り上げています。これらの文書の役割を知り、適切に作成・使用しましょう。
領収書と領収証の違い
領収書について、国税庁のウェブサイトでは、「金銭または有価証券の受取書」に当たる旨の記載があります。他方、領収証もまた、「レシート」や「預り書」、「受取書」などと共に、金銭または有価証券の受取書に該当するとされています。つまり、両者はほぼ同じものと捉えて差し支えありません。経理上も区別は不要です。
ただ、国税庁のウェブサイトでは証拠書類の大枠として「領収書」を用い、その中の1つに「領収証」が含まれるといった記載がなされています。あえて言えば、この点が両者の違いです。
出典:国税庁「No.7105 金銭又は有価証券の受取書、領収書」
一般的にはどのように使い分けられている?
領収書は、金銭などの支払いがあったことを示す書類として使われています。一般的には、民間で発行されるレシートなどの総称です。領収証は、金銭の取引・授受があったことを示す証書で、公的機関や金融機関が発行するものを指します。
領収書・領収証とレシートの違い
領収書・領収証とレシートの違いは、宛名と明細があるかどうかです。通常、レシートには宛名の記載がなく、他方で明細は記載されます。
レシートを領収書として扱う際の注意点
レシートを領収証代わりとして扱う場合、少なくとも以下の項目が記載されていなければなりません。
- 発行者(住所および氏名)
- 発行の日付
- 商品・サービス名
- 取引の内容
- 金額
店舗によっては、取引の内容などが記載されていない場合があります。レシートに必要記載項目が欠けているのであれば、領収書をもらいましょう。
領収書・領収証と預かり証の違い
預かり証とは、物品や金銭などを預かる形で受け取ったときに、受け取った側が発行する書類です。ただし、預かり証と呼ばれる書類には、いくつかの種類があります。
- 後日に領収書を発行する予定で、金銭を受け取ったときに仮の領収書として発行
- 前金や手付金など、代金の一部を受け取ったときに発行
- 支払いとしてではなく、保管を目的として物品や金銭を受け取ったときに発行
預かり証が領収書・領収証と違う点は、所有権の移転を示すか否かです。預かり証が示すのは物品や金銭などを預かった事実であり、それらの所有権は受け取った側には移っていません。その一方で、領収書は支払いが行われたときに発行されるため、購入物の所有権が購入者側へ移ったことを示します。
領収書や領収証は求められたら発行する義務がある
領収書・領収証の発行について、民法第486条第1項には以下の規定があります。
弁済をする者は、弁済と引換えに、弁済を受領する者に対して受取証書の交付を請求することができる。
引用:e-Gov「民法」
弁済とは「支払い」を指します。受取証書は領収書と同様の書類です。つまり、本条が規定するのは「支払い時には、領収書を請求できる」ということです。これにより、支払いを受けた者は、領収書を請求された場合に発行義務があると解されます。
なお、領収書の再発行については、拒否することも可能です。これは支払いと領収書の発行が同時履行の関係(民法第533条)にあるからで、二重の支払いや水増し請求などの予防という意味もあります。また、同時履行関係にあることの帰結として、代金を支払う際に領収書が発行されない場合、購入者は代金の支払いを拒否できます。
出典:e-Gov「民法」
領収書・領収証に記載すべき項目
領収書・領収証は、以下の項目と書き方を守って書きましょう。
- 文書名
- 文書の上部の中央もしくは左側に、「領収書(もしくは領収証)」と記載します。
- 取引の日付
- 発行した日付ではなく、実際の取引(支払い)がなされた日付です。
- 宛名
- 取引をした個人または企業・店舗名を記載します。(株)など省略した表記も可能ですが、正式名称で記載する方が適切です。
- 取引金額
- 後から金額を書き換えられるといった不正を防止するため、以下の書き方を守りましょう。
- 金額の最初に「¥」または「金」を書く
- 3桁ごとにコンマ(,)を書く
- 最後に「-」または「也」を書く
- 空白を作らない
- はっきり読めるよう書く
例:¥1,000円- - ただし書き
- 「〇〇代として」と記載し、購入した内容がわかる記載をしましょう。
- 金額の内訳(税込・税抜)
- 領収書を取引の証拠書類として扱うケースにおいて、軽減税率(8%)と標準税率(10%)の適用商品がある場合は、商品を税率ごとに分けて記載します。
- 発行者情報
- 発行者の名前(個人事業主は個人名や屋号、企業は社名)、住所、電話番号を記載します。
このほか、取引金額が50,000円以上であれば、収入印紙も貼る必要があります。
適格請求書(インボイス)として発行する場合の注意点
領収書を適格請求書(以下「インボイス」)として発行したい場合には、記載する内容に注意しましょう。インボイスでは、要件を満たした領収書でなければ仕入税額控除ができず、仕入れに要した消費税分を消費税額から控除することができません。
インボイス形式の領収書にするには、以下の項目が必要です。
適格請求書
-
①適格請求書発行事業者の氏名又は名称及び登録番号
-
②取引年月日
-
③取引内容(軽減税率の対象品目である旨)
-
④税率ごとに区分して合計した対価の額
(税抜き又は税込み)及び適用税率 -
⑤税率ごとに区分した消費税額等
-
⑥書類の交付を受ける事業者の氏名又は名称
適格簡易請求書
-
①適格請求書発行事業者の氏名又は名称及び登録番号
-
②取引年月日
-
③取引内容(軽減税率の対象品目である旨)
-
④税率ごとに区分して合計した対価の額
(税抜き又は税込み) -
⑤税率ごとに区分した消費税額等又は適用税率
引用:国税庁「適格請求書等保存方式の概要(p.5)」
領収書や領収証を授受するメリット
領収書や領収証は、不正防止や税務調査における支払いの証明に役立つため、必ず授受しましょう。
過払いや二重請求を防止できる
領収書がないと、支払いをした事実を証明するのは難しくなります。そのため、支払いを受けた側が「支払われていない」と主張して、再度請求することがないとはいえません。領収書や領収証があれば、そうしたトラブルが防げます。また、領収書は代金の受け取りと同時に発行するため、二重請求のミスも予防できます。
内部不正を防止できる
領収書・領収証がないと、お金を使っていないのに使ったと虚偽の計上を行う架空請求もできてしまいます。また、実際使った額よりも高い額を請求することで、差額の着服も可能です。領収書・領収証は、社内の不正を防止する意味もあります。
経費として計上できる
領収書・領収証があれば、使ったお金を経費として計上可能です。レシートの他、請求書、クレジットカードの利用明細なども領収書の代わりになります。もし領収書を紛失しても、購入日時、金額、購入したもの、購入した企業・店舗など、取引内容のメモを残し、それを元に出金伝票を作成するといった対処をすれば、経費として認められる場合があります。
領収書と領収証はどちらも正しい!でも記載事項には注意しよう
領収書と領収証の関係について、国税庁では領収書の一種を領収証としており、両者の役割に違いはありません。よって、領収書・領収証どちらの名称も正しいことになります。
経費として計上するため領収書・領収証を作成するのであれば、クラウド請求書作成ソフト「Misoca」をおすすめします。必要事項を入力するだけで作成でき、取引先を登録すると自動で領収書作成時に反映されるといったメリットもあります。すばやく正確に領収書を作成したい方は、ぜひ「Misoca」の導入を検討してください。
クラウド見積・納品・請求書サービスなら、請求業務をラクにできる
クラウド請求書作成ソフトを使うことで、毎月発生する請求業務をラクにできます。
今すぐに始められて、初心者でも簡単に使えるクラウド見積・納品・請求書サービス「Misoca」の主な機能をご紹介します。
「Misoca」は月10枚までの請求書作成ならずっと無料、月11枚以上の請求書作成の有償プランも1年間0円で使用できるため、気軽にお試しすることができます。
見積書・納品書・請求書をテンプレートでキレイに作成

Misocaは見積書 ・納品書・請求書・領収書・検収書の作成が可能です。取引先・品目・税率などをテンプレートの入力フォームに記入・選択するだけで、かんたんにキレイな帳票ができます。
各種帳票の変換・請求書の自動作成で入力の手間を削減

見積書から納品書・請求書への変換や、請求書から領収書・検収書の作成もクリック操作でスムーズにできます。固定の取引は、請求書の自動作成・自動メール機能を使えば、作成から送付までの手間を省くことが可能です。
インボイス制度(発行・保存)・電子帳簿保存法に対応だから”あんしん”

Misocaは、インボイス制度に必要な適格請求書の発行に対応しています。さらに発行した請求書は「スマート証憑管理」との連携で、インボイス制度・電子帳簿保存法の要件を満たす形で電子保存・管理することが可能です。
確定申告ソフトとの連携で請求業務から記帳までを効率化

Misocaで作成した請求書データは、弥生の確定申告ソフト「やよいの青色申告 オンライン」に連携することが可能です。請求データを申告ソフトへ自動取込・自動仕訳できるため、取引データの2重入力や入力ミスを削減し、効率的な業務を実現できます。
会計業務はもちろん、請求書発行、経費精算、証憑管理業務もできる!
法人向けクラウド会計ソフト「弥生会計 Next」では、請求書作成ソフト・経費精算ソフト・証憑管理ソフトがセットで利用できます。自動的にデータが連携されるため、バックオフィス業務を幅広く効率化できます。

「弥生会計 Next」で、会計業務を「できるだけやりたくないもの」から「事業を成長させるうえで欠かせないもの」へ。まずは、「弥生会計 Next」をぜひお試しください。
この記事の監修者高崎文秀(税理士)
高崎文秀税理士事務所 代表税理士/株式会社マネーリンク 代表取締役
早稲田大学理工学部応用化学科卒
都内税理士事務所に税理士として勤務し、さまざまな規模の法人・個人のお客様を幅広く担当。2019年に独立開業し、現在は法人・個人事業者の税務顧問・節税サポート、個人の税務相談・サポート、企業買収支援、税務記事の監修など幅広く活動中。また通常の税理士業務の他、一般社団法人CSVOICE協会の認定経営支援責任者として、業績に悩む顧問先の経営改善を積極的に行っている。











