住民税申告とは?申告方法や必要な方、不要な方を解説
監修者: 齋藤一生(税理士)
更新
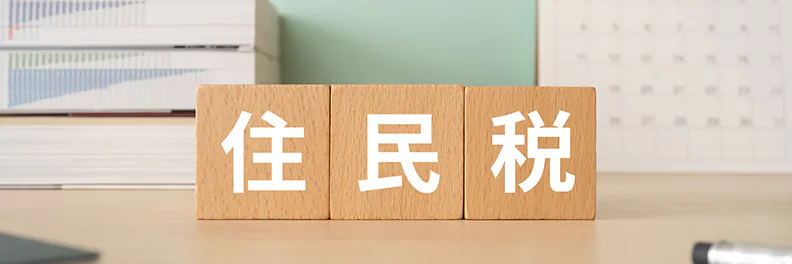
日本国内に住んでいる方は、前年の所得額に応じた住民税を自治体に納めなければなりません。もっとも、住民税申告をしなければならない方はそれほど多くありません。では、どのような方に住民税申告が必要になるのでしょうか。
ここでは、住民税申告を行わなければならない方と必要がない方の違いや、住民税申告の仕方について解説します。
日付や金額などを入力するだけで、確定申告に必要な帳簿や申告書類が完成します
初年度無料ですべての機能が使用できます。
e-Taxも製品から直接できるので、自宅からかんたんに確定申告が可能です

住民税申告とは、都道府県民税・区市町村民税といった住民税の納税額を申告すること
住民税申告とは、都道府県民税・区市町村民税といった住民税の納税額を申告することです。なお、住民税には、法人が支払う法人住民税と個人が支払う個人住民税がありますが、本記事では個人住民税について解説します。
住民税は、住所地の自治体に対して納める地方税です。都道府県に納める都道府県民税と、市区町村に納める市区町村民税をまとめて納税します。
納税額は、住民税を納付する年の前年1月1日から12月31日までの所得に応じて決まります。そのため、所得金額を自治体に申告する必要があるのです。
はじめての確定申告もかんたん!無料から使える弥生のクラウド申告ソフト
基本的に年末調整や確定申告をすれば住民税申告は不要
勤務先で年末調整を受けた方や、確定申告をした方については、その結果が住所地の自治体に共有されるため、基本的には住民税の申告をする必要がありません。
年末調整や確定申告は、年間の所得金額と所得税額を明らかにし、正しく納税するために行います。このデータが自治体と共有されることで、自治体は住民の年間所得金額を把握し、所得金額に応じた住民税額を算出できるようになります。
なお、年末調整や確定申告は所得税に関する手続きで、所得税は国に納める国税です。一方、住民税は自治体に納める地方税です。所得税と住民税には、以下のような違いがあります
所得税と住民税の主な違い
| 違いが生じる項目 | 所得税 | 住民税 |
|---|---|---|
| 税金の種類 | 国税 | 地方税 |
| 申告書の様式 | 確定申告書(給与所得のみの場合に年末調整している場合には所得税も住民税も申告不要)※ | 住民税申告書(年末調整や確定申告をしていれば提出不要)※ |
| 申告書の提出先 | 所轄の税務署 | 住所地の自治体の市区町村役場 |
| 税額の計算を行う主体 | 納税者自ら計算(年末調整を受ける場合は勤務先が計算) | 自治体が計算 |
| 納付時期 | 所得のあった年の確定申告期限(通常は翌年3月15日、土日祝日の場合は翌平日)までに納付 | 所得のあった翌年6月以降に納付 |
| 税率 | 所得金額に応じて税額が変わる累進課税 | 一律 |
| 均等割(納税者全員が同額を負担する税金) | なし | あり |
- ※給与所得のみで、年末調整している場合には所得税も住民税も申告不要
確定申告については以下の記事で詳しく解説していますので参考にしてください。
はじめての確定申告もかんたん!無料から使える弥生のクラウド申告ソフト
住民税申告が必要な方の具体例
1円以上の所得があり、なおかつ年末調整や確定申告を受けていない方は、基本的に住民税の申告が必要です。具体的には、以下のような方が該当します。
主な住民税申告が必要な方
- 所得税の確定申告を行わない方のうち、1円以上の所得がある方
- 給与所得があったが、退職などの理由により年末調整を受けていない方
- 年末調整を受けていない副業収入があるが、20万円以下で確定申告をしない方
- 住民税の減免制度の適用を受ける方
例えば「副業で日雇いバイトをしていて、収入の年間合計金額が10万円だった」といった会社員の場合は、副業の確定申告をする必要はありません。しかし、住民税の申告は必要です。
また、生活保護を受けている場合や災害によって生活が困難になった場合などで住民税の減免制度の適用を受けたい方は、確定申告や年末調整の有無にかかわらず、住民税の申告を行いましょう。
なお、上記はあくまでも一般的なケースです。住民税は地方税に該当するため、自治体ごとに細かい規定が異なっている可能性もあります。住民税の申告が必要かどうか詳しく知りたい場合は、お住まいの自治体に確認してください。
はじめての確定申告もかんたん!無料から使える弥生のクラウド申告ソフト
住民税申告が不要な方の具体例
年間の所得金額を税務署に申告した方は、住民税申告をする必要がありません。具体的には、自ら確定申告をした方や、勤務先で年末調整を受けた方などが該当します。ただし、勤務先で年末調整を受けた方のうち、副業収入がある方は住民税の申告をしなければならない可能性があります。
住民税申告が不要な方の具体例は以下のとおりです。ただし、以下はあくまでも一般例であるため、詳細はお住まいの自治体で確認してください。
主な住民税申告が不要な方
- 所得税の確定申告を行った方
- 勤務先で年末調整をした方
- 所得が公的年金のみで、申告によって適用される控除がない方
なお、退職金にかかる住民税については、勤務先が事前に計算して退職金から天引きすることになっています。そのため、退職所得に関する住民税の申告は不要です。
はじめての確定申告もかんたん!無料から使える弥生のクラウド申告ソフト
住民税申告の期限と提出方法
住民税申告の期限は、例年3月15日までです。土日祝日に期限日が重なった場合は、翌平日が期限日になります。2025年3月15日は土曜日であるため、2024年分の所得に関する住民税申告の期限は2025年3月17日でした。
住民税申告の提出方法は、自治体ごとに定められています。自治体窓口への持ち込み、郵送、eLTAXによる電子申告などの方法が考えられますが、詳細は自治体の窓口やWebサイトなどで確認しましょう。
万が一期限を過ぎてしまった場合は、速やかにお住まいの自治体に連絡してください。申告が遅れると翌年の住民税の算出に間に合わないおそれがあるため、早めに準備を進めることをおすすめします。
はじめての確定申告もかんたん!無料から使える弥生のクラウド申告ソフト
住民税申告の必要書類
住民税申告をする際は、申告書類と添付書類を用意しなければいけません。住民税申告に必要な書類を以下にまとめました。なお、必要な書類の種類は申告内容などによって異なります。不安がある方は、お住まいの自治体窓口で相談してください。
住民税申告書
住民税申告には、住民税の申告書の提出が必要です。住民税申告書は、自治体のWebサイトや窓口で入手できます。自治体によって書式が異なるため、必ずお住まいの自治体の申告書を用意しましょう。
自宅にプリンターがない方は、自治体窓口で配布されている申告書を使うのが便利です。書き方の案内や手引きなども併せて用意されているのが一般的であるため、まとめて入手しておくことをおすすめします。
所得を証明する書類
住民税申告では、所得を証明する書類も添付しなければなりません。所得を証明する書類は、所得の種類によってさまざまです。以下で例を紹介します。なお、副業所得がある方などは、収入がわかる書類と経費がわかる書類を用意しておきましょう。
所得を証明する書類の例
| 納税者の区分 | 書類の例 |
|---|---|
| 個人事業主 | 収支内訳書など |
| 給与所得者(退職者を含む) | 給与所得の源泉徴収票、給与明細書など |
| 年金受給者 | 公的年金等の源泉徴収票 |
各種控除に関する証明書
住民税申告では、確定申告と同様に所得控除や税額控除などの適用を受けることができますが、そのためには各種控除に関する証明書が必要です。控除の対象となる方は、以下のような証明書を用意しておきましょう。なお、住民税で利用できる控除は以下の制度だけではないため、状況に応じて必要書類をそろえてください。
主な控除に関する証明書の例
| 控除の種類 | 書類の例 |
|---|---|
| 生命保険料控除 | 民間の生命保険会社から送られてくる生命保険料控除証明書 |
| 医療費控除 | 年間の医療費を取りまとめた医療費控除の明細書 |
| 寄附金控除 | 寄附をした先から交付される寄附金受領証明書など |
| 社会保険料控除 | 社会保険料(国民年金保険料)控除証明書など(国民健康保険料の納入済額通知書については、必要かどうかは自治体によって異なる) |
本人確認書類
住民税申告では、本人確認書類も必要になります。本人確認書類は、以下のいずれかを用意してください。
用意が必要な本人確認書類
- マイナンバーカード
- マイナンバーがわかる住民票などの書類と運転免許証などの身分証明書類
マイナンバーカードを所持している方は、マイナンバーカードの写しを本人確認書類として利用できます。それ以外の方は、マイナンバーがわかる書類と身分証明書類をそれぞれ用意しなければいけません。
はじめての確定申告もかんたん!無料から使える弥生のクラウド申告ソフト
住民税の申告・納税の手順
住民税の申告と納税の手順は、以下のとおりです。期限日直前に慌てることがないように、手順を確認したうえで早めに準備を進めましょう。
1. 住民税申告書と必要書類の準備
最初に、住民税申告書と必要書類を準備します。住民税申告書の書式は自治体によって異なるため、お住まいの自治体の申告書を用意してください。記載方法や記載例についても、自治体のWebサイトで確認できる場合があります。
記載例などを見ても書き方に迷ったときや、記載方法の説明などが見つからない場合は、市区町村役場の市民税課や税務課などで相談しましょう。
2. 住民税申告書と必要書類の提出
住民税申告書と必要書類を準備したら、期限内に提出を行います。提出方法は、窓口への持ち込み、郵送、eLTAXなどですが、自治体によって特定の方法が推奨されている場合もあります。どのように提出すべきかは、各自治体のWebサイトなどで確認しましょう。
推奨されている提出方法がわからない場合や、申告方法などについて不安がある場合は、自治体の窓口で相談するのが確実です。
3. 住民税の納税
住民税の納税は、普通徴収または特別徴収といった方法で行います。基本的に、給与所得と公的年金等に係る所得の住民税は特別徴収となり、それ以外の所得は特別徴収か普通徴収を選択して納税することになります。
普通徴収は、住民税の納税者が自分で住民税を納める方法です。毎年6月に、申告内容に応じて算出された住民税額の通知書と納付書が自宅に届きます。納付書を近隣の金融機関や市区町村役場、コンビニなどに持参して税金を納付しましょう。
口座振替を受け付けている自治体もあるため、希望する方は確認してみてください。普通徴収では、住民税額を6月、8月、10月、翌年1月の4回に分けて納付できますが、一括で納付することも可能です。
特別徴収は、給与からの天引きで住民税を納税する方法です。住民税の総額を、所得のあった年の翌年6月から翌々年5月までの12か月で分割して支払います。給与から天引きされた住民税は、勤務先の企業が本人に代わって自治体に納税します。
企業には、従業員の住民税を特別徴収する義務があるため、給与所得者は原則として特別徴収で住民税を納付します。ただし、給与所得以外の副業所得があって確定申告を行う場合は、副業に関する住民税のみ普通徴収で納めることも可能です。
はじめての確定申告もかんたん!無料から使える弥生のクラウド申告ソフト
住民税の申告期限に間に合わなかった場合のペナルティ
住民税の申告を期限内に行えず、結果として住民税の納付が遅れた場合は、延滞金を支払わなければならない可能性があります。具体的に延滞金が発生する条件や延滞金の利率は、自治体によって異なります。「申告が遅れてしまい、延滞金が発生するか確認したい」といった方は、市区町村役場で確認してください。
なお、所得税の確定申告を忘れた場合も、結果として住民税の申告漏れにつながる可能性があります。所得税の確定申告をしなければならない方が申告を行わず、所得税と住民税の延滞につながった場合は、それぞれの税金に対する延滞税と延滞金を課せられるおそれがあるため、注意しましょう。
はじめての確定申告もかんたん!無料から使える弥生のクラウド申告ソフト
住民税申告が必要かどうかを確認して、早めに申告を行おう
所得税の確定申告をしていない方は、住民税申告が必要になる可能性があります。住民税申告が必要かどうかを確認して、早めに対処しましょう。
確定申告を行えば住民税の申告は必要ないため、所得が一定額以下でも確定申告をしておくというのも住民税申告を省略する1つの方法です。特に個人事業主は、確定申告を継続して行うことで所得金額の証明にもなり、青色申告の場合は赤字を繰り越すこともできます。
「やよいの青色申告 オンライン」や「やよいの白色申告 オンライン」を利用すれば、確定申告を手間なくスムーズに進めることが可能です。所得金額の計算や確定申告書への転記も自動で行えるため、計算ミスや転記ミスの心配もありません。e-Taxにも対応しているため、ぜひご活用ください。
はじめての確定申告もかんたん!無料から使える弥生のクラウド申告ソフト
確定申告ソフトなら、簿記や会計の知識がなくても確定申告が可能
確定申告ソフトを使うことで、簿記や会計の知識がなくても確定申告ができます。
今すぐに始められて、初心者でも簡単に使える弥生のクラウド確定申告ソフト「やよいの白色申告 オンライン」とクラウド青色申告ソフト「やよいの青色申告 オンライン」から主な機能をご紹介します。
「やよいの白色申告 オンライン」は、ずっと無料、「やよいの青色申告 オンライン」は初年度無料です。両製品とも無料期間中もすべての機能が使用できますので、気軽にお試しいただけます。もちろん、確定申告やe-Taxでの申告が可能です!
【損してない?】青色申告でいくら安くなる?売上・経費を入れて今すぐ比較!
初心者にもわかりやすいシンプルなデザイン

弥生のクラウド確定申告ソフトは、初心者にもわかりやすいシンプルなデザインで、迷うことなく操作できます。日付や金額などを入力するだけで、確定申告に必要な帳簿や必要書類が作成できます。
取引データは自動取込&AIの自動仕訳で入力の手間を大幅に削減!

弥生のクラウド確定申告ソフトは、銀行・クレジットカードなどの金融機関の明細や電子マネー、POSレジ、請求書、経費精算等のサービスと連携すると日々の取り引きデータを自動で取得します。
自動取得した取引データはAIが自動で仕訳して帳簿に反映します。学習機能があるので、使えば使うほど仕訳の精度がアップします。紙のレシートは、スマホやスキャンで取り込めば、文字を認識してデータに変換し、自動で仕訳します。これにより入力の手間と時間が大幅に削減できます。
確定申告書類を自動作成。e-Tax対応で最大65万円の青色申告特別控除もスムーズに

弥生のクラウド確定申告ソフトは、画面の案内に沿って入力していくだけで、収支内訳書や青色申告決算書、所得税の確定申告書、消費税の確定申告書等の提出用書類が自動作成されます。
「やよいの青色申告 オンライン」なら、青色申告特別控除の最高65万円/55万円の要件を満たした資料の用意も簡単です。インターネットを使って直接申告するe-Tax(電子申告)にも対応し、最大65万円の青色申告特別控除もスムーズに受けられます。
自動集計されるレポートで経営状態がリアルタイムに把握できる

弥生のクラウド確定申告ソフトに日々の取引データを入力しておくだけで、レポートが自動で集計されます。経営状況やお金の流れをリアルタイムで確認できます。最新の経営状況を正確に把握することで、早めの判断ができるようになります。











