アルバイトを掛け持ちしている場合の確定申告はどうする?必要なケース・やり方を解説
監修者: 奥 典久(奥典久税理士事務所)
更新
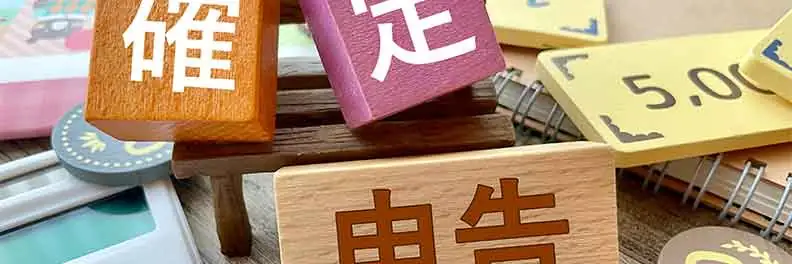
アルバイトを複数掛け持ちしている場合、「確定申告が必要なのか?」と疑問を持つ方は少なくありません。アルバイト先が1社のみであれば、年末調整で対応できますが、複数のアルバイト先がある場合や副業が一定の金額を超える場合は、確定申告が必要になることがあります。
本記事では、確定申告が必要となる具体的なケースや、正しい申告方法について詳しく解説します。また、適切な申告をしなかった場合のペナルティについても紹介しています。本記事を読むことで、確定申告に関する不安や疑問を解消し、適切な納税ができるようになります。
アルバイトを掛け持ちしている場合は基本的に確定申告が必要
2社以上のアルバイトを掛け持ちしている場合、原則として所得税の確定申告が必要です。これは、年末調整が1社でしか行えないためです。通常、年末調整は給与支払額が多いアルバイト先に「扶養控除等(異動)申告書」を提出することで行われます。しかし、アルバイトを複数掛け持ちしている場合、他のアルバイト先の収入はその年末調整に反映されません。そのため、すべてのアルバイト収入を合算し、正しい所得税と住民税を計算するために、確定申告を行う必要があります。
次に、確定申告と年末調整の違いについて詳しく解説します。
確定申告と年末調整の違い
確定申告と年末調整は、どちらも税金に関する手続きですが、仕組みや対象者に違いがあります。
所得税の確定申告とは、1年間の収入から経費や控除を差し引いた所得を自分で申告し、その内容に基づいて納税額を決定する制度です。主な対象は個人事業主やフリーランスです。また、複数のアルバイトを掛け持ちしている場合や、給与所得者でも副収入がある場合には、確定申告が必要です。
一方、年末調整とは、従業員の所得が確定した時点で正しい納税額を勤務先が算出し、これまでの源泉徴収額と実際の税額を比較し、過不足分を従業員に還付したり、追加徴収したりすることです。対象は主に会社員などの給与所得者です。所得の申告や納税を自身の代わりに勤務先がしてくれるため、確定申告は必要ありません。そして、年末調整は扶養控除等(異動)申告書を提出したメインの勤務先1社でのみ行われます。
ただし、医療費控除など年末調整で対応できない控除を受ける場合は、別途で確定申告を行う必要があります。
無料で【確定申告の流れがわかる手順と確定申告ソフトの活用方法】をダウンロードする
アルバイト収入にかかる税金の種類
アルバイトで得た収入にも、給与所得者と同様に税金がかかります。以下では、アルバイト収入にかかる所得税と住民税について詳しく解説します。
所得税
所得税とは、個人が1年間に得たすべての所得に対して課される税金です。1月1日から12月31日までの1年間に得た収入から、各種所得控除を差し引いた金額に基づいて、所得税が計算されます。税率は累進課税方式で、所得が増えるほど高くなり、最大で45%です。特にアルバイトで年収が103万円を超えた場合、所得税が発生します。これは、給与所得控除額55万円と基礎控除額48万円を合わせた103万円を超える収入に対して、所得税が課される仕組みゆえです。
所得税についての詳細は、以下の記事をご覧ください。
住民税
住民税は、居住している地方自治体に納める地方税であり、地方公共サービスを支える財源となっています。住民税の計算は「均等割」と「所得割」の2つで構成されています。均等割は、収入に関係なく一律に課税される部分です。一方、所得割は、前年の1月1日から12月31日までの1年間に得た収入から経費などを差し引いた所得に対して課され、税率は10%です。なお、住民税の場合、給与所得控除額は55万円、基礎控除額は43万円となっており、年収が98万円を超えた場合に住民税が発生します。
住民税についての詳細は、以下の記事をご覧ください。
無料で【確定申告の流れがわかる手順と確定申告ソフトの活用方法】をダウンロードする
アルバイトを掛け持ちしている人で確定申告が必要なケース
アルバイトを複数掛け持ちしていて、合計収入が103万円を超えた場合、確定申告が必要になる場合があります。以下では、確定申告が必要な具体的なケースについて、詳しく解説します。
アルバイトを掛け持ちしており、1か所のみで年末調整が行われている
2か所以上から給与を受け取っていて、そのうち1か所のアルバイト先が年末調整を行っている場合、確定申告が求められます。
年末調整は通常、扶養控除等(異動)申告書を提出した給与支払額が最も多いアルバイト先で行われます。しかし、他のアルバイト先から得た収入は、この年末調整に反映されていません。そのため、税金を正確に納めるためには、すべてのアルバイト先から得た収入の合計額から正しい所得税と住民税を計算し、確定申告を行う必要があります。
アルバイトを掛け持ちしており、2か所以上で年末調整が行われている
複数のアルバイト先で年末調整を受けている場合でも、確定申告が必要です。
通常、1か所のアルバイト先でしか年末調整を行わないのが原則です。しかし、誤って複数のアルバイト先に扶養控除等(異動)申告書を提出し、2か所以上で年末調整を受けることがあるかもしれません。この場合、控除が重複して適用され、正しい税額が計算されていない可能性があります。こうした場合は、所得税の過不足を調整するために確定申告が必要です。特に、基礎控除や給与所得控除が重複適用されると、納税不足が生じ、延滞税や無申告加算税といったペナルティを受ける可能性もあるため、確定申告を必ず行いましょう。
どのアルバイト先でも年末調整をしていない
掛け持ちしているアルバイトの合計収入が103万円を超え、どのアルバイト先でも年末調整を受けていない場合、確定申告が必要です。アルバイト先が収入の全体を把握していないため、最終的にすべての収入を合算し、確定申告を通じて正しい所得税を計算する必要があります。
また、年末調整前にアルバイトを辞めてしまった場合も同様です。年末調整は、基本的に12月31日時点で在籍している従業員に対して行われます。そのため、年内にアルバイトを辞めていると、年末調整を受けられません。その際は、退職時に発行される「源泉徴収票」を基に確定申告を行います。なお、年収が103万円以下で、源泉徴収された金額がなければ確定申告は不要です。
年末調整前にアルバイトを辞め、年内に別のアルバイト先に転職し、12月31日まで勤務している場合、新しいアルバイト先に前のアルバイト先の源泉徴収票を提出することで、年末調整を1か所でまとめて行うことが可能です。この場合、原則として確定申告は必要ありません。
メインのアルバイト以外での副業所得が20万円を超えている
アルバイト以外に副業をしており、その所得が年間20万円を超える場合も確定申告が必要です。例えば、アルバイトの給与とは別に副業で得た収入があり、その収入から必要経費を差し引いた所得が20万円を超えている場合が該当します。一方、収入が20万円を超えていても、経費を差し引いた後の所得が20万円以下の場合、確定申告は不要です。副業を複数している場合は、すべての所得を合算し、20万円を超えるかどうかで判断してください。
無料で【確定申告の流れがわかる手順と確定申告ソフトの活用方法】をダウンロードする
アルバイトを掛け持ちしている学生の場合は、確定申告が不要なケースもある
アルバイトを掛け持ちしている学生でも、勤労学生控除の対象で、年収が130万円を超えなければ、確定申告をする必要はありません。勤労学生控除とは、一定の要件を満たすことで適用され、27万円の所得控除を受けることが可能です。
出典:国税庁「No.1175 勤労学生控除」
勤労学生控除の要件などについての詳細は、以下の記事をご覧ください。
無料で【確定申告の流れがわかる手順と確定申告ソフトの活用方法】をダウンロードする
アルバイトを掛け持ちしている場合の確定申告のやり方
適切に税金を申告するために、確定申告の流れを押さえておくことが大切です。以下では、確定申告に必要な具体的な手順を紹介します。
1. 確定申告のスケジュールを確認する
まず確定申告をスムーズに進めるためには、スケジュールの確認と計画的な準備が必要です。確定申告は、前年1月1日から12月31日までの収入を基に行い、書類の提出期限が決められています。したがって、収入があった年の翌年1月から2月中旬までに必要書類を集め、申告準備を整えましょう。
そして、確定申告の提出期間は、原則として収入があった年の翌年2月16日から3月15日までです。ただし、それぞれの日付が土曜・日曜・祝日にあたる場合、翌日(または翌々日)の月曜日になります。2025年の場合(2024年分の確定申告について)、2月16日は日曜日、3月15日は土曜日となります。そのため、確定申告の提出期間は2025年2月17日から2025年3月17日までです。また、書類の提出期限だけでなく、税金の納付期限も同じく3月15日(2025年は3月17日)までとなりますので、スケジュールに余裕を持って行動してください。
2. 必要書類を集める
確定申告を行うためには、以下の書類を準備する必要があります。
- 確定申告書:国税庁のウェブサイトや税務署で入手可能です。また、確定申告の補助ソフトを使用する場合は、ソフト内でフォーマットを自動生成してくれます。
- マイナンバーカード:確定申告の際にマイナンバーを確認する番号確認書類と身元確認書類が必要ですが、マイナンバーカードはその両方を満たします。
- 源泉徴収票:内容を転記するのに必要な場合、勤務先から受け取りましょう。
- 控除証明書:生命保険料控除など、各種控除を受ける場合、控除証明書を用意してください。
- 銀行の口座情報:確定申告後に還付金の振込先となるため、忘れずに用意してください。
3. 確定申告書類を作成する
次に、確定申告書に必要事項を記入して書類を作成します。基本的には、アルバイト先から発行された源泉徴収票に記載されている情報を転記する形になります。源泉徴収票には、1年間に支払われた給与の合計額である「支払金額」や、「給与所得控除後の金額」などが記載されています。
確定申告書には「第一表」と「第二表」があるため、すべてに漏れなく記入してください。なお、源泉徴収票は申告書を作成する際に必要ですが、税務署に提出する際には添付する必要はありません。
4. 確定申告書類を提出する
確定申告の提出方法には、主に3つの方法があります。
まず、e-Taxを利用する方法です。国税庁の「確定申告書等作成コーナー」で確定申告書を作成し、オンラインで提出できます。この方法で作成する場合、マイナンバーカードと、マイナンバーカードの読み取りに対応したスマートフォンまたはICカードリーダが必要です。手続きに必要な利用者識別番号を持っていない場合、「利用者情報の登録」にて登録作業を行いましょう。
次に、郵便または信書便を利用して、所轄の税務署や業務センターへ送付する方法です。この場合、確定申告書は「信書」に該当するため、第一種郵便物または信書便物として送付してください。
最後に、所轄の税務署に直接持参する方法です。時間外の場合は、税務署の収受箱への投函も可能です。業務センターに直接持参することはできないので注意してください。
必ず期限である3月15日(2025年は3月17日)までに提出してください。
確定申告書の作成などについてさらに詳しく知りたい方は、以下の記事を参考にしてください。
無料で【確定申告の流れがわかる手順と確定申告ソフトの活用方法】をダウンロードする
確定申告が必要なケースでしないとどうなる?
確定申告が必要にもかかわらず、期限内に申告をしない場合、税務署から指摘が入る可能性があります。税務署は、アルバイト先から送られる源泉徴収票や各種データを通じて個々の収入を把握しており、未申告の収入も追跡できます。申告を怠ると、ペナルティが発生するため、確定申告が必要な人は期限内に申告を済ませることが重要です。以下では、主なペナルティについて詳しく解説します。
延滞税が課せられる
所得税を本来の期限までに納付しなかった場合、延滞税が課せられます。延滞税とは、納めるべき税金を納付期限までに支払わなかった場合に発生する追加の税金です。延滞税の税率は複雑な計算方法に基づいており、最高で年14.6%となる場合があります。延滞税は納税が遅れた日数に応じて課されるため、申告や納税を怠ると、その負担は次第に大きくなります。特に長期間の遅延は大きな負担となるため、早めの対応が必要です。
延滞税については、以下の記事も参考にしてください。
参照:国税庁「延滞税の計算方法」
無申告加算税が課せられる
確定申告が必要にもかかわらず、期限内に申告をしなかった場合には、無申告加算税が課されます。無申告加算税は、納めるべき税金に対して50万円までは15%、50万円を超える部分には20%が加算される仕組みです。ただし、申告期限を過ぎた場合でも、税務署の調査の通知前に申告を行えば、この加算率が5%に軽減されます。
さらに、法定申告期限より1カ月以内に期限後申告をした場合や、期限内に申告する意思があったことが認められる一定の場合において、無申告加算税が課されない場合もあります。
過少申告加算税が課せられる
確定申告で申告・納付した税額が、実際に納めるべき金額より少なかった場合、過少申告加算税が課されます。ただし、税務署からの調査通知を受ける前に自主的に修正申告を行った場合は、過少申告加算税が課されることはありません。そのため、申告した税額が少ないことに気づいた場合は、なるべく早く修正申告を行うことが重要です。
過少申告加算税の税率は、差額として新たに納める金額の10%です。しかし、追加で納める税額が当初の申告額または50万円を超える場合、その超えた部分については15%の税率が適用されます。
重加算税が課せられる
重加算税とは、納めるべき税金を意図的に隠蔽したり、仮装したりといった不正手段を用いた場合に課される、非常に重いペナルティです。たとえ期限内に確定申告をしていたとしても、虚偽の内容で申告した場合には重加算税が課される可能性があります。
重加算税の税率は、過少申告の場合に本来納めるべき税額の35%が加算されます。無申告の場合には40%が加算されます。さらに、過去5年以内に無申告加算税や重加算税を課された経験がある場合、追加で10%が加算されます。加えて、これらの不正が発覚すると、刑事事件に発展する可能性もあるため、必ず適正な申告を行いましょう。
無料で【確定申告の流れがわかる手順と確定申告ソフトの活用方法】をダウンロードする
アルバイト収入の確定申告は正しく行おう
アルバイトを複数掛け持ちしている場合は、すべてのアルバイト収入を合算して確定申告を行う必要があります。確定申告の手順としては、まず申告期限を確認し、必要な書類をそろえ、申告書類を作成することが重要です。適切な申告が行われない場合、ペナルティが発生するため、正しい手続きを踏み、適切な納税を心がけましょう。
確定申告に慣れていない方で、事業所得としての所得がある方には、確定申告ソフトの利用をおすすめします。特に「やよいの白色申告 オンライン」や「やよいの青色申告 オンライン」は、シンプルなレイアウトで操作が分かりやすく、素早く申告を完了させられます。ぜひご活用ください。
無料で【確定申告の流れがわかる手順と確定申告ソフトの活用方法】をダウンロードする
確定申告ソフトなら、簿記や会計の知識がなくても確定申告が可能
確定申告ソフトを使うことで、簿記や会計の知識がなくても確定申告ができます。
今すぐに始められて、初心者でも簡単に使える弥生のクラウド確定申告ソフト「やよいの白色申告 オンライン」とクラウド青色申告ソフト「やよいの青色申告 オンライン」から主な機能をご紹介します。
「やよいの白色申告 オンライン」は、ずっと無料、「やよいの青色申告 オンライン」は初年度無料です。両製品とも無料期間中もすべての機能が使用できますので、気軽にお試しいただけます。もちろん、確定申告もe-Taxでの申告が可能です!
【無料・税額シミュレーター】売上と経費を入力して青色と白色の税額を比較してみよう!
初心者にもわかりやすいシンプルなデザイン

弥生のクラウド確定申告ソフトは、初心者にもわかりやすいシンプルなデザインで、迷うことなく操作できます。日付や金額などを入力するだけで、確定申告に必要な帳簿や必要書類が作成できます。
取引データの自動取込・自動仕訳で入力の手間を大幅に削減

弥生のクラウド確定申告ソフトは、銀行・クレジットカードなどの金融機関の明細や電子マネー、POSレジ、請求書、経費精算等のサービスと連携すると日々の取り引きデータを自動で取得します。
自動取得した取引データはAIが自動で仕訳して帳簿に反映します。学習機能があるので、使えば使うほど仕訳の精度がアップします。紙のレシートは、スマホやスキャンで取り込めば、文字を認識してデータに変換し、自動で仕訳します。これにより入力の手間と時間が大幅に削減できます。
確定申告書類を自動作成。e-Tax対応で最大65万円の青色申告特別控除もスムーズに

弥生のクラウド確定申告ソフトは、画面の案内に沿って入力していくだけで、収支内訳書や青色申告決算書、所得税の確定申告書、消費税の確定申告書等の提出用書類が自動作成されます。
「やよいの青色申告 オンライン」なら、青色申告特別控除の最高65万円/55万円の要件を満たした資料の用意も簡単です。インターネットを使って直接申告するe-Tax(電子申告)にも対応し、最大65万円の青色申告特別控除もスムーズに受けられます。
自動集計されるレポートで経営状態がリアルタイムに把握できる

弥生のクラウド確定申告ソフトに日々の取引データを入力しておくだけで、レポートが自動で集計されます。経営状況やお金の流れをリアルタイムで確認できます。最新の経営状況を正確に把握することで、早めの判断ができるようになります。
無料お役立ち資料【「弥生のクラウド確定申告ソフト」がよくわかる資料】をダウンロードする
この記事の監修者奥 典久(奥典久税理士事務所)
奥典久税理士事務所 代表
簿記専門学校で税理士講座講師として勤めたのち、会計事務所で勤務。その後独立し、奥典久税理士事務所を開業。相続(贈与)対策や事業承継コンサルティング経営、財務コンサルティングから各種セミナーなど、幅広く税理士業務に従事。










