【どちらがいい?】合同会社と個人事業主の違いを8項目で比較|設立するデメリットは?
監修者: 高崎 文秀(税理士)
更新
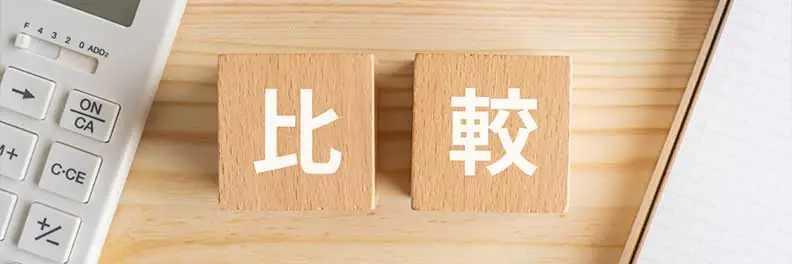
会社設立を検討していると、「合同会社」と「個人事業主」、どちらを選択すべきか迷うこともあるでしょう。両者にメリットとデメリットがあるため、自分に合った選択ができるか不安を感じている方もいるかもしれません。適切な判断をするには、事業の現状や将来の目標を整理し、まずは合同会社と個人事業主の違いを理解することが重要です。
本記事では、合同会社と個人事業主の違いを8項目で比較し、設立するメリット・デメリットを解説します。法人に切り替える判断基準も紹介するので、個人事業主から会社設立を検討している方は、ぜひご活用ください。
法人設立ワンストップサービスを利用して、オンラインで登記申請も可能。
個人事業主から法人成りを予定している方にもおすすめです。

【無料】はじめてでもカンタン・安心な「会社設立」の書類作成はこちらをクリック
合同会社と個人事業主の基礎知識
事業の形態を選ぶ際、合同会社と個人事業主のどちらと相性がよいか判断するには、両者の概要をよく理解することが重要です。
合同会社
合同会社とは、日本の会社形態の1つです。特徴は出資者と経営者が同一人物であることで、社員全員が有限責任(出資額以上の責任を負わない制度のこと)を負います。有限責任の制度により、万が一事業が失敗しても、個人の資産が保護される利点があります。
また合同会社は株式会社よりも設立費用がかからず、簡易な手続きで法人化できる点も魅力です。その他にも、経営の自由度が高い、節税しやすいなどさまざまなメリットがあります。詳しくは後述の「合同会社と個人事業主の違いを8項目で比較」をご覧ください。
個人事業主
個人事業主は、法人格を持たず、個人で事業を行う経営形態です。設立が簡単で、合同会社のように設立費用がかかりません。税務署に開業届を提出するだけで事業が開始できます。
その設立の手軽さから、初めて事業を行う方や、エステやパーソナルジム、フリーランスエンジニアなど個人規模の事業をスタートしたい方に選ばれやすい傾向があります。ただし、税金面や経営の柔軟性に限界があります。自由度には魅力がありますが、節税や法人取引のように事業拡大を考えている場合は少し物足りなく感じるかもしれません。
【無料】はじめてでもカンタン・安心な「会社設立」の書類作成はこちらをクリック
合同会社と個人事業主の違いを8項目で比較
合同会社と個人事業主の違いを8項目で比較しました。
- 開業にかかるコスト
- 適用される税率
- 資金の管理方法
- 経費の範囲
- 社会保険の加入義務
- 赤字の繰越期間
- 社会的な信用
- 責任の範囲
開業にかかるコスト
- 個人事業主:基本的に、開業にかかるコストはほとんどありません。手続きの手間はあるものの、税務署に開業届を提出するだけで事業をスタートできます。
- 合同会社:合同会社の設立には約6万円以上のコストがかかります。合同会社の設立費用の内訳は、登記費用や定款作成費用、印紙代などが該当します。
事業開始当初で資金が限られている場合、個人事業主を選択する人が多いかもしれません。設立のコストと今後の事業展望を照らし合わせた判断が必要です。
合同会社の設立費用についてこちらの記事で解説しています。
適用される税率
- 個人事業主:個人事業主は所得税の累進課税に基づいて課税されます。例えば、所得が195万円以下の場合、税率5%が適用されます。所得が400万円を超えると税率は20%、さらに695万円を超えると税率は23%になります。
- 合同会社:合同会社は法人税が適用されます。法人税の税率は原則として23.2%です。ただし、2025/3/31設立までの中小法人は、課税所得が800万円以下の場合、15%(※)(800万円超は23.2%)が適用されます。
- ※2025年1月31日時点の情報です。
そのため、 課税所得が700万円の場合、合同会社であれば15%の法人税が適用されるため、個人事業主よりも税負担を抑えられます。また、合同会社では役員報酬に対して給与所得控除(最大195万円)を適用できるため、より税金を抑えることができます。ただし個人事業主も青色申告で要件等を満たしていれば青色申告特別控除で最大65万円の控除が利用できる利点があります。
資金の管理方法
- 個人事業主:事業の収入を自由に使えるため、納税分を差引いた収入を自分の生活費などに使うことができます。
- 合同会社:会社の収入と個人の収入を明確に分ける必要があります。
個人事業主は、事業の収入と個人の資金を分けて管理する必要がありません。その一方で合同会社では、事業の収入と個人の収入を明確に区分する必要があります。個人の収入は役員報酬として受け取る分です。個人で使うお金がなくなったとしても、原則として個人事業主のように会社のお金を自由に引き出すことができません。
経費の範囲
- 個人事業主:事業に必要な支出であれば経費として認められます。
- 合同会社は、経費に計上できる項目が広く、税金面で大きな節税効果があります。
例えば合同会社の場合、会社の経費としてオフィスの家賃や、社員の給与、社用車の維持費、福利厚生費などが経費として認められます。その一方で、個人事業主は経費の範囲が限られており、自宅をオフィス扱いにしても、一般的には2〜3割ほどしか経費になりません。合同会社として法人化して社宅として契約できた場合は、家賃の大半を経費として計上できます。
社会保険の加入義務
- 個人事業主:基本的に個人事業主は社会保険への加入義務はありません。ただし常時5人以上の従業員を雇用する場合は、原則として社会保険への加入手続きが必要です。(一部業種は除く)
- 合同会社:社員数に関係なく、経営者本人も社会保険に加入する義務があります。
当然ながら一人社長の場合でも例外ではなく、社会保険に加入しない場合は、罰則が課されるケースもあります。ただし役員報酬が0円の場合、社会保険に加入する必要はありません。役員報酬を0円にする際はデメリットもあるため注意が必要です。
赤字の繰越期間
- 個人事業主:青色申告を行うことで、赤字を最大3年間繰り越すことができます。
- 合同会社:合同会社は、最大10年間の赤字繰越が認められています。
例えば、合同会社を設立して事業スタートから数年間赤字が続いた場合、翌年以降の定められた期間までに発生した黒字と相殺でき、納税額を抑えられます。個人事業主も、翌年以降に黒字を出しても赤字と相殺できるため、納税額を抑えることが可能です。
社会的な信用
- 個人事業主:個人事業主は、本名や住所などの公開義務がありません。そのため社会的信用が低くなる傾向があります。
- 合同会社:法人化する場合、社名・住所・資本金などの情報を法務局に提出して登記する必要があります。
登記により社会的信用が高まるため、個人事業では取引できないような企業との契約が実現できる可能性が上がります。特に大手企業とも契約を締結できるようになるため、事業の拡大も実現しやすくなります。
責任の範囲
- 個人事業主:個人事業主は無限責任を負い、事業のために借金を負った場合、債務整理をしない限り返済の義務が発生します。
- 合同会社:合同会社では、有限責任が適用されるので、出資金を超える責任は問われません。
例えば個人事業の飲食店が失敗して、多額の借金を負った場合、個人の住宅や預金も差し押さえられるリスクがあります。合同会社では、経営がうまくいかず負債を抱えて倒産した場合でも、有限責任の制度により、差押など経済的なリスクが軽減されます。
【無料】はじめてでもカンタン・安心な「会社設立」の書類作成はこちらをクリック
個人事業主が合同会社を設立するメリット
合同会社を設立することによって、次のようなメリットがあります。
- 節税対策しやすい
- 株式会社と比較して手続きがしやすく費用を抑えられる
節税対策しやすい
合同会社を設立した場合、大きな節税効果が期待できます。例えば控除を活用するケースの場合、合同会社では役員報酬による最大195万円の給与所得控除が追加で利用できます。
しかし、個人事業主は青色申告特別控除で最大65万円の控除と、合同会社と比較して控除できる額が少なくなります。また、法人の課税所得800万円以下には法人税率15%が適用され、個人事業主よりも税率を低く抑えられます。課税所得が700万円の場合、個人事業主の税率は23%ですが、合同会社では軽減税率の適用により、大幅に節税効果が期待できるでしょう。合同会社で節税対策した分は、翌年の販促費や採用コストに投下するなど、会社の成長に資金を投下できるようになります。
株式会社と比較して手続きがしやすく費用を抑えられる
合同会社の利点は、株式会社よりも手続きがしやすく、費用を抑えられる点です。株式会社の手続きに必要な定款認証手続きが必要ありません。また合同会社の設立費用は6万円から、株式会社の設立費用は22万円からと大きな違いがあります。合同会社であれば設立コストも安く抑えられるため、創業初期で資金力がないスタートアップなどにおすすめです。
合同会社設立についてこちらの記事で解説しています。
【無料】はじめてでもカンタン・安心な「会社設立」の書類作成はこちらをクリック
個人事業主が合同会社を設立するデメリット
合同会社を設立するには以下のデメリットもあります。
- 資本金を用意する必要がある
- 株式会社に比べて社会的な信用度が低い傾向にある
資本金を用意する必要がある
資本金を用意する必要がある点は、人によってはデメリットとなるかもしれません。特に資金が少ないスタートアップの場合、資本金は悩みのタネとなるでしょう。
法律上、合同会社の資本金は1円でも設立可能ですが、円滑な経営を行うために十分な額を準備することをおすすめします。目安は、家賃や光熱費、人件費などの経営活動にかかる費用の数ヶ月分です。これだけ用意しておくと、突発的な支出やトラブルが起きた際に、余裕をもって対策できます。
合同会社の資本金についてこちらの記事で解説しています。
社会的な信用度が低い傾向にある
個人事業主と比較して、合同会社の信用度は高い傾向にあります。しかし株式会社と比べると、社会的な信用の観点で劣る傾向にあります。そのため特定の金融機関(大手銀行など)や、ファンドからの資金調達の幅が狭くなったり、上場できなかったり、さまざまな制限があります。上場や数億規模の事業拡大を目指す経営者にとっては大きなデメリットとなるため、合同会社の設立を検討する際は注意するようにしましょう。
合同会社の役員についてこちらの記事で解説しています。
【無料】はじめてでもカンタン・安心な「会社設立」の書類作成はこちらをクリック
【どちらがいい?】個人事業主から合同会社に切り替える判断基準
個人事業主から合同会社への切り替えは、いくつかのタイミングを考慮することが重要です。
従業員を雇用したいタイミング
従業員を雇用する予定がある場合、合同会社の設立を検討するのが理想的です。前述のとおり、合同会社を設立すると社会保険への加入義務が発生し、健康保険や厚生年金の福利厚生を従業員に提供します。この福利厚生が求職者からの安心感を高めて、優秀な人材の確保につながります。
実際に自分が求職者の立場でも、社会保険の福利厚生がある法人のほうが安心でき、魅力的に映るでしょう。従業員の雇用を見据えたタイミングでの法人化は、事業の成長に大きく貢献します。
個人事業主の課税所得が695万円を超えたタイミング
個人事業主の課税所得が695万円を超えると、所得税率が23%に引き上げられ、税金の負担が重くのしかかります。経費で695万円以下に抑えて、節税効果をねらっている個人事業主もいるでしょう。しかし節税に限界がきて、課税所得が695万円を超えるときこそが、合同会社に移行する絶好のタイミングです。
例えば、個人事業の年間売上が1,000万円で経費が300万円の場合のケースです。このケースだと、課税所得は700万円となり、個人事業主では約23%の税率が適用されます。しかし合同会社では15%の法人税率が適用されるうえに、役員報酬を設定して給与所得控除の適用により、さらに節税効果をより高めることができます。節税対策は今後の経営活動で必要となる項目の1つです。早めに対策しておくことで、安定した経営を図れます。
事業を拡大するタイミング
事業を拡大するタイミングは、個人事業主が合同会社に切り替える1つの判断基準となるでしょう。
会社の成長のために取引先を増やしたい場合、収入に関わらず合同会社の設立が有効な選択肢となります。前述でも軽く触れたとおり、法人同士でしか契約できない企業が存在するためです。特にコンプライアンスなど、ルールが厳格に決まっている大企業にこのような取り決めが多い傾向にあります。法人化して大企業を取引先にできた場合、大きな実績を獲得できた流れで続々と取引先を獲得できるかもしれません。
法人の設立のコストはかかるものの、取引先の増加により売上が増加すれば、設立費用や運営コストを考慮してもプラスに転換するでしょう。
【無料】はじめてでもカンタン・安心な「会社設立」の書類作成はこちらをクリック
個人事業主が合同会社を兼任するときの注意点
個人事業と合同会社が同じ事業を運営している場合、事業実態がないペーパーカンパニーとみなされないようにしなければなりません。税務調査が入った際に、意図的に所得を分散させていると判断された場合、一体の事業とみなされて追徴課税を課される可能性があるからです。そのため、個人事業と合同会社は別々の事業を行っていることが前提となります。例えば、個人事業ではインターネットサービス業を、合同会社では不動産業を運営するなど、異業種で事業を展開するようにしましょう。
また、申告業務も個人事業主と合同会社で分けて処理する必要がある点にも、注意が必要です。事務的な負担は増えますが、安全に個人事業主と合同会社を兼任するために、欠かせないことといえます。
【無料】はじめてでもカンタン・安心な「会社設立」の書類作成はこちらをクリック
個人事業主と合同会社と株式会社で迷った場合は?
個人事業主、合同会社、株式会社のいずれかの形態で迷った場合、どれを選択するべきか、今後の事業の目的や規模によって異なります。
| 個人事業主 | 初めて事業を行う場合や、エステサロンやパーソナルトレーニングジム、Web系フリーランスなど、小規模なビジネスを展開する場合に最適 |
|---|---|
| 合同会社 | 資金力は少ないものの、法人との取引の獲得や社会的な信用度の向上を図りたい場合に最適 |
| 株式会社 | 大規模な出資を受ける場合、数億、数十億円単位の事業拡大をねらう場合、上場を目指す場合に最適 |
どの経営形態にするか判断できない場合は、専門家に相談するのも1つの方法です。
会社形態の選び方についてこちらの記事で解説しています。
【無料】はじめてでもカンタン・安心な「会社設立」の書類作成はこちらをクリック
個人事業主から合同会社の切り替えは専門家に相談を
本記事では、合同会社と個人事業主の違いや、切り替えのタイミングを解説しました。合同会社と個人事業主にはさまざまな違いがあります。開業コストには大きな差があり、合同会社を設立すると社会保険への加入義務も発生します。まずは合同会社の理解を深めて、今後の事業にどの経営形態がマッチしているか確認するところから始めてみましょう。
専門家へ相談したい場合は、「弥生のかんたん会社設立」をご活用ください。弥生が提携する専門家をご紹介いたします。「弥生のかんたん会社設立」では、専門知識がなくてもかんたんに会社設立手続を行うことができます。無料で使えるので、ご自身で会社設立を行いたい方に最適です。
【無料】はじめてでもカンタン・安心な「会社設立」の書類作成はこちらをクリック
この記事の監修者高崎 文秀(税理士)
高崎文秀税理士事務所 代表税理士/株式会社マネーリンク 代表取締役。早稲田大学理工学部応用化学科卒。
都内税理士事務所に税理士として勤務し、さまざまな規模の法人・個人のお客様を幅広く担当。2019年に独立開業。現在は法人・個人事業者の税務顧問・節税サポート、個人の税務相談・サポート、企業買収支援、税務記事の監修など幅広く活動中。また一般社団法人CSVOICE協会の認定経営支援責任者として、業績に悩む顧問先の経営改善を積極的に行う。









