出勤簿とは?保存期間・必要事項・書き方・注意点などを解説
更新
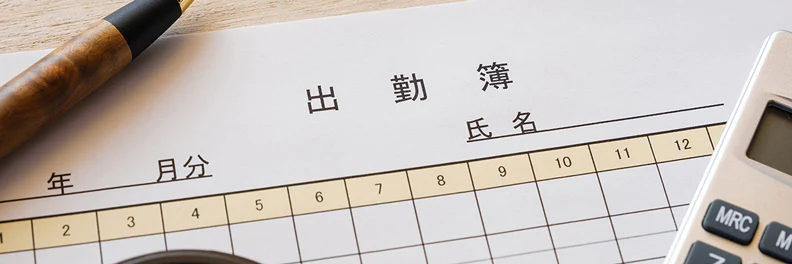
出勤簿とは、労働者の労働日数や労働時間を正確に把握するための帳簿です。給与計算においても欠かせない重要な帳簿であり、従業員を雇用した際には必ず作成し、一定期間保存する義務があります。出勤簿には、始業・終業時刻、労働時間、休憩時間などの情報を記載することが必要です。
本記事では、出勤簿の役割や記載すべき内容、保存期間について詳しく解説します。勤怠管理の基礎知識として、正確な出勤簿の作成と管理方法を学びましょう。
【最大3か月無料でお試し】弥生のクラウド給与ソフトで大幅コスト削減
今ならAmazonギフトカード半額相当がもらえる「弥生給与 Next」スタート応援キャンペーン実施中!

無料お役立ち資料【「弥生給与 Next」がよくわかる資料】をダウンロードする
出勤簿とは労働基準法の法定三帳簿の1つ
出勤簿とは法定三帳簿の1つであり、労働者の労働日数や出退勤時間が記録された書類です。労働基準法には出勤簿の作成に関しての明確な規定はありません。ただし、厚生労働省のガイドラインでは次のように記載されています。
使用者は、労働者名簿、賃金台帳のみならず、出勤簿やタイムカード等の労働時間の記録に関する書類について、労働基準法第109条に基づき、3年間保存しなければならないこと。
引用:厚生労働省「労働時間の適正な把握のために使用者が講ずべき措置に関するガイドライン
」
このように出勤簿は法律で定められた重要な書類であり、企業は出勤簿を作成し保存しなければなりません。
出勤簿の保存期間
出勤簿は、法律によって一定期間の保存が義務付けられています。保存期間は2020年4月の労働基準法改正によって、3年から5年に延長されました。労働基準法109条では、次のとおり定められています。
使用者は、労働者名簿、賃金台帳及び雇入れ、解雇、災害補償、賃金その他労働関係に関する重要な書類を五年間保存しなければならない。
引用: e-Gov 法令検索「労働基準法
」
ただし、当面の間は経過措置として保存期間を3年間とすることが、同第143条で規定されています。
第百九条の規定の適用については、当分の間、同条中「五年間」とあるのは、「三年間」とする。
引用:e-Gov 法令検索「労働基準法
」
保存期間の起算日は、当該従業員が最後に出勤した日です。例えば、2020年11月末日まで従業員が出勤していた場合、その出勤簿は原則2025年11月末日まで(現在は、経過措置として2023年11月末日まで)保存しなければなりません。ただし、最後に記載された出勤日より賃金支払期日が遅い場合には、賃金支払期日が起算日です。
なお、税務上、賃金台帳が源泉徴収簿を兼ねている場合には、7年間保管しなければなりません。もし出勤簿の保管を怠った場合、労働基準法違反となり30万円以下の罰金の対象となります。たとえ故意ではなくても、破棄や紛失をしないようにしっかり管理しましょう。
出勤簿の記載対象者
出勤簿の対象は、基本的にはすべての従業員です。正社員、パートタイム、アルバイトなどの雇用形態にかかわらず、従業員全員の勤務状況を記録する必要があります。
なお、労働基準法の「管理監督者」に該当する管理職に関しても、2019年4月に改正労働基準法や改正労働安全衛生法が施行され、労働時間を把握することが義務化されました。そのため、管理監督者についても安全衛生管理などの面から出勤簿に記載し、労働時間を管理しなければなりません。
管理監督者とは、労働条件の決定などにおいて、経営者と一体的な地位や権限を付与されている人のことを指します。管理監督者に該当するか否かは、役職名ではなく、権限や職務内容、賃金などから総合的に判断されます。管理職だから管理監督者であるとは限りません。管理監督者についての詳細は、厚生労働省の「管理監督者の範囲の適正化」で確認できます。
参照:厚生労働省「管理監督者の範囲の適正化」
管理監督者への残業代支給などについて、こちらの記事で解説しています。
出勤簿とタイムカードの違い
タイムカードは、出退勤時刻を記録し、労働時間を把握するためのツールとして活用されています。ただし、打刻忘れが発生すると正確な記録ができない場合があるため、近年では、所定時間を登録し、時間外労働や休日出勤を把握できる機能を備えたものもあります。
その一方で、出勤簿は、労働時間の記録だけでなく、出勤状況を総合的に管理する目的で活用されています。出退勤時刻の記録に加え、時間外労働や休日出勤の管理が可能なものもありますが、出勤状況のみを把握するものも存在します。ただし、労働基準法においては「労働時間の適正な把握」が求められており、企業は適切な管理を行う必要があります。
企業は実態に応じて、出勤簿やタイムカードを適切に活用し、法令に基づいた運用を行うことが重要です。
出勤簿と賃金台帳の違い
賃金台帳は、法定三帳簿の1つであり、賃金の支払いに関する事項を記載するための重要な台帳です。この台帳には、賃金計算期間、労働時間、基本給、賃金の種類ごとの金額などが詳細に記載されます。しかし、出勤簿と異なり、賃金台帳には出退勤の時間は記載されません。
その一方で、出勤簿は労働者の出退勤時間を記録するための帳簿であり、労働時間の管理や給与計算の基礎資料として使用されます。
賃金台帳が主に賃金の支払いに関連する情報を管理するものであるのに対し、出勤簿は出勤状況を記録するという点で、役割が異なります。
【最大3か月無料でお試し】弥生のクラウド給与ソフトで大幅コスト削減
出勤簿の必要事項と書き方
出勤簿に記載しなければならない事項について、法的な規定があるわけではありません。ただし出勤状況を適正に管理するために記載すべき項目があります。一般的には労働者の氏名以外にも以下の項目を記載します。
出勤日および労働日数、日別の労働時間数と始業・終業時刻、休憩時間
従業員の労働時間を正確に把握するためには、出勤簿に以下の項目を記載することが重要です。
- 出勤日および労働日数
- 日別の労働時間数
- 始業・終業時刻
- 休憩時間
これらの情報は、賃金を正しく算定するために必要な項目です。特に始業時刻や終業時刻は1分単位で管理します。これらの項目を適切に管理し、従業員の労働時間を確実に把握することが企業には求められます。また、年次有給休暇や特別休暇などの休暇取得状況の管理は企業により異なります。出勤簿に併記している企業も、別に管理している企業もあります。
時間外労働を行った日付・時刻・時間数
時間外労働を行った日付や時刻、時間数を記載します。時間外労働には、以下の時間が含まれます。
- 企業が定めた所定労働時間を超過して働いた時間
- 労働基準法で定められた法定労働時間を超過して働いた時間
労働基準法では、労働時間の上限を「1日8時間・週40時間」と定めています。原則として、企業はこの上限を超えて従業員を働かせることはできません。法定労働時間を超えて時間外労働をさせる場合には、36協定(労働基準法36条によって求められる労使協定)の締結・届出が必要です。労使による36協定を締結し、届け出ることで、協定の定める時間まで規制が解除され、時間外労働も可能となります。これを「免罰効果」または「免罰的効力」といいます。
ただし、法定労働時間を超える労働には、割増賃金を支払わなければなりません。
時間外労働と割増賃金について、こちらの記事で解説しています。
休日労働(休日出勤)を行った日付・時刻・時間数
休日労働(休日出勤)を行った日付や時刻、時間数を記載します。休日には、労働基準法によって「週に1回または4週間で4回」と規定されている「法定休日」と、法定休日の他に会社が任意で定める「所定休日」の2種類があります。休日労働に関しては、法定休日、所定休日それぞれについて記載しなければいけません。
深夜労働を行った日付・時刻・時間数
深夜労働を行った日付や時刻、時間数を記載します。深夜労働とは、労働基準法において例外の場合を除き、午後10時から午前5時までの労働を指します。従業員が深夜労働を行った場合、割増賃金を支払わなくてはなりません。
深夜労働と割増賃金について、こちらの記事で解説しています。
月60時間超の法定時間外労働時間数
「月60時間超の法定時間外労働時間数」とは、労働基準法で定められた労働時間(1日8時間、1週間40時間)を超える労働時間のうち、月60時間を超えた部分の時間数のことです。出勤簿には、この労働時間も記載します。
2023年4月1日から施行された改正労働基準法では、月60時間を超える法定時間外労働に対する割増賃金率が大企業・中小企業ともに50%に引き上げられました。企業はこの時間数も正確に把握し、適切な割増賃金を支払う必要があります。
参照:厚生労働省「2023年4月1日から月60時間を超える時間外労働の 割増賃金率が引き上げられます」
【最大3か月無料でお試し】弥生のクラウド給与ソフトで大幅コスト削減
出勤簿で押さえておきたい注意点
手書きの出勤簿やハンコを押しただけの出勤簿は、適切な出勤簿として認められないため注意が必要です。また、出勤簿の記載および計算で端数処理をする場合、労働時間の切り捨ては原則として認められないため注意しましょう。ただし、一部例外があります。詳しくは「労働時間を切り捨てない」で解説します。
手書きの出勤簿は違法になる可能性がある
手書きの出勤簿は違法になる可能性があるため、注意しましょう。手書きに代表される自己申告の出勤簿は改ざんが可能であり、厚生労働省の定める客観的な記録に該当しないためです。
ただし、厚生労働省が公表している「労働時間の適正な把握のために使用者が講ずべき措置に関するガイドライン」には次のとおり、自己申告制でも許容される場合が定められています。
(2)やむを得ず自己申告制で労働時間を把握する場合(一部抜粋)
① 自己申告を行う労働者や、労働時間を管理する者に対しても自己申告制の適正な運用等ガイドラインに基づく措置等について、十分な説明を行うこと
② 自己申告により把握した労働時間と、入退場記録やパソコンの使用時間等から把握した在社時間との間に著しい乖離がある場合には実態調査を実施し、所要の労働時間の補正をすること
③ 使用者は労働者が自己申告できる時間数の上限を設ける等適正な自己申告を阻害する措置を設けてはならないこと。さらに36協定の延長することができる時間数を超えて労働しているにもかかわらず、記録上これを守っているようにすることが、労働者等において慣習的に行われていないか確認すること
引用:厚生労働省「労働時間の適正な把握のために使用者が講ずべき措置に関するガイドライン
」
違法であるとの指摘を受けないようにするためには、改ざんできないシステムの導入が望まれます。ICカードやパソコン・タブレットなどによって打刻を行えば、客観的な記録として残すことができます。
ハンコを押すだけの出勤簿は認められない
ハンコを押すだけの出勤簿は認められていません。出勤簿には、始業や終業、休憩時間などの記載が必要です。2019年4月施行の改正労働基準法では、残業時間の上限が定められました。同月からの適用が猶予されていた中小企業も2020年4月から適用されたため、出退勤時刻を明確にしなければなりません。
労働時間を切り捨てない
出勤簿に記載された労働時間は切り捨ててはいけません。たとえ1分であっても無給は認められず、端数の切り捨ては原則として行えません。
労働基準法では、労働者が労働したすべての時間に対して賃金を支払うことが求められています。端数処理が許されるのは、1か月の時間外労働・休日労働・深夜労働時間の合計に1時間未満の端数がある場合に、30分未満の端数を切り捨て、それ以上を1時間に切り上げる場合に限られています。
参照:厚生労働省「労働時間を適正に把握し正しく賃金を支払いましょう」
【最大3か月無料でお試し】弥生のクラウド給与ソフトで大幅コスト削減
勤怠管理システムの導入によるメリット
従業員の労働時間を客観的かつ正確に把握するためには、ICカードやパソコン、スマホなどで、出退勤の時間管理を行う勤怠管理システムの導入をおすすめします。勤怠管理システムは、リモートワークなどの多様な働き方に対応し、ミス・不正の防止や法改正への対応に役立ちます。
さまざまなシーンでの勤怠管理に対応できる
勤怠管理システムは、さまざまなシーンでの勤怠管理に適しています。例えば、事業所が複数ある場合でも事業所ごとにタイムカードを導入したり、勤務時間を管理したりといった面倒な作業がなく、一元管理が可能です。
また、最近ではリモートワークや在宅勤務など働き方が多様化し、必ずしも従業員が出勤して業務を行うとは限りません。そのような場合でも、勤怠管理システムであれば、パソコンやスマホで会社以外の場所でも勤務時間を入力できるため、勤怠管理作業のためにわざわざ出社しなくても済みます。
ミスや不正を防ぎ業務効率化にも期待できる
勤怠管理システムは、記録された実労働時間や残業時間が自動で集計されるため、人の手を介した入力作業が不要になり、人的なミスを減らせます。手書きやタイムカードと比べて不正を行いにくい点もメリットです。給与計算ソフトと連携できる製品を利用すれば、勤怠記録を基に自動で給与計算も可能になり、業務の効率化につながります。
法改正に対応しやすい
勤怠管理システムを使えば、法改正に迅速かつ正確に対応できます。手書きやエクセルでの勤怠管理は、法改正に対応するための手続きが煩雑で、担当者の負担が大きいのが難点です。対応漏れによるミスも起こり得ます。しかし、勤怠管理システムを導入することで、法改正に対応するためのプロセスが自動化され、担当者の負担を軽減できます。システムは定期的に更新され、最新の法律や規制が自動的に適用されるため、手書きやエクセルで発生しがちなミスも防げます。
保管スペースが不要になる
出勤簿は原則として、最後に出勤した日から5年間保存しなければなりません(現在は経過措置として3年間)。紙で出勤簿を保存する場合、破損や紛失のリスクがあるうえ、社員数が増えた場合に保管スペースが足りなくなってしまう場合もあります。勤怠管理システムならデータとして保管できるため、物理的な保管スペースは不要です。
【最大3か月無料でお試し】弥生のクラウド給与ソフトで大幅コスト削減
出勤簿に関するよくある質問
ここでは、出勤簿に関してよくある質問とその答えをピックアップしてまとめました。
出勤簿を作成する必要はある?
出勤簿は必ず作成し、備え付けしなければなりません。出勤簿は労働者名簿や賃金台帳と併せて法定三帳簿といわれる書類であり、非常に大切な書類です。保管期間も長く、退職した労働者の最終出勤日から5年間保存する必要があります(現在は経過措置として3年間)。出勤簿には労働日数や出退勤時間などの必要項目を記載のうえ、確実に保存しましょう。出勤簿を保存しなければ30万円以下の罰金を科される対象となります。
出勤簿を紙に書くことは違法?
出勤簿を紙に記録すること自体は違法ではありません。ただし、紙の出勤簿は内容の改ざんが容易であるため、労働時間管理の手段としては適切ではないとされることがあります。特に、紙の出勤簿に印鑑を押すだけでは、正確な労働時間を証明する手段として不十分です。
そのため、信頼性の高い勤怠管理を行うためには、デジタル打刻を用いることが推奨されています。厚生労働省のガイドラインでも、タイムカード、ICカード、パソコンなどによる客観的な記録を基本とするよう求めています。
また、デジタルかアナログかを問わず、自己申告による記録は適切ではありません。労働時間の管理は、客観的な事実に基づいた記録を徹底することが重要です。
タイムカードは出勤簿の代わりになる?
タイムカードだけでは出勤簿の代わりにはなりません。出勤簿には時間外労働時間や休日出勤日数などを記録する必要がありますが、基本的な打刻機能しか持たない場合には、タイムカードでこれらの情報を正確に記録できません。タイムカードを出勤簿代わりに使用する場合は、以下の条件を満たす必要があります。
- 時間外労働や休日出勤の記録が可能である
- 正確な打刻ができる
- 残業申請書やその他の書類を添付できる
タイムカードの機能が限定されている場合は、残業申請書などの書類を添付して正確な業務時間を記録する必要があります。
出勤簿はエクセルでも問題ない?
出勤簿をエクセルで作成することは可能です。自作することもできますし、自動計算可能な無料のテンプレートも利用できます。ただし、エクセルの出勤簿は入力ミスや改ざんのリスクがあり、また打刻が手動・自己申告になることが多いため、正確な記録が難しい場合があります。このため、タイムカードやアプリで確認できるようにする必要があります。また、法改正への対応もその都度行わなければなりません。
こうした点から、エクセルよりも勤怠管理システムの導入をおすすめします。勤怠管理システムは自動集計で正確にデータを管理し、法改正にも迅速に対応できます。
【最大3か月無料でお試し】弥生のクラウド給与ソフトで大幅コスト削減
正しい出勤簿で適正な労務管理を行おう
適正な労務管理を行うためには、正確な出勤簿の作成が欠かせません。出勤簿は労働基準法で定められた重要な帳簿であり、労働時間や休憩時間、残業時間などを正確に記録する必要があります。
紙の出勤簿やエクセルでの管理は入力ミスや改ざんのリスクがあるため、勤怠管理システムの導入を検討しましょう。勤怠管理システムは労働時間を正確に記録し、法改正にも柔軟に対応できるため、労務管理の効率化や従業員の労働環境の改善につながります。適正な出勤簿の管理を通じて、健全な職場環境を築きましょう。
【最大3か月無料でお試し】弥生のクラウド給与ソフトで大幅コスト削減
「弥生給与 Next」で給与・勤怠・労務をまとめてサクッとデジタル化
弥生給与 Nextは、複雑な人事労務業務をシームレスに連携し、効率化するクラウド給与サービスです。
従業員情報の管理から給与計算・年末調整、勤怠管理、保険や入社の手続きといった労務管理まで、これひとつで完結します。
今なら「弥生給与 Next」 スタート応援キャンペーン実施中です!
この機会にぜひお試しください。
この記事の監修者税理士法人古田土会計
社会保険労務士法人古田土人事労務
中小企業を経営する上で代表的なお悩みを「魅せる会計事務所グループ」として自ら実践してきた経験と、約3,000社の指導実績で培ったノウハウでお手伝いさせて頂いております。
「日本で一番喜ばれる数の多い会計事務所グループになる」
この夢の実現に向けて、全力でご支援しております。
解決できない経営課題がありましたら、ぜひ私たちにお声掛けください。必ず力になります。







