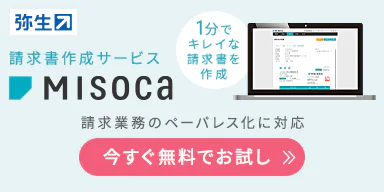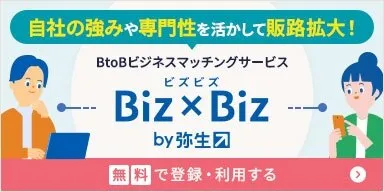預り証の書き方|種類や押さえておきたいポイントを紹介
監修者: 高崎文秀(税理士)
更新

預り証は物品や金銭を一時的に預かったことを証明する書類です。記載方法に法的な決まりがなく、何をどのように書けばよいのか悩んでいる方もいるはずです。本記事では、預り証の書き方やすぐに役立つ預り証のテンプレート、また預り証の種類、印紙税や決算での扱いに関する注意点など、預り証を扱うのなら、知っておくべきポイントを解説します。
預り証の書き方
預り証は、物品や金銭を一時的に預かったことを証明する文書です。書式や様式に決まりはありませんが、以下の項目を記載します。
- 預けた者の名前および住所
- 預かった者の名前および住所
- 預かったことがわかる文言
- 預かった物の内容
- 預かった日付
- 預かった物を返却する場合は返却条件
他にも現金を預かった場合には、金額および預かる目的を記入します。すぐに取引内容がわかるように、だれがだれに預けたのか、保管の方法・預かった物品を毀損した場合の措置の方法、預かる際にかかる費用の記載も必要です。また、署名や押印がなければ、預り証の法的効力が弱まる点に注意してください。
預り証のテンプレート例
預り証の書き方に悩んでいる方でも、テンプレートを活用すれば簡単に作成できます。インターネット上には、主にWord用とExcel用のテンプレートが公開されており、無料でダウンロードできます。
預り証の目的別のテンプレートを紹介しますので、参考にしてください。
現金預かりの場合
現金を預かる場合、金額や預かる目的を記載できるテンプレートを活用します。タイトルは現金預り証とするのが一般的です。タイトルの下に現金を預けた者の住所および氏名を記載する欄があり、金額と、ただし書きとして現金を預かる事情などを記載できるテンプレートを使用しましょう。
例えば、賃貸借契約の際の敷金として現金を預かった場合、ただし書きには「原状回復費用を差し引いた残金を返還する」と一筆書いておきます。一番下には預かった日付と預かった者の住所および氏名を記載するのが基本の書き方です。
Word用テンプレート
Excel用テンプレート
物品預かりの場合
品物を預かる場合、物品名の詳細、数量を記載できるテンプレートを利用します。タイトルは、物品預り証とします。テンプレートには、タイトルの下に品物を預けた者の氏名および住所を記載する欄があり、預かり物、数量、備考が記載できる表を配置しているものが一般的です。最後に、預かった日付と預かった者の住所および氏名を記載します。
物品預り証が使われる場面には、パソコンやスマートフォンの修理が挙げられます。この場合、ほとんどが預り証と依頼書が一体のため、修理内容なども記入しなければなりません。修理依頼書兼預り証は、多くの修理業者が専用テンプレートを用意しています。
他には、改修工事や不動産の賃貸借契約などで鍵を引き渡すときにも預り証を作成します。鍵を引き渡す場合、物品預り証を利用しても問題ありませんが、鍵専用の預り証のテンプレートを利用するもおすすめです。
Word用テンプレート
Excel用テンプレート
預り証に関して押さえておきたいポイント
預り証は領収書のように日常的に発行するものではないため、利用する際に戸惑う方もいるでしょう。預り証に関して押さえておきたいポイントを紹介します。
預り証返却時のポイント
預けた物品や現金は預り証と引き換えに返却してもらえます。後述しますが、預り証にはさまざまな種類があり、目的別に処理の仕方が異なる点は注意しましょう。
担保目的や預託目的、運搬・保管目的の場合、基本的に物品や現金を預り証と交換します。ただし、担保目的の場合、預かった物品や現金は担保の条件が満たされた場合には返却されません。例えば、住宅ローンの返済ができなくなった場合、担保とした土地や家は売却されます。このとき預り証は、処分の対象です。また、不動産取引で内金として現金を預かるなど、代金を支払う目的で預り証を発行することがありますが、契約成立時に預り証と引き換えに領収書を渡すのが一般的です。
預り証紛失時のポイント
万が一、預り証を失くしても特に心配いりません。それは、基本的に現金や品物の取引は双方が把握しており、預り証以外のもので取引を明らかにできるためです。ただし、預けた者から紛失の申告があった場合、二重請求の恐れがある点に注意しなければなりません。後に二重請求されないためにも、預かった者が預けた者に預り証の紛失を証明する文書の作成を依頼してください。紛失証明書は、預けた者と預かった者の双方で保管する方が無難です。また、紛失した際の対応について事前に説明しておけば、トラブルを回避しやすくなります。
印紙税に関するポイント
物品預り証には印紙税は不要です。その一方で、現金や株式、債券などの預り証の場合、額面が5万円以上になると、印紙税が必要となります。収入印紙を購入し預り証に貼り付けてください。収入印紙を貼り忘れると過怠税を徴収され、本来の印紙税額の3倍を納めることになります。印紙税額については、以下の表を参考にしてください。
| 記載金額 | 税額 |
|---|---|
| 5万円未満 | 非課税 |
| 100万円超え200万円以下 | 400円 |
| 200万円超え300万円以下 | 600円 |
| 300万円超え500万円以下 | 1,000円 |
| 500万円超え1,000万円以下 | 2,000円 |
| 記載金額 | 税額 |
|---|---|
| 5万円未満 | 非課税 |
| 5万円以上 | 200円 |
参照:国税庁「No.7105 金銭または有価証券の受取書、領収書」
決算におけるポイント
売上代金のうち何割かを受け取った場合の預り証の扱いは慎重にしなければいけません。売上として計上するかどうかや計上のタイミングによって、所得税や法人税の金額に影響します。品物の取引の場合、代金の支払いがあっても品物を引き渡していなければ売上は確定しません。そのため、品物の引き渡し時に売上を計上するのが原則です。
その一方で、サービスを提供する取引の場合、確定したサービス部分のみの売上を計上します。例えば弁護士との契約では、内金を支払った時点でその分のサービスの提供が行われたと判断されるため、売上の計上が必要です。なお、預り証の保存期間は7年です。特に有価証券預り証は法人税法により7年間の保存が義務付けられています。
参照:国税庁「No.5930 帳簿書類等の保存期間」
【目的別】預り証の種類
預り証は、目的別に大きく分けて4種類あります。預り証の種類ごとのポイントを詳しく解説します。
代金支払い目的
日常的に取り扱われる預り証は、代金の支払いを目的としたものです。売上代金の何割かを内金または手付金として預かることを証明する目的として発行されます。預り証の中でも、代金支払いを目的として発行されるケースは以下を参考にしてください。
- 不動産売買で内金を支払った
- パッケージツアーなどに申し込む際、旅行会社に代金の何%かを申込金として事前に支払った
- 車を購入する際に頭金を支払った
なお、現金や品物の所有権は、内金を受け取ったときには移行することはなく、預けた者にあります。その後、残金を支払い、預り証と領収書を交換した際に所有権は移行します。売買が成立したら預かった内金は返還しなければなりませんが、一般的には内金を代金の一部とし、売買成立後に残金を支払うケースがほとんどです。
担保目的
担保として現金や品物を受け取る場合に発行される預り証もあります。利用されるケースは以下のとおりです。
- 質屋が品物を預かり現金を融資する
- 金融機関でローンを組む
- 投資家が株式や債券を担保として融資を受ける
- 企業が機械や車を担保として融資を受ける
- 不動産などの賃貸借契約をする際に大家が敷金を預かる
託された現金や品物は、契約が終われば預り証と引き換えに返すのが一般的です。ただし、賃貸借契約の場合、敷金は退去時の原状回復に充てられます。敷金がすべて原状回復に使われてしまえば、預けた者の手元に戻る現金はありません。この場合、預り証は有効性を失うため、処分対象となります。
預託目的
運用・積立が目的で、現金や債券などを金融機関に預ける際に発行される預り証もあります。例えば、投資信託に投資し、専門家に運用を任せたときに発行される預り証は、預託目的のものです。預託目的の預り証の発行は、銀行法で義務付けられていますが、預金の預入は頻繁に行われるため、一般的に預り証発行は省略されます。通帳などで預入の事実が確認できるため問題にはなりません。
運搬・保管目的
運搬および保管目的の預り証は、運送や保管する現金や品物が引き渡されたことを証明するために発行されます。実際は領収書と預り証は兼ねますが、両者は本来異なる書類である点には注意が必要です。運送や保管を目的として預り証を発行する例としては、宅配便を利用するケースが挙げられます。
宅配業者に荷物を預ける際に運搬費用を支払うと預り証を兼ねた領収書が作成されます。他には、貸倉庫を利用する際に発行されるものも運送や保管を目的とした預り証です。預り証の提示で、保管している品物の取り出しがスムーズに行えます。
【Q&A】預り証に関するよくある質問
預り証に関するよくある質問は次の2点です。
預り証とはどのような書類?
預り証とは、現金や物品を一時的に預かったことを証明する書類です。現金や品物を預かった者が発行し、預けた相手に渡します。預り証には、預かった物品の状態や預かった相手の氏名や連絡先、受渡しの日時などを記載します。預かった現金や物品の所有権が預けた者にあると示せます。紛失や破損などのトラブルが発生した際には、その対応や補償を検討する際の重要な証拠書類としても機能するものです。
預り証と領収書の違いは?
預り証は物品や金銭を一時的に預かったことを証明する書類です。預り証は現金や品物の所有権が変わらないことを、預かる者と預ける者が合意した前提で発行します。そのため、託された現金や品物の所有権は預けた者にあります。その一方で、領収書は代金の支払いが完了したことを証明する書類です。商品やサービスに対する支払いを証明するのが領収書で、レシートや振込明細書、クレジットカードの利用明細書がこれに当たります。領収書は提供商品やサービスの所有権が、支払った者に移行した証明として発行します。
預り証の書き方はポイントを押さえることが重要
預り証とは、第三者の現金や品物を預かった際に、それを明確にするために発行する書類です。書き方に法的な決まりはありませんが、取引内容が客観的にわかるように記載する必要があります。
預り証も書き方に明確なルールはありませんが、何を目的に発行するかで種類が分かれます。作成の際は、本記事で紹介したテンプレートをぜひ、活用してみてください。また、預り証を発行する際は、返すときや失くしたときの対応をあらかじめ相談しておくことも大切です。決算での扱いや印紙税が必要な点にも注意しましょう。
クラウド見積・納品・請求書サービスなら、請求業務をラクにできる
クラウド請求書作成ソフトを使うことで、毎月発生する請求業務をラクにできます。
今すぐに始められて、初心者でも簡単に使えるクラウド見積・納品・請求書サービス「Misoca」の主な機能をご紹介します。
「Misoca」は月10枚までの請求書作成ならずっと無料、月11枚以上の請求書作成の有償プランも1年間0円で使用できるため、気軽にお試しすることができます。
見積書・納品書・請求書をテンプレートでキレイに作成

Misocaは見積書 ・納品書・請求書・領収書・検収書の作成が可能です。取引先・品目・税率などをテンプレートの入力フォームに記入・選択するだけで、かんたんにキレイな帳票ができます。
各種帳票の変換・請求書の自動作成で入力の手間を削減

見積書から納品書・請求書への変換や、請求書から領収書・検収書の作成もクリック操作でスムーズにできます。固定の取引は、請求書の自動作成・自動メール機能を使えば、作成から送付までの手間を省くことが可能です。
インボイス制度(発行・保存)・電子帳簿保存法に対応だから”あんしん”

Misocaは、インボイス制度に必要な適格請求書の発行に対応しています。さらに発行した請求書は「スマート証憑管理」との連携で、インボイス制度・電子帳簿保存法の要件を満たす形で電子保存・管理することが可能です。
確定申告ソフトとの連携で請求業務から記帳までを効率化

Misocaで作成した請求書データは、弥生の確定申告ソフト「やよいの青色申告 オンライン」に連携することが可能です。請求データを申告ソフトへ自動取込・自動仕訳できるため、取引データの2重入力や入力ミスを削減し、効率的な業務を実現できます。
会計業務はもちろん、請求書発行、経費精算、証憑管理業務もできる!
法人向けクラウド会計ソフト「弥生会計 Next」では、請求書作成ソフト・経費精算ソフト・証憑管理ソフトがセットで利用できます。自動的にデータが連携されるため、バックオフィス業務を幅広く効率化できます。

「弥生会計 Next」で、会計業務を「できるだけやりたくないもの」から「事業を成長させるうえで欠かせないもの」へ。まずは、「弥生会計 Next」をぜひお試しください。
この記事の監修者高崎文秀(税理士)
高崎文秀税理士事務所 代表税理士/株式会社マネーリンク 代表取締役
早稲田大学理工学部応用化学科卒
都内税理士事務所に税理士として勤務し、さまざまな規模の法人・個人のお客様を幅広く担当。2019年に独立開業し、現在は法人・個人事業者の税務顧問・節税サポート、個人の税務相談・サポート、企業買収支援、税務記事の監修など幅広く活動中。また通常の税理士業務の他、一般社団法人CSVOICE協会の認定経営支援責任者として、業績に悩む顧問先の経営改善を積極的に行っている。