クラウド請求書発行システムを解説!機能や導入メリット、選び方のポイント
監修者: 小林祐士(税理士法人フォース)
更新
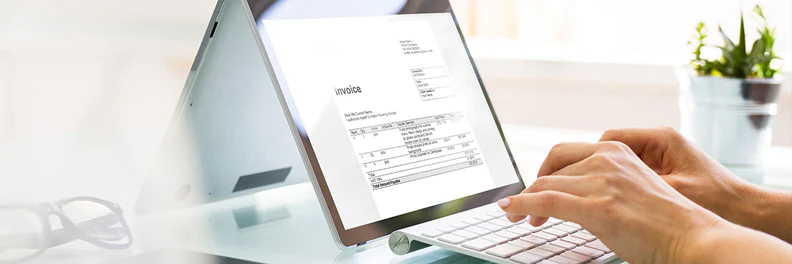
請求書発行に関する悩みや疑問を抱えている企業の経理担当者や管理者の方々に向けて、クラウド請求書発行システムの選定に必要な基本概念、種類、主な機能、導入メリット・デメリット、そして選び方のポイントについて解説します。自社に最適な請求書発行システムを見定め、業務効率化やコスト削減を実現させるために、ぜひ参考にしてください。
無料【クラウド請求書作成ソフト「Misoca」がよくわかる資料】をダウンロードする
請求書発行システム(クラウド請求書発行システム)とは
「請求書発行システム」は、請求書の作成から発行までの過程を効率化するものです。従来の手作業による請求書発行と比べ、時間と労力を大幅に削減できるため、生産性の向上に寄与します。ほとんどのシステムはクラウド型であり、「クラウド請求書発行システム」とも呼ばれます。インターネット経由でどこからでもアクセスできるので、リモートワークの環境でもスムーズな業務が可能です。
また、クラウド型のシステムは自動バックアップやセキュリティ対策が充実しており、データの安全性も確保されます。多くの企業がこのシステムを採用し、業務効率化を実現しています。
【無料でお試し】クラウド請求書作成ソフト「Misoca」でかんたんキレイに請求書作成!
請求書発行システムの種類
請求書発行システムは、「オンプレミス型」「インストール型」「クラウド型」の3つに大きく分類され、それぞれ特徴が異なります。
オンプレミス型請求書発行システム
オンプレミス型とは、社内ネットワークのみを使用し、自社で運用・管理するサーバーにシステムを構築するタイプです。カスタマイズの自由度が高いため、自社の既存システムと連携して利用できるものも多くなっています。大企業などでは、一般的に経理業務全体をIT化する一環として導入されます。
ただし、初期費用が高額になる傾向があります。また、運用には専門知識を持つエンジニアが欠かせないため、運用コストも高くなりがちです。
インストール型請求書発行システム
インストール型とは、パッケージのソフトウェアを購入し、コンピューターにインストールして使用するタイプです。基本的に買い切りであり、購入後は無制限に使用できます。
ただし、法令の改正やバージョンアップがあった場合は、最新版の購入が必要になるものもあります。保守契約を結ぶことで、法令改正やバージョンアップに対応するためのアップデート版が提供されることもあります。
クラウド型請求書発行システム
クラウド型とは、インターネット上のシステムに、コンピューターやスマートフォンでアクセスして、サービスを利用するタイプです。インターネット環境が整っていれば、オフィスはもちろん、自宅や外出先などどこからでもアクセスして利用できます。最新の法令改正やバージョンアップへの対応も自動で行われるため、手間がかかりません。
さらに、「ソフトウェアのインストールやメンテナンスが不要」「データの安全性が高い」などのメリットがあります。
【無料でお試し】クラウド請求書作成ソフト「Misoca」でかんたんキレイに請求書作成!
請求書発行システムの主な機能
請求書発行システムには、以下のような機能が備わったものが多くあります。
| 請求書作成・発行機能 | 定期的な請求があれば予約設定することで自動で請求書を作成・発行し、手作業の手間を削減。迅速で正確な請求書発行を実現。 |
| 請求書発行代行 | 請求書の作成・送信を自動化。業務効率化と誤請求のリスク軽減により、自社での業務が不要。 |
| 請求書保存機能 | 発行された請求書は、システム内に保存するほか、システムが稼働する場所以外のストレージに保管。検索・確認が容易で、保管スペースを節約。法令に基づく保存義務を満たす製品もある。 |
| 入金管理機能 | 入金状況を管理し、入金確認や未入金の追跡が可能。回収漏れを防止する自動リマインダー機能が備わっている製品もある。 |
請求書作成・発行機能
取引先や品目を記録することにより、事前に設定されたフォーマットに基づいて自動で請求書の内容を入力・作成し、顧客に対して迅速に請求書を発行する機能です。手作業で請求書を作成する手間を大幅に削減し、正確でスピーディーな請求書発行を実現します。
請求書発行代行
請求書の発行を代行する機能を利用することで、システムが自動的に請求書を作成・送信してくれます。自社で請求書を発行する手間がなくなり、業務効率化に期待できます。また、誤請求のリスク軽減にも効果的です。
請求書保存機能
発行された請求書をいつでも参照できるように、システム内に保存する機能です。過去の請求書を簡単に検索・確認できるので、紙の請求書を保管するスペースや手間を省けます。また、法令に基づく保存義務を満たすための機能も備えています。
入金管理機能
発行した請求書に対する入金状況を管理する機能も提供しています。入金確認や未入金の追跡が容易になり、キャッシュフローの管理に役立ちます。また、未入金時には自動でリマインダーを送信する機能により、回収漏れを防止します。これらの機能によって、請求書発行業務の効率化と正確性の向上を実現し、業務を円滑に進められるようになります。
請求書作成システムのメリット・デメリットなどについて詳しくは、以下の記事をご覧ください。
【無料でお試し】クラウド請求書作成ソフト「Misoca」でかんたんキレイに請求書作成!
請求書発行システムを導入するメリット
請求書発行システムを導入すると、請求書を電子データで発行できるようになるため、従来のような紙の書類の送付が不要になります。その他に得られる導入メリットは以下のとおりです。
作業の効率化
必要項目を入力するだけで、時間をかけずにきれいな請求書を作成できます。自社に適した請求書の用紙を探したり、Excelでフォーマットを作ったりする必要はありません。インボイス制度(適格請求書)(以下、インボイス)や電子帳簿保存などに必要な項目や適切な要件に対応するだけではなく、項目の追加なども簡単に行えるため、取引先や取引内容に合わせた請求書の作成が可能です。
さらに、システムによっては、請求書にかかわるさまざまな業務を一元管理できる機能があり、業務効率化につながります。例えば、請求書の自動生成や自動送信などの機能を利用すれば、手作業によるエラーを減らし、業務効率の大幅な向上が期待できます。
加えて、請求書発行システムは、取引先とのコミュニケーションの円滑化や業務の透明化にも効果的です。また、リモートワークの普及に伴い、働き方改革の推進にも寄与しています。
請求書発行システムで自動化できることの例
請求書発行システムの導入により、以下の業務を自動化できます。
- ・取引先や品目の自動入力
- 取引先や品目を一度記録しておくと、次回以降は自動で入力されるため、手動での入力作業を大幅に減らせる
- ・定額請求の自動発行
- 毎月、定額の請求がある場合、設定しておいた発行日に請求書を自動的に発行・送付できるため、定期的な請求作業が効率化される
- ・請求書作成と同時の納品書・領収書の自動作成
- 請求書の作成と同時に、納品書や領収書、送付状まで自動的に作成できるため、複数の書類作成作業が効率化される
発送作業のアウトソーシング&ペーパーレス
請求書発行システム「Misoca」は、郵送代行サービスにも対応しています。手作業によるアナログな請求書送付作業には、想像以上に手間と時間がかかり、人的コストも大きくなりがちです。しかし、取引先によっては、「紙の請求書を送ってほしい」と依頼してくる企業も存在します。
その場合でも、システムの郵送代行サービスを利用することで、発送作業のアウトソーシングが可能です。所定の郵送代行費用は必要ですが、空いた時間で従業員をより重要な業務に集中させられることを考えれば、メリットが大きいと言えます。
また、取引先の承認を得たうえで、電子データで請求書を発行すれば、請求書にかかわる業務はよりいっそう効率化されます。ペーパーレスになることから、紙や印刷代、封筒、切手代などを省ける他、取引先が紙の請求書を保管するためのスペースを確保する必要もありません。システムによって、請求書管理が容易になり、セキュリティが強化されます。
請求漏れ、誤請求などの防止
手作業で行う請求書の作成・発送は、どうしてもヒューマンエラーが起こり得るものです。万が一、請求漏れや誤請求が起こってしまうと、正確に支払いを受けられないばかりか、取引先からの信頼を損ねることにもなりかねません。請求書発行システムの機能を活用すれば、そのようなリスクを減らすことができます。
例えば、システム上での宛先データの管理によって、送付先を誤るリスクを回避し、毎月の自動発行機能によって、請求書の作成忘れの防止が可能です。また、請求済み件数・未請求件数・入金予定額を一括管理し、請求漏れがないかどうかも確認できます。
「AI-OCR(AI技術を組み込んだ光学文字認識)」を搭載した請求書発行システムであれば、そのAI技術を活用して、請求内容をチェックし、誤請求のリスクを回避します。より正確な請求書の発行が可能となり、取引先との信頼関係の維持に寄与します。
リモートワーク支援・働き方改革の推進
クラウド型の請求書発行システムは、インターネット環境が整っていれば、どこからでも利用が可能です。自宅でも業務を行えるため、経理担当者が請求書発行の目的でオフィスに出社する必要がありません。
これにより、リモートワークが普及し、働き方改革の推進につながります。また、高いセキュリティ対策が施されたシステムを導入すると、リモートワーク時のデータ保護に有効です。
見積もりの共有化
請求書発行システムの中には、請求書だけではなく見積書や納品書、注文書など、取引や契約が成立したことを証明する「証憑書類」も、作成・管理できるタイプがあります。1つの取引において、証憑書類をすべて一括したデータ管理が可能なので、共有や検索が容易です。
これにより、部署間で問い合わせたり、過去の見積もりを探すために時間をかけたりすることも省けます。常に最新情報をシステム上で一元管理することで、より効率的に業務を進められるようになります。
【無料でお試し】クラウド請求書作成ソフト「Misoca」でかんたんキレイに請求書作成!
請求書発行システムを導入するデメリット
請求書発行システムにより多くのメリットを得られますが、把握しておきたいデメリットもあります。メリットとデメリットの両方を確認したうえで、導入を検討するとよいでしょう。
取引先もシステムの導入が必要に
電子データで請求書を発行する場合、取引先の理解が欠かせません。取引先には、事前に請求書発行システムについて説明し、電子帳簿保存法を含めた対応の確認が必要です。また、中には紙の請求書を希望する企業も存在するため、請求書の完全な電子化は難しいと考えられます。その場合は、上述した郵送代行サービスをうまく活用することをおすすめします。
月額利用料がかかる
多くのクラウド型の請求書発行システムは、月額または年額の利用料を支払う必要があります。他のタイプのシステムでも、月額や年額の利用料の代わりに、初期費用が発生するものが一般的です。無料のサービスも提供されていますが、機能が限られているため、業務に使用する場合はコストを含めた検討が必要です。
【無料でお試し】クラウド請求書作成ソフト「Misoca」でかんたんキレイに請求書作成!
請求書発行システムの選び方のポイント
請求書発行システムは、多くの会社がサービスを展開しており、それぞれ特徴が異なります。自社に適したシステムを導入するためには、以下の点に注目して選びましょう。
事業形態に合ったシステムか
一口に請求書発行システムと言っても、カバーする範囲は製品によってさまざまです。請求書発行のみ効率化したいのか、入金管理までシステム上で行いたいのかなど、自社のニーズに合わせて確認しなければなりません。
ポイントは現状解決したい課題に加え、将来的な業務効率化も視野に入れたうえで、システムを選ぶことです。例えば、「自社が小規模(または個人事業主)なので、手軽なシステムがいい」「取引先が多いため、効率よく大量の請求書を送りたい」「請求以外の業務もまとめて効率化したい」など、自社の事情などを踏まえて、最適なシステムを検討してみましょう。
また、電子帳簿保存法やインボイス制度など最新の法令に対応しているかどうかも重要です。この点を押さえれば、法令遵守の面に関しても心配することなく選べます。
現在の業務フローに合致するか
請求書発行にあたっての業務フローは、企業によって異なります。例えば、請求書を発行する際に営業担当者が確認するケースもあれば、関係部署や役職者の承認が必要なケースもあります。まずは、自社がどのような流れで請求書を作成・発行・管理しているのかを把握し、そのフローに自然に組み込めるシステムを導入するとよいでしょう。
CSVファイルに記載した請求情報をインポートして、請求書を一括作成できる「CSV連携」や、機能やデータを他のアプリケーションと連携する「API連携」、顧客管理システムと連動させて、請求書作成や売上計上ができる「CRM連携」など、既存のシステムとの連携が可能かどうかも確認しておくことをおすすめします。
操作性・機能性は見合っているか
いくら豊富な機能が揃っていても、操作がわかりにくいシステムは、経理担当者や従業員が使いこなせません。そもそも自社に必要な機能かどうかも含め、担当者にとって使いやすいシステムかどうかをしっかり見極める必要があります。特に、複数人で運用する場合、初心者でも簡単に使える操作性の良さは、システム選びの重要な要素です。初心者や非専門家が使いやすいインターフェースが求められています。
高いセキュリティ性はあるか
請求書には取引先や取引内容、金額、口座番号など、取引上の機密情報が多く記載されています。特に、クラウド型のシステムを利用する際には、セキュリティ対策の内容に十分注意を払いましょう。
情報漏えいを防ぐための高いセキュリティ性が保たれているか、システム管理者によって利用制限をどの程度設定できるかなどを確認することが重要です。また、最新のセキュリティ技術や暗号化手法が適用されているか、定期的なセキュリティ監査が行われているかなどの点も欠かせません。
改正電子帳簿保存法、インボイス制度に対応しているか
2022年1月に電子帳簿保存法が施行され、電子取引のデータ保存が義務付けられました。2023年12月31日までは経過措置が設けられていたため、やむをえない事情がある場合のみ紙での保存が認められていましたが、2024年1月1日からは完全義務化されました。これにより、相当な理由があると認められない限り、電子データで受け取った書類は電子データのまま保存する必要があります。
また、2023年10月にインボイス制度が導入され、原則として売手側が発行するインボイスがなければ、買手側は仕入税額控除を受けられなくなりました。請求書発行システムを導入する際には、これらの法改正にも対応しているかどうかも大きなポイントです。
料金体系は自社と合っているか
請求書発行システムの料金体系は、主に「従量課金制」と「月額制」に分類されます。従量課金制は、発行した請求書の枚数に応じて料金を支払う方式です。発行数に応じたプランが用意されているため、請求書の発行数が少ない企業に適しています。
その一方で、月額制は発行数に制限がなく、ユーザー数や利用可能な機能によってプランが異なる方式です。多くの請求書を発行する企業や、多機能なシステムを必要とする企業などに適しています。
自社の請求書発行頻度や業務ニーズに合った料金体系を選ぶことで、コストパフォーマンスの向上が期待できます。
サポートが充実しているか
システム上でトラブルが発生した場合に、適切なサポートを提供してくれるかどうかもポイントの1つです。例えば、操作方法や設定方法などで困った際も、メールや電話、チャットなどによる質問が可能なサポート体制があれば、心置きなく導入できます。
実際の操作性を確かめるために、無料トライアルが用意されているシステムを選ぶこともおすすめです。また、最新のサポート体制やユーザーレビューを参考にすることで、選ぶシステムの信頼性を高められます。
【無料でお試し】クラウド請求書作成ソフト「Misoca」でかんたんキレイに請求書作成!
【Q&A】請求書の発行に関するよくある質問
請求書はなぜ発行する必要がある?
請求書は納品した商品や提供したサービスの対価を、期日までに支払ってもらうために発行する重要な書類です。取引先に正確な金額や支払期日、振込先情報を提供し、支払い漏れを防ぎます。また、トラブルを防いだり信頼関係を築いたりする取引の証拠としても不可欠です。2023年10月からインボイス制度が導入され、請求書発行の正確性がいっそう求められるようになりました。
請求書には保存義務がある?
法人の場合、請求書などの証憑書類は、その事業年度の確定申告期限の翌日から7年間保存する義務があります。青色申告で欠損金額が生じた場合や、災害損失欠損金額が生じた場合は10年間です。個人事業主は5年間の保存義務があります。2023年10月以降のインボイス制度の導入により、課税事業者は7年間の保存が義務付けられました。ただし、簡易課税制度を選択している場合は例外です。
【無料でお試し】クラウド請求書作成ソフト「Misoca」でかんたんキレイに請求書作成!
クラウド請求書発行システムで請求業務を効率化
請求書発行システムの活用は、手作業による時間や労力を削減できるだけでなく、人的ミスの低減にも有用です。弥生の請求書作成ソフト「Misoca」は、請求業務の効率化をサポートするクラウド型の見積・納品・請求書システムです。取引先や品目など、必要な情報をテンプレートに入力するだけでかんたんに帳票を作成できます。適格請求書(インボイス)の発行にも対応しているため、書類作成の見直しにもおすすめです。
【無料でお試し】クラウド請求書作成ソフト「Misoca」でかんたんキレイに請求書作成!
クラウド見積・納品・請求書サービスなら、請求業務をラクにできる
クラウド請求書作成ソフトを使うことで、毎月発生する請求業務をラクにできます。
今すぐに始められて、初心者でも簡単に使えるクラウド見積・納品・請求書サービス「Misoca」の主な機能をご紹介します。
「Misoca」は月10枚までの請求書作成ならずっと無料、月11枚以上の請求書作成の有償プランも1年間0円で使用できるため、気軽にお試しすることができます。
見積書・納品書・請求書をテンプレートでキレイに作成

Misocaは見積書 ・納品書・請求書・領収書・検収書の作成が可能です。取引先・品目・税率などをテンプレートの入力フォームに記入・選択するだけで、かんたんにキレイな帳票ができます。
各種帳票の変換・請求書の自動作成で入力の手間を削減

見積書から納品書・請求書への変換や、請求書から領収書・検収書の作成もクリック操作でスムーズにできます。固定の取引は、請求書の自動作成・自動メール機能を使えば、作成から送付までの手間を省くことが可能です。
インボイス制度(発行・保存)・電子帳簿保存法に対応だから”あんしん”

Misocaは、インボイス制度に必要な適格請求書の発行に対応しています。さらに発行した請求書は「スマート証憑管理」との連携で、インボイス制度・電子帳簿保存法の要件を満たす形で電子保存・管理することが可能です。
確定申告ソフトとの連携で請求業務から記帳までを効率化

Misocaで作成した請求書データは、弥生の確定申告ソフト「やよいの青色申告 オンライン」に連携することが可能です。請求データを申告ソフトへ自動取込・自動仕訳できるため、取引データの2重入力や入力ミスを削減し、効率的な業務を実現できます。
会計業務はもちろん、請求書発行、経費精算、証憑管理業務もできる!
法人向けクラウド会計ソフト「弥生会計 Next」では、請求書作成ソフト・経費精算ソフト・証憑管理ソフトがセットで利用できます。自動的にデータが連携されるため、バックオフィス業務を幅広く効率化できます。

「弥生会計 Next」で、会計業務を「できるだけやりたくないもの」から「事業を成長させるうえで欠かせないもの」へ。まずは、「弥生会計 Next」をぜひお試しください。
無料【クラウド請求書作成ソフト「Misoca」がよくわかる資料】をダウンロードする
この記事の監修者小林祐士(税理士法人フォース)
東京都町田市にある東京税理士会法人登録NO.1
税理士法人フォース 代表社員
お客様にとって必要な税理士とはどのようなものか。私たちは、事業者様のちょっとした疑問点や困りごと、相談事などに真剣に耳を傾け、AIなどの機械化では生み出せない安心感と信頼感を生み出し、関与させていただく事業者様の事業発展の「ちから=フォース」になる。これが私たちの法人が追い求める姿です。












