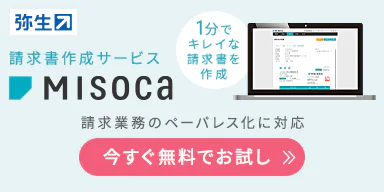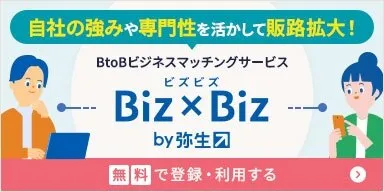請求書の再発行を依頼されたときの対処法|日付の記載方法や書き方を解説
監修者: 小林祐士(税理士法人フォース)
更新
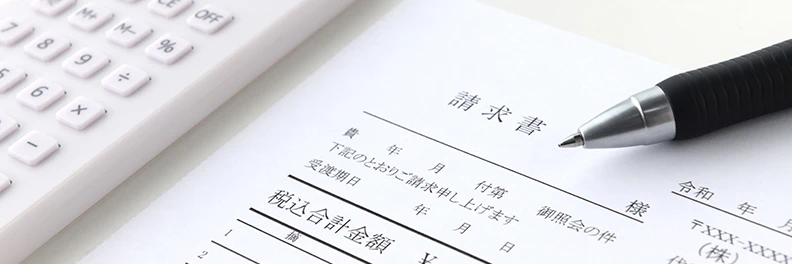
ビジネスでやり取りされる請求書は、取引先の紛失や誤記載などの理由で再発行を依頼されることも少なくありません。請求書の再発行が必要になった際は、請求の重複や請求先の混乱を避けるためにも、正しい手順で対処することが大切です。
本記事では、請求書を再発行する際に迷いやすいポイントや具体的な再発行ケース、再発行の手順について解説します。また、インボイス制度(適格請求書、以下インボイス)が開始されたことによる変更点や、電子帳簿保存法の要件との関連についても詳しく取り上げます。
請求書の再発行を依頼されたときに迷いやすいポイント
請求書の再発行を依頼された場合、「再発行しても問題ないのか」「日付や請求書番号をどう扱えばよいのか」といった疑問が生じるかと思います。以下では、再発行時に迷いやすいポイントについて解説します。
そもそも再発行してよいのか?
請求書を再発行すること自体に問題はありません。請求書は証憑(しょうひょう)の一種であり、受け取った企業は一定期間の保存義務があります。万が一紛失したまま放置すると、取引先が税務調査で指摘を受ける可能性もあります。さらに、再発行を拒否すると、支払いが滞るリスクもあるため、正当な理由がある場合は速やかに応じてください。ただし、二重発行によるトラブルが起きないよう、適切に対応する必要があります。
日付は前回と同じにすればよいのか?
再発行時の日付について、「日付を前回の発行時と同じにすべきか、再発行日にすべきか?」といった疑問を持つかもしれません。新しい日付で請求書を再発行した場合、新たな請求書とみなされて請求が重複するリスクがあります。これを踏まえて、請求書再発行時は前回と同じ日付にして、再発行であることを備考欄などに明記してください。また、支払期限を過ぎている場合でも日付は変更せず、別途書面やメールで新たな支払期限を指定しましょう。
請求書番号は変更した方がよいのか?
請求書を再発行する際、元の請求書番号に枝番を付けることを推奨します。例えば、元の請求書番号が「123456」である場合、再発行時には「123456-1」としてください。このように枝番を付けることで、元の請求書と関連があることを示しつつ、再発行されたものであることを明確にできます。ただし、枝番を付けただけでは再発行と認識されにくいので、備考欄などに再発行であることを明記してください。
請求書の再発行が必要となる主なケース
請求書は、紛失や記載内容の誤りといった理由で再発行が必要となる場合があります。特に、取引先が請求書を紛失した場合、支払期限の都合もあるため、できるだけ早く対応することが重要です。
以下では、請求書の再発行が必要になる主なケースを解説し、適切な対応方法を紹介します。
請求書の保存期間中に紛失した場合
請求書は法律によって保存期間が定められており、紙の場合は紙のままもしくは電子データ化して保存、電子データの場合は電子データとして保存しなければなりません。保存期間中に紛失した場合は再発行が必要です。保存期間中に請求書を紛失すると、法的義務を怠ったとみなされるかもしれません。そのため、自社の過失で紛失したのであれば、できるだけ早急に対処してください。
なお、法人の請求書保存期間は原則7年ですが、欠損金の繰越控除がある場合は10年に延長されます。一方、個人事業主の保存期間は原則5年ですが、消費税の課税事業者であれば7年となります。保存期間は紙でも電子データでも同じです。このように業態によって請求書の保存期間は異なるため、自社がどのケースに当てはまるのかを把握しておくことも重要です。
請求書の保存期間に関しては、以下の記事を参照してください。
送付後に請求書の誤りに気付いた場合
請求書の送付後に自社の誤りがあると気付いた場合、早急に取引先に連絡したうえで、お詫びと再発行を実施してください。その際、記載する発行日や支払期日は初回に発行した日付のままで発行しましょう。また、再送付時にはお詫び状を添えることで、取引先への配慮を示すことができます。
さらに、同様のミスが再度起こらないように、請求書発行作業やチェック体制に問題がないかを確認することも重要です。
送付後に請求先から請求書の誤りを指摘された場合
請求先である取引先から記載内容の誤りを指摘された場合、まずその正否を発行側である自社で確認する必要があります。修正が必要であれば、該当部分を修正・チェックして再発行しましょう。また、支払方法の変更など、請求先の依頼に応じて再発行が必要になるケースもあります。
インボイス制度導入以降、発行側が適格請求書発行事業者でありながら適格請求書の記載要件を満たしていない場合や、記載に誤りがある場合には、修正後の適格請求書を速やかに交付する必要があります。適格請求書の受領側が、適格請求書の記載事項を追記したり修正したりしないでください。なお、受取側で修正する場合は、修正する事項について、発行側に確認を受けることで仕入税額控除の適用を受けることができるインボイスとすることが可能となります。
なお、請求書再発行時に、発行側が請求先の同意を得ずに勝手に修正や追加を行うことは、トラブルの要因となるので控えましょう。修正や追記が必要な場合は、請求先へ確認し、必ず了承を得たうえで再発行してください。
【無料】実務対応もこれで安心!電子帳簿保存法の完全ガイドをダウンロードする
請求書を再発行する際の書き方
請求書を再発行する際には、記載すべき項目を正確に盛り込む必要があります。特に、インボイス制度に対応した適格請求書を発行する場合は、追加の注意点が求められます。以下に具体的な記載項目を解説します。
- ・請求書の宛名
- 請求先の会社名や氏名を記載します。会社名などは正式名称を使用し、「株式会社」も「(株)」などと略さずに記載するのがマナーです。また、宛名には必ず「御中」「様」といった敬称を添えます。
- ・請求書を発行する側の情報
- 発行側の会社名や氏名、住所、連絡先を、省略せずに正式名称で記載します。
- ・請求書作成(発行)日
- 原則として、初回発行の請求書に記載した発行日を使用します。再発行日を記載する場合、備考欄などに記載すると、請求の重複を避けやすくなります。
- ・請求書番号
- 再発行時には、初回の請求書番号に枝番を付けるなどして管理をしやすくするのが一般的です。
- ・取引内容の詳細
- 商品やサービス名、納品日や数量などをわかりやすく詳細に記載します。
- ・取引金額の詳細
- 合計額に加えて、各商品の単価や小計、消費税、源泉徴収などを記載します。
- ・支払期日
- 支払期日は初回発行時と同じ日付を記載します。支払期日が過ぎている場合は、別紙で新たな支払期日を指定しましょう。ただし、延滞利息に関する契約をした場合は、契約内容のうえ対応してください。
- ・振込先の情報
- 振込先の金融機関名、支店名、口座の種類、口座番号、口座名義を記載します。
インボイス制度(適格請求書)の場合に記載が必要な項目
2023年10月1日に開始されたインボイス制度に基づく適格請求書では、以上に加えて以下の2つの項目の記載が必要です。
- ・適格請求書発行事業者の登録番号
- 適格請求書には「登録番号」の記載が義務付けられています。登録番号とは、所轄の税務署に「適格請求書発行事業者の登録申請書」を提出し、登録を受けた事業者に対して通知される番号です。法人の場合「T+法人番号」、個人事業主の場合「T+13桁の数字」で構成されます。この13桁の数字はマイナンバーと重複しない、事業者ごとの番号です。
- ・適用税率と税率ごとに区分された消費税額及び対価の額
- インボイス制度では、適用税率と税率ごとに区分された消費税額及び対価の額の記載が必要です。インボイス制度に対応した請求書のフォーマットの用意をおすすめします。また、請求書発行システムを導入する場合、インボイス制度に対応しているかを確認してください。
適格請求書の書き方についてはこちらの記事で詳しく解説していますので、参考にしてください。
請求書を再発行する手順
請求書を再発行する際は、初回に請求書を発行したときとはいくつか手順が異なる場合があります。以下では、請求書を再発行する流れを、3つの手順に分けて解説します。
1. 再発行を依頼された請求書の内容を確認する
まず、再発行する請求書に記載すべき会社名や氏名、案件名、その内容、金額、日付などの基本事項を再確認してください。 修正を依頼された内容だけでなく、他に誤りがないかも確認し、必要に応じて適切に修正しましょう。
2. 該当の請求書を再発行する
次に、該当する請求書を作成します。再発行する請求書の日付は、取引先が紛失した場合でも、自社の記載に誤りがあった場合でも、原則として初回に発行した請求書の日付にします。
ただし、初回発行の請求書の支払期日が過ぎている場合は、契約書を確認し、新たな支払期日を設定する必要がある場合もあります。この対応は契約内容によって異なります。
また、紛失したと思われていた請求書が後日発見され、再発行分と重複する事態を防ぐため、新たな請求書が再発行分である旨を明記してください。さらに、請求書番号には元の番号に枝番を追加し、二重請求を防ぐ工夫を施しましょう。
請求書番号についての記事は、以下もご参照ください。
3. 請求書を送付する
請求書を再発行して送付する際は、状況の説明を添えた文書を同封またはメールに記載してください。また、自社の誤りによる再発行であれば、謝罪文も添えましょう。さらに、請求の重複を避けるためにも、過去に送付した初回発行の請求書の破棄を希望する旨を書き添えておくと安心です。
メールで請求書の再発行を依頼する・依頼された場合の文例
請求書の再発行に関して、取引先へ依頼する場合と、取引先から依頼される場合の両方が考えられます。以下では、それぞれのケースに応じたメールの文例をご紹介します。
取引先に請求書の再発行を依頼する場合
取引先に請求書の再発行を依頼する際には、再発行を希望する請求書の番号や、再発行が必要となった理由を明記しましょう。
以下では、メールを送る際の文例を紹介しますので、送付時の参考にしてください。
文例
件名:
請求書再発行のお願い
本文:
◯◯株式会社
◯◯部 ◯◯課
◯◯様
いつも大変お世話になっております。
ミソカインボイス株式会社の◯◯です。
先日、貴社よりお送りいただいた請求書(請求書番号:No.◯◯◯◯)について、誠に恐縮ですが、再発行をお願いしたくご連絡いたしました。
上記の請求書は◯月◯日に受理いたしましたが、私の不手際でお送りいただいた請求書を紛失してしまいました。
今後は、再発防止のために改善策を徹底してまいります。
お忙しい中、多大なご迷惑をおかけしてしまい大変申し訳ありませんが、請求書を再発行していただきますよう、よろしくお願い申しあげます。
ミソカインボイス株式会社
◯◯部 ◯◯
TEL:000-000-000
メールアドレス:xxxx@ xxxxxx.com
取引先に再発行を依頼された場合
請求書の再発行依頼に返信する際には、再発行した請求書番号を明記します。また、取引先が紛失した請求書を発見した場合には破棄するよう依頼する一文を忘れずに添えてください。
以下では、返信メールを送る際の文例をご紹介しますので、送付時の参考にしてください。
文例
件名:
請求書再発行のご依頼に関して
本文:
◯◯株式会社
◯◯部 ◯◯課
◯◯様
いつも大変お世話になっております。
ミソカインボイス株式会社の◯◯です。
先日、お問い合わせいただきました請求書(請求書番号:No.◯◯◯◯)の再発行についてご連絡申しあげます。
添付ファイルにて、請求書をお送りいたしますので、ご確認ください。
なお、紛失された請求書が見つかりました場合には、そちらの請求書は破棄いただきますようお願い申しあげます。
不明点については遠慮なく◯◯までお問い合わせください。
よろしくお願い申しあげます。
ミソカインボイス株式会社
◯◯部 ◯◯
TEL:000-000-000
メールアドレス:xxxx@xxxxxx.com
請求書を再発行する際の注意点
請求書を再発行する際は、請求が重複するリスクの回避や支払期日の再設定について注意が必要です。以下では、具体的にどのような点に注意すべきなのかを解説します。
再発行であることを明記する
再発行した請求書は、初回発行分の請求書と混同したり、紛失したと思われた請求書が後日発見されて請求が重複したりすることを防止するために、再発行であることを明記しましょう。特に再発行であることが明瞭になるように、赤い文字で記載する、または「再発行」のスタンプを押す方法が効果的です。
支払期日を過ぎていた場合は契約内容を確認する
初回発行分の請求書に記載した支払期日が過ぎてしまっていた場合も、再発行する請求書では期日の変更を行わないのが基本です。
しかし、契約書に延滞利息に関する内容がある取引では、支払期日を2週間から1か月程度延長する場合もあります。そのため、請求書の支払期日が過ぎてから再発行する場合は、契約書の支払期日に関する内容を確認したうえで対応を決めましょう。
請求書のミスを訂正する際はお詫びをする
自社のミスに起因して請求書を再発行する場合、相手にとって不要な手間をかけさせることになるため、礼儀をもってお詫びをする必要があります。また、相手が支払期限などで戸惑うことがないように、再発行後の対応についても明確に伝えましょう。
問題が発覚した際には、できるだけ早く電話やメールでミスがあった事実とその内容、今後取るべき対応などを伝えてください。さらに相手に迷惑を及ぼすことにお詫びしたうえで、実際に請求書を送る際にもお詫び状を添えてください。
お詫び状の例文
件名:
請求書の誤記載に関するお詫び
本文:
◯◯株式会社
◯◯部 ◯◯課
◯◯様
いつも大変お世話になっております。
ミソカインボイス株式会社の◯◯です。
先日、お送りさせていただきました請求書(請求書番号:No.◯◯◯◯)に以下の誤りがありました。
誤:○○の個数 ××個
正:△△の個数 ××個
なお、今回の誤記載は商品の名称に関するものであり、請求金額自体には誤りはございません。
上記の誤記載を修正した請求書をお送りいたしますので、ご確認ください。
また、お手元にある旧請求書については、お手数ですが破棄いただけますようお願い申しあげます。
今後はこのようなミスを防ぐため、再発防止に向けた対策を徹底してまいります。
お忙しい中、多大なご迷惑をおかけしてしまい大変申し訳ありませんが、何卒よろしくお願い申しあげます。
ミソカインボイス株式会社
◯◯部 ◯◯
TEL:000-000-000
メールアドレス:xxxx@xxxxxx.com
電子帳簿保存法に関する注意点
請求書の作成や発行に請求書発行システムを利用する企業や個人事業主が増えています。電子発行された請求書は、記載漏れやダウンロード提供期間の終了といった特別な場合を除けば、相手先にデータが保存されているため、再発行が必要となる可能性は低くなります。また、請求書発行システムから印刷した紙の請求書を送付した場合でも、再度プリントアウトすることが容易なため、迅速に対応できます。
2024年1月1日以降は、法人・個人事業主にかかわらず、電子データで発行・受領した請求書を電子取引データとして保存することが義務付けられています。
令和5年度税制改正による改正点
電子帳簿保存法で規定される電子取引のデータ保存について、令和5年度税制改正では以下の2点が変更されました。
- (1)電子帳簿保存法の要件に従えなかった場合
- 電子帳簿保存法では、「真実性の確保」と「可視性の確保」の2つを満たすことが求められます。ただし、以下の条件をすべて満たした場合には猶予措置が適用され、要件に沿わないままでも電子取引データを保存することが認められます。
- 電子取引のデータ保存ができない「相当の理由」があり、所轄税務署長がそれを認めた場合(事前申請は不要)。
- 税務調査などの際に、電子取引データを印刷した書面を提示・提出できること。
- 税務調査などの際に、電子取引データのダウンロード要求に応じられること。
- また、「相当の理由」として認められる主なケースは以下のとおりです。
- 電子帳簿保存法に対応するシステムの整備が間に合わない場合。
- 電子帳簿保存法に沿って必要な電子データを保存するシステムを整えたとしても、マンパワーや資金の不足などで電子帳簿保存法に沿った処理ができなかった場合。
なお、猶予措置が適用される期限については2024年11月時点で未定のため、早めの対応を心がけることが重要です。 - (2)電子帳簿保存法の要件である検索機能がない場合
- 電子取引データには、取引の日付・金額・取引先を検索できる機能が求められます。ただし、以下のいずれかの要件を満たしている場合、税務職員から電子取引データのダウンロード要求があった際にこれに応じられる体制を整えていれば、検索機能がなくても認められます。
- 基準期間の売上高が5,000万円以下である場合。
- 電子取引データをプリントアウトした書面を、取引年月日やその他の日付、取引先ごとに整理された状態で提示・提出できる場合。
また、以上の要件に該当しない場合でも、(1)の要件をすべて満たしている場合は、猶予措置が適用されます。
参照:国税庁「電子帳簿保存法 電子取引データの保存方法をご確認ください」
請求書の再発行手順や管理方法を見直しましょう
請求書は重要な証憑書類の一種であり、発行や受領の機会が多いため、紛失や誤記載が発生するリスクは常に存在します。また、請求書には保存義務があるため、なんらかの問題が生じた場合には迅速かつ適切に対応することが求められます。再発行を行う際には、請求書番号に枝番を付けるなどして再発行であることを明確にし、請求の重複を防ぐ工夫が必要です。
最初に発行した請求書は、電子保存の場合なら修正前のデータをそのまま保存し、「無効」や「キャンセル」などのステータスを付けて区別する方法があります。紙で保存する場合は、再発行前の請求書をスキャンまたはそのままファイリングして保存しておくとよいでしょう。
さらに、請求書はインボイス制度や電子帳簿保存法と密接に関連する書類でもあります。そのため、請求書の発行や管理方法を見直し、制度対応に漏れや誤りがないようにすることが重要です。この機会に、請求書の取り扱い方法を再確認し、より適切な管理体制を整えましょう。
クラウド見積・納品・請求書サービスなら、請求業務をラクにできる
クラウド請求書作成ソフトを使うことで、毎月発生する請求業務をラクにできます。
今すぐに始められて、初心者でも簡単に使えるクラウド見積・納品・請求書サービス「Misoca」の主な機能をご紹介します。
「Misoca」は月10枚までの請求書作成ならずっと無料、月11枚以上の請求書作成の有償プランも1年間0円で使用できるため、気軽にお試しすることができます。
見積書・納品書・請求書をテンプレートでキレイに作成

Misocaは見積書 ・納品書・請求書・領収書・検収書の作成が可能です。取引先・品目・税率などをテンプレートの入力フォームに記入・選択するだけで、かんたんにキレイな帳票ができます。
各種帳票の変換・請求書の自動作成で入力の手間を削減

見積書から納品書・請求書への変換や、請求書から領収書・検収書の作成もクリック操作でスムーズにできます。固定の取引は、請求書の自動作成・自動メール機能を使えば、作成から送付までの手間を省くことが可能です。
インボイス制度(発行・保存)・電子帳簿保存法に対応だから”あんしん”

Misocaは、インボイス制度に必要な適格請求書の発行に対応しています。さらに発行した請求書は「スマート証憑管理」との連携で、インボイス制度・電子帳簿保存法の要件を満たす形で電子保存・管理することが可能です。
確定申告ソフトとの連携で請求業務から記帳までを効率化

Misocaで作成した請求書データは、弥生の確定申告ソフト「やよいの青色申告 オンライン」に連携することが可能です。請求データを申告ソフトへ自動取込・自動仕訳できるため、取引データの2重入力や入力ミスを削減し、効率的な業務を実現できます。
会計業務はもちろん、請求書発行、経費精算、証憑管理業務もできる!
法人向けクラウド会計ソフト「弥生会計 Next」では、請求書作成ソフト・経費精算ソフト・証憑管理ソフトがセットで利用できます。自動的にデータが連携されるため、バックオフィス業務を幅広く効率化できます。

「弥生会計 Next」で、会計業務を「できるだけやりたくないもの」から「事業を成長させるうえで欠かせないもの」へ。まずは、「弥生会計 Next」をぜひお試しください。
この記事の監修者小林祐士(税理士法人フォース)
東京都町田市にある東京税理士会法人登録NO.1
税理士法人フォース 代表社員
お客様にとって必要な税理士とはどのようなものか。私たちは、事業者様のちょっとした疑問点や困りごと、相談事などに真剣に耳を傾け、AIなどの機械化では生み出せない安心感と信頼感を生み出し、関与させていただく事業者様の事業発展の「ちから=フォース」になる。これが私たちの法人が追い求める姿です。