経費精算で使う勘定科目は?仕訳の具体例や注意点を解説
更新
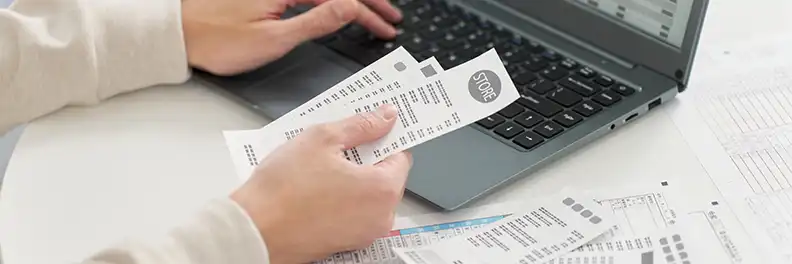
経費精算の際には、適切な勘定科目で仕訳を行わなければなりません。しかし、どの科目を使えばいいのかわからなかったり、仕訳のやり方に不安を感じたりする方もいるのではないでしょうか。勘定科目の正しい理解と運用は、経理処理の正確性はもちろん、経営分析や税務対応にも直結します。
本記事では、経費精算で使う主な勘定科目や、経費精算のときの仕訳例に加え、勘定科目を選ぶ際の注意点などを解説します。
今なら「弥生会計 Next」スタート応援キャンペーン実施中!

会計・経費・請求、誰でもカンタンまとめて効率化!法人向けクラウド会計ソフト「弥生会計 Next」
勘定科目とは、取引を分類・記録するための項目
勘定科目とは、取引の内容を性質ごとに分類するために使う、簿記上の項目のことです。取引で発生するお金の流れについて「何に使ったのか」「なぜ入金があったのか」といった内容を示すラベルのような役割を持っています。
事業を営むうえでは、商品を販売したり、仕入代や各種経費を支払ったりするなど、さまざまなお金の動き(取引)が発生します。すべての取引は、その内容に応じて適切な勘定科目を用い、帳簿に記録しなければなりません。
帳簿に記録する際には、1つの取引を「借方」と「貸方」に分け、それぞれにふさわしい勘定科目をあてはめる「仕訳」を行います。例えば、経費を支出した場合、「何の目的で使ったのか」「どのような性質の支出か」に応じて、該当する勘定科目を選び、記帳します。
さらに、勘定科目は貸借対照表や損益計算書といった財務諸表(決算書)を作成するうえでも欠かせません。財務諸表では、勘定科目ごとに金額を集計し、内容別に分類・記載するため、日々の取引を正しく仕訳しておくことは、正確な決算書の作成にもつながります。
勘定科目についてはこちらの記事で解説していますので、参考にしてください。
会計・経費・請求、誰でもカンタンまとめて効率化!法人向けクラウド会計ソフト「弥生会計 Next」
経費精算で使う主な勘定科目
経費精算とは、会社の事業活動のために従業員が一時的に立て替え、後日会社がその金額を払い戻すしくみです。精算後は、支出の内容に応じて適切な勘定科目を使い、仕訳を行います。ここでは、経費精算で使う主な勘定科目を見ていきましょう。
交通費・旅費交通費
「交通費」「旅費交通費」は、業務のための移動にかかる費用を処理するための勘定科目です。具体的には、電車・バスなどの公共交通機関の運賃のほか、タクシー代、高速道路料金、ガソリン代、宿泊費、出張手当などが含まれます。
業務上の移動は大きく分けて、取引先訪問や仕入・納品のための近距離の移動と、出張などによる遠方への移動の2つです。企業によっては、近距離の移動費を「交通費」、出張にかかる費用を「旅費交通費」として使い分けている場合もあります。
精算時には、訪問先や目的に加え、使用した交通機関、経路、運賃などの情報を明確に記載することが求められます。公共交通機関の利用では領収書が出ない場合も多いため、交通費精算書を用いた処理が一般的です。
旅費交通費についてはこちらの記事で解説していますので、参考にしてください。
会議費・接待交際費
「会議費」は、社内外の会議や打ち合わせに関連する費用を処理するための勘定科目です。例えば、会議室の利用料や弁当代、昼食・夜食代、喫茶代、茶菓子代などが該当します。
「接待交際費」は、取引先や仕入先など、事業に関係する相手との接待や贈答にかかる費用を処理する勘定科目です。中でも、飲食にかかる支出は「接待飲食費」として扱われます。
税法上、法人の接待交際費は原則として損金に算入できません。ただし、資本金1億円以下の中小法人であれば、年間800万円まで、または接待飲食費の50%までのいずれか多い額を損金として計上できる特例が認められています。この制度は、2024年の税制改正により、適用期限が2027年3月31日まで延長されました。一方、資本金1億円超100億円以下の法人は接待飲食費の50%までのみ損金として計上できます。
さらに、1人あたり1万円以下の飲食費については、内容が領収書などで明確になっていれば、「接待交際費」から除外し、「会議費」といった別の科目で処理することも可能です。
このように、「接待交際費」には経費計上の上限がありますが、「会議費」には特に制限が設けられていません。同じ飲食費であっても、性質に応じて適切な勘定科目を選ぶ必要があります。誤って処理した場合、法人税の計算に影響を与える可能性もあるため、注意しましょう。
会議費についてはこちらの記事で解説していますので、参考にしてください。
接待交際費についてはこちらの記事で解説していますので、参考にしてください。
消耗品費・雑費
「消耗品費」は、短期間で使い切る少額の物品を購入した際に用いる勘定科目です。具体的には、「使用可能期間が1年未満、または取得価額が10万円未満の什器や備品の購入費」と定義されています。例えば、帳簿や文房具、コピー用紙、電池などが該当し、こうした支出は「消耗品費」として処理します。
「雑費」は、少額かつ一時的な支出であり、ほかに該当しない場合に使用される勘定科目です。ただし、「雑費」の多用は、経費の内訳が不明瞭となり、事業実態の把握を難しくする可能性もあります。また、税務調査で内容を問われる可能性も高まるため注意しなければなりません。該当する勘定科目が見当たらない場合でも、その支出が高額または継続的であるなら、あいまいにせず、新たに適切な勘定科目を設定しましょう。
消耗品費についてはこちらの記事で解説していますので、参考にしてください。
雑費についてはこちらの記事で解説していますので、参考にしてください。
福利厚生費・通信費・新聞図書費
「福利厚生費」は、従業員の福利厚生に関する支出を処理する勘定科目です。企業が従業員に対して、給与や賞与とは別に提供する、各種サービスまたは保障にかかる費用のことで、勤務中の従業員に提供する飲料の購入費、レクリエーション費用、社員旅行費、慶弔見舞金などが該当します。
また、業務で使用する携帯電話の通話料やインターネットの利用料は「通信費」、業務に関連する書籍や新聞、雑誌の購入費用は「新聞図書費」として区分します。
いずれも私的利用との線引きを明確にし、業務に必要な支出であることが帳簿上から客観的に判断できるように処理しなければなりません。
福利厚生費についてはこちらの記事で解説していますので、参考にしてください。
会計・経費・請求、誰でもカンタンまとめて効率化!法人向けクラウド会計ソフト「弥生会計 Next」
経費精算の仕訳方法
経費精算には、「従業員が立て替えた経費を後で精算する方法」と、「前もって概算の金額を仮払金として従業員に渡しておき、後日実費との差額を精算する方法」があります。
それぞれのケースにおける仕訳例に加え、「領収書・証憑がないときの対処法」についても確認していきましょう。
従業員が立て替えたときの仕訳例
従業員が経費を立て替えた場合は、申請内容が上司や経理部門によって承認されたうえで、会社から払い戻しを行います。経費精算の際には、精算書や領収書などの証憑類の提出が必要です。
万が一、領収書を紛失してしまった場合には、発行元に再発行を依頼するなど、適切な対応を取らなければなりません。帳簿に記載された内容に対する領収書が添付されていないと、消費税の処理に支障をきたすなどの影響が考えられます。
一般的には、立て替えた経費を会社が従業員に支払ったタイミングで仕訳を行います。例えば、交通費を立て替えた場合の仕訳は以下のとおりです。
仕訳例:取引先訪問のために電車代1,200円を従業員が立て替え、精算時に会社が払い戻した
| 借方 | 貸方 | ||
|---|---|---|---|
| 交通費 | 1,200円 | 現金 | 1,200円 |
また、企業によっては経費申請の承認時に未払金計上を行う場合もあります。その場合は、承認時と支払時の2回に分けて仕訳を行います。
仕訳例:業務に使用する文房具3,000円を従業員が立て替えて支払い、経費精算の申請が承認された
| 借方 | 貸方 | ||
|---|---|---|---|
| 消耗品費 | 3,000円 | 未払金 | 3,000円 |
仕訳例:従業員に未払い金を支払った
| 借方 | 貸方 | ||
|---|---|---|---|
| 未払金 | 3,000円 | 現金 | 3,000円 |
このように、仕訳のタイミングや方法は企業の会計方針によって異なりますが、一般的には従業員の支払時に費用計上を行うケースが多いでしょう。
仮払金を利用したときの仕訳例
出張時の旅費交通費など、高額な経費が見込まれる場合には、あらかじめ概算の金額を従業員に渡すことがあります。会社が一時的に支出するお金の勘定科目は、「仮払金」を使うケースが多いです。
従業員に仮払金を支給した場合は、出張などが終了し、用途や金額が確定したタイミングで精算します。実際にかかった費用が仮払金を下回れば差額を返金してもらい、上回った場合は不足分を追加で支払います。
仕訳のタイミングは、「仮払金を渡した時」と「経費精算を行った時」の2回です。
仮払金についてはこちらの記事で解説していますので、参考にしてください。
仕訳例:従業員の出張にあたり、前もって現金10万円を渡した
| 借方 | 貸方 | ||
|---|---|---|---|
| 仮払金 | 100,000円 | 現金 | 100,000円 |
従業員が出張から戻り、経費の用途と金額が確定したら、仮払金からそれぞれ該当する勘定科目へ振り替えて処理します。
仕訳例:新幹線代・ホテル代各3万円、得意先への手土産代8,000円が確定し、残金の3万2,000円について従業員から返金を受けた
| 借方 | 貸方 | ||
|---|---|---|---|
| 旅費交通費 | 60,000円 | 仮払金 | 100,000円 |
| 接待交際費 | 8,000円 | ||
| 現金 | 32,000円 | ||
領収書・証憑がないときの対処法
経費の中には、自動販売機での購入や、取引先への冠婚葬祭に伴う慶弔金の支払いなど、領収書が発行されないケースもあります。そのような場合は、支払日・支払先・金額・内容などの詳細を記載した「出金伝票」を作成すれば、経費として認められることがあります。出金伝票とは、現金支出の事実を記録・証明するための社内書類のことです。
また、領収書を紛失したり破損したりした場合にも、企業によっては出金伝票での代用が認められることもあります。ただし、こうした対応については、あらかじめ社内ルールを明確に定め、全社員に周知しなければなりません。
なお、出金伝票のみで経費を処理する場合は、金額の制限を設けることが重要です。特にインボイス制度のもとで金額によって適格請求書等に該当する領収書の保存が義務付けられているケースへの対応には社内の出金伝票のルールを合わせておく必要があります。
会計・経費・請求、誰でもカンタンまとめて効率化!法人向けクラウド会計ソフト「弥生会計 Next」
経費精算で正しい勘定科目を使うメリット
経費精算をする際には、経費の性質に応じて、正しい勘定科目を設定しなければなりません。経費精算で正しい勘定科目を使うと、以下のようなメリットがあります。
経営状態の把握がしやすくなる
経費を適切な勘定科目で仕訳すれば、どの項目にどれだけお金を使っているかが明確になります。さらに、補助科目や摘要欄を活用すれば、部門別の支出傾向や使途をより具体的に把握することが可能です。
補助科目とは、勘定科目の内訳を管理するために設ける分類項目です。また、摘要は取引の詳細や目的を補足的に記載する欄で、内容をわかりやすくする役割があります。
これらを活用することで、どの部門が何の目的でいくら支出したのかが可視化され、予算管理やコスト削減の計画にもつながります。財務状況を正確に把握できれば、経営分析がしやすくなり、的確な意思決定の助けにもなるでしょう。
税務処理の精度を高められる
経費精算で適切な勘定科目を使用することには、税務処理の正確性を高められるといったメリットもあります。企業の支出が損金に算入できるかどうか、また課税対象に該当するかどうかは、勘定科目の内容に基づいて判断されるためです。
経費精算時に勘定科目を誤って区分すると、法人税などの税額計算に影響を及ぼす可能性があります。例えば、本来「会議費」として処理すべき支出を「接待交際費」で仕訳した場合、損金算入に制限がかかり、その分の税負担が増えることもあります。反対に、接待に該当する費用を「会議費」として処理した場合、税務調査で否認される場合もあるでしょう。
勘定科目はその性質に応じて、「資産」「負債」「純資産」「収益」「費用」の5つに分類されます。決算では、資産・負債・純資産は貸借対照表に、収益・費用は損益計算書にそれぞれ反映されます。法人の決算申告は一般的に税理士へ依頼しますが、税理士とのスムーズな連携のためにも、正確な勘定科目の使用が求められるのです。
共通費用を正しく分類できる
経費精算で正しい勘定科目を使うことにより、複数部門に関わる共通費用を正確に分類できます。備品の購入費や会議費、通信費といった支出は、全社的に利用されることが多いため、明確な配分が難しい場合もあります。しかし、補助科目や摘要を活用すれば、どの部門で使われたのか、どの目的に使われたのかを把握しやすくなるのです。
共通費用を適切に分類・管理できれば、部門や拠点ごとの費用配分(配賦)が明確になり、部門別の損益管理・原価計算の精度も向上するでしょう。さらに、共通費用を一括で整理しておくことで、経理業務の効率化や重複発注の防止にもつながり、結果としてコスト削減にも寄与します。
会計・経費・請求、誰でもカンタンまとめて効率化!法人向けクラウド会計ソフト「弥生会計 Next」
経費精算で勘定科目を選ぶときの注意点
経費精算において、勘定科目を正しく使うことで得られるメリットは多くありますが、そのためには運用上の注意点も押さえておく必要があります。勘定科目を選ぶ際は、以下の点に注意しましょう。
社内でルールを統一する
経費精算で勘定科目を正しく選ぶためには、社内で仕訳ルールを統一しておくことが欠かせません。費用の内容によってどの勘定科目を使うのかがあいまいなままだと、入力ミスや担当者ごとの処理のばらつきが発生しやすくなります。
そのため、勘定科目の分類ルールをあらかじめ明文化し、マニュアルや帳票サンプルと共に、全社で共有する体制を整える必要があります。また、経理処理の一貫性を保つためにも、一度決めた勘定科目の扱いは原則変更せず、継続することが大切です。
会計ソフトと連携しやすい設定を心掛ける
会計ソフトと整合性のある勘定科目設定にしておくことも、注意点の1つとしてあげられます。勘定科目の選択に迷う場面では、会計ソフトにあらかじめ登録されている科目を参考にするのも有効です。これにより、自社のルールと会計ソフトがかみ合い、入力ミスの防止や自動仕訳の活用にもつながります。
ただし、会計ソフトの初期設定がすべての取引に適しているとは限らないため、不明点がある場合は税理士や税務署に相談しながら調整しましょう。
誤分類を防ぐチェック体制を整える
勘定科目の誤分類を防ぐには、社内にチェック体制を設けておくことも大切です。経費の仕訳は財務諸表や税務申告に直結するため、正確性が求められます。
例えば、経理担当者によるダブルチェックや月次レビューなどを業務フローに組み込めば、ミスの早期発見につながるでしょう。また、仕訳時には勘定科目だけでなく、取引先名や用途も併せて記録しておくと、後から内容を確認する際にも役立ちます。
会計・経費・請求、誰でもカンタンまとめて効率化!法人向けクラウド会計ソフト「弥生会計 Next」
会計ソフトなら日々の帳簿付けや決算書作成もかんたん
「弥生会計 Next」は、使いやすさを追求した中小企業向けクラウド会計ソフトです。帳簿・決算書の作成、請求書発行や経費精算もこれひとつで効率化できます。
画面を見れば操作方法がすぐにわかるので、経理初心者でも安心してすぐに使い始められます。
だれでもかんたんに経理業務がはじめられる!
「弥生会計 Next」では、利用開始の初期設定などは、対話的に質問に答えるだけで、会計知識がない方でも自分に合った設定を行うことができます。
取引入力も連携した銀行口座などから明細を取得して仕訳を登録できますので、入力の手間を大幅に削減できます。勘定科目はAIが自動で推測して設定するため、会計業務に慣れていない方でも仕訳を登録できます。
仕訳を登録するたびにAIが学習するので、徐々に仕訳の精度が向上します。

会計業務はもちろん、請求書発行、経費精算、証憑管理業務もできる!
「弥生会計 Next」では、請求書作成ソフト・経費精算ソフト・証憑管理ソフトがセットで利用できます。自動的にデータが連携されるため、バックオフィス業務を幅広く効率化できます。

自動集計されるレポートで経営状態をリアルタイムに把握!
例えば、見たい数字をすぐに見られる残高試算表では、自社の財務状況を確認できます。集計期間や金額の累計・推移の切りかえもかんたんです。
会社全体だけでなく、部門別会計もできるので、経営の意思決定に役立ちます。

「弥生会計 Next」で、会計業務を「できるだけやりたくないもの」から「事業を成長させるうえで欠かせないもの」へ。まずは、「弥生会計 Next」をぜひお試しください。
会計・経費・請求、誰でもカンタンまとめて効率化!法人向けクラウド会計ソフト「弥生会計 Next」
会計ソフトを活用して経費精算の仕訳を効率化しよう
経費精算を正確かつ効率的に行うには、勘定科目の正しい理解と使い分けが欠かせません。仕訳の内容が明確になれば、経営状態や税務上のリスクを把握しやすくなり、企業活動全体の透明性も高まります。交通費や会議費、消耗品費など、日々の支出に応じた勘定科目を適切に使い分けることで、経費の管理はもちろん、損益管理や税務対応の精度も向上します。
経費精算の仕訳を効率化するなら、会計ソフトの利用がおすすめです。取引の内容に応じて自動で仕訳ができたり、帳簿付けの手間を大幅に軽減できたりするうえ、ミス防止にも役立ちます。会計ソフトを上手に活用して、経費精算をはじめとする経理業務の効率化を目指しましょう。
会計・経費・請求、誰でもカンタンまとめて効率化!法人向けクラウド会計ソフト「弥生会計 Next」
【無料】お役立ち資料ダウンロード
「弥生会計 Next」がよくわかる資料
「弥生会計 Next」のメリットや機能、サポート内容やプラン等を解説!導入を検討している方におすすめ

この記事の監修者渋田貴正(税理士、司法書士、行政書士、社会保険労務士)
税理士、司法書士、社会保険労務士、行政書士、起業コンサルタント®。
1984年富山県生まれ。東京大学経済学部卒。
大学卒業後、大手食品メーカーや外資系専門商社にて財務・経理担当として勤務。
在職中に税理士、司法書士、社会保険労務士の資格を取得。2012年独立し、司法書士事務所開設。
2013年にV-Spiritsグループに合流し税理士登録。現在は、税理士・司法書士・社会保険労務士として、税務・人事労務全般の業務を行う。








