従業員の給与の決め方とは?個人事業主が知るべき基本知識と給与計算
更新
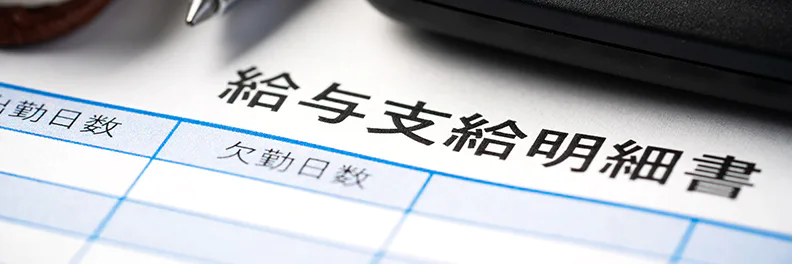
「従業員を雇用できるのは法人だけ」と思っている方もいるかもしれませんが、個人事業主であっても従業員を雇うことは可能です。店舗運営や事業拡大のために、従業員を雇用する個人事業主も少なくありません。個人事業主が従業員を雇用する際に、必ず決めなければならないのが給与額です。とはいえ、1人で事業を行っている個人事業主にとっては、「従業員を雇いたいが、給与の決め方がわからない」と戸惑うことが多いのではないでしょうか。
本記事では、個人事業主が初めて従業員を雇用する場合に知っておきたい給与の決め方や給与の計算方法、必要な手続きなどについて解説します。
【無料で資料ダウンロード】「弥生給与 Next」でバックオフィス業務をスムーズに
今なら「弥生給与 Next」スタート応援キャンペーン実施中!

無料お役立ち資料【「弥生給与 Next」がよくわかる資料】をダウンロードする
従業員の給与を決めるときの基本的な流れ
従業員を雇用する場合、給与額の設定は重要な課題の1つです。一度決めた給与は、事業主の都合で一方的に減額することは、本人の同意がなければ認められません。そのため、従業員の給与を決めるときには、法律で定められたルールを守りつつ、継続して支払える金額かどうかを十分に検討する必要があります。
個人事業主が初めて従業員を雇用する際には、次の流れに沿って給与額を決めていくとよいでしょう。
1. 給料の相場を調べる
まずは、自分が従業員に任せようと思っている仕事の、給与相場を把握することが大切です。例えば、店舗スタッフを募集したいと考えているなら、求人雑誌や求人サイトで、同じ地域、規模、職種の店舗が設定している給与額を調べてみましょう。
相場を下回る水準で従業員を募集すると、人材を確保することが難しくなるかもしれません。反対に、相場より高すぎる水準では、次に雇い入れる従業員も同水準以上で雇い入れることが必要になるため将来的な事業経営に悪影響を及ぼす可能性があります。
2. 最低賃金を下回らないように注意する
従業員の給与を決める際には、最低賃金を下回らないように注意が必要です。最低賃金とは、最低賃金法に基づき国が定めた賃金の最低限度額のことです。企業は従業員に対して、必ず最低賃金以上の賃金を支払わなければなりません。
最低賃金には、都道府県ごとに定められた「地域別最低賃金」と、特定の産業を対象にした「特定(産業別)最低賃金」があり、両方に該当する場合は高い方の賃金額以上を支払います。
従業員に支払う給与が地域別最低賃金を下回った場合には最低賃金法により50万円以下の罰金、特定(産業別)最低賃金を下回った場合は労働基準法により30万円以下の罰金と、それぞれ罰則の対象となります。
また、最低賃金は毎年10月前後に改定されるため、最新情報を定期的にチェックしましょう。
3. 残業代や有給休暇の影響を考える
従業員に支払う給与は基本給だけではありません。給与を決めるときには、残業代や有給休暇の影響についても考えておく必要があります。
厚生労働省「毎月勤労統計調査 令和4年分結果確報」によれば、一般労働者の月間の平均残業時間は13.8時間、パートタイム労働者は2.2時間です。残業が発生すれば、残業時間に応じた残業代を支払わなければなりません。もし、法定労働時間(1日8時間・週40時間)を超えて残業を行った場合は、通常賃金の1.25倍以上の割増賃金(時間外手当)を支払う必要があります。
また、労働基準法によって、6か月以上継続勤務し、全労働日の8割以上出勤した労働者には、所定日数の年次有給休暇を使用することができる権利が付与されます。これはパートやアルバイトも対象になります。従業員が年次有給休暇を取得すると、実際に働いていなくても給与支払いの義務が生じるため、その金額も人件費として考慮しておくことが大切です。
パートやアルバイトの有給休暇に関する賃金の計算方法についてはこちらの記事で解説していますので、参考にしてください。
4. 社会保険料など給与以外の支出を考える
社会保険とは、「厚生年金保険」「健康保険」「介護保険」「雇用保険」「労災保険」のことです。ただし、一般的には厚生年金保険、健康保険、介護保険の3つを狭義の「社会保険」と呼び、雇用保険と労災保険を「労働保険」と呼びます。
なお、労働保険は、原則として従業員を雇用するすべての事業主が対象です(農林水産業の一部を除く)。特に、労災保険は従業員を1人でも雇用したら必ず加入しなければならず、保険料は全額事業主負担です。従業員が雇用保険の加入要件を満たす場合は、雇用保険料は従業員と事業主の双方で負担しますが、負担割合は事業主の方が大きくなっています。
また、個人事業主でも、所定の要件を満たした場合は、社会保険(厚生年金保険・健康保険・介護保険)の適用事業所(対象事業者)です。従業員が社会保険の加入要件を満たした場合は、従業員と事業主が半分ずつ保険料を負担します。
従業員を雇用する際には、社会保険料の事業主負担分についてもしっかり把握しておくことが大切です。加えて、通勤手当や実費精算となる制服代、消耗品代といった給与以外の細かい支出についても考えておきましょう。
社会保険についてはこちらの記事で解説していますので、参考にしてください。
【無料で資料ダウンロード】「弥生給与 Next」でバックオフィス業務をスムーズに
従業員に支払う給与の計算方法
従業員に支払う給与の金額は、総支給額から控除額を差し引いて算出する差引総支給額です。計算式は以下のとおりです。
給与計算の計算式
差引総支給額(手取り額)=総支給額−控除額
ここからは、総支給額と控除額の算出に必要な項目を解説します。
総支給額の計算に必要な項目
給与計算は、勤怠情報を基に計算した給与額に割増賃金や各種手当を加算し、総支給額を求めます。総支給額の計算に必要な項目は、以下のとおりです。
勤務時間
タイムカードや出勤簿を確認して、出勤日数や有給休暇取得状況、欠勤日数、遅刻・早退の有無・時間数、労働時間、残業時間などの勤怠情報を確認します。
この勤怠情報がしっかり管理されていないと、給与計算を正しく行うことができません。タイムカードやクラウド形式の勤怠管理システムなどを活用し、勤怠を正しく管理するようにしましょう。
割増賃金
割増賃金には「時間外労働」「所定休日・法定休日労働」「深夜労働」等があり、それぞれ割増率が定められています。
従業員に割増賃金の対象になる労働をさせた場合は、1時間当たりの基礎賃金にそれぞれの割増率を掛けて割増賃金を計算します。
各種手当
通勤手当や資格手当など、独自に手当を設定している場合は、その金額を計算します。特に通勤手当は、通勤経路や手段によって一人ひとり計算が変わるので注意が必要です。
控除額の計算に必要な項目
従業員の給与から控除するものは、主に以下のとおりです。
社会保険料(厚生年金保険、健康保険、介護保険、雇用保険)
厚生年金保険、健康保険、介護保険、雇用保険に加入している従業員については、各保険料の従業員負担分を計算します。厚生年金保険料、健康保険料、介護保険料は従業員ごとの標準報酬月額(社会保険料を算出しやすくするために、従業員の月々の給料を特定の範囲ごとに区分したもの)、雇用保険料は従業員に支給する給与額を基に算出されます。
社会保険についてはこちらの記事で解説していますので、参考にしてください。
所得税ならびに復興特別所得税
従業員の所得税(所得税および復興特別所得税)は、給与から差し引き、本人に代わって事業主が国に納めなければなりません。個人事業主であっても、従業員を雇っていれば源泉徴収義務があります。源泉所得税の額は、従業員の社会保険料控除後の給与の課税対象額や扶養親族等の数に応じて、「給与所得の源泉徴収税額表(月額表)」より計算します。
源泉所得税についてはこちらの記事で解説していますので、参考にしてください。
住民税
住民税の特別徴収とは、従業員が納付すべき住民税を、事業主が毎月の給与から控除し、本人の代わりに納付する方法です。毎年1月末までに従業員が居住する市区町村に「給与支払報告書」を提出すると、前年の所得に基づいて市区町村が住民税を計算し、事業主に通知されるので、事業者はその金額を給与から控除します。
住民税についてはこちらの記事で解説していますので、参考にしてください。
【無料で資料ダウンロード】「弥生給与 Next」でバックオフィス業務をスムーズに
給与額と合わせて確認・準備が必要なこと
従業員を雇用する際には、給与額の決定と併せて、社会保険や法定三帳簿などさまざまな準備が必要です。特に初めて従業員を雇う場合、下記の確認事項を見落とさないように注意しましょう。
賃金支払いの五原則の遵守
労働基準法第24条により、賃金は「通貨で」「労働者に直接」「全額を」「毎月1回以上」「一定の期日を定めて」支払わなければならないと定められています。これを「賃金支払の五原則」といいます。従業員に給与を支払うときには、この五原則を守らなければなりません。
賃金についてはこちらの記事で解説していますので、参考にしてください。
法定三帳簿の作成と管理
法定三帳簿とは、「労働者名簿」「賃金台帳」「出勤簿」のことです。従業員を1人でも雇い入れたら、必ず法定三帳簿を作成しなければなりません。
法定三帳簿は、それぞれ営業所や店舗、工場などの事業場ごとに個人別に作成し、原則として5年間の保存が義務付けられています。従業員を雇用する際には、法定三帳簿の作成準備も忘れずに行っておきましょう。
労働条件の通知
従業員を雇用する際、事業主は必ず「労働条件通知書」を作成して交付しなければなりません。労働条件通知書は、給与や勤務時間などの労働条件が明記された書類で、労働基準法によって雇用する側の事業主が労働者に交付することが義務付けられています。
労働条件通知書に決まった形式はありませんが、厚生労働省「主要様式ダウンロードコーナー(労働基準法等関係主要様式)」からテンプレートのダウンロードが可能です。
また、従業員を雇用するときに取り交わす「雇用契約書」という書類もあります。雇用契約書に法的な作成義務はありませんが、後々の不要なトラブルを避けるためにも、従業員の入社時に取り交わすことが一般的です。
なお、事業主は、労働条件通知書や雇用契約書といった労働関係書類を、従業員が退職または死亡してから5年間保管する義務があります。
社会保険関係への加入準備
従業員を雇用すると、原則として労働保険(雇用保険・労災保険)に加入しなければなりません。また、要件を満たした場合は、社会保険(厚生年金保険・健康保険・介護保険)の加入義務が生じます。これら社会保険関係の加入要件と準備についても、しっかり確認しておきましょう。
労働保険(雇用保険・労災保険)
雇用保険と労災保険は、原則として従業員を雇用するすべての事業主が対象となります。初めて従業員を雇用するときは、所轄の労働基準監督署に労働保険の「保険関係成立届」と「概算保険料申告書」など、所轄のハローワークに「雇用保険適用事業所設置届」と「雇用保険被保険者資格取得届」などを提出して労働保険の手続きを行います。
社会保険(厚生年金保険・健康保険・介護保険)
5人以上の従業員を雇用している個人事業主は、一部業種を除き、社会保険の加入義務のある強制適用事業所となります。また、強制適用事業所に該当しなくても、従業員の半数以上の同意があれば、任意で適用事業所になることもできます。
新たに適用事業所になった際は、5日以内に所轄の年金事務所宛に「健康保険・厚生年金保険 新規適用届」提出が必要です。
税務署に給料支払事務所等の開設の届出を提出する
初めて従業員を雇用する際には、納税地を所轄する税務署へ「給与支払事務所等の開設届出書」の提出が必要です。この届出書は所得税の源泉徴収を行うために必要な書類で、提出期限は雇用した日から1か月です。「給与支払事務所等の開設届出書」の用紙は、国税庁「A2-7 給与支払事務所等の開設・移転・廃止の届出」からダウンロードでき、e-Taxでの提出も可能です。
給与支払事務所等の開設届出書についてはこちらの記事で解説しています。
労働基準監督署へ就業規則の届出
就業規則とは、従業員の賃金や労働時間などの労働条件、事業所内の服務規律など雇用に関するルールをまとめた書面のことをいいます。
1つの事業場において常時10人以上の従業員を雇用する場合は、労働基準法の規定により「就業規則」を作成し、所轄の労働基準監督署への届出が義務付けられていますので注意しましょう。
【無料で資料ダウンロード】「弥生給与 Next」でバックオフィス業務をスムーズに
従業員の給与処理に関する注意
従業員を雇用した後は、従業員に支払う給与や事業主負担分の社会保険料などを正しく帳簿に記録し、適切な税務処理を行わなければなりません。また、従業員を雇用すると、所得税(所得税および復興特別所得税)の源泉徴収や住民税の特別徴収の義務が生じます。
従業員の給与を処理する際には、次の点に注意が必要です。
所得税の源泉徴収、住民税の特別徴収を原則として行う必要がある
源泉徴収した所得税と住民税は、原則として、給与を支払った月の翌月10日までに国に納付しなければなりません。源泉所得税を期限までに納めないと、ペナルティとして不納付加算税の対象になるため注意しましょう。
なお、給与を支払う人数が常に10人未満である場合、あらかじめ税務署に申請すれば、半年分の源泉所得税をまとめて納付できる「源泉所得税の納期の特例」があります。
また、従業員に最初の給与を支払う日の前日までに「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」を提出してもらい、年末には年末調整を行う必要があります。
給料賃金として帳簿に計上する
従業員に支払った給与は「給料賃金」、事業主負担分の社会保険料は「法定福利費」として経費計上が可能です。給与などを支払ったときには、日々の取引と同様に帳簿に記録し、適切に処理しましょう。なお、社会保険料には法定福利費のほかに、従業員負担分の「預り金」もありますが、これらを正確に仕訳することが大切です。帳簿を正確につけることは、確定申告や税務調査においても重要です。
なお、家族を従業員とした場合は、所定の要件を満たせば、青色申告なら青色事業専従者給与、白色申告なら事業専従者控除を適用できます。
【無料で資料ダウンロード】「弥生給与 Next」でバックオフィス業務をスムーズに
従業員の給与を計算するなら給与計算ソフトで作成・保存すれば効率的
個人事業主が従業員を雇うと、給与計算や帳簿付けに多大な手間がかかります。さらに、給与から控除される所得税や住民税、社会保険料などについても、手作業で計算していると時間がかかり、本業を圧迫しかねません。
煩雑な給与計算をスムーズに行うには、給与計算ソフトの導入がおすすめです。自社に合った給与計算ソフトで、給与計算業務を効率化しましょう。
【無料で資料ダウンロード】「弥生給与 Next」でバックオフィス業務をスムーズに
「弥生給与 Next」で給与・勤怠・労務をまとめてサクッとデジタル化
弥生給与 Nextは、複雑な人事労務業務をシームレスに連携し、効率化するクラウド給与サービスです。
従業員情報の管理から給与計算・年末調整、勤怠管理、保険や入社の手続きといった労務管理まで、これひとつで完結します。
今なら「弥生給与 Next」 スタート応援キャンペーン実施中です!
この機会にぜひお試しください。
この記事の監修者税理士法人古田土会計
社会保険労務士法人古田土人事労務
中小企業を経営する上で代表的なお悩みを「魅せる会計事務所グループ」として自ら実践してきた経験と、約3,000社の指導実績で培ったノウハウでお手伝いさせて頂いております。
「日本で一番喜ばれる数の多い会計事務所グループになる」
この夢の実現に向けて、全力でご支援しております。
解決できない経営課題がありましたら、ぜひ私たちにお声掛けください。必ず力になります。







