給与計算でミスが発覚したら?対処法とリスク、防止策を解説
更新
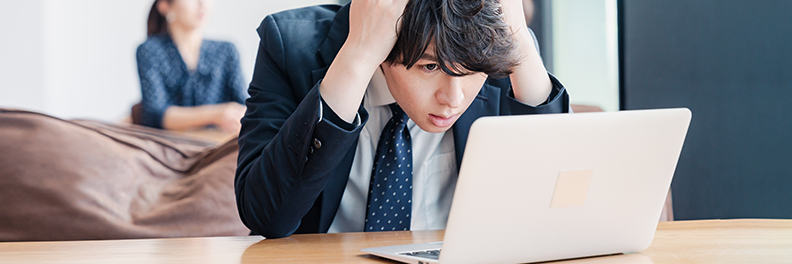
従業員に支払う給与の計算は、ミスがないように細心の注意を払わなければなりません。しかし、人の手で給与計算を行っていると、気を付いていてもミスが起こってしまうときはあります。
本記事では、給与計算にミスがあったときの対処法や、給与計算のミスによって起こりうるリスク、給与計算のミスを防ぐ方法などについて解説します。
【無料で資料ダウンロード】「弥生給与 Next」でバックオフィス業務をスムーズに
無料お役立ち資料【「弥生給与 Next」がよくわかる資料】をダウンロードする
給与計算でミスが発覚したときの対処法
基本的に、給与計算のミスは発生しないことが前提です。しかし、手作業で給与計算を行っている場合や、雇用条件など給与に関わる変更があった場合は、計算時にミスが起こることもあります。給与計算のミスに気がついたときは、どう対処すればいいのでしょうか。
給与計算でミスが発覚したときの対処法を、順を追って確認していきましょう。
1. 従業員に説明とお詫びをする
給与計算のミスが発覚したら、当該の従業員に対して、すぐに説明とお詫びの連絡をします。
連絡の際は、ていねいな謝罪に加えて「◯月◯日の残業代が反映されていなかった」など間違いのあった箇所を明確にし、「差額は◯月分の給与支給において調整する」など具体的な対応方法を明示します。そして、今後はミスが発生しないよう、是正策とチェックを徹底する旨を真摯に伝えましょう。
2. 給与明細を訂正する
給与計算のミスを従業員本人に連絡すると同時に、ミスのあった給与明細の訂正を行い差し替えます。特に、基本給をはじめ、通勤手当などの各種手当、経費の立替金といった支給項目は、源泉徴収される所得税額や雇用保険料にも影響する場合があるため注意が必要です。
また、給与から控除する社会保険料にミスがあると、年末調整時の所得税額に影響します。給与計算のミスに気づかないまま所得税を納めてしまうと、修正手続きが必要になってしまうため、できるだけ早く給与計算を訂正しましょう。
給与明細についてはこちらの記事で解説していますので、参考にしてください。
3. 給与の過不足分を精算する
従業員本人への謝罪と給与明細の訂正が終わったら、給与の過不足分を精算します。ミスによって給与を多く支払った場合と、少なく支払っていた場合では、対処法が異なります。
過払い時は当月から翌月支給日までに調整する
労働基準法第24条では、「賃金は、通貨で、直接労働者に、その全額を支払わなければならない」「賃金は、毎月一回以上、一定の期日を定めて支払わなければならない」と定められています。この「全額支払いの原則」により、たとえ給与を多く支払ってしまったときでも、当月中に調整することが望ましいです。
なお、給与の過払い時には、源泉所得税や雇用保険料などの控除額も、本来の金額より多くなっている可能性があります。控除額を考慮して正しく計算したうえで、過払い分を従業員から現金で返金してもらうか、翌月支給する給与から差し引きます。
不足時は当月内にすみやかに調整する
従業員に支給した給与が不足していたときは、上述した全額支払いの原則により、当月中のすみやかな調整が必要です。実務的には、翌月の給与で精算する場合がありますが、この場合には本人に了承を得るため、労使協定の締結の確認をしておきましょう。
【無料で資料ダウンロード】「弥生給与 Next」でバックオフィス業務をスムーズに
支給額不足は労基法違反に問われるリスクも
給与計算ミスによって起こる大きなリスクが、会社が労働基準法違反を問われることです。給与計算ミスによって過払いとなった場合には、法律違反になりません。しかしその一方で、故意ではなかったとしても、給与計算ミスによって支給額が不足して給与未払いとなれば、労働基準法に違反してしまいます。
これは、労働基準法においては、30万円以下の罰金の対象となります。
また、給与や賞与などの未払いには、遅延損害金が発生します。さらに、時間外・休日・深夜の割増賃金の未払いで従業員が裁判を起こした場合、裁判所から付加金(未払い金と同一額)の支払いを命じられることもありますので注意が必要です。
また、給与計算ミスで給与額が本来より多かったり少なかったりすると、正しい納税ができなくなるリスクもあります。正しく納税ができなければ、従業員への損害だけではなく、企業としての信用問題にも関わります。
【無料で資料ダウンロード】「弥生給与 Next」でバックオフィス業務をスムーズに
給与計算で起こりやすいミス
ここからは、給与計算でミスが起こりやすい事例について紹介していきます。以下のようなシーンではミスが発生しないように、特に注意を払いましょう。
時間外勤務の割増賃金
従業員が残業や休日出勤、深夜労働などを行ったときは、会社は割増賃金を支払わなければなりません。割増賃金はただ多ければいいというわけではなく、法律により定められた計算方法があります。割増賃金の割増率は、労働を行った日や時間帯などでも変動するため、計算ミスが起こりやすくなります。
割増賃金についてはこちらの記事で解説していますので、参考にしてください。
扶養家族を外れたときの所得税への反映漏れ
従業員に税法上の扶養家族がいると、扶養人数に応じた一定の金額が年間所得から控除されます。しかし、「子供が就職した」「配偶者の収入が増えた」などの理由で、それまで扶養対象だった家族が扶養を外れると、税法上の扶養控除は受けられなくなります。従業員から家族が扶養を外れた申告があったにもかかわらず、会社のミスで反映ができていないと、給与から源泉徴収される所得税の額にも影響を及ぼしてしまいます。
もしも反映漏れがあった場合は、年末調整で対応することも可能です。ただし、ミスに気づかないまま年末調整を終え、源泉徴収票を発行してしまうと、その後の修正に大変な手間がかかりますので、社内での対応が難しそうなときには、税理士など専門家に相談することをおすすめします。
各種手当の反映漏れ
会社によっては、役職に応じた役職手当など、基本給に加えて各種手当が支給されるケースもあります。社内人事や、手当の仕組みなどを給与計算の担当者が正しく把握していないと、手当の支給額の変動を給与に反映できず、ミスが生じてしまいます。
介護保険料の控除漏れ
介護保険料の徴収漏れが、給与計算ミスを招くケースもあります。
40歳以上の従業員については、健康保険料に加えて、介護保険料も給与から徴収しなければなりません。介護保険料は原則として、40歳になる誕生日の前日を含む月から徴収を行います。誕生日が1日の人は、誕生月ではなく、その前月から徴収することになるため注意が必要です。
また、介護保険料は、基本的に3年ごとに改訂が行われます。
介護保険料についてはこちらの記事で解説していますので、参考にしてください。
月途中退職者の社会保険料控除
社会保険料は、「被保険者の資格を喪失した月の前月」(退職日の翌日が属する月の前月)までの分を徴収するルールです。日割り計算はせず、月単位で徴収します。そのため、月の途中で従業員が退職した場合、退職月の社会保険料は控除対象になりません。誤って退職月分の社会保険料を差し引いた場合には、速やかに過徴収した保険料を返金しなければなりません。
なお、月の末日に退職した場合は、翌月1日が資格喪失日となるため、退職月分までの社会保険料控除が必要です。
社会保険料についてはこちらの記事で解説していますので、参考にしてください。
【無料で資料ダウンロード】「弥生給与 Next」でバックオフィス業務をスムーズに
給与計算のミスを防ぐには?
給与計算には、ミスが起こりやすい場面が多々あります。さらに近年では、リモートワークやフレックスタイム制など働き方の多様化により、勤怠管理が複雑で難しくなっています。
そのような中、手作業で給与計算をしていると、毎月変化する状況に対応しきれず、どうしてもヒューマンエラーが発生しやすくなるもの。では、給与計算のミスを防ぐには、どのような対策をとればいいのでしょうか。
チェック体制の見直し
給与の計算には、割増賃金や各種手当、控除など、ミスをしやすいポイントがたくさんあります。ミスをしてしまってもすぐに気づけるように、社内のチェック体制を整備しましょう。
ミスが起こりやすいポイントを中心にチェックリストを作成し、ダブルチェック、トリプルチェックの体制を整えるのがおすすめです。
給与計算のアウトソーシングを活用
給与計算は、社会保険労務士(社労士)や税理士といった専門家に依頼することが可能です。社内の人材やリソースの問題で、給与計算の人為的ミスを防ぐのが難しい場合、専門家に依頼することで、ミスのリスクと自社の業務負担を同時に軽減できるでしょう。
ただし、給与計算のアウトソーシングにはコストがかかるうえ、自社にノウハウが蓄積されないなどのデメリットもあります。メリットとデメリットの両方を比較検討したうえで、アウトソーシングするかどうかを決めてください。
給与計算のアウトソーシングについてはこちらの記事で解説していますので、参考にしてください。
給与計算ソフトを活用
「できるだけコストをかけずにミスなく給与計算をしたい」「従業員数がそれほど多くないので、給与計算は社内で行いたい」といった場合は、給与計算ソフトを活用するのもひとつの方法です。初心者でもかんたんに使える給与計算ソフトを活用すれば、人為的ミスを抑えながら効率良く給与計算を進めることができるでしょう。
また、給与計算ソフトは法改正にも自動的に対応するため、保険料改定などの最新情報をわざわざ担当者がチェックする必要がなく、反映漏れも防ぐことができます。特に、中小規模の法人の場合は、給与計算をアウトソーシングするより、給与計算ソフトを使って自社で対応するほうが、コストを抑えられる可能性があります。
【無料で資料ダウンロード】「弥生給与 Next」でバックオフィス業務をスムーズに
給与計算ミスを防ぐツールの活用という選択肢
給与計算ミスによって賃金未払いになってしまうと、労働基準法違反になるなど大きなリスクがあります。たとえ過払いであっても、後日従業員から払いすぎた給与を返還してもらうなど、手続きが煩雑となります。給与計算にミスが発生したときには、迅速な対応が求められますが、そもそもミスが起こらないようにすることが重要です。
しかし、人の手で給与計算を行っていると、計算間違いや控除漏れなど、どうしてもミスが起こりやすくなります。給与計算のミスを防ぐには、給与計算ソフトなどの便利なツールを活用するという選択肢もあります。
給与の計算や管理をミスなく行うには、弥生の給与計算サービス「弥生給与 Next」の導入がおすすめです。自社に合った給与計算ソフトで、ミスなく効率的に給与計算を行いましょう。
【無料で資料ダウンロード】「弥生給与 Next」でバックオフィス業務をスムーズに
「弥生給与 Next」で給与・勤怠・労務をまとめてサクッとデジタル化
弥生給与 Nextは、複雑な人事労務業務をシームレスに連携し、効率化するクラウド給与サービスです。
従業員情報の管理から給与計算・年末調整、勤怠管理、保険や入社の手続きといった労務管理まで、これひとつで完結します。
今なら、すべての機能を最大2か月間無料で利用できます!
この機会にぜひお試しください。
この記事の監修者税理士法人古田土会計
社会保険労務士法人古田土人事労務
中小企業を経営する上で代表的なお悩みを「魅せる会計事務所グループ」として自ら実践してきた経験と、約3,000社の指導実績で培ったノウハウでお手伝いさせて頂いております。
「日本で一番喜ばれる数の多い会計事務所グループになる」
この夢の実現に向けて、全力でご支援しております。
解決できない経営課題がありましたら、ぜひ私たちにお声掛けください。必ず力になります。








