飲食店の領収書はなぜ必要?書き方や発行時の注意点、インボイス対応を解説
監修者: 高崎文秀(税理士)
更新
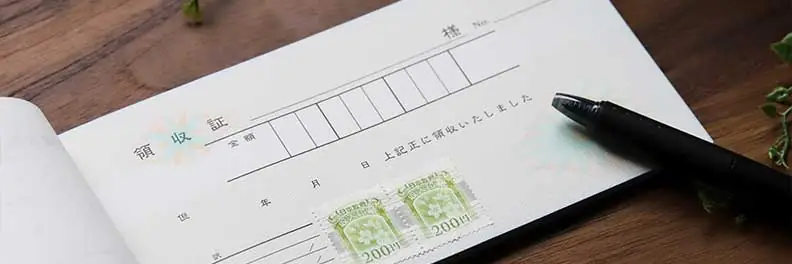
飲食店の領収書は、顧客対応や経理処理で重要になる書類です。特に2023年(令和5年)10月から始まったインボイス制度(適格請求書等保存方式)により、「飲食店の領収書には何を記載すべきか」「簡易インボイスで問題ないのか」など、発行時のルールや注意点を正しく理解する必要があります。
本記事では、小規模飲食店の経営者・従業員の方向けに、「領収書の正しい書き方」「収入印紙や印鑑の必要性」「再発行の可否」「インボイス制度への対応」など、よくある疑問を解説します。経費精算や税務調査でトラブルにならないよう、今一度知識を整理しましょう。
無料【クラウド請求書作成ソフト「Misoca」がよくわかる資料】をダウンロードする
飲食店の領収書はなぜ必要?
領収書は、飲食代金を受け取った事実を証明するための書類です。飲食店に限らず、売買契約での金銭の授受があった際は、領収書の交付を求められます。民法486条でも、以下のように定められています。
弁済をした者は、弁済を受領した者に対して受取証書の交付を請求することができる
-
引用:e-Gov法令検索「(受取証書の交付請求)第四百八十六条
」
一般的にレシートでも問題ありませんが、感熱紙は時間がたつと文字が消えやすくなるのが難点です。このような理由から、企業や団体の経費精算では、領収書の提出を求められる場合もあるでしょう。
さらには2023年からスタートしたインボイス制度(適格請求書等保存方式)により、一定の要件を満たした領収書が必要とされるケースも増えています。適格請求書発行事業者として登録した飲食店には、顧客に求められた場合、インボイスを交付する義務があります。飲食店は領収書を求められる機会も多いため、インボイス登録を行っておく方が無難です。
手書きの領収書は、「税率記載なし」「登録番号なし」「但し書きの記入漏れ」など、形式的な不備が出やすくなりがちです。最近では、手書き領収書を廃止する飲食店も増えています。こうした背景もあり、領収書の正しい書き方を知る必要があります。
【1年間無料】フリーランスの見積・請求・申告は「Misoca×やよいの青色申告 オンライン」セットがお得!
飲食店の領収書に記載する項目と書き方
飲食店が領収書を発行する際は、記載すべき基本項目があります。領収書に適切な情報が記載されていない場合、受領者は経費として認めてもらえずに不利益を被る可能性があるため注意が必要です。以下で、領収書に記載すべき項目ごとに、正しい書き方のポイントを解説します。
領収書の詳しい書き方については、以下の記事で解説していますので参考にしてください。
①日付 ※インボイス必須
領収書の日付欄には、飲食した日付や来店日ではなく、「実際に代金を受け取った日」を記載します。特に注意すべきなのは、支払日が月末や年度末に近い場合です。
会計処理では、会計年度を境に取り扱いが異なります。例えば、3月31日を決算日とする企業の場合、3月31日までは前期の経費、4月1日以降は当期の経費となります。顧客側の経費計上時期にも影響するため、日付の誤記には十分注意しましょう。
②宛名 ※インボイス必須
宛名は、領収書の信頼性を高めるための重要な情報であり、インボイスに記載が必要な情報です。法人の場合は、「株式会社〇〇」「有限会社〇〇」といった正式名称を記載するのが基本です。略称や通称、グループ名だけで記載するのは避けましょう。ただし、簡易インボイスの発行が認められている飲食店の場合、宛名の記載がなくても問題ありません。簡易インボイスのレシートもよいか確認をすると丁寧ですね。
宛名は必須ではなく、要望があれば空欄や「上様」表記でも領収書としては成立します。
しかし領収書の宛名が適切に記載されていないと、顧客が経費として計上できなかったり、税務調査で問題視されたりと思わぬトラブルが発生する可能性があります。飲食店としては、宛名の記載を求められたら、名刺を見せてもらったり、メモ紙などに名前を書いてもらって確認するなどをして、できるだけ正確な宛名を記載する姿勢が大切です。
③発行者名 ※インボイス必須
領収書には、代金を受け取った「発行者名」の記載が必須です。飲食店であれば、店舗名(屋号)に加えて、店舗の所在地(住所)、連絡先(電話番号)、代表者名を記載するのが一般的です。上記の情報によって、発行者がだれであるかが明確になり、トラブル防止につながります。
発行者情報は、手書きで記載しても問題ありませんが、毎回同じ情報を記入するのは手間がかかります。そのため、店舗名・住所・電話番号・代表者名・登録番号などをまとめたゴム印(スタンプ)を用意すると、記載漏れの防止につながるほか、作業効率も大幅に向上します。
④金額 ※インボイス必須
領収書に記載する金額は、記入ミスや不正利用を防ぐために、以下のような形式で記載するのが一般的です。
-
- 金額の冒頭には「¥(円マーク)」を入れる
- 3桁ごとにカンマで区切る
- 金額の末尾に「-」または「也(なり)」を付ける
飲食店では「1グループ全体に対する領収書」だけでなく、「人数分で領収書をわける」対応を求められるケースもあります。「分割領収書」の発行も問題ありませんが、会計金額と合致していることが前提となります。不正な経費精算を防ぐためにも、正確に金額を記載し、必要に応じて明細を添付するのが理想です。
⑤但し書き
但し書きとは、受け取った金額がどのような目的の支払いに対するものかを示すための記載欄です。飲食店であれば、「御食事代として」「御飲食代として」「接待飲食費として」などのように、用途を簡潔に記載します。
テイクアウト商品に対して領収書を発行する場合は、「御品代として」や「お弁当代として」と記載するのが一般的です。用途に応じた但し書きを記載すれば、相手方の経理処理にも配慮した領収書になります。インボイスの場合は、但し書きで軽減税率の対象品目であることを明確に示さなければなりません。
-
参照:国税庁「インボイス記載事項
」
⑥収入印紙
飲食店で領収書を発行する際、受領金額のうち、消費税を含めない額が5万円以上となる場合は、収入印紙の貼付が必要です。売上代金が5万円以上〜100万円以下の領収書には、200円分の収入印紙を貼り、さらに割印を行う必要があります。
ただし支払方法によっては、印紙が不要になるケースもあります。例えばクレジットカードは「信用取引」になるため、現金の受領には該当せず、印紙税の課税対象とはなりません。クレジットカードで支払われた場合、たとえ5万円以上の領収書でも収入印紙の貼付は不要です。
収入印紙に関する詳しい基準や貼り方、消印の方法は、以下の記事で詳しく解説していますので参考にしてください。
-
参照:国税庁「No.7124 消費税額等が区分記載された契約書等の記載金額
」
また、コード決済の場合は加盟店契約などの内容によって印紙税の要不要が異なります。詳しくは以下の国税庁サイトをご確認ください。
-
参照:国税庁「コード決済サービスを利用して決済を行った者に交付する領収書
」
【1年間無料】フリーランスの見積・請求・申告は「Misoca×やよいの青色申告 オンライン」セットがお得!
飲食店は簡易インボイスの発行が可能
インボイス制度が導入され、飲食店でも対応が求められるようになりました。ただし場合によっては、「簡易インボイス」と呼ばれる簡略様式での発行が認められています。以下、簡易インボイスの概要と飲食店での対応方法を解説します。
簡易インボイスとは
簡易インボイスとは、不特定多数の消費者に対して、反復的に商品・サービスを提供する業種に認められている形式です。例えば飲食店や小売店、タクシー業などがその対象とされています。
通常のインボイスでは、「税率ごとの消費税額」「宛名」など、詳細な情報の記載が必要です。しかし簡易インボイスでは、項目の一部を省略できます。通常の手書き領収書と比べて、記載漏れのリスクが低く、スムーズな対応が可能です。
なお、簡易インボイスを発行するためには、飲食店が「適格請求書発行事業者」として登録を済ませている必要があります。飲食店側の事務負担を軽減しつつ、顧客側も仕入税額控除が受けられるため、双方にとってメリットのある形式です。
簡易インボイスに記載する項目
飲食店で簡易インボイスを発行する場合には、以下の項目を漏れなく記載する必要があります。
- 【①適格請求書発行事業者の氏名または名称および登録番号】
- 国税庁から交付された「T」から始まる13桁の登録番号と、店舗名(または法人名)を明記します。
- 【②取引年月日】
- 会計が行われた日付を記載します。
- 【③取引内容】
- 飲食代、テイクアウト代などの具体的な内容を記載します。軽減税率(8%)の対象となる品目が含まれる場合はその旨を明記してください。
- 【④税率ごとに区分して合計した対価の額(税抜または税込)】
- 10%対象分と8%対象分が混在する場合、それぞれの税込または税抜金額を分けて記載します。
- 【⑤税率ごとに区分した消費税額等または適用税率】
- 税率ごとに対応する消費税額(または単に「10%」「8%」といった税率)を記載します。
上記の要件を満たしていれば、レジで発行されるレシートも簡易インボイスとして有効です。
飲食店が適格請求書発行事業者になるには?
飲食店が適格請求書発行事業者になるには、まず税務署へ登録申請を行います。登録が完了すると、国税庁の「インボイス制度適格請求書発行事業者公表サイト」に情報が掲載され、Tから始まる登録番号が付与されます。
登録を行うだけでなく、インボイスに対応した会計システムやレジを導入するのも重要です。適切なインボイス項目を自動でレシートや領収書に反映させるのに役立ちます。特に手書きでは対応漏れや記載ミスが起こりやすいため、システムの導入がおすすめです。
インボイス制度に対応するためのシステム改修やレジ購入には費用が発生するため、なかなか導入に踏み切れない場合もあるかもしれません。しかし一定の条件を満たせば、国や自治体の補助金制度を活用できる可能性もあります。
インボイス制度の基本や、飲食店が対応すべき具体的なポイントについては、以下の記事で詳しく解説していますので参考にしてください。
【1年間無料】フリーランスの見積・請求・申告は「Misoca×やよいの青色申告 オンライン」セットがお得!
発行した領収書に不備があったときの対処法
飲食店で発行した領収書に、金額や日付、宛名などの記載ミスが見つかる場合もあります。原則として、修正液や修正テープでの訂正は不可です。発行済みの領収書を回収し、新たに正しい情報で再発行する必要があります。
適格請求書(インボイス)として領収書を交付した場合、原則として受領者側での修正は認められていません。発行者である飲食店側が修正・再交付する必要があります。再発行の際は、履歴として管理できるよう、変更前の領収書と控えの情報を残すのが重要です。
誤った領収書を回収したら、単に廃棄するのではなく、バツ印などを記して「無効であることが明確な状態」にします。そのまま控えと一緒に保管し、トラブル時に対応できるようにしてください。
【1年間無料】フリーランスの見積・請求・申告は「Misoca×やよいの青色申告 オンライン」セットがお得!
飲食店の領収書発行における注意点
適正な領収書の発行は、飲食店の信用維持や法令順守の観点で非常に重要です。以下、発行時に特に注意すべきポイントを解説します。
日付や金額を空欄にしない
領収書を発行する際、日付や金額、但し書きなどを空欄にして渡してほしいと依頼されるケースがあります。しかし空欄による発行はインボイスとして認められず、重大な法令違反につながる可能性があるため厳禁です。
飲食店としては、どんなに親しい顧客からの依頼でも、空欄での領収書発行は避け、正確な日付・金額・取引内容を記入してください。
領収書とレシートはどちらか片方を発行する
飲食店で会計をする際、顧客から「レシートと領収書の両方をください」と依頼されるケースもあるかもしれません。しかし基本的に、レシートと領収書はどちらか片方のみを発行するのが正しい対応です。
レシートと領収書は、どちらも支払いの証明として有効な書類です。両方を渡すと、同じ取引に対して2回経費精算が行われるリスクがあります。例えば、レシートで精算した後に、領収書を使って再度精算するなどの行為です。
レシートと領収書の両方を渡してしまった場合は、どちらか一方をその場で回収するか、受け取った方に片方を破棄してもらうよう依頼するのが適切な対応です。従業員全員でこのルールを共有し、日々の接客対応で徹底しましょう。
領収書の控えを正しく保管する
飲食店で領収書を発行した場合、控えは適切に保管してください。特にインボイス制度が開始されて以降、保管義務はより厳格になっています。具体的に、法人や青色申告をしている個人事業主は7年間、白色申告の個人事業主は5年間の保存義務があります。
保存期間は「領収書を発行した日」ではなく、「決算書または確定申告書の提出期限の翌日」から起算されるのが原則です。例えば、2024年3月末に発行した領収書であれば、2025年3月の確定申告提出期限の翌日からカウントされます。
適格請求書(インボイス)として領収書を交付している場合は、控えの作成と7年間の保存が義務化されています。受領者が仕入税額控除を受けるために必要です。
店の屋号とインボイス登録者名が異なる場合、電話番号の記載などが必要
飲食店には、日常的に使用している店舗の屋号と、インボイス登録時の事業者名(法人名や個人名)が異なるケースもあります。屋号や省略した名称を使用しても、電話番号等で適格請求書登録事業者と特定できれば問題ないとされています。
例えば「○○食堂」という屋号を使っていて、インボイスの登録名義が「弥生太郎」や「合同会社〇〇」などである場合でも、電話番号や所在地などをあわせて記載すればインボイスの要件を満たせます。
なお、受領した領収書等に記載されている登録番号が取引時点において有効なものかを確認するために利用されるものであるため、その登録番号の有効性が確認できれば、一義的には有効な適格請求書等として取り扱うこととして差し支えありませんとされています。
問い合わせが多くなりそうであれば、対応として、例えば、個人事業主は、申出により「主たる屋号」を公表することもあるでしょう。 また、法人については「主たる屋号」ができる仕組みはないので、レシートに、店名や屋号に加えて「国税庁適格請求書発行事業者公表サイト」に掲載されている運営 会社等の名称を併記したり、店頭に「公表サイトには運営会社等の名称(○○(株))が表 示される」旨を掲示する等の方法によることなども検討するとよいでしょう。
【1年間無料】フリーランスの見積・請求・申告は「Misoca×やよいの青色申告 オンライン」セットがお得!
【Q&A】飲食店の領収書に関するよくある質問
飲食店で領収書を発行する際には、日付の取り扱いや再発行、印紙の有無など、実務上で迷うポイントが少なくありません。以下、領収書に関するよくある質問をQ&A形式でまとめて解説します。
後日領収書を発行することは可能?
飲食代の支払いが完了した後で、領収書を後日発行すること自体は可能です。ただし、その際の日付は「実際に代金を受け取った日」を記載しなければなりません。
一方、「領収書を紛失したので再発行してほしい」と依頼されるケースもありますが、再発行する法的義務はありません。同じ取引に対して二重で経費精算されるリスクや、不正利用の懸念などがあるため、慎重な対応が求められます。
対応する場合は、「再発行」の旨を明記し、日付や金額を変更せずに記録を残します。
領収書に印紙を貼付しないとどうなる?
領収書の発行金額(消費税を含めない金額)が5万円以上の場合、印紙税法に基づき収入印紙の貼付が必要です。これを怠った場合、本来納付すべき印紙税額の3倍にあたる過怠税を課される可能性があります。200円の印紙が必要な場合、600円の過怠税が徴収されます。
収入印紙は郵便局だけでなく、多くのコンビニでも購入可能です。業務で頻繁に領収書を発行する店舗は、あらかじめ印紙を常備しておくと安心です。収入印紙の貼付についてはこちらをご覧ください。
クレジットカード払いでも領収書は必要?
クレジットカード払いの場合、信用取引により商品を引き渡すものであり、実際に代金を受け取るのは顧客からではなくカード会社からになりますが、交付を求められたら領収書発行をおすすめします。受領者が経費処理に使うケースも多いためです。
なおクレジットカード払いに対する領収書は、現金の受領を伴わないため、印紙貼付が必要な第17号の1文書には該当しませんので、収入印紙の貼付も不要です。その際は、「クレジットカードにてお支払い」などと支払方法を明記しましょう。クレジットカード利用の場合その旨を「領収書」に記載しないと、第17号の1文書に該当することになりますので印紙が必要になります。詳しくはこちらをご覧ください。
領収書は複数枚にわけても問題ない?
複数の企業や事業所が飲食店に集まり、会食や懇親会を行った際は、飲食代の支払いを割り勘で精算するケースもあります。この場合、1つの会計に対して複数の領収書を発行しても問題ありません。例えば、1万2,000円の会計を4人で支払う場合、それぞれ3,000円分の領収書を4枚発行するような対応ができます。
分割する金額は、均等でなくても問題ありません。ただし、合計金額が会計金額と一致していること、内容が明確であることが重要です。レシートでは全体の金額を清算し、手書きで個々にインボイスの発行を求められるケースもあるため、対応時には、記載ミスや不正使用が起こらないよう注意しましょう。
飲食店もインボイスに対応する必要がある?
インボイス制度に登録すると、原則として消費税の納税義務が発生します。そのため、個人事業主など小規模な飲食店では「対応すべきか迷う」という声もあります。とはいえ、法人・個人問わず、事業者が顧客となるケースが多い飲食店では登録するのが無難です。
登録していない場合、顧客が仕入税額控除を受けられず、「領収書が使えない」と判断されて来店を避けられる可能性もあります。飲食店のインボイス対応についてはこちらをご覧ください。
【1年間無料】フリーランスの見積・請求・申告は「Misoca×やよいの青色申告 オンライン」セットがお得!
飲食店も領収書を適切に発行・管理しよう
領収書の発行は、法令遵守や信頼構築に欠かせない業務です。インボイス制度の開始により、記載項目の正確さや控えの保存、再発行時の対応など、より慎重な管理が求められるようになりました。
記載ミスや手書きによる不備を防ぐためにも、領収書や見積書を効率よく作成・管理できるツールの導入がおすすめです。
「Misoca」は、インボイス制度にも対応したクラウド見積書・請求書作成サービスです。飲食店を含む個人事業主や小規模事業者に幅広く利用されています。ぜひこの機会に、自店の領収書対応を見直してみましょう。
【1年間無料】フリーランスの見積・請求・申告は「Misoca×やよいの青色申告 オンライン」セットがお得!
クラウド見積・納品・請求書サービスなら、請求業務をラクにできる
クラウド請求書作成ソフトを使うことで、毎月発生する請求業務をラクにできます。
今すぐに始められて、初心者でも簡単に使えるクラウド見積・納品・請求書サービス「Misoca」の主な機能をご紹介します。
「Misoca」は月10枚までの請求書作成ならずっと無料、月11枚以上の請求書作成の有償プランも1年間0円で使用できるため、気軽にお試しすることができます。
見積書・納品書・請求書をテンプレートでキレイに作成

Misocaは見積書 ・納品書・請求書・領収書・検収書の作成が可能です。取引先・品目・税率などをテンプレートの入力フォームに記入・選択するだけで、かんたんにキレイな帳票ができます。
各種帳票の変換・請求書の自動作成で入力の手間を削減

見積書から納品書・請求書への変換や、請求書から領収書・検収書の作成もクリック操作でスムーズにできます。固定の取引は、請求書の自動作成・自動メール機能を使えば、作成から送付までの手間を省くことが可能です。
インボイス制度(発行・保存)・電子帳簿保存法に対応だから”あんしん”

Misocaは、インボイス制度に必要な適格請求書の発行に対応しています。さらに発行した請求書は「スマート証憑管理」との連携で、インボイス制度・電子帳簿保存法の要件を満たす形で電子保存・管理することが可能です。
確定申告ソフトとの連携で請求業務から記帳までを効率化

Misocaで作成した請求書データは、弥生の確定申告ソフト「やよいの青色申告 オンライン」に連携することが可能です。請求データを申告ソフトへ自動取込・自動仕訳できるため、取引データの2重入力や入力ミスを削減し、効率的な業務を実現できます。
会計業務はもちろん、請求書発行、経費精算、証憑管理業務もできる!
法人向けクラウド会計ソフト「弥生会計 Next」では、請求書作成ソフト・経費精算ソフト・証憑管理ソフトがセットで利用できます。自動的にデータが連携されるため、バックオフィス業務を幅広く効率化できます。

「弥生会計 Next」で、会計業務を「できるだけやりたくないもの」から「事業を成長させるうえで欠かせないもの」へ。まずは、「弥生会計 Next」をぜひお試しください。
無料【クラウド請求書作成ソフト「Misoca」がよくわかる資料】をダウンロードする
この記事の監修者高崎文秀(税理士)
高崎文秀税理士事務所 代表税理士/株式会社マネーリンク 代表取締役
早稲田大学理工学部応用化学科卒
都内税理士事務所に税理士として勤務し、さまざまな規模の法人・個人のお客様を幅広く担当。2019年に独立開業し、現在は法人・個人事業者の税務顧問・節税サポート、個人の税務相談・サポート、企業買収支援、税務記事の監修など幅広く活動中。また通常の税理士業務の他、一般社団法人CSVOICE協会の認定経営支援責任者として、業績に悩む顧問先の経営改善を積極的に行っている。










