領収書の控えとは?正本とどっちを保管する?必要な理由や保管期間を解説
監修者: 高崎文秀(税理士)
更新
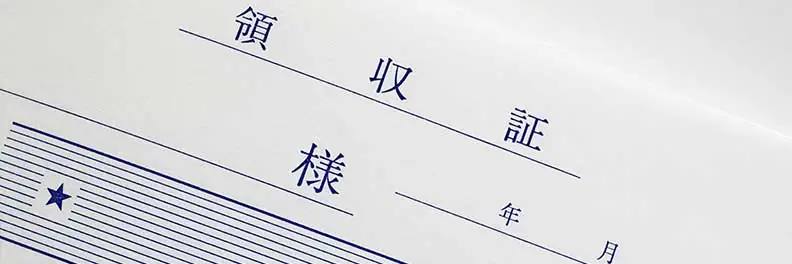
紙の領収書は、支払者に渡す「正本」と、発行者が手元に残す「控え」がセットになっているのが一般的です。領収書の処理に慣れていないと、正本と控えのどちらを発行元である自社側で保管すべきか迷うこともあるのではないでしょうか。あるいは、控えを保管する必要性に疑問を感じている方もいるかもしれません。本記事では、領収書の控えの役割や保管が必要な理由、正しい保管方法、保存期間までをわかりやすく解説します。
無料【クラウド請求書作成ソフト「Misoca」がよくわかる資料】をダウンロードする
領収書の控えは領収書を発行したという証拠書類
領収書の授受に際しては、「正本」を支払者に渡し、「控え」を発行者が保管するのが基本です。控えは、領収書を確かに発行したことを客観的に示す証拠書類として機能します。ここでは、領収書や控えについての基本を解説していきます。
そもそも領収書とは
領収書とは、代金の支払いを受けた事業者が、その事実を証明するために発行する書類です。一般的には、支払われた金額(受領した金額)、取引日(支払われた日または受領した日)、宛名(支払者の氏名や会社名)、発行者の氏名や店舗、会社名、取引内容(購入した商品やサービス)などの記載が必要です。いずれの項目も、誤りなく正確に記載しなければなりません。
領収書は、見積書・請求書・納品書などと並び、経理や税務処理に欠かせない「証憑書類」の1つです。支払者は、この領収書に基づいて支払いの事実を確認し、会計処理や税務申告を行います。特に法人では、現金で経費を支払う際に領収書を取得し、経理部門に提出することが義務付けられていることが多くあります。
領収書については、こちらの関連記事も参考にしてください。
領収書の控えとは
領収書の控えとは、領収書を発行した事業者が自社で保管する「写し」のことです。取引の証拠としての役割を果たし、内容の確認や会計処理に使用できます。控えには原則として、取引内容や金額、取引日、取引先の情報など、正本と同じ内容を記載します。
特に紙の領収書では、記載ミスや抜け漏れを防ぐため、複写式の領収書が多く利用されています。複写式では、上の1枚目が支払者に渡す「正本」、その下に転写される2枚目が「控え」となっており、同時に同内容を記録できるしくみです。
【1年間無料】フリーランスの見積・請求・申告は「Misoca×やよいの青色申告 オンライン」セットがお得!
領収書の控えが必要な理由
領収書を発行する際は、発行者がその控えを保管する必要があります。ここでは、控えの保管が必要とされる主な理由を3つの視点から詳しく解説します。
取引の証明になる
領収書の控えは、取引が実際に行われたことを証明する重要な書類です。支払日や金額、取引先名、取引の内容などが記載されており、取引の事実と詳細を客観的に証明する手段として役立ちます。
例えば税務調査において、発行者には売上の裏付けとして取引内容の提示が求められます。それに対して、支払者の場合には、経費の正当性を確認するため、発行元に対し領収書の内容照会が行われるケースも見られます。その際、控えが保管されていれば、取引の正当性を裏付ける根拠として提示することが可能です。
金額の照会・訂正が容易になる
領収書を発行した後に、支払者から「金額に誤りがあるのではないか」と指摘を受けることもあります。控えが手元にあれば、金額や内容をすぐに確認できるため、修正が必要な場合にも迅速な対応が可能です。反対に、控えがない場合、特に現金取引では事実関係を証明するのが難しくなります。
さらに、会計処理においても、領収書の控えは帳簿記入前に金額や取引内容を再確認するための資料として有効です。控えを活用することで、誤記や漏れの防止につながり、経理業務の正確性が高まります。
売上の確認にも使用できる
領収書の控えを整理・活用すると、期間ごとの正確な売上データを把握できるようになります。例えば、1日ごと、1週間ごと、1か月ごとといった単位で控えを見直せば、その期間に発生した売上や取引金額を明確に確認でき、取引先ごとの売上傾向も把握しやすくなります。
日々の売上を記録・集計する作業も、正確な控えがあればミスの防止や作業の時短にもつながります。その結果、経理担当者の業務負担を大きく軽減でき、他の業務に時間を振り分けられるというメリットも生まれます。
さらに、こうして日々積み上げられた売上データは、経営判断を行う際の大切な材料になります。例えば、「ある月の売上が前月より大きく増減している」「取引額が減った得意先がある」などの変化に気づいた際に、領収書の控えを確認することで、取引内容の傾向や要因の分析が可能です。
【1年間無料】フリーランスの見積・請求・申告は「Misoca×やよいの青色申告 オンライン」セットがお得!
領収書の控えは自社か取引先のどちらが保管する?
領収書は、記入済みの「正本」を取引先(支払者)に渡し、転写された2枚目の「控え」を自社で保管します。一般的な複写式用紙には、「控え」と明記されているため、正本との区別がしやすくなっています。
また、正確な取引履歴を維持するためには、正本と控えを取り違えないようにすることが非常に重要です。誤って両方の用紙を支払者に渡してしまったり、控えを紛失してしまったりすると、取引記録の裏付けが取れなくなり、経理処理や税務調査の際に不備を指摘される可能性もあります。特に複数の領収書を一度に処理する場合には、記載内容のチェックや保管の手順を明確にしておくことが、トラブル防止の鍵となります。
【1年間無料】フリーランスの見積・請求・申告は「Misoca×やよいの青色申告 オンライン」セットがお得!
領収書の控えの保管期間
領収書の控えは、法人・個人事業主を問わず法人税法や所得税法で一定期間の保管が義務付けられています。税務調査などで控えの提示を求められることもあるため、所定の期間を守って適切に保管することが重要です。
原則として7年
法人の場合、領収書を含む帳簿書類は原則7年間の保管が必要です。個人事業主の場合は、青色申告なら7年、白色申告は5年の保存義務があります。ただし、青色申告者でも、前々年の所得が300万円以下であれば、保存期間は5年です。
なお、保存期間は「領収書の発行日」ではなく、「その年の確定申告の提出期限の翌日」から数える点に注意が必要です。誤って期間内に処分してしまわないよう、管理には十分気をつけましょう。
参照:国税庁「No.5930 帳簿書類等の保存期間」
参照:国税庁「記帳や帳簿等保存・青色申告」
欠損金の繰越控除を行う場合は10年
欠損金の繰越控除を行う場合、その事業年度に限って帳簿書類の保存期間は10年です。これは、税務調査で過年度の損益を確認する必要があるためです。
いずれの場合も、領収書の控えは最低でも5年、通常は7年、場合によっては10年の保存が必要です。経理担当者は、破損や紛失を防ぎ、必要なときにすぐ取り出せる保管体制の整備が求められます。
参照:国税庁「No.5930 帳簿書類等の保存期間」
領収書の保管期間については、以下の記事も参考にしてください。
【1年間無料】フリーランスの見積・請求・申告は「Misoca×やよいの青色申告 オンライン」セットがお得!
領収書の控えの保管方法
近年は、紙での保管に加え、業務効率化や法令対応の観点から電子化も進んでいます。ここでは、それぞれの保管方法のポイントについて解説します。
紙のまま保管する
紙の領収書は、原本をそのまま紙の状態で保管して問題ありません。複写式の領収書を使用している場合、正本と同時に控えが自動的に残ります。この控えを綴じてファイル化し、保管棚などで整理するのが基本的な方法です。
ただし、整理ルールがないと、照会のための控えを探すのに手間取る可能性があります。そのため、取引先ごと・年月日順など、一定のルールを決めてファイリングすることが重要です。
また、控えは長期間の保管が求められるため、紙の劣化や紛失を防ぐための保管環境も整えておきましょう。特に感熱式のレシートは時間の経過により文字が消えてしまうことがあるため注意しましょう。
電子化して保存する
電子帳簿保存法の改正により、電子取引の場合、証憑書類を電子形式のまま保存することが義務化されました。また紙で発行した領収書の控えも、税務当局の事前承認なしにスキャンして電子化することが可能となっています。
電子データで保存することにより、紙の保管スペースを削減できる他、紛失・劣化のリスクも軽減され、検索や共有のしやすさなど、業務の効率化にもつながります。さらに、電子帳簿保存法に対応した帳票発行システムを導入すれば、領収書の作成から保存までを一貫して効率的に管理できます。
ただし、電子的に保存する場合は、電子帳簿保存法で定められた保存要件(タイムスタンプの付与、改ざん防止措置、検索機能の確保など)を満たす必要があります。これらの要件をクリアしていない保存方法は、制度上の「電子保存」として認められない可能性があるため、導入にあたっては運用ルールの整備や、法令対応済みのシステム選定が重要です。
【1年間無料】フリーランスの見積・請求・申告は「Misoca×やよいの青色申告 オンライン」セットがお得!
領収書の控えの取り扱いについて
領収書の発行に際しては、収入印紙の扱いや押印の要否など、迷いやすいポイントがあります。以下では、特に気をつけたい2つの点について紹介します。
印紙は領収書の正本にだけ貼る
5万円以上の現金取引において、紙の領収書を直接手渡しする場合は、原則として取引金額に応じた収入印紙を正本に貼付し、消印を行う必要があります。これは印紙税法で定められたルールであり、所定の形式にしたがっていない場合は、過少申告として指摘される可能性もあります。
それに対して、発行者が保管する控えについては、印紙税法上の課税文書には該当しないため、収入印紙を貼る必要はありません。正本ではなく控えに貼ってしまうといったミスをしないようにしましょう。控えには「印紙貼り付け済み」などと記載し、収入印紙を貼って渡したことがわかるようにしておくのがおすすめです。
領収書の収入印紙について詳しくは、以下の関連記事を参考にしてください。
義務ではないが正本・控えの両方に印鑑を押すのがよい
法的には、領収書の正本・控えいずれにも押印の義務はありません。しかし、実務上や商慣習上の観点からは、両方に印鑑を押しておくのが一般的です。特に法人間の取引では、印鑑の有無が書類の信頼性や正式な文書としての扱いに影響することもあるため、形式を整える意味でも押印が推奨されます。
また、正本と控えの記載内容を完全に一致させるうえでも、双方に同じ印鑑を押すことで照合しやすくなり、トラブル防止にもつながります。万が一、不正な書き換えや偽造が発生した場合でも、押印があることで書類の正当性を主張しやすくなるため、リスク管理の観点からも有効です。
【1年間無料】フリーランスの見積・請求・申告は「Misoca×やよいの青色申告 オンライン」セットがお得!
領収書の控えについて理解し、正しく扱いましょう
領収書の控えは、取引の事実を示す重要な証拠書類です。発行者側で適切に管理・保管しておくことで、金額の照会や会計処理、税務調査への対応も円滑に進められます。
また、領収書やその控えは、紙だけでなく電子データとして発行・保存することも可能です。弥生のクラウド請求書作成ソフト「Misoca」を活用すれば、領収書の作成から発行・保存まで一括管理でき、業務効率化にもつながります。請求業務に課題を抱えている企業の方は、ぜひ導入をご検討ください。
【1年間無料】フリーランスの見積・請求・申告は「Misoca×やよいの青色申告 オンライン」セットがお得!
クラウド見積・納品・請求書サービスなら、請求業務をラクにできる
クラウド請求書作成ソフトを使うことで、毎月発生する請求業務をラクにできます。
今すぐに始められて、初心者でも簡単に使えるクラウド見積・納品・請求書サービス「Misoca」の主な機能をご紹介します。
「Misoca」は月10枚までの請求書作成ならずっと無料、月11枚以上の請求書作成の有償プランも1年間0円で使用できるため、気軽にお試しすることができます。
見積書・納品書・請求書をテンプレートでキレイに作成

Misocaは見積書 ・納品書・請求書・領収書・検収書の作成が可能です。取引先・品目・税率などをテンプレートの入力フォームに記入・選択するだけで、かんたんにキレイな帳票ができます。
各種帳票の変換・請求書の自動作成で入力の手間を削減

見積書から納品書・請求書への変換や、請求書から領収書・検収書の作成もクリック操作でスムーズにできます。固定の取引は、請求書の自動作成・自動メール機能を使えば、作成から送付までの手間を省くことが可能です。
インボイス制度(発行・保存)・電子帳簿保存法に対応だから”あんしん”

Misocaは、インボイス制度に必要な適格請求書の発行に対応しています。さらに発行した請求書は「スマート証憑管理」との連携で、インボイス制度・電子帳簿保存法の要件を満たす形で電子保存・管理することが可能です。
確定申告ソフトとの連携で請求業務から記帳までを効率化

Misocaで作成した請求書データは、弥生の確定申告ソフト「やよいの青色申告 オンライン」に連携することが可能です。請求データを申告ソフトへ自動取込・自動仕訳できるため、取引データの2重入力や入力ミスを削減し、効率的な業務を実現できます。
会計業務はもちろん、請求書発行、経費精算、証憑管理業務もできる!
法人向けクラウド会計ソフト「弥生会計 Next」では、請求書作成ソフト・経費精算ソフト・証憑管理ソフトがセットで利用できます。自動的にデータが連携されるため、バックオフィス業務を幅広く効率化できます。

「弥生会計 Next」で、会計業務を「できるだけやりたくないもの」から「事業を成長させるうえで欠かせないもの」へ。まずは、「弥生会計 Next」をぜひお試しください。
無料【クラウド請求書作成ソフト「Misoca」がよくわかる資料】をダウンロードする
この記事の監修者高崎文秀(税理士)
高崎文秀税理士事務所 代表税理士/株式会社マネーリンク 代表取締役
早稲田大学理工学部応用化学科卒
都内税理士事務所に税理士として勤務し、さまざまな規模の法人・個人のお客様を幅広く担当。2019年に独立開業し、現在は法人・個人事業者の税務顧問・節税サポート、個人の税務相談・サポート、企業買収支援、税務記事の監修など幅広く活動中。また通常の税理士業務の他、一般社団法人CSVOICE協会の認定経営支援責任者として、業績に悩む顧問先の経営改善を積極的に行っている。












