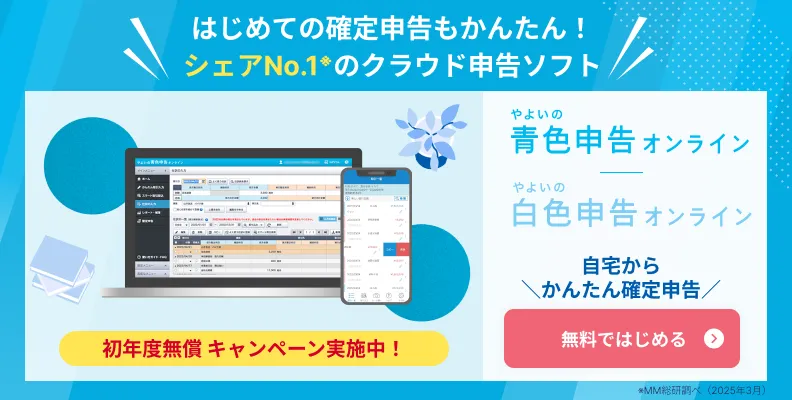個人事業主の帳簿の付け方は?エクセルや手書きでの作成方法も解説
監修者: 田中卓也(田中卓也税理士事務所)
更新

個人事業主は、事業において生じた取引によるお金の動きを帳簿に記録し、保管する義務を負っています。しかし、帳簿を付ける際に何をすればよいのかわからない方も少なくないのではないでしょうか。
ここでは、個人事業主の帳簿の付け方や種類、保存期間のほか、エクセルや手書きでの作成方法などを解説します。帳簿は、確定申告ソフトや会計ソフト、エクセル、手書きなど、さまざまな方法で作成できますが、どの場合でも基本は変わりません。基本的な役割や流れを知っておくことで、帳簿や事業のお金の管理について理解を深めていきましょう。
日付や金額などを入力するだけで、確定申告に必要な帳簿や申告書類が完成します
初年度無料ですべての機能が使用できます。
e-Taxも製品から直接できるので、自宅からかんたんに確定申告が可能です

帳簿は個人事業主をはじめ、すべての事業主が付けなければならない
帳簿の作成と保存は、個人事業主か法人かを問わず、事業を営むすべての事業者の義務です。青色申告でも白色申告でも、個人事業主は帳簿を作成しなければなりません。
取引の内容を記録した帳簿がなければ正しい確定申告はできないため、すべての事業者は正確に帳簿を作成する必要があります。
個人事業主が帳簿を付けるメリット
個人事業主が帳簿を付けるメリットは、以下の2点です。
個人事業主が帳簿を付けるメリット
- 事業に関するお金の流れや経営の状況を確認できる
- 事業所得として確定申告ができる
帳簿を付ければ、年間の売上やかかった必要経費、その内訳などを詳しく記録として残し、いつでも確認できます。事業の取引内容や損益を正しく把握することで、経営や資金繰りの判断材料として活用できます。
また、帳簿は所得を事業所得として申告するためにも必要です。帳簿を作成していないと、事業による所得を雑所得として申告することになります。雑所得は他の所得と損益通算ができないため、税負担を軽減するためにも帳簿の作成は重要です。
さらに、帳簿を付けなければ青色申告特別控除も利用できません。青色申告特別控除は、所得金額から申告方法に応じて最大65万円を控除できる制度です。節税効果が高いため、帳簿を付けて積極的に活用しましょう。
帳簿の記載方法
帳簿は、複式簿記と単式簿記のどちらかの方法で記帳します。どちらを選ぶかは任意ですが、記帳方法に応じて利用できる青色申告特別控除の額などが変わる点に注意してください。それぞれ、以下のように帳簿を記載します。
複式簿記
複式簿記とは、1つの取引について原因と結果を表す2つの勘定科目で記帳する方法です。65万円または55万円の青色申告特別控除を利用したい事業者は、複式簿記で記帳する必要があります。
例えば、1万円の商品を販売して普通預金口座に代金が振り込まれた場合、原因は「1万円の商品を売った」こと、結果は「普通預金残高が1万円増えた」ことです。複式簿記では、これを借方、貸方と呼ばれる項目に分けて記帳していきます。
1つの取引を2つの側面から表現しているため、借方と貸方の残高合計は必ず一致します。一致しない場合は記帳が間違っているため、ミスがあった際に気付きやすい記帳方法です。
複式簿記の記帳では、上記のように現金や普通預金の変動額だけを帳簿に記載していきます。このような帳簿を「仕訳帳」と呼びます。
複式簿記による仕訳帳の記帳例
| 日付 | 借方科目 | 借方 | 貸方科目 | 貸方 |
|---|---|---|---|---|
| 20XX.4.1 | 普通預金 | 10,000 | 売上 | 10,000 |
| 20XX.4.1 | 仕入 | 50,000 | 現金 | 50,000 |
| 20XX.4.3 | 現金 | 3,000 | 売上 | 3,000 |
| 20XX.4.10 | 消耗品費 | 600 | 現金 | 600 |
仕訳帳があれば、普通預金の変動も現金の変動も1つの帳簿でまとめて確認することが可能です。ただし、普通預金や現金の残高を確認することはできません。
なお、1つの取引で複数の「原因」や「結果」が生じる場合もあります。例えば「1万円の商品を販売し、先方が振込手数料として200円を差し引いた9,800円を普通預金口座に振り込んできた」といったケースでは、「1万円の商品を売った」「200円の振込手数料を支払った」「普通預金残高が9,800円増えた」という3つの事実を記録しなければなりません。この場合は、以下のように記帳しましょう。
振込手数料が差し引かれていた場合の複式簿記の記帳例
| 日付 | 借方科目 | 借方 | 貸方科目 | 貸方 |
|---|---|---|---|---|
| 20XX.4.1 | 普通預金 | 9,800 | 売上 | 10,000 |
| 支払手数料 | 200 |
単式簿記
単式簿記は、1つの取引を1つの勘定科目を使って記録していくシンプルな記帳方法です。お小遣い帳のようなイメージで記帳できます。白色申告者と、10万円の青色申告特別控除を利用する青色申告者は、単式簿記でも問題ありません。
単式簿記による記帳例
| 日付 | 勘定科目 | 収入 | 支出 |
|---|---|---|---|
| 20XX.4.1 | 売上 | 10,000 | |
| 20XX.4.1 | 仕入 | 50,000 | |
| 20XX.4.3 | 売上 | 3,000 | |
| 20XX.4.10 | 消耗品費 | 600 |
単式簿記では、取引によって変動したお金の種類を問わずその原因だけを記録していきます。例えば、1万円の商品を販売した場合に、それが現金で回収されても、通帳に振り込まれても記帳には影響しません。単式簿記は、損益状況を一目で確認できる反面、事業全体のお金の動きや残高は見えづらい記帳方法です。
なお、「1万円の売上から200円の手数料を引かれて、9,800円が普通預金口座に振り込まれた」といったケースでは、以下のように記帳します。
振込手数料が差し引かれていた場合の単式簿記の記帳例
| 日付 | 勘定科目 | 入金 | 出金 |
|---|---|---|---|
| 20××.4.1 | 売上 | 10,000 | |
| 支払手数料 | 200 |
この場合、入金額は9,800円ですが、それだけを記録すると9,800円の商品を販売したことになり、事実と齟齬が出ます。そのため、支払手数料についても記録しなければなりません。
単式簿記では、損益に関する事実である、1万円の商品を販売したことと支払手数料を200円支払ったことだけを記載すればよく、現金で回収したことや通帳から支払ったことについては記載しない記帳方法となります。
帳簿の種類
帳簿には、さまざまな種類があります。主要簿と補助簿の2種類に分けて、帳簿の種類とそれぞれの役割や特徴を解説します。
なお、複式簿記で記帳を行う事業者は主要簿と補助簿の両方、単式簿記で記帳を行う事業者は補助簿の作成が必要です。
主要簿
主要簿は、仕訳帳と総勘定元帳の2種類です。複式簿記で記帳を行い、65万円または55万円の青色申告特別控除の適用を受ける事業者は、必ず主要簿を作成しなければなりません。
仕訳帳
仕訳帳とは、借方と貸方の2つの勘定科目を使って取引を日付順に記録していく帳簿です。とはいえ、会計ソフトを使えば後から日付順に並び替えることも容易です。入力順にこだわる必要はありません。
勘定科目別にお金の流れを記録していくと、特定の時点での資産と負債の内訳と額を表す貸借対照表を作成できるようになります。65万円または55万円の青色申告特別控除の適用を受ける際は、確定申告書に貸借対照表を添付しなければならないため、仕訳帳の作成が必要です。仕訳帳自体を税務署に提出することはありませんが、税務調査などの際は提出や提示を求められる可能性があります。
総勘定元帳
総勘定元帳は、仕訳帳の内容を勘定科目ごとに集計した帳簿です。仕訳帳には日付順に取引の内訳を記載しますが、総勘定元帳には勘定科目別に取引の内訳を記載します。
総勘定元帳は、勘定科目別の資金の流れを確認するのに便利な帳簿です。例えば、普通預金残高の推移は仕訳帳を見てもわかりませんが、総勘定元帳の「普通預金」欄を見ればすぐに推移がわかります。
総勘定元帳は、仕訳帳を勘定科目ごとに転記して作ります。会計ソフトには、仕訳帳の内容を勘定科目ごとに自動で集計する機能があるため、いつでも簡単に総勘定元帳を作成することが可能です。一方、手書きの場合は手作業で転記しなければならないため、転記漏れや計算ミスに気を付ける必要があります。
補助簿
補助簿は、青色申告か白色申告かにかかわらず必要に応じて作成しなければならない帳簿です。取引の詳細を記録するために作成する帳簿で、主要簿の内容を補足する役割を持ちます。
補助簿には多様な種類があり、取引内容に応じて作成する帳簿を選択します。例えば、掛売をしていない個人事業主が売掛帳を作成する必要はありません。
補助簿は大きく、補助記入帳と補助元帳に分けられます。それぞれの特徴と具体的な種類は以下のとおりです。
補助記入帳
補助記入帳は、取引の発生内容に応じて記載していく帳簿です。代表例としては、以下の4種類があげられます。
補助記入帳の主な種類
| 名称 | 内容 |
|---|---|
| 現金出納帳 | 現金の入出金の動きを記録する |
| 預金出納帳 | 預金口座の入出金の動きを口座別に記録する |
| 売掛帳 | 売掛金の発生状況や回収状況を記録する |
| 買掛帳 | 買掛金の発生状況や回収状況を記録する |
個人事業主は、個人のお金と事業のお金を混同しないように管理しなければなりません。現金出納帳や預金出納帳を活用しましょう。また、売掛帳や買掛帳を作成することで、売掛金や買掛金の残高や発生状況を一目で確認できるようになります。
補助元帳
補助元帳は、勘定科目別の取引の詳細を記載する帳簿です。主な補助元帳には、以下の4種類があります。
補助元帳の主な種類
| 名称 | 内容 |
|---|---|
| 商品有高帳 | 商品ごとに繰越商品と仕入を記録する |
| 得意先元帳(売掛金元帳) | 顧客ごとの売掛金を記録する |
| 仕入先元帳(買掛金元帳) | 仕入先ごとの買掛金を記録する |
| 固定資産台帳 | 固定資産の取得状況や減価償却の状況などを記録する |
補助元帳を作成すると、得意先別の売掛金残高などを確認できるようになります。知りたい情報に合わせて作成しましょう。
帳簿を付ける際の会計処理の方法
帳簿を付ける際は、会計処理の方法を定めなければいけません。会計処理方法には、発生主義、現金主義、実現主義の3種類があります。いずれかを選択したうえで、記帳を行いましょう。
それぞれの会計処理の方法と特徴は以下のとおりです。
発生主義
発生主義は、売上や必要経費が発生した時点で記帳する会計処理方法です。例えば、4月30日に商品を売って請求書を発行し、5月31日に入金があったとします。この場合、売上日は請求書を発行した4月30日です。そのため、売上は4月30日時点で記帳します。
発生主義の記帳
| 日付 | 借方科目 | 借方 | 貸方科目 | 貸方 |
|---|---|---|---|---|
| 20××.4.30 | 売掛金 | 10,000 | 売上 | 10,000 |
| 20××.5.31 | 普通預金 | 10,000 | 売掛金 | 10,000 |
売掛金が発生する場合は、売上と入金を異なるタイミングで記帳するため、発生主義では年間の売上額と入金額が一致しません。なお、取引先の倒産などによって売掛金の回収見込みがなくなった場合は、一定の要件に合致する場合、該当の金額を貸倒損失として処理します。
現金主義
現金主義は、お金が実際に動いた時点で記帳する会計処理方法です。例えば、4月30日に商品を売って5月31日に代金が振り込まれた場合、売上のあった日は5月31日として記帳します。
現金主義の記帳
| 日付 | 借方科目 | 借方 | 貸方科目 | 貸方 |
|---|---|---|---|---|
| 20××.5.31 | 普通預金 | 10,000 | 売上 | 10,000 |
現金主義は、飲食店や小売店のように現金のやりとりが頻繁に行われる業種にとって便利な会計処理方法です。ただし、現金主義での記帳を行えるのは以下の一定の要件を満たす事業者のみです。また、現金主義を用いている事業者は65万円または55万円の青色申告特別控除の適用を受けられません。10万円の青色申告特別控除の利用は可能です。
現金主義での帳簿付けが認められる要件
- 青色申告者であること
- 前々年分の事業所得と不動産所得の合計金額(青色事業専従者給与または事業専従者控除額を差し引く前の金額)が300万円以下であること
- 適用を受けたい年の3月15日まで(1月16日以後に新たに事業を始めた方は事業開始から2か月以内)に「現金主義による所得計算の特例を受けることの届出書
」を提出すること
なお、白色申告者については、別途、掛売の取引であっても現実に代金を受け取った時に現金売上として記載することが認められています。ただし、年末に売掛金残高を記載しなければいけません。
現金主義や発生主義については以下の記事で詳しく解説していますので参考にしてください。
実現主義
実現主義は、売上や必要経費の発生が確実になった時点で記帳をする会計処理方法です。発生主義と似ていますが、会計期間をまたぐ長期の取引などの場合に現実に即した記録が可能です。
例えば、100万円の商品の販売を契約して10万円の手付金を受け取った場合、発生主義では契約時点で100万円の売上を立てることになります。しかし、実際には手付金が放棄されて契約解除になる可能性もあります。その点、実現主義では、手付金を受け取った時点では手付金に関する記帳しか行いません。その後、商品の納入が完了したタイミングで売上について記帳します。
帳簿を付ける手順
帳簿を付ける際には、一定の手順に沿って進めることで、正確な記帳が可能になります。以下の4つのステップで帳簿を作成しましょう。
1. 領収書や通帳などの記載内容を整理する
帳簿を付けるためには、最初に領収書や通帳など、記帳の基となる書類やデータの記載内容を整理します。例えば、領収書であれば購入した商品によって勘定科目が変わります。
また、現金払いなのか、クレジットカード払いなのか、振り込みなのかといった点も確認しなければなりません。クレジットカード払いの場合、クレジットカードの明細書とレシートがそれぞれ発行されることもあるため、二重に計上しないよう注意してください。
2. 帳簿を付ける
領収書や通帳などの記載内容を整理したら、それらの書類を基に帳簿を付けましょう。複式簿記であれば、取引内容を勘定科目ごとに仕訳帳に記載します。単式簿記の場合は取引内容に応じた帳簿に内訳と金額を記載してください。
レシートなどをためておいてまとめて作業しようとすると、膨大な時間がかかり、ミスも発生しやすくなります。取引が発生した時点で記帳するよう、習慣付けることをおすすめします。
3. 関係帳簿に転記する
帳簿を付けたら、必要に応じて帳簿の内容を関係帳簿に転記します。複式簿記であれば、仕訳帳の取引内容を総勘定元帳にも転記しなければなりません。
また、現金の動きは現金出納帳、預金口座の動きは預金出納帳への転記が必要です。その他の補助簿についても、取引内容に応じて作成してください。
4. 利益・損失を計算する
帳簿の内容を関係帳簿に転記したら、最後に、総勘定元帳などを基に青色申告であれば損益計算、白色申であれば収支計算を行います。算出した利益額や損失額を、確定申告書に記載することになります。
個人事業主の帳簿や領収書などの保存期間
帳簿や、帳簿の記載内容の根拠となる領収書・請求書などの書類は、一定期間の保存が法律で義務付けられています。青色申告者、白色申告者、適格請求書(インボイス)発行事業者のそれぞれで、保存が必要な書類と保存期間は以下のように異なります。
青色申告の場合
青色申告者は、確定申告期限の翌日から7年間、帳簿類を保存しなければなりません。仕訳帳や総勘定元帳のような主要簿も、現金出納帳や売掛帳のような補助簿も保存期間は同一です。
また、領収書や預金通帳といった現金預金取引等関係書類と、貸借対照表や損益計算書といった決算関係書類も7年間保存してください。一方、請求書や見積書、契約書のような、取引に関連して作成、受領した書類の保存期間は5年間です。
なお、前々年の事業所得や不動産所得が300万円以下の青色申告者は、領収書などの現金預金取引等関係書類の保存期間が5年間になります。
白色申告の場合
白色申告者は、収入や必要経費を記録した帳簿(法定帳簿)については、確定申告期限の翌日から7年間保存しなければなりません。法定帳簿以外の、業務に関連して作成した任意帳簿や決算関係書類、領収書、請求書などについては、5年間保存します。
適格請求書発行事業者の場合
適格請求書発行事業者は、自社で発行した適格請求書の控えと、受け取った適格請求書を課税期間の末日の翌日から2月を経過した日から7年間保存しなければなりません。これは、青色申告者でも白色申告者でも同一です。
適格請求書の要件を満たす領収書やレシートなども7年間保存する必要があるため、注意しましょう。
帳簿の作成には領収書・レシート・請求書の管理が重要となる
帳簿の作成は、領収書やレシート、請求書といった取引時にやりとりした書類を基に行います。これらの書類がなければ、帳簿の内容が正しいかどうか判断することができません。取引に際してやりとりした書類は税務調査などでも確認されるポイントとなるため、整理しておきましょう。
領収書やレシート、請求書といった書類をこまめに整理せず、ため込んで確定申告直前に処理しようとすると、どうしても抜けや漏れが生じる可能性が高まります。何に使ったのかわからない支払いが見つかったり、領収書を紛失してしまったりすることもあるかもしれません。また、オンラインで領収書などをダウンロードするシステムの場合、ダウンロード期限が設定されていることもあります。
領収書や請求書を受け取ったときは、その場で整理し、こまめに記帳することをおすすめします。オンラインで発行された領収書や請求書なども、後回しにせずに即座にダウンロードするのが重要です。電子データで送られてきた場合は、電子帳簿保存法の規定に則した方法で保存することも忘れないようにしてください。
帳簿の作成は、エクセルや手書きでもできる
帳簿の作成は、会計ソフトのほか、エクセルや手書きでも可能です。現金出納帳や預金出納帳といったシンプルな帳簿はもちろん、仕訳帳や総勘定元帳をエクセルや手書きで作ることも不可能ではありません。
複式簿記での記帳には、仕訳帳と総勘定元帳が必須です。エクセルや手書きで対応するのであれば、まず仕訳帳を作成して、その後、総勘定元帳や補助簿に転記しましょう。エクセルであれば集計などは自動化できますが、手書きの場合は計算も自分で行わなければなりません。ミスがないように検算を十分に行う必要があります。一方、エクセルで作成するときは、入力ミスや式の破損、記載漏れなどに気を付けてください。
なお、それぞれの帳簿には、必ず盛り込まなければならない記載項目があります。例えば仕訳帳なら、取引日付、借方と貸方の勘定科目、金額、摘要といった項目は必須です。エクセルや手書きで帳簿を自作するときは、項目の漏れがないようにしなければなりません。
必須項目を押さえた帳簿を作成したい場合は、テンプレートを活用するのが便利です。エクセルのテンプレートは、「【無料】個人事業主向けの帳簿テンプレート(Excel形式)」などからダウンロードできます。
ただし、エクセルや手書きで帳簿を付けるのは手間と時間がかかり、記載ミスを防ぐのも困難です。簡単に正確な記帳をしたいなら、自動集計や確定申告書類への転記も可能な「やよいの青色申告 オンライン」や「やよいの白色申告 オンライン」のような会計ソフトを利用するのがおすすめです。
手書きでの帳簿の付け方については以下の記事で詳しく解説していますので参考にしてください。
帳簿を付けなかった場合のペナルティ
帳簿を正しく付けていないと、確定申告で正しい数字を申告できずにペナルティを受ける可能性があります。特に、本来納めるべき税金を期限までに納付しなかったり、納めるべき税金よりも少ない金額で申告したりした場合は、以下のようなペナルティが科される可能性があるため、注意が必要です。
過少申告加算税
過少申告加算税は、本来納めるべき金額よりも少ない金額で確定申告や納税をした際に加算される税金です。帳簿の記載内容が不正確なケースなどで、本来よりも少ない金額で税額を申告してしまうと過少申告加算税を課せられます。
過少申告加算税の納税額は、原則として新たに納めることになった税金の10%相当額です。ただし、新たに納める税金が、当初の申告納税額と50万円のいずれか大きい方を超えている場合は、超えた部分について15%の税金が課せられます。
さらに、売上に関する帳簿が保存されていなかったり不備があったりすると、過少申告加算税が最大10%加重される可能性があります。この規定の対象となる帳簿は、仕訳帳・総勘定元帳の売上に関する部分や、売上帳・現金出納帳といった売上金額を確認できる帳簿などです。
なお、税務調査の事前通知がある前に自ら間違いに気付いて申告内容を修正する修正申告をした場合、過少申告加算税は課せられません。税務署に指摘される前に修正申告をしましょう。
重加算税
重加算税は、申告内容を意図的に隠したり、虚偽の申告をしたりして脱税したときに加算される税金です。
本来よりも少ない金額を申告していた場合は、納めるべき税額の35%、無申告の場合は40%が加算されます。さらに、電子帳簿保存法に従ってスキャナ保存した書類や、電子データでやりとりした取引関係書類の改ざんがあった場合は10%の加重があります。
故意の隠蔽や無申告には重いペナルティが課せられるため、正直な申告を心掛けてください。
青色申告者の認定取り消し
帳簿の不備は、青色申告者の認定取り消しにつながるおそれもあります。そもそも青色申告は、一定水準の記帳を行い、帳簿に基づく正しい申告をする事業者を対象にした制度です。帳簿を付けずに青色申告をすることはできません。
しかし、災害などのやむを得ない事情がなく、帳簿作成や保存に不備があったとしても、直ちに青色申告が取り消しとなるわけではありません。青色申告の承認の取り消しについては、国税庁の事務運営指針である「個人の青色申告の承認の取消しについて」にもとづき、検討したうえで判断されます。
例えば、税務署から提示を求められたにもかかわらず、正当な理由なく帳簿や書類の提示を行わないと所得税法に則り、青色申告の承認の取消事由に該当することになります。
そのようなケースでは、提示できない年にさかのぼって青色申告の認定を取り消される可能性があります。また、脱税などにつながる悪質な帳簿の作成なども、取り消しの理由になります。
インボイス制度による個人事業主の帳簿作成への影響
2023年10月の適格請求書等保存方式(インボイス制度)導入以降、個人事業主の帳簿作成手順や書類の保存方法などにも変化がありました。
インボイス制度とは、複数税率に対応した消費税計算を行うための制度です。従来、消費税の課税事業者は、課税売上高にかかる消費税額から仕入にかかる消費税額を控除(仕入税額控除)して、差額を消費税として納税していました。しかし、インボイス制度導入後は、仕入税額控除の対象が、原則として適格請求書が発行された仕入のみに変更されています(経過措置あり)。
個人事業主の場合、前々年の課税売上高が1,000万円を超える事業者や、インボイス制度導入によって適格請求書発行事業者になった事業者は、消費税の課税事業者となり、仕入税額控除の計算をすることになります。その際は、原則として適格請求書発行事業者が発行した適格請求書の受領と、内容に沿った記帳、適格請求書の保存が必要です。一方、消費税の納税を行わない免税事業者の帳簿作成方法や書類の保存方法は、制度導入前と変わりません。
以下で、通常の課税事業者、小規模事業者に該当する課税事業者といった個人事業主の立場ごとに、インボイス制度による影響を確認していきましょう。
インボイス制度については以下の記事で詳しく解説していますので参考にしてください。
通常の課税事業者
小規模事業者に該当しない、通常の課税事業者へのインボイス制度の影響は、仕入税額控除について一般課税(本則課税)と簡易課税のいずれの方法を採用しているかによって異なります。
一般課税とは、実際に仕入に関して支払った消費税額を計算して仕入税額控除を行う方式です。一方、売上にかかった消費税額に、業種ごとに定められた「みなし仕入率」を掛けて仕入税額控除の金額を求めるのが簡易課税です。
一般課税を採用している事業者は、受け取った領収書や請求書が適格請求書としての要件を満たしているか確認しなければなりません。記帳する前に、「記載項目に不足がないか」「記載された適格請求書発行事業者の登録番号が正しいか」といった確認が必要です。
一方、簡易課税を採用している事業者は、適格請求書を保存していなくても仕入税額控除ができるため、確認の必要はありません。簡易課税制度の適用を受けたい場合は、原則として適用を受ける課税期間の前日までに「消費税簡易課税制度選択届出書」を所轄の税務署に提出する必要があります。
また、インボイス制度をきっかけに課税事業者になった免税事業者が、納める消費税額を売上税額の2割とすることができる特例を利用する場合も、簡易課税と同様受け取った領収書や請求書が適格請求書としての要件を満たしているか確認する必要はありません。この特例の適用期限は2026年9月30日までの⽇の属する各課税期間です。
小規模事業者に該当する課税事業者
課税事業者のうち、前々年の課税売上高が1億円以下、または前年1月から6月までの課税売上高が5,000万円未満の小規模事業者に該当する個人事業主は、少額特例を利用できます。事前の届出は必要ありません。
少額特例とは、税込1万円以下の課税仕入について、適格請求書がなくても、一定の要件を満たす帳簿の保存のみで仕入税額控除の適用を受けられる制度です。適用を受ける場合は、帳簿に以下の内容を記載しましょう。なお、少額特例の適用を受ける旨の記載は不要です。
少額特例の適用を受けるための帳簿の記載事項
- 課税仕入を行った取引相手の名称
- 取引年月日
- 取引内容(軽減税率の対象になる場合はその旨を記載する)
- 課税仕入の額
ただし、少額特例の対象期間は2029年9月30日までです。
電子帳簿保存法による個人事業主の帳簿作成への影響
個人事業主が、帳簿や紙でやりとりした取引関係書類などを電子データで保存したい場合や、電子データのまま取引先と書類をやりとりした場合には、電子帳簿保存法の規定に従う必要があります。
電子帳簿保存法には、国税関係帳簿や国税関係書類を電子データとして保存するための要件が定められています。仕訳帳や総勘定元帳、売掛帳、買掛帳などは国税関係帳簿に該当し、電子帳簿保存法の対象です。また、貸借対照表や損益計算書、請求書、領収書などは国税関係書類に該当します。
国税関係帳簿や国税関係書類は、電子帳簿保存法の要件を満たせば、データのまま保存することが認められています。会計ソフトなどを使用している人は対象になる可能性があるため、確認してみましょう。ただし、データで保存するかどうかは任意のため、紙で保存していても問題ありません。
一方、請求書や領収書などをデータで受け取った場合は、電子帳簿保存法の要件に沿う形で、必ずデータのまま保存しなければなりません。記帳が済んだ後の書類の保存方法には注意が必要です。保存要件を確認しておく必要があります。
電子帳簿保存法については以下の記事で詳しく解説していますので参考にしてください。
帳簿の作成業務を効率化するなら会計ソフトがおすすめ
帳簿の作成と保存は、個人事業主の義務なので、必ず対応しなければなりません。しかし、日々の業務に追われてなかなか時間が取れないこともあります。そのうえ、複式簿記での帳簿の作成は、簿記の知識が必要であるなど煩雑なため、特にエクセルや手書きだと、帳簿の作成や転記にも時間がかかるかもしれません。その場合、確定申告書を作成するための集計なども困難です。
正確な帳簿を手間なく作成するために、「やよいの青色申告 オンライン」や「やよいの白色申告 オンライン」のような会計ソフトの活用を検討しましょう。
「やよいの青色申告 オンライン」や「やよいの白色申告 オンライン」であれば、銀行口座明細の自動取込や自動仕訳機能を使って、記帳にかかる時間を短縮できます。簿記の知識がなくても、簡単に複式簿記での記帳ができるため、ぜひご活用ください。
確定申告ソフトなら、簿記や会計の知識がなくても確定申告が可能
確定申告ソフトを使うことで、簿記や会計の知識がなくても確定申告ができます。
今すぐに始められて、初心者でも簡単に使える弥生のクラウド確定申告ソフト「やよいの白色申告 オンライン」とクラウド青色申告ソフト「やよいの青色申告 オンライン」から主な機能をご紹介します。
「やよいの白色申告 オンライン」は、ずっと無料、「やよいの青色申告 オンライン」は初年度無料です。両製品とも無料期間中もすべての機能が使用できますので、気軽にお試しいただけます。もちろん、確定申告もe-Taxでの申告が可能です!
【無料・税額シミュレーター】売上と経費を入力して青色と白色の税額を比較してみよう!
初心者にもわかりやすいシンプルなデザイン

弥生のクラウド確定申告ソフトは、初心者にもわかりやすいシンプルなデザインで、迷うことなく操作できます。日付や金額などを入力するだけで、確定申告に必要な帳簿や必要書類が作成できます。
取引データの自動取込・自動仕訳で入力の手間を大幅に削減

弥生のクラウド確定申告ソフトは、銀行・クレジットカードなどの金融機関の明細や電子マネー、POSレジ、請求書、経費精算等のサービスと連携すると日々の取り引きデータを自動で取得します。
自動取得した取引データはAIが自動で仕訳して帳簿に反映します。学習機能があるので、使えば使うほど仕訳の精度がアップします。紙のレシートは、スマホやスキャンで取り込めば、文字を認識してデータに変換し、自動で仕訳します。これにより入力の手間と時間が大幅に削減できます。
確定申告書類を自動作成。e-Tax対応で最大65万円の青色申告特別控除もスムーズに

弥生のクラウド確定申告ソフトは、画面の案内に沿って入力していくだけで、収支内訳書や青色申告決算書、所得税の確定申告書、消費税の確定申告書等の提出用書類が自動作成されます。
「やよいの青色申告 オンライン」なら、青色申告特別控除の最高65万円/55万円の要件を満たした資料の用意も簡単です。インターネットを使って直接申告するe-Tax(電子申告)にも対応し、最大65万円の青色申告特別控除もスムーズに受けられます。
自動集計されるレポートで経営状態がリアルタイムに把握できる

弥生のクラウド確定申告ソフトに日々の取引データを入力しておくだけで、レポートが自動で集計されます。経営状況やお金の流れをリアルタイムで確認できます。最新の経営状況を正確に把握することで、早めの判断ができるようになります。
無料お役立ち資料【「弥生のクラウド確定申告ソフト」がよくわかる資料】をダウンロードする
この記事の監修者田中卓也(田中卓也税理士事務所)
税理士、CFP®
1964年東京都生まれ。中央大学商学部卒。
東京都内の税理士事務所にて13年半の勤務を経て独立・開業。
従来の記帳代行・税務相談・税務申告といった分野のみならず、事業計画の作成・サポートなどの経営相談、よくわかるキャッシュフロー表の立て方、資金繰りの管理、保険の見直し、相続・次号継承対策など、多岐に渡って経営者や個人事業主のサポートに努める。一生活者の視点にたった講演活動や講師、執筆活動にも携わる。