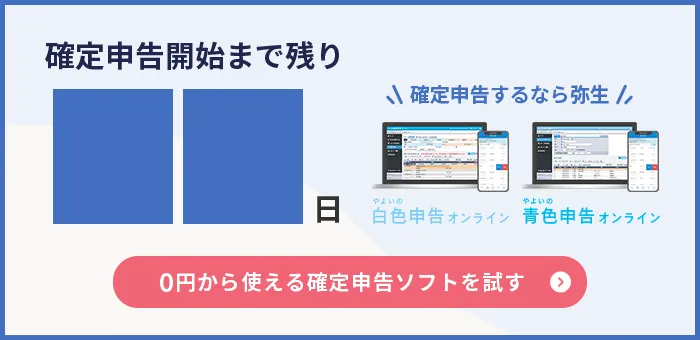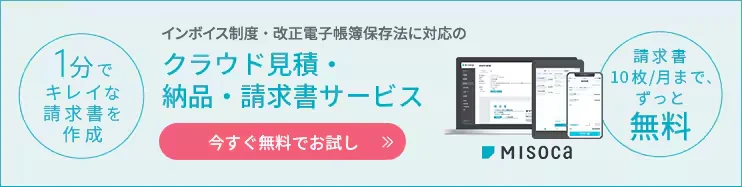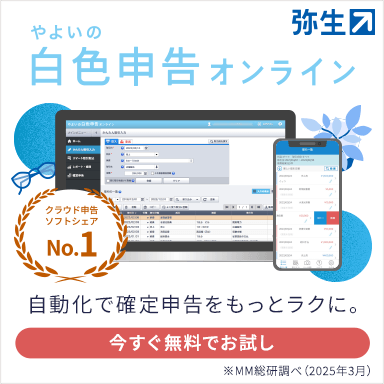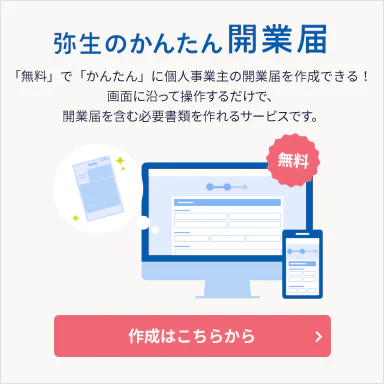副業の税金はいくら?税金の種類や計算方法について解説
監修者: 齋藤一生(税理士)
更新

副業で得た年間所得を含め、本業以外の所得の合計額が20万円を超える場合、所得税の確定申告を行う必要があります。では、いくらくらいの税金がかかるのでしょうか。
本記事では、副業の所得にかかわる税金の種類や確定申告の条件などを踏まえ、税金の計算方法を紹介していきます。
【無料・税額シミュレーター】売上と経費を入力して青色と白色の税額を比較してみよう!
副業で所得が増えると納める税金も増える
副業の所得に課せられる税金には、主に所得税、住民税、消費税があります。
所得税と住民税はいずれも個人の所得(収入から経費などを差し引いた額)に対してかかる税金です。基本的には確定申告を行うことで、所得税と住民税の額が決まります。なお、それぞれ納税先が異なり、所得税は「国の税金」であるのに対し、住民税は「都道府県または市区町村の税金」です。
まず、所得税は、課税される所得金額が高くなればそれに応じて税率も高くなる「超過累進課税」が採用されています。つまり、副業の収入が多くなるほど、納める税金の割合が増えるのです。所得税の税率については後述します。
一方で住民税の税率に関しては、課税される所得金額に対し、一律10%です。
また、副業の取引先によっては、適格請求書(インボイス)の発行を求められるケースがあります。適格請求書を発行するためには適格請求書(インボイス)発行事業者の登録が必要です。適格請求書発行事業は、インボイス制度に則って、帳簿付けや適格請求書の発行と保存、消費税の納税義務が生じます。
ずっと無料で使えるクラウド白色申告ソフトで帳簿も確定申告もかんたんに!
副業の税金はいくら?計算方法を解説
副業で収入を得た場合、納めなければならない税金はいくらくらいになるのか気になる方もいるでしょう。そこで、ここからは税金の計算方法について、順を追って解説します。
所得税の計算方法
前述のとおり、所得税は課税される所得額によって税率が変わります。所得税の算出は、「所得金額の算出」「課税される所得金額の算出」「所得税額の算出」の3ステップで行います。
1. 所得金額を算出する
所得税を計算するには、最初に所得金額を算出することが必要です。
所得は所得税法上、10種類に分類されています。副業の所得が該当するのは主に「雑所得」「事業所得」「給与所得」「不動産所得」の4つです。所得区分によって所得金額の計算式が異なりますが、給与所得以外は、売上から経費を差し引いて計算します。
給与所得以外の副業所得の計算式
副業所得=売上-必要経費
- 雑所得
本業が会社員など給与所得者の副業の場合、副業所得の多くは雑所得に該当します。雑所得とは9種類の所得区分のいずれにも当てはまらないその他の所得です。副業の収入を給与ではなく報酬として受け取っており、事業的規模ではないものは、基本的に雑所得に分類されるケースが多いといえます。
- 事業所得
事業所得とは、農業、製造業、卸売業、小売業などの事業活動から得られる所得です。副業の場合でも、事業規模や費やす時間、継続性の観点から事業所得として認められるケースがあります。なお、事業所得の場合は、原則として、帳簿書類の作成・保存が必要です。副業の規模が事業的規模であっても、帳簿書類の作成・保存をしていない場合は、事業所得と認められない可能性が高いです。
なお、事業所得の場合、青色申告を選択できるので節税になります。売上から必要経費を引いた後に、更に青色申告特別控除を引いた後の金額を所得とすることができます。
- 給与所得
給与所得とは、会社から従業員に対して支払われる年間の給与の合計から、給与所得控除を差し引いた金額のことです。副業のパート・アルバイトなど給与として得た収入が給与所得に該当します。本業・副業ともに給与所得の場合、年末調整ができるのは1社のみとなるため、副業の年収によっては確定申告が必要となります。給与所得の算出においては、本業・副業両方の1年間の給与を足し、給与所得控除を差し引きます。
給与所得の計算式
給与所得=1年間の給与合計金額-給与所得控除
- 不動産所得
不動産所得は、不動産を貸し出して得た所得です。具体的には、土地や建物などの不動産の貸し付けの他、船舶や航空機の貸し付けなどが不動産所得に該当します。
事業所得と同様、不動産所得も青色申告を選択できます。
2. 課税される所得金額を算出する
次に、算出した所得金額から所得控除を差し引き、課税される所得金額を算出します。
課税される所得金額の算出式
課税される所得金額=所得金額-所得控除
所得控除とは扶養家族の人数や支払った医療費など、納税者の状況に合わせ、所得税の負担を軽減するために設けられているしくみです。
控除ごとに差し引ける金額の計算方法が定められているため、適用できる控除を確認し、漏れなく申告しましょう。
-
※国税庁「No.1100 所得控除のあらまし
」
所得控除についてはこちらの記事でも解説していますので、参考にしてください。
3. 所得税額を計算する
課税される所得金額に所定の所得税の税率を掛け、所得税額を算出します。
所得税額の算出方法
所得税額=課税される所得金額×所得税の税率
所得税の税率は、課税される所得金額によって7つに区分されており、所得税額の算出は複雑です。そのため、所得税額の算出をする際には、国税庁による所得税の速算表に当てはめるとよいでしょう。
| 課税される所得金額 | 税率 | 控除額 |
|---|---|---|
| 1,000円から194万9,000円まで | 5% | 0円 |
| 195万円から329万9,000円まで | 10% | 9万7,500円 |
| 330万円から694万9,000円まで | 20% | 42万7,500円 |
| 695万円から899万9,000円まで | 23% | 63万6,000円 |
| 900万円から1,799万9,000円まで | 33% | 153万6,000円 |
| 1,800万円から3,999万9,000円まで | 40% | 279万6,000円 |
| 4,000万円以上 | 45% | 479万6,000円 |
- ※課税される所得金額は、1,000円未満の端数を切り捨てた後の金額
-
※国税庁「No.2260 所得税の税率
」
例えば、課税される所得金額が300万円の場合、計算方法は以下のとおりです。
課税される所得金額が300万円の場合の所得税額
300万円×10%-9万7,500円=20万2,500円
住民税の計算方法
住民税には、都道府県に納めるものと、市区町村に納めるものの2種類があり、2つを合せて納税します。本業が会社員の場合、住民税は給与から天引きされるのが一般的です。所得に応じて住民税額が決まるため、副業の所得があり確定申告をしていない場合、住民税の申告が必要になります。
住民税の計算方法は次のとおりです。
1. 所得額を算出する
本業と副業の所得額を合算し、総所得金額を算出します。
2. 課税される所得額を算出する
「1」の総所得金額から所得控除を差し引き、課税される所得額を算出します。
3. 所得割額を算出する
所得割とは、課税される所得に課せられる住民税になります。税率は一律で10%です。「2」で算出した課税される所得額に10%を掛け、所得割額を算出します。
4. 税額控除を差し引く
「3」で算出した所得割額から住宅ローン控除(住宅借入金等特別控除)などの税額控除を差し引き、最終的な所得割の金額を計算します。
5. 均等割を加算する
均等割とは、所得額にかかわらず、居住する市区町村から均等に課される住民税です。自治体により異なるケースもありますが、均等割の金額は基本的に5,000円になります。
「4」で算出した所得割の金額に、均等割の金額を加算したものが、納めるべき住民税額です。
住民税の計算方法などについてはこちらの記事でも解説していますので、参考にしてください。
消費税の計算方法
副業に伴い適格請求書発行事業者として登録した場合、消費税はどのように計算したらよいのでしょうか。計算方法としては、「本則課税(原則課税)」と「簡易課税」の2つがあります。いずれかを選ぶことができますが、簡易課税を選択する場合は事前に届出が必要です。なお、インボイス制度を機に適格請求書発行事業者になることで消費税の申告が必要になった人は、一定期間2割特例(売上にかかる消費税の2割を納めればよい)があります。
本則課税(原則課税)の計算式
消費税納税額=受け取った消費税の額-仕入等の際に支払った消費税の額
簡易課税の計算式
消費税納税額=受け取った消費税額×業種ごとの一定の割合(みなし仕入率)
計算方法としては、簡易課税の方が本則課税よりも簡単ですが、原則として基準期間の課税売上高が5,000万円以下の事業者のみ適用できます。副業の場合、課税売上高が5,000万円を超えることは稀と考えられるでしょう。
適格請求書発行事業者に登録した場合、適格請求書の発行や帳簿付けも必要になるため、確定申告ソフトの導入なども検討することをおすすめします。
ずっと無料で使えるクラウド白色申告ソフトで帳簿も確定申告もかんたんに!
副業の所得が年間20万円超なら、所得税の確定申告が必要
業務の副業の年間所得が20万円を1円でも超える場合、所得税の確定申告をしなければなりません。副業がアルバイトなど給与所得の場合は、副業の年間収入が20万円を超えると、確定申告が必要です。
20万円以下で税務署に確定申告しない場合において、利益が出ているのであれば住民税の申告が必要となります。
副業で経費計上できるもの
給与所得以外の副業は経費計上が認められます。収入から経費を引いた金額が所得となるため、経費を漏れなく計上することで節税対策となるのです。
例えば、経費計上できる費用として、以下のようなものがあげられます。
経費計上できる費用例
- 業務で使用するパソコンやスマートフォン、タブレットの購入費
- 打ち合わせや取材の交通費・飲食費
- コワーキングスペースの利用料
- コピー用紙や文房具などの事務用品費
- 水道代や電気代、家賃などの一部(自宅を仕事場として利用している場合)
また、副業であっても減価償却(高額な購入費用を使用可能期間にわたって分割して計上する)が可能です。取得金額が10万円を超え、1年以上使うものについては、取得金額を耐用年数で割った金額で経費計上できます。
副業の経費についてはこちらの記事でも解説していますので、参考にしてください。
確定申告の方法は2種類
確定申告の方法には、「白色申告」と「青色申告」があります。
本業が会社員など給与所得者の場合、副業が給与所得か雑所得の場合は白色申告で確定申告をしなければなりません。白色申告とは、簡易的な帳簿に記載することで確定申告を行う方法を指します。
副業が事業所得か不動産所得に該当する場合は、白色申告か青色申告を選ぶことが可能です。青色申告をする場合は事前の届出が必要になりますが、条件を満たすことで最大65万円の青色申告特別控除を受けられるなど、節税の面でメリットが大きいといえます。
青色申告と白色申告の違いについてはこちらの記事でも解説していますので、参考にしてください。
確定申告には確定申告ソフトの利用がお勧め
副業でも確定申告を行うためには、前述したように1年間の所得を算出しなければなりません。副業の雑所得では帳簿付けは義務ではありませんが、収入や経費から所得を計算するには、帳簿付けをしておくと楽です。副業が事業所得に該当する場合はもちろん帳簿付けが必要です。雑所得の人でも適格請求書発行事業者の場合は、消費税申告とインボイス制度に則った帳簿付が必要です。
弥生のクラウド確定申告ソフト「やよいの白色申告 オンライン」は、ずっと無料で帳簿作成や所得税の確定申告書作成、収支内訳書作成、消費税申告にも対応しています。副業が事業所得の場合は、ぜひご活用ください。副業が雑所得の場合も、無料で使えるので帳簿付けに活用してみてください。
副業所得が20万円以下でも確定申告をした方がいいケースも
副業の年間所得が20万円以下の場合でも、確定申告を行うことで納めた税金の一部が戻ってくる可能性があります。
例えば、副業の報酬から所得税がすでに源泉徴収されて支払われている場合は、確定申告を行うことで払いすぎた源泉徴収税が還付される可能性が高いです。
また、医療費控除や住宅ローン控除など年末調整の対象とならない控除を受けたい場合、確定申告によって還付を申告することができます。このように副業以外の理由で確定申告をする場合は、副業の年間所得を漏れなく申告してください。
ずっと無料で使えるクラウド白色申告ソフトで帳簿も確定申告もかんたんに!
副業は納めるべき税金にもかかわる!収入や経費などをきちんと把握しよう
副業で得る収入には、所得税や住民税がかかるほか、適格請求書発行事業者として登録した場合は消費税の納税義務が生じます。
副業の年間所得が20万円を1円でも超える場合、所得税の確定申告が必要となります。日本の所得税は超過累進課税制度が採用されており、所得が増えるほど税率が高くなるため、漏れなく経費を計上することが大切です。
確定申告を行う場合は、データを取り込むだけで複雑な帳簿を作成し、必要な書類を揃えることができる確定申告ソフトの導入も検討したいところです。「やよいの白色申告 オンライン」や「やよいの青色申告 オンライン」であれば、書類作成に加えてe-Tax(電子申告)にも対応しているため、税務署に行かずに確定申告ができます。
なお、ずっと無料で使える「やよいの白色申告 オンライン」は、作成した収支内訳書から確定申告書を作成すると、事業所得に集計されます。副業の所得を雑所得として確定申告をする場合は、「やよいの白色申告 オンライン」で作成した書類を基に、国税庁の確定申告書等作成コーナーで収支内訳書と確定申告書に転記するとスムーズです。
ずっと無料で使えるクラウド白色申告ソフトで帳簿も確定申告もかんたんに!
副業のバックオフィス業務は弥生のクラウドソフトで効率化
事業所得になる副業の確定申告は申告ソフトを使って楽に済ませよう
会社員などが副業をした場合、副業の所得が20万円を超えると、原則として確定申告が必要です。副業の収入や報酬から源泉徴収をされているなら、確定申告をすれば納めすぎた税金が返金される可能性が高いでしょう。ただ、所得税の確定申告をするには、書類の作成や税金の計算など面倒な作業が多いため、負担に感じる方もいるかもしれません。
事業所得になる副業は、帳簿付けが必要です。そんなときにおすすめなのが、弥生のクラウド確定申告ソフト『やよいの白色申告 オンライン』です。『やよいの白色申告 オンライン』はずっと無料で使えて、初心者や簿記知識がない方でも必要書類を効率良く作成することができます。e-Tax(電子申告)にも対応しているので、税務署に行かずに確定申告をスムーズに行えます。
副業の所得区分を事業所得・雑所得どちらにするか迷っている場合、まずは帳簿付けをしておきましょう。事業所得で確定申告する場合は帳簿が必要です。雑所得の場合、帳簿付けの義務はありませんが、売上や仕入・経費などの集計に帳簿がある方が便利です。
なお、『やよいの白色申告 オンライン』では、雑所得の収支内訳書と所得税の確定申告書は作成できません。もし、『やよいの白色申告 オンライン』で作成した収支内訳書から確定申告書を作成すると自動で「事業所得」に集計されます。国税庁の確定申告コーナーで、自分で収支内訳書と確定申告書に転記して申告をしてください。
【無料・税額シミュレーター】売上と経費を入力して青色と白色の税額を比較してみよう!
クラウド見積・納品・請求書サービスなら、請求業務をラクにできる
クラウド請求書作成ソフトを使うことで、毎月発生する請求業務をラクにできます。今すぐに始められて、初心者でも簡単に使えるクラウド見積・納品・請求書サービス「Misoca」の主な機能をご紹介します。
「Misoca」は月10枚までの請求書作成ならずっと無料、月11枚以上の請求書作成の有償プランも1年間0円で使用できるため、気軽にお試しすることができます。また会計ソフトとの連携も可能なため、請求業務から会計業務を円滑に行うことができます。