領収書をメール添付で送るのは問題ない!例文や送付方法を紹介
監修者: 高崎文秀(税理士)
更新
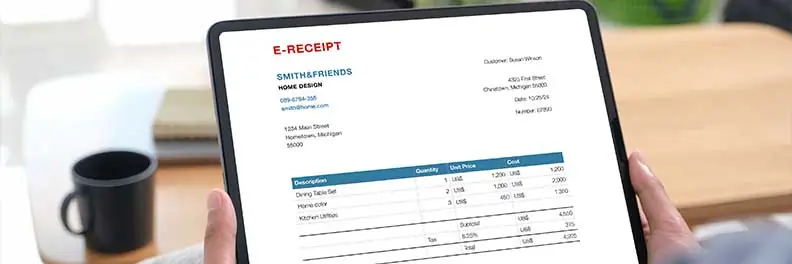
個人事業主や中小企業の経理担当者にとって、領収書の送付方法はきちんと押さえておかなければならない業務の1つです。本記事では、領収書をメールで送付する方法や注意点を詳しく解説します。
メールで領収書を送ることで、切手代や印紙代を削減でき、送付の手間を減らせるだけでなく、紙の領収書よりも保存・管理がしやすくなるといったメリットがあります。領収書を正しくメールで送るための方法や注意点がわかる内容ですので、ぜひ確認してみてください。
無料【クラウド請求書作成ソフト「Misoca」がよくわかる資料】をダウンロードする
領収書をメールに添付して送るのは問題ない
電子データ化した領収書をメールで送付することは、法律上問題ありません。電子帳簿保存法では、国税関係書類の一部を電子データとして保存することが認められており、2024年1月以降、電子取引のデータ保存が完全義務化されました。このため、メールでの領収書送付は適法であり、実務にも広く採用されています。
【1年間無料】フリーランスの見積・請求・申告は「Misoca×やよいの青色申告 オンライン」セットがお得!
領収書をメールで送る方法
領収書を電子データとしてメールで送るには、いくつかの方法があります。
紙の領収書をスキャンしてメールに添付する
紙の領収書をメールに添付するためには、まず紙の領収書をスキャンしてPDF化する必要があります。スキャンする際には、電子帳簿保存法の「スキャナ保存」の適用要件を満たす必要があります。
電子帳簿保存法のスキャナ保存制度について、詳しくは以下の記事をご覧ください。
Word・ExcelをPDF化してメールに添付する
ワード(Word)やエクセル(Excel)で作成した領収書をメールに添付して送る場合には、領収書の原本性を確保し、改ざんのリスクを低減するために、ファイルをPDF形式に変換することが推奨されます。ファイルをそのまま送ると、文字化けが発生したり、意図しない変更が加えられたりするリスクがあるため、PDF化することが重要です。
ただし、PDF化しても完全に改ざんを防止できるわけではなく、編集することは可能です。したがって、PDFへの変換後に、パスワードで保護するなどのセキュリティ対策を講じることが望まれます。これにより、誤解を招くことなく、領収書としての信頼性を高められます。
PDF化の手順は簡単で、Wordなどで作成した領収書を「名前を付けて保存」する際、ファイル形式でPDFを選択すれば完了です。
領収書作成システムを使ってメールで送付する
領収書作成システムを利用すれば、領収書の作成と送付を一元管理できます。この方法は特に取引先が多い場合に便利です。領収書作成システムでは、領収書をそのままメールで送信することが可能になり、切手代や印紙代を削減できます。
また、領収書作成システムであれば、紙の領収書をスキャンしてメールに添付する手間が省けます。領収書の保存・管理もデジタル化できるためペーパーレス化にも寄与し、領収書にかかる業務が効率的に進められます。
メール本文に領収内容を記載して送付する
領収内容をメール本文に記載して送付する方法もあります。要件を満たす場合、メールそのものが領収書として認められます。以下の手順で行います。
-
-
(1)メール本文に領収内容を記載:領収書の内容(発行日、金額、取引内容、発行者情報など)をメール本文に記す
-
(2)取引先の承認を得る:メールでの領収書送付について、取引先の了承を得ておく
-
(3)改ざん防止のための措置:メールは内容を改ざんできず、証憑書類としての要件を満たせるように講じる
-
ただし、念のために送信前に内容を再確認し、送信後に送信済みメールを保存しておくことをおすすめします。この方法は簡便で、急ぎの取引や少額の取引に適しています。また、紙の領収書をスキャンして送付する手間が省けるため、効率的です。
【1年間無料】フリーランスの見積・請求・申告は「Misoca×やよいの青色申告 オンライン」セットがお得!
領収書をメールで送るときの例文
件名:領収書の送付について
株式会社〇〇〇〇
〇〇様
お世話になっております。
〇〇株式会社の〇〇です。
先日のご注文に関する領収書をPDF形式にて添付しております。
以下の内容をご確認ください。
領収日:20◯◯年12月24日
金額:¥XX,XXX
注文番号:123456789
何かご不明な点がございましたら、お気軽にご連絡ください。
今後とも、よろしくお願いいたします。
◯◯株式会社 経理部 ◯◯(担当者名)
連絡先:◯◯◯◯◯◯◯◯
(添付ファイル:領収書.pdf)
領収書の内容(領収日、金額、注文番号)をメール本文にも記載することで、受け取る側が内容を確認しやすくなります。また、質問や問題があった場合にすぐ連絡してもらえるように、担当者の名前や連絡先も漏れなく記載します。
【1年間無料】フリーランスの見積・請求・申告は「Misoca×やよいの青色申告 オンライン」セットがお得!
領収書をメールで送るメリット
領収書をメールで送れば、次のようなメリットが得られます。
-
(1)郵送代・印紙代を削減できる
-
(2)送付の手間を減らせる
-
(3)紙よりも保存・管理しやすくなる
切手代・印紙代を削減できる
領収書をメールで送る大きなメリットの1つは、郵送にかかる切手代や印紙代を削減できることです。通常、紙の領収書を郵送する場合、以下の費用が発生します。
- ・切手代
- 紙の領収書を郵送する場合、封筒や切手の費用、送付状の印刷代などが発生します。しかし、メールで送付すれば、インターネットを介して送信するため、これらの郵送コストがかかりません。
- ・印紙代
- 紙の領収書では、金額が5万円以上の場合、印紙税がかかります。これは、印紙税法に基づくもので、紙の書類が対象です。しかし、電子データとして領収書を送付する場合、印紙税法の対象外となるため、金額を問わず印紙税がかかりません。
例えば、紙の領収書に税抜き5万円以上~100万円以下の取引内容を記載した場合、200円の印紙代が必要になりますが、電子データで送付すればこれを節約できます。
領収書の収入印紙について、詳しくは以下の記事をご覧ください。
送付の手間を減らせる
送付の手間を大幅に減らせることも大きなメリットです。特に領収書の発行数が多い場合、この方法は非常に効果的です。
- ・作成や印刷の省力化
- 紙の領収書を発行する場合、領収書の作成、印刷、封筒への封入といった手間がかかりますが、メール送付に切り替えれば、これらのプロセスが不要になります。
- ・時間の節約
- 領収書の印刷や封入にかかる時間が削減されるため、その分の時間を他の業務に充てることが可能です。業務が効率化し、生産性の向上が期待できます。
- ・迅速な送付
- メールで領収書を即座に送信できるため、郵送に比べて大幅に時間を短縮できます。取引先にとっても、速やかに領収書を受け取れる点は大きな利点です。
紙よりも保存・管理しやすくなる
保存と管理の面でも多くのメリットがあります。
- ・データとして保存できる
- 電子化された領収書は、データとしてそのまま保存できるため、紙の領収書を整理して保管する手間が省けます。
- ・検索機能で迅速にアクセスできる
- 電子データは検索が簡単になるため、過去の領収書を探す際にも時間をかけることなく、迅速にアクセスできます。紙の領収書の場合には、ファイルから探し出すのに時間がかかることが多く、効率的とは言えません。
- ・保存スペースを削減できる
- 発行する領収書が多い場合、紙で保管するためには相応のスペースが必要です。電子データであれば、物理的なスペースを必要とせず、オフィスのスペースを有効活用できます。
- ・バックアップが容易
- 電子データは容易にバックアップできます。クラウドストレージや外付けハードディスクなどに保存すれば、万が一のデータ消失時にも安心です。
【1年間無料】フリーランスの見積・請求・申告は「Misoca×やよいの青色申告 オンライン」セットがお得!
領収書をメールで送るときの注意点
メリットの多い領収書のメール送付ですが、いくつか注意すべきポイントがあります。
取引先の承諾を得る
領収書をメールで送る際には、前もって取引先の承諾を得ておく必要があります。取引先から依頼があった場合を除き、先方が電子データでの領収書発行に同意していない場合には、郵送など他の方法で発行します。これは改正電子帳簿保存法によって、電子データで受け取った領収書は電子保存の義務があり、税務調査の際にデジタル記録での提示が必要となるためです。
また、領収書に押印が必要であるかの確認も忘れずに行いましょう。電子データで領収書を発行する場合、取引先によっては押印を必要とする場合もあります。この点についても、事前に取引先に確認し、もし押印が必要であれば、対応方法(例えば、電子印鑑の使用や、印刷した領収書に押印する方法)を決めておくことが重要です。
誤送信しないようメールアドレスを確認する
領収書をメールで送る際には、誤送信しないように細心の注意を払います。誤送信は情報漏洩につながり、信頼関係や企業価値を著しく落とす危険性があります。以下の点を押さえて、確実に正しい相手に送信するようにしましょう。
- ・メールアドレスの確認
- 送信前にメールアドレスを再確認します。入力ミスがないか、正しいアドレスであるかをしっかりと確認することが重要です。送信前にダブルチェックを行えば、誤送信のリスクを低減できます。
- ・PDFにパスワードを設定する
- セキュリティ対策として、領収書をPDF形式に変換し、パスワードを設定する方法があります。しかし、近年ではPPAP(Password Protected Attachment Protocol:パスワード付き添付ファイルの送信)が廃止される流れが主流となっています。理由は、パスワードを別メールで送る方法がセキュリティ上のリスクを伴うからです。
- ・セキュリティ上のリスク
- 一部の取引先では、セキュリティ上のリスクを理由にメール添付を禁止している場合があります。そのような場合は、別の安全な送信方法を検討する必要があります。例えば、クラウドストレージを利用してファイル共有する方法などがあります。
【1年間無料】フリーランスの見積・請求・申告は「Misoca×やよいの青色申告 オンライン」セットがお得!
領収書はメールで送って正しく管理しよう
領収書をメールで送ることは、切手代や印紙代といったコストの削減や業務効率化に貢献します。紙の請求書をスキャンして送る方法、WordやExcelのファイルをPDF化して送る方法、領収書作成システムを利用する方法、さらにメール本文に領収内容を記載して送る方法など、さまざまな手段があります。
領収書をメールで送る際は、取引先の承諾を得て誤送信しないよう注意する必要があります。特にセキュリティ面にも配慮し、適切な手段を講じましょう。
「領収書作成システムを使ってメールで送付する」を採用したい方には、弥生が提供するクラウド請求書作成ソフト「Misoca」がおすすめです。領収書などの帳票の発行からメール送信までクリック操作で簡単に行えます。業務効率化はもちろんのこと、取引先の登録をしておくことで、リストから送信できるので誤送信を防ぐといった観点からも役立ちます。ぜひ、「Misoca」の活用を検討してみてください。
【1年間無料】フリーランスの見積・請求・申告は「Misoca×やよいの青色申告 オンライン」セットがお得!
クラウド見積・納品・請求書サービスなら、請求業務をラクにできる
クラウド請求書作成ソフトを使うことで、毎月発生する請求業務をラクにできます。
今すぐに始められて、初心者でも簡単に使えるクラウド見積・納品・請求書サービス「Misoca」の主な機能をご紹介します。
「Misoca」は月10枚までの請求書作成ならずっと無料、月11枚以上の請求書作成の有償プランも1年間0円で使用できるため、気軽にお試しすることができます。
見積書・納品書・請求書をテンプレートでキレイに作成

Misocaは見積書 ・納品書・請求書・領収書・検収書の作成が可能です。取引先・品目・税率などをテンプレートの入力フォームに記入・選択するだけで、かんたんにキレイな帳票ができます。
各種帳票の変換・請求書の自動作成で入力の手間を削減

見積書から納品書・請求書への変換や、請求書から領収書・検収書の作成もクリック操作でスムーズにできます。固定の取引は、請求書の自動作成・自動メール機能を使えば、作成から送付までの手間を省くことが可能です。
インボイス制度(発行・保存)・電子帳簿保存法に対応だから”あんしん”

Misocaは、インボイス制度に必要な適格請求書の発行に対応しています。さらに発行した請求書は「スマート証憑管理」との連携で、インボイス制度・電子帳簿保存法の要件を満たす形で電子保存・管理することが可能です。
確定申告ソフトとの連携で請求業務から記帳までを効率化

Misocaで作成した請求書データは、弥生の確定申告ソフト「やよいの青色申告 オンライン」に連携することが可能です。請求データを申告ソフトへ自動取込・自動仕訳できるため、取引データの2重入力や入力ミスを削減し、効率的な業務を実現できます。
会計業務はもちろん、請求書発行、経費精算、証憑管理業務もできる!
法人向けクラウド会計ソフト「弥生会計 Next」では、請求書作成ソフト・経費精算ソフト・証憑管理ソフトがセットで利用できます。自動的にデータが連携されるため、バックオフィス業務を幅広く効率化できます。

「弥生会計 Next」で、会計業務を「できるだけやりたくないもの」から「事業を成長させるうえで欠かせないもの」へ。まずは、「弥生会計 Next」をぜひお試しください。
無料【クラウド請求書作成ソフト「Misoca」がよくわかる資料】をダウンロードする
この記事の監修者高崎文秀(税理士)
高崎文秀税理士事務所 代表税理士/株式会社マネーリンク 代表取締役
早稲田大学理工学部応用化学科卒
都内税理士事務所に税理士として勤務し、さまざまな規模の法人・個人のお客様を幅広く担当。2019年に独立開業し、現在は法人・個人事業者の税務顧問・節税サポート、個人の税務相談・サポート、企業買収支援、税務記事の監修など幅広く活動中。また通常の税理士業務の他、一般社団法人CSVOICE協会の認定経営支援責任者として、業績に悩む顧問先の経営改善を積極的に行っている。












