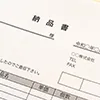請求書と領収書の違いは?請求書は領収書の代わりに使える?詳しく解説
監修者: 高崎文秀(税理士)
更新
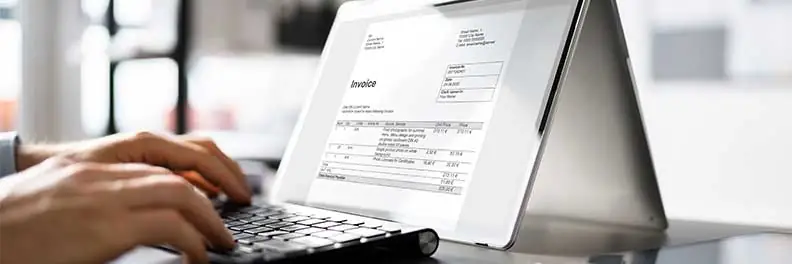
請求書と領収書はどちらも取引における重要書類ですが、その役割や発行タイミングなどに大きな違いがあります。その一方で、一部のケースでは「請求書兼領収書」という形で一緒にまとめられることもあるため、戸惑ってしまう方も多いのではないでしょうか。そこで本記事では、請求書と領収書の違いや使い分けなどについて、基礎からわかりやすく解説します。
無料【クラウド請求書作成ソフト「Misoca」がよくわかる資料】をダウンロードする
請求書と領収書の違い
以下の表に示されるように、請求書と領収書は、多くの点で異なります。
| 請求書 | 領収書 | |
|---|---|---|
| 発行目的 | 買い手側に支払いを促すため | 支払いの事実を証するため |
| 発行タイミング | 代金の支払前 | 代金の支払後 |
| 収入印紙の貼付 | 原則不要 | 現金での取引金額が5万円以上の場合、原則必要 |
| 保管期間 | 法人は7年間、個人事業主は5年間※1 | 法人・個人事業主ともに原則7年間※2 |
- ※1ただし、消費税の課税事業者または適格請求書発行事業者は、個人事業主でも7年間
- ※2ただし、白色申告の個人事業主、または前々年度の所得金額が300万円以下の青色申告の個人事業主は5年間でも可
請求書とは
請求書とは、売り手が商品やサービスを提供した後、買い手に対して代金の支払いを求めるために発行する書類です。請求書には、取引内容や金額、支払期限、振込先などが記載されており、金銭を正確かつ円滑に授受するために重要な役割を果たします。
請求書の作成方法について詳しくは、以下の記事をご参照ください。
請求書を発行するタイミング
請求書の役割は、取引の対価として支払われる金額や支払条件などを買い手側に明示し、その支払いを促すことにあります。そのため、請求書の発行は代金の支払前に行われるのが通例です。具体的には、商品の納品に併せて個別に請求書を送るパターン、一定期間の取引分をまとめた請求書を送るパターンなどがあります。
請求書における収入印紙の扱い
請求書は、印紙税法における課税文書に該当しないため、通常は収入印紙の貼付が不要です。ただし、後述する「請求書兼領収書」として金銭の受領を証する文言がある場合には、領収書と同様に課税文書(第17号文書)に分類されるため、収入印紙の貼付が必要になる場合があります。
参照:国税庁「印紙税額の一覧表(第1号文書から第20号文書まで)」
請求書の保管期間
請求書の保管義務は、受領者だけでなく、発行者が作成した控えも対象となるため、一定期間適切に保管しなければなりません。この保管期間は事業形態によって異なります。法人の場合は、法人税法に基づき、保管期間は原則7年間です。個人事業主のうち一定の場合、所得税法に基づき、原則5年間保管するように義務付けられています。ただし、消費税の課税事業者または適格請求書発行事業者に該当する場合、個人事業主でも7年間の保管が必要です。
参照:国税庁「No.5930 帳簿書類等の保存期間」
参照:国税庁「記帳や帳簿等保存・青色申告」
領収書とは
領収書とは、売り手が商品やサービスの代金を受け取ったことを証明するために買い手へ発行する書類です。記載内容には、取引日(受領した日)、金額(受領した額)、宛名(支払者の名称)、取引内容(ただし書き)などが含まれます。
領収書は、金銭の授受が実際に行われた証拠として、税務処理の面でも、社内の会計処理の面でも非常に重要な書類です。例えば、社員が現金取引で経費を支払った場合、企業は経費精算するためにその領収書の提出を求めるのが一般的です。
領収書について詳しくは、こちらの記事もご参照ください。
領収書を発行するタイミング
領収書は、金銭の授受が実際に行われたことを証明する書類であるため、その発行タイミングは代金の支払後が原則です。一般的な小売業などの場合、買い手側から商品の購入時に領収書を要望し、売り手側がその場で発行するケースが多く見られます。
領収書における収入印紙の扱い
請求書とは異なり、領収書は課税文書に分類されるため、要件によっては収入印紙の貼付が必要です。収入印紙の貼付が必要となる代表的な要件としては、取引金額が5万円以上であり、かつ現金で支払われた場合などが挙げられます。また、貼付した印紙には割印(消印)を行うことが義務付けられています。
なお、支払方法がクレジットカードの場合や、PDFのように電子的に発行された領収書の場合などのケースでは取引金額にかかわらず収入印紙が不要です。
詳しくは以下の記事をご参照ください。
参照:国税庁「No.7140 印紙税額の一覧表(その1)第1号文書から第4号文書まで」
参照:国税庁「No.7141 印紙税額の一覧表(その2)第5号文書から第20号文書まで」
領収書の保管期間
領収書の保管期間は、法人・個人事業主共に原則7年間です。ただし、白色申告の個人事業主は5年間の保管でよいとされています。また、欠損金の繰越控除を適用する場合には、10年間の保管が必要です。
参照:国税庁「No.5930 帳簿書類等の保存期間」
参照:国税庁「記帳や帳簿等保存・青色申告」
請求書兼領収書とは
上記のように、請求書と領収書は多くの点で異なりますが、「請求書兼領収書」というように、1枚の書類にまとめられることがあります。請求書兼領収書が利用されるのは、代金の請求タイミングと支払タイミングが同時の場合です。例えば、医療機関や、対個人の一部取引では「請求書兼領収書」が使われることがあります。それに対して、企業間取引ではあまり一般的ではありません。
請求書兼領収書は、印紙税法上は領収書と同様に課税文書の扱いになります。そのため、領収書と同じように、取引金額が5万円以上など、一定要件を満たした場合は収入印紙の貼付が必要です。なお、標題に「請求書」としか書かれていなくても、その記載内容が金銭の受領を証するもの(=領収書の内容を含むもの)であれば、収入印紙を貼付しなければなりません。
請求書兼領収書について、詳しくはこちらの記事もご参照ください。
【無料でお試し】クラウド請求書作成ソフト「Misoca」でかんたんキレイに請求書作成!
請求書は領収書の代わりとして使える?
上述のように、請求書と領収書は多くの点で性質が異なりますが、場合によっては請求書を領収書の代わりとして使うこともできます。ここでポイントになるのは、「領収書の代わりに支払いの事実を証明できる手段が他にあるか」どうかです。以下では、請求書を領収書の代わりとして使えるケース・使えないケースをそれぞれ解説します。
現金による支払いの場合は代わりとして使えない
支払いが現金で行われた場合、請求書を領収書の代わりに使うことは原則できません。というのも、現金支払いでは、支払記録が口座や決済システムなどに残らないため、領収書やレシートなどがないと、「実際に支払いがあった」という事実を証明することが難しくなるからです。通常の請求書はあくまで支払い前に「代金を請求するための書類」に過ぎませんので、支払いが完了した証明にはなりません。
請求書が領収書代わりとして認められるケース
その一方で、銀行振込やクレジットカードなど、支払記録が明細として残る決済手段を用いた場合には、その明細と組み合わせて請求書を領収書代わりに使うことが認められる可能性があります。
請求書はそれ自体では支払いの事実があったことを示す手段にはなりませんが、その代わりに、支払金額や取引内容などの詳細情報は記載されています。それに対して、口座履歴やクレジットカードの明細には通常、簡易的な情報しか記載されていませんが、支払いの事実があったことを示す手段としては有効です。
そのため、請求書と明細の対応関係を証明できれば、領収書なしでも証憑書類としての信頼性を確保できます。
とはいうものの、実務上は領収書があった方が処理をスムーズに進めやすいため、基本的には領収書を受け取っておいた方が無難です。また、請求書だけでは領収書代わりにならないのと同様、銀行の口座履歴やクレジットカードの支払明細だけでは領収書の代わりにはなりません。
【無料でお試し】クラウド請求書作成ソフト「Misoca」でかんたんキレイに請求書作成!
請求書や領収書は電子化するのがおすすめ
近年、業務の効率化やコスト削減を目的に、請求書や領収書を電子化する企業が増えています。紙と異なり、電子データとして扱うことで多くのメリットが得られる他、法制度の整備も進み、電子取引に対応した保存方法が一般化しつつあります。ここからは、請求書や領収書を電子化することで得られる具体的なメリットや、導入の方法について解説します。
電子化するメリット
まず、請求書と領収書双方の電子化に共通するメリットとしては、以下が挙げられます。
- ・簡単に作成できる
テンプレートやシステムを利用すれば、形式や体裁の整った帳票を作成できます。
- ・再発行の手間を減らせる
上記と同じ理由から、取引先が帳票を紛失してもすぐに再発行できます。
- ・保存が容易になる
紙と違って、ファイリングの手間や保管スペースの確保などをする必要がありません。また、劣化する心配もなく、定期的にバックアップしておけば、データの紛失・破損のリスクも減らせます。
- ・検索での確認が容易になる
-
一般的に請求書発行システムには、日付や取引先名、金額などで必要なデータを簡単に検索できる機能が搭載されています。これにより、目的のデータを瞬時に見つけることが可能です。また、紙と比べてテレワークにも簡単に対応できます。
さらに、これらに加え、領収書を電子化する場合は、「印紙が不要になる」という大きなメリットがあります。領収書や請求書の電子化は、業務効率化、コスト削減、買い手側と売り手側双方の利便性向上に貢献します。
電子化する方法
請求書や領収書を電子化するには、帳票発行に対応したシステムを導入するのがおすすめです。例えば、クラウド型の帳票発行システムを活用することで、見積書・納品書・請求書・領収書などを一括で作成・管理し、社内外で簡単にデータを共有できます。また、電子帳簿保存法やインボイス制度などに対応したシステムを使えば、法令遵守も容易です。
なお、帳票の電子化を実現する際は、社内の運用フローを整備することも欠かせません。だれが、どのタイミングで帳票を作成・送信・保存するのかを明確にし、業務が円滑に進む体制を構築しましょう。
帳票の電子化については、以下の記事も参考にしてください。
【無料でお試し】クラウド請求書作成ソフト「Misoca」でかんたんキレイに請求書作成!
請求書と領収書の違いを把握して正しく扱おう
請求書と領収書は役割や発行タイミングなど異なる点が多いため、適切に使い分けることが重要です。特に現金支払いでは領収書が必須で、請求書では代用できません。請求書や領収書の発行業務を効率化するためには、弥生のクラウド請求書作成ソフト「Misoca」がおすすめです。「Misoca」を活用すれば、請求書や領収書の作成・発行・保存までを簡単に行えるようになります。インボイス制度や電子帳簿保存法にも対応可能です。ぜひ導入をご検討ください。
【無料でお試し】クラウド請求書作成ソフト「Misoca」でかんたんキレイに請求書作成!
クラウド見積・納品・請求書サービスなら、請求業務をラクにできる
クラウド請求書作成ソフトを使うことで、毎月発生する請求業務をラクにできます。
今すぐに始められて、初心者でも簡単に使えるクラウド見積・納品・請求書サービス「Misoca」の主な機能をご紹介します。
「Misoca」は月10枚までの請求書作成ならずっと無料、月11枚以上の請求書作成の有償プランも1年間0円で使用できるため、気軽にお試しすることができます。
見積書・納品書・請求書をテンプレートでキレイに作成

Misocaは見積書 ・納品書・請求書・領収書・検収書の作成が可能です。取引先・品目・税率などをテンプレートの入力フォームに記入・選択するだけで、かんたんにキレイな帳票ができます。
各種帳票の変換・請求書の自動作成で入力の手間を削減

見積書から納品書・請求書への変換や、請求書から領収書・検収書の作成もクリック操作でスムーズにできます。固定の取引は、請求書の自動作成・自動メール機能を使えば、作成から送付までの手間を省くことが可能です。
インボイス制度(発行・保存)・電子帳簿保存法に対応だから”あんしん”

Misocaは、インボイス制度に必要な適格請求書の発行に対応しています。さらに発行した請求書は「スマート証憑管理」との連携で、インボイス制度・電子帳簿保存法の要件を満たす形で電子保存・管理することが可能です。
確定申告ソフトとの連携で請求業務から記帳までを効率化

Misocaで作成した請求書データは、弥生の確定申告ソフト「やよいの青色申告 オンライン」に連携することが可能です。請求データを申告ソフトへ自動取込・自動仕訳できるため、取引データの2重入力や入力ミスを削減し、効率的な業務を実現できます。
会計業務はもちろん、請求書発行、経費精算、証憑管理業務もできる!
法人向けクラウド会計ソフト「弥生会計 Next」では、請求書作成ソフト・経費精算ソフト・証憑管理ソフトがセットで利用できます。自動的にデータが連携されるため、バックオフィス業務を幅広く効率化できます。

「弥生会計 Next」で、会計業務を「できるだけやりたくないもの」から「事業を成長させるうえで欠かせないもの」へ。まずは、「弥生会計 Next」をぜひお試しください。
無料【クラウド請求書作成ソフト「Misoca」がよくわかる資料】をダウンロードする
この記事の監修者高崎文秀(税理士)
高崎文秀税理士事務所 代表税理士/株式会社マネーリンク 代表取締役
早稲田大学理工学部応用化学科卒
都内税理士事務所に税理士として勤務し、さまざまな規模の法人・個人のお客様を幅広く担当。2019年に独立開業し、現在は法人・個人事業者の税務顧問・節税サポート、個人の税務相談・サポート、企業買収支援、税務記事の監修など幅広く活動中。また通常の税理士業務の他、一般社団法人CSVOICE協会の認定経営支援責任者として、業績に悩む顧問先の経営改善を積極的に行っている。