白色申告で受けられる控除とは?控除額や青色申告の控除との違いを解説
監修者: 田中卓也(田中卓也税理士事務所)
更新
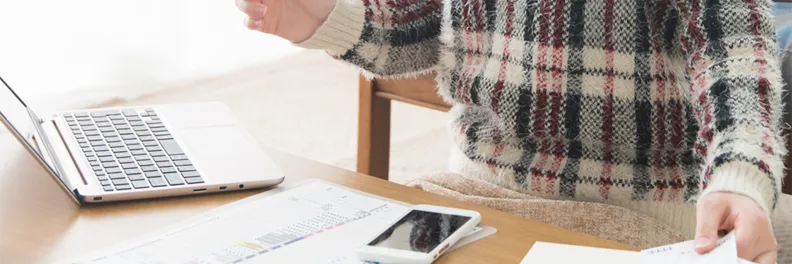
確定申告には白色申告と青色申告があり、どちらで申告するかで、利用できる控除が異なります。
白色申告をする際に適用を受けられる控除には、年間所得金額が2,500万円以下の人なら誰でも利用できる基礎控除のほか、白色申告の場合のみ受けられる事業専従者控除もあります。
ここでは、白色申告で受けられる控除や白色申告と青色申告の違い、白色申告する際の納付税額の計算方法について解説します。
なお、本記事は、令和7年度税制改正での2025年(令和7年)12月1日施行の内容を前提に記載をしております。また、この改正は原則として、2025年(令和7年)分以後の所得税について適用されます。
ただし、2025年(令和7年)11月までの給与及び公的年金等の源泉徴収事務に変更は生じません。
日付や金額などを入力するだけで、確定申告に必要な帳簿や申告書類が完成します
初年度無料ですべての機能が使用できます。
e-Taxも製品から直接できるので、自宅からかんたんに確定申告が可能です

白色申告で受けられる控除
個人事業主の確定申告には、白色申告と青色申告、2とおりの申告方法があります。白色申告では、基礎控除などの所得控除や住宅借入金等特別控除(住宅ローン控除)といった税額控除のほか、事業専従者控除の適用も受けられます。
一方、青色申告は、原則として複式簿記方式での記帳とそれに基づいた申告をする必要があるものの、白色申告よりもさまざまな税制の優遇措置を受けることができます。
はじめての確定申告もかんたん!無料から使える弥生のクラウド申告ソフト
白色申告と青色申告では適用を受けられる控除が異なる
白色申告と青色申告では、適用を受けられる控除や利用できる制度に違いがあります。これは、白色申告と青色申告では、求められる記帳方法や確定申告時の添付書類が異なるためです。
青色申告は、白色申告に比べて手続きや書類の作成が複雑ですが、白色申告にはない税制の優遇措置を受けられる申告方法になります。ただし、所得の区分が、事業所得、不動産所得、山林所得のいずれかでなければ、青色申告は行えません。
その分、青色申告は、最大65万円の控除の適用を受けられる青色申告特別控除など、白色申告にはない、さまざまな税制の優遇措置を受けられるメリットがあります。
一方、白色申告では、取引の損益状況のみを記録する単式簿記方式での記帳が認められています。また、確定申告時には貸借対照表の提出は不要で、収支内訳書を添付するだけです。しかし、白色申告では、青色申告に認められている、以下のような税制での優遇措置について適用を受けられません。
青色申告特別控除の適用を受ければ、その分課税所得額は小さくなり、納付税額も小さくなります。節税を考慮するなら、白色申告より青色申告の方がおすすめといえるでしょう。
【あなたはいくらお得?】青色・白色の税額を比較|今すぐ無料シミュレーション!
白色申告では適用を受けられない主な青色申告の特典
青色申告特別控除の適用
青色申告者は、納付税額を計算する際に65万円、55万円、10万円のいずれかの金額を所得から差し引ける、青色申告特別控除の適用を受けられる
青色事業専従者給与の適用
青色申告者は、生計を一にする配偶者や15歳以上の親族が申告者の事業に従事している場合、親族に支払った給与のうち相当と認められる金額の全額を必要経費にできる
純損失の繰越控除および繰戻還付の適用
青色申告では、事業で赤字が出た場合にその赤字を翌年以降3年間にわたって繰り越せる、繰越損失を申告できる。また、赤字になった前年も青色申告をしていれば、前年分の所得金額に繰り戻し、その分の税金の還付を受けることも可能
少額減価償却資産の特例の適用
取得価額が30万円未満の固定資産であれば、全額を取得時に必要経費として計上できる制度が、少額減価償却資産の特例です。通常、取得価額が10万円以上の固定資産を購入した場合には資産として計上し、減価償却を通じて、購入費用を一定期間に分散して計上しなければなりません。
白色申告と青色申告の違いや青色申告の特例については以下の記事で詳しく解説していますので参考にしてください。
はじめての確定申告もかんたん!無料から使える弥生のクラウド申告ソフト
所得や所得税額から控除を差し引くしくみ
所得から所得控除を差し引くと所得税額が算出され、さらにここから税額控除を差し引くと、納付すべき税額を計算できます。
所得税の最終的な納付税額は、所得から所得控除を差し引いて算出した、課税所得を基に計算します。また、所得税額から直接差し引ける税額控除という制度もあります。
所得控除、税額控除について、詳しく見ていきましょう。
所得控除は所得収入から差し引ける控除
所得控除は、収入から必要経費を差し引いた金額(所得)から、さらに差し引ける控除です。所得は所得税の計算をする際にベースとなる金額ですが、所得に直接税率を掛けて所得税を算出するのではなく、所得からさまざまな所得控除を差し引いた課税所得に税率を掛けて所得税を計算します。
ただし、実際に税率をかけて税額を計算する際に使うのは、所得ではなく、所得から各種所得控除を差し引いた課税所得になります。
課税所得を求める計算式は、以下のとおりです。
課税所得を求める計算式
課税所得=(収入-必要経費)-所得控除
所得から差し引く所得控除には、合計所得金額2,500万円以下のすべての申告者に、合計所得金額に応じて適用される基礎控除と、条件に応じて適用される控除があります。
基礎控除の控除額は、合計所得金額に応じて、16万円から95万円(2024年分までは16万円から48万円)です。
一方、条件に応じて適用される所得控除には、国民健康保険の保険料などを支払った場合に適用される社会保険料控除や、医療費が一定額を超えた場合に適用される医療費控除、生命保険料控除、配偶者控除、寄附金控除など全部で15種類あります。なお、控除額は人によって異なります。
所得控除、基礎控除については以下の記事で詳しく解説していますので参考にしてください。
税額控除は所得税額から直接差し引ける控除
税額控除とは、所得税額から一定額を差し引ける制度です。主な例としては、住宅借入金等特別控除(住宅ローン控除)や配当控除、政党等寄附金特別控除などがあります。それぞれの控除の要件を満たした場合に、算出した所得税額から直接一定の金額を差し引くことが可能です。
納めるべき所得税額を計算するには、課税所得に所得税率を掛けることで所得税額を算出し、そこから税額控除分を差し引きます。ただし、この金額が最終的に納めるべき税額になるわけではありません。
税額控除については以下の記事で詳しく解説していますので参考にしてください。
納付税額とは納めるべき所得税額
納付税額とは、最終的に納めるべき税額のことです。所得税の納付税額は、所得税額から税額控除を差し引き、そこに復興特別所得税を加えた金額になります。源泉徴収や予定納税により、既に納税した分がある場合は、最後にその金額を差し引きます。
納付税額を求める計算式
納付税額=(課税所得×所得税率)-税額控除+復興特別所得税額-既に納税した源泉徴収や予定納税分
既に納税した源泉徴収や予定納税分の金額が大きいと、納付税額がマイナスになることもあります。その場合の確定申告は、申告をすることで納めすぎた税金の還付を受けられる還付申告になります。
なお、所得税率は、課税所得の金額が高い部分ほど高い割合になります。
例えば、課税所得が500万円の場合、195万円までの部分にかかる所得税率は5%、195万円から330万円までの部分にかかる所得税率は10%、330万円を超える部分にかかる所得税率は20%という具合で、所得税額を求める計算はかなり複雑です。この計算を簡単にするために、以下のような「所得税の速算表」が利用されます。
所得税の速算表
| 課税される所得金額 | 税率 | 控除額 |
|---|---|---|
| 1,000円から194万9000円まで | 5% | 0円 |
| 195万円から329万9,000円まで | 10% | 9万7,500円 |
| 330万円から694万9,000円まで | 20% | 42万7,500円 |
| 695万円から899万9,000円まで | 23% | 63万6,000円 |
| 900万円から1,799万9,000円まで | 33% | 153万6,000円 |
| 1,800万円から3,999万9,000円まで | 40% | 279万6,000円 |
| 4,000万円以上 | 45% | 479万6,000円 |
-
※国税庁「No.2260 所得税の税率
- ※1,000円未満の端数金額は切り捨て
これを使うと、例えば、課税所得が500万円の所得税額は、「500万円×20%-42万7,500円=57万2,500円」というように計算できます。
復興特別所得税とは、東日本大震災の復興施策に必要な財源を確保するために、2037年まで課されている税金のことです。復興特別所得税の税額は、所得税額から税額控除分を差し引いた金額に、2.1%をかけた金額です。
例えば、所得税額が57万2,500円で、税額控除が5万2,500円なら、復興特別所得税額の額は、「(57万2,500円-5万2,500円)×2.1%=1万920円」になります。
また、源泉徴収や予定納税とは、以下のような制度です。
源泉徴収
源泉徴収とは、事業主が個人事業主に報酬を支払う際に、あらかじめ所得税などを差し引き、個人事業主に代わって納税するしくみのことです。例えば、ライターの原稿料や講演料、士業の報酬、プロのスポーツ選手の報酬などでは、源泉徴収が行われます。
予定納税
予定納税とは、所得税額の一部を事前に納める制度です。前年の所得金額や税額などを基に計算した金額が15万円以上となる方は、この予定納税が必要になります。
白色申告だけが使える事業専従者控除
所得控除と税額控除は、確定申告を行う全納税者が該当する要件があれば、適用を受けられる控除です。それらとは別に、白色申告の個人事業主のみが利用できる控除として、事業専従者控除があります。
事業専従者控除とは、親族などの家族従業員に給与を支払った場合に、支払った給与のうち一定額を、必要経費として所得から差し引ける制度です。対象となるのは、白色申告をする納税者と生計を一にする配偶者や15歳以上の親族で、納税者が営む事業に年間6か月以上専ら従事している方に、給与を支払った場合です。
事業専従者控除は、配偶者の場合は最大86万円、その他の親族の場合は1人につき最大50万円です。確定申告書にその適用を受ける旨および事業専従者控除額に関する事項を記載することにより、必要経費として差し引くことができます。
白色申告では、親族などの家族従業員に支払った給与は、必要経費として計上できないのが原則です。しかし、この制度によって、一定の範囲で必要経費として計上することが認められています。
なお、青色申告の場合は、事業専従者控除は利用できませんが、青色事業専従者給与という制度は利用可能です。これも家族従業員に支払った給与を必要経費にできる制度ですが、青色事業専従者給与は家族従業員に支払った全額を必要経費として計上できます。
事業専従者控除、青色事業専従者給与については以下の記事で詳しく解説していますので参考にしてください。
はじめての確定申告もかんたん!無料から使える弥生のクラウド申告ソフト
インボイス制度は白色申告に直接関係しない
2023年から導入されている適格請求書等保存方式(インボイス制度)は消費税法上の制度であり、所得税の確定申告の方法である白色申告や青色申告には、特に直接の影響はありません。
インボイス制度とは、課税事業者が自身の納める消費税額を計算する際、仕入税額控除を行うには、取引相手が発行した適格請求書(インボイス)の保存が必要とされる制度です。なお、仕入税額控除とは、売上の消費税額から仕入や必要経費などにかかった消費税額を差し引ける控除のことです。
また、適格請求書(インボイス)とは、一定の記載要件を満たした請求書や領収書などのことで、適格請求書発行事業者に登録した課税事業者のみが発行できます。適格請求書発行事業者は、取引相手から発行を依頼された場合には、原則として適格請求書(インボイス)を発行する義務があります。
ただし、所得税の確定申告や白色申告、青色申告には影響がなくてもインボイス対応は、帳簿付けには影響があります。所得税と消費税の申告に対応した確定申告ソフトを使うと間違いのない申告ができるのでおすすめです。
はじめての確定申告もかんたん!無料から使える弥生のクラウド申告ソフト
専従者控除は、確定申告ソフトを使って手軽に白色申告をしよう
所得税の納付税額の計算では、さまざまな控除を差し引くことができるため、適用を受けられる控除はしっかり申告することが重要です。白色申告でも要件が合えば、16種類の所得控除や税額控除、事業専従者控除は適用されます。控除の要件を満たす場合は、抜け漏れなく、必ず申告するようにしましょう。
【あなたはいくらお得?】青色・白色の税額を比較|今すぐ無料シミュレーション!
日々の取引の記帳や確定申告の提出書類の作成は大変なイメージがありますが、「やよいの白色申告 オンライン」や「やよいの青色申告 オンライン」といった確定申告ソフトを使えば、記帳や書類作成にかかる手間を大幅に減らすことができます。専従者控除や各控除も質問に答えていくだけで適用できます。もちろん、インボイス対応をしていますので、インボイス対応で必要な帳簿付けや消費税の確定申告も万全に対応ができます。
「やよいの白色申告 オンライン」はずっと無料、「やよいの青色申告 オンライン」は初年度無料で使えるため、ぜひご利用を検討してみてください。
はじめての確定申告もかんたん!無料から使える弥生のクラウド申告ソフト
よくあるご質問
白色申告で受けられる控除は??
白色申告では、基礎控除などの所得控除や、住宅借入金等特別控除(住宅ローン控除)といった税額控除の他、事業専従者控除の適用が受けられます。一方で、青色申告は、青色申告特別控除など、白色申告にはない、さまざまな税制の優遇措置を受けられるメリットがあります。
白色申告で10万円控除は受けられますか?
青色申告者は、納付税額を計算する際に65万円、55万円、10万円のいずれかの金額を所得から差し引ける「青色申告特別控除」の適用を受けられますが、白色申告では受けられません。節税を考慮するなら、白色申告より青色申告の方がおすすめといえるでしょう。
事業専従者控除とは?
事業専従者控除とは、親族などの家族従業員に給与を支払った場合に、支払った給与のうち一定額を、必要経費として所得から差し引ける制度です。対象となるのは、白色申告をする納税者と生計を一にする配偶者や15歳以上の親族で、納税者が営む事業に年間6か月以上専ら従事している方に、給与を支払った場合です。
はじめての確定申告もかんたん!無料から使える弥生のクラウド申告ソフト
確定申告ソフトなら、簿記や会計の知識がなくても確定申告が可能
確定申告ソフトを使うことで、簿記や会計の知識がなくても確定申告ができます。
今すぐに始められて、初心者でも簡単に使える弥生のクラウド確定申告ソフト「やよいの白色申告 オンライン」とクラウド青色申告ソフト「やよいの青色申告 オンライン」から主な機能をご紹介します。
「やよいの白色申告 オンライン」は、ずっと無料、「やよいの青色申告 オンライン」は初年度無料です。両製品とも無料期間中もすべての機能が使用できますので、気軽にお試しいただけます。もちろん、確定申告やe-Taxでの申告が可能です!
【損してない?】青色申告でいくら安くなる?売上・経費を入れて今すぐ比較!
初心者にもわかりやすいシンプルなデザイン

弥生のクラウド確定申告ソフトは、初心者にもわかりやすいシンプルなデザインで、迷うことなく操作できます。日付や金額などを入力するだけで、確定申告に必要な帳簿や必要書類が作成できます。
取引データは自動取込&AIの自動仕訳で入力の手間を大幅に削減!

弥生のクラウド確定申告ソフトは、銀行・クレジットカードなどの金融機関の明細や電子マネー、POSレジ、請求書、経費精算等のサービスと連携すると日々の取り引きデータを自動で取得します。
自動取得した取引データはAIが自動で仕訳して帳簿に反映します。学習機能があるので、使えば使うほど仕訳の精度がアップします。紙のレシートは、スマホやスキャンで取り込めば、文字を認識してデータに変換し、自動で仕訳します。これにより入力の手間と時間が大幅に削減できます。
確定申告書類を自動作成。e-Tax対応で最大65万円の青色申告特別控除もスムーズに

弥生のクラウド確定申告ソフトは、画面の案内に沿って入力していくだけで、収支内訳書や青色申告決算書、所得税の確定申告書、消費税の確定申告書等の提出用書類が自動作成されます。
「やよいの青色申告 オンライン」なら、青色申告特別控除の最高65万円/55万円の要件を満たした資料の用意も簡単です。インターネットを使って直接申告するe-Tax(電子申告)にも対応し、最大65万円の青色申告特別控除もスムーズに受けられます。
自動集計されるレポートで経営状態がリアルタイムに把握できる

弥生のクラウド確定申告ソフトに日々の取引データを入力しておくだけで、レポートが自動で集計されます。経営状況やお金の流れをリアルタイムで確認できます。最新の経営状況を正確に把握することで、早めの判断ができるようになります。
無料お役立ち資料【「弥生のクラウド確定申告ソフト」がよくわかる資料】をダウンロードする
この記事の監修者田中卓也(田中卓也税理士事務所)
税理士、CFP®
1964年東京都生まれ。中央大学商学部卒。
東京都内の税理士事務所にて13年半の勤務を経て独立・開業。
従来の記帳代行・税務相談・税務申告といった分野のみならず、事業計画の作成・サポートなどの経営相談、よくわかるキャッシュフロー表の立て方、資金繰りの管理、保険の見直し、相続・次号継承対策など、多岐に渡って経営者や個人事業主のサポートに努める。一生活者の視点にたった講演活動や講師、執筆活動にも携わる。













