請求書払いとは?仕組みや支払方法を決める流れについて解説
監修者: 小林祐士(税理士法人フォース)
更新
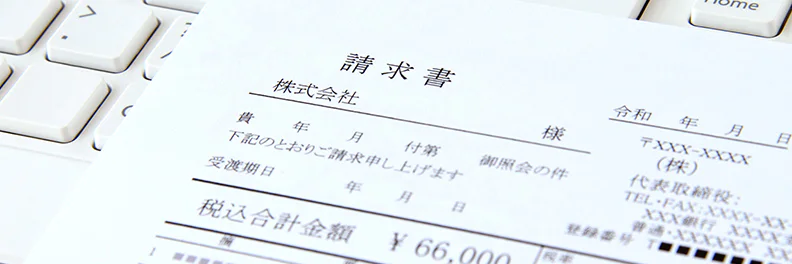
請求書払いは、法人・個人事業主などの企業間取引で用いられる決済手段の1つです。請求書払いは多くの企業で導入されており、新しい取引が始まるときは「請求書払いで」と頼まれることも少なくありません。
この請求書払いはどのような仕組みで、請求する側と支払う側にはそれぞれどのようなメリット・デメリットがあるのでしょうか。導入時の注意点や、支払いの流れとともに解説します。
無料【クラウド請求書作成ソフト「Misoca」がよくわかる資料】をダウンロードする
請求書払いとは後払い決済のこと
請求書払いとは、商品やサービスの代金について一定期間の取引をまとめた請求書を発行し、指定日に入金してもらう後払い決済のことです。商品やサービスを引き渡すときに代金を受け取るのではなく、特定の期日に支払ってもらう決済方法です。
BtoBの企業間取引のほとんどが請求書払いで成り立っており、BtoC取引においても請求書払いは採用されています。請求書払いは「料金後払い」や「掛け払い」の他、双方の信用のうえで成り立つことから、「与信取引」や「信用取引」とも呼ばれています。
請求書払いは、従来は経理担当者が社内で請求書を作成し送付する方法が一般的でした。しかし、近年はクラウドサービスの普及によって、リモートで対応することも可能となっています。
請求書の書き方についての詳細は以下の記事で解説していますので、参考にしてください。
【無料でお試し】クラウド請求書作成ソフト「Misoca」でかんたんキレイに請求書作成!
請求書払いの条件
請求書払いは、一定の条件を満たしたうえで始めることが大切です。請求書払いは後払いであるため、代金を回収する側(請求側)は支払う側に支払い能力があるかどうかを判断したうえで請求書払いを始める必要があります。
この支払い能力の有無の調査を「与信調査」といい、支払い能力があるかどうかを決める基準は「与信基準」と呼ばれます。請求側が請求書払いを承諾するかどうかは、この与信基準を満たしているかどうかが条件となるのです。与信基準は様々な情報を元に判断しますが、その1つとして、その企業の貸借対照表をもとに決められます。
【無料でお試し】クラウド請求書作成ソフト「Misoca」でかんたんキレイに請求書作成!
請求書払いのメリット
請求書払いを導入することで、請求側と支払う側の双方にさまざまなメリットがあります。それぞれどのようなメリットがあるのか見ていきましょう。
請求する側のメリット
請求書払いは、請求する側にとって下記のようなメリットがあります。
請求業務を効率化できる
請求書払いには「都度請求」と「一括請求(締め請求)」の2つの請求方法があります。一定期間に同じ取引先と複数回の取引がある場合は、取引が発生するたびに請求作業を行う都度請求よりも、一定期間の取引内容をまとめて請求する一括請求(締め請求)の方が、請求作業と回収作業が1回ずつで済むため効率的です。
また、少ない取引量の取引先が複数ある場合でも、取引があるたびに請求書を発行するよりも、一定期間分をまとめて請求する一括請求(締め請求)の方が、作業回数が少なく負担も抑えられます。
会計ミスを軽減できる
請求書払いには、誤請求や二重請求、請求漏れ、入金消込ミスといった会計ミスを軽減する効果も期待できます。
請求書払いのうち、一括請求(締め請求)なら請求業務が月に1回となり、会計処理の手間を大きく減らせます。その分、会計処理におけるミスも軽減可能です。
請求業務のコストを効率化により、軽減できる
請求書発行にかかる費用を削減できる点も、請求書払いのメリットです。取引先が増えるほど、請求書の送付先や請求内容に誤りがないかを確認する手間も大きくなります。その点、月に1回の請求書払いなら煩雑な確認業務や発送の回数も減らせるため、請求業務における人件費や通信費の削減が期待できます。
支払う側のメリット
請求書払いの支払う側のメリットは下記のとおりです。
資金繰りがしやすくなる
請求書払いを導入すると、商品やサービスに対する代金の支払いを後払いにできるため、支払う側は余裕を持った資金繰りができるようになります。当面の支払い額を把握できるため、資金計画や資金調達の計画も立てやすくなります。
振込業務とコストを削減できる
都度請求ではなく一括請求(締め請求)による請求書払いの場合は、一定期間の支払いを一度で済ませられるため、金融機関での手続きにかかるコストやその手数料を削減可能です。1回あたりの振込手数料は数百円程度とさほど高く感じられませんが、都度請求で頻繁に振り込む場合は、その総額が大きくなる可能性もあります。
一括請求の請求書払いによってこうした経費を削減することで、より利益を出しやすい企業体質に変えていくことができるでしょう。
【無料でお試し】クラウド請求書作成ソフト「Misoca」でかんたんキレイに請求書作成!
請求書払いのデメリット
請求書払いの導入には、注意すべきデメリットもあります。メリットと同様に、請求側と支払う側のデメリットを確認していきましょう。
請求する側のデメリット
請求書払いは、請求する側にとって下記のようなデメリットがあります。
未回収のリスクがある
1つの取引を成立させるためには、営業活動や顧客対応、商品の仕入れなどが必要です。そうした費用がかかっているからこそ、代金をきちんと回収しなくてはなりません。いかに未回収を防ぎながら請求書払いを運用していくかという対策が大切です。
支払いまでは資金繰りが悪化する可能性がある
請求書払いは後払いであるため、請求する側は代金が支払われるまで資金を手元に確保できません。金額が高額であったり、入金までに期間があったり、大きな支出があったりすると、請求する側の資金繰りが悪化する可能性があります。未回収のリスクにも備えて、資金計画をしっかり立てて事業を行うなどの対策が必要です。
また、新規取引では、前払いや都度払いを採用する場合や取引先の企業規模や資本金によっては、請求書払い自体を受け付けないなどの基準を設けている企業もあります。
信用調査の負担が増える
請求書払いを始めるかどうかを判断するためには、取引先の信用調査が必要です。また、信用調査をすれば安心が確保されるわけではありません。調査した結果、請求書払いでは取引できないという結論になる可能性もあります。
信用情報を調査したり、信用調査会社に依頼したりする費用は自社負担です。手間だけでなく、コストもかかる点にも注意する必要があります。あらかじめ基準を決めておくといいでしょう。
支払う側のデメリット
請求書払いの支払う側のデメリットは下記のとおりです。
支払い期日を管理する必要がある
支払う側は、請求書払いを導入することで資金計画ができる一方、毎月まとまった金額の出金が集中して発生する日があることとなります。資金繰りの管理がきちんとできていないと、代金の支払いができなくなる可能性があるため注意が必要です。
支払いができなくなると取引先から取引を断られるリスクもあるため、支払い期日と資金繰りの管理を徹底しなければなりません。
信用調査への対応が求められる
取引先から請求書払いの可否を判断してもらうためには、信用調査に対応する必要があります。調査では、直近の決算書類の提出を求められることも珍しくありません。調査の結果、請求書払いでの取引はできないと判断される可能性もあります。
支払い忘れが発生すると信用喪失のリスクがある
請求書払いは、後払いであるという性質上、支払いを忘れてしまう可能性があります。支払いを遅延させてしまった場合、取引先の信用を損なってしまうため注意が必要です。
最悪の場合、継続取引を断られてしまう可能性もあるため、受け取った請求書は管理を徹底し、支払期日までに確実に入金するようにしてください。
【無料でお試し】クラウド請求書作成ソフト「Misoca」でかんたんキレイに請求書作成!
請求書払いを始める際の注意点
請求書払いを導入する場合は、いくつかの注意点があります。ここでは、売手側(請求する側)が請求書払いを始める際の4つの注意点について解説します。
押印する
請求書への押印は義務ではありませんが、押印があることで請求書の改ざんと偽造防止効果があるため重要です。また、請求書自体の信頼度も高まります。
中には、押印のない請求書は受け付けない企業もあるため、対応は任意だとしても押印はしておく方が無難だといえます。
内税・外税を確認する
請求書の内税・外税の表記は、どちらを選んでも基本的には問題ありません。ただし、内税と外税のどちらで表記するかの確認は大切です。内税・外税をきちんと表記することで、増税による値上げなどに対する誤解を避けることができます。
なお、事業者が消費者に対してあらかじめ価格を表示する場合には、消費税額を含めた価格(税込価格)を表示することが必要です。すなわち、総額表示が義務付けられております。この場合、税込価格が明瞭に表示されていれば、消費税額や税抜価格を併せて表示することも可能です。
支払期日を確認する
取引先と契約を結ぶ際は、必ず支払期日を確認しておきましょう。「月末締めで翌月末もしくは翌々月末に支払い」と設定する企業が多いですが、全ての企業が当てはまるわけではありません。
支払期日の確認が不十分だと支払いミスや遅延、トラブルが起こる可能性があるため、必ず事前に確認しておくことをおすすめします。そのうえで請求書には、決められた支払期間と期日で支払期日を記載しておくと双方のミスが防げます。契約書を締結する場合は、あらかじめ契約書に支払条件を明示しておくなどもいいでしょう。
振込手数料の負担者を確認する
請求する側と支払う側のどちらが振込手数料を負担するかは、契約時に取り決めておくことが大切です。特段の意思表示がなければ、支払う側が手数料を負担します。
しかし、企業によって方針は異なるため、事前に確認しておくと安心です。
【無料でお試し】クラウド請求書作成ソフト「Misoca」でかんたんキレイに請求書作成!
請求書払いの流れ
続いては、請求書払いの一般的な流れを解説します。請求書払いを始める際の参考にしてください。
1. 取引先の情報収集
取引を行うに際して、例えば、取引相手の経営状況や資産状況などを調査します。
2. 与信審査
取引予定先の情報にもとづいて行うのが与信審査です。取引先の支払い能力を、自社の与信基準にもとづいて審査します。与信基準が低いと代金未回収のリスクが高まり、反対に高すぎると取引先が審査に通過しにくくなって取引の機会損失の原因になるため、基準は慎重に設定する必要があります。
自社で判断が難しい場合は、第三者機関へ与信調査を依頼するのも1つの方法です。
3. 与信枠の設定
与信調査の審査結果が出たら、その結果にもとづいて取引先の与信枠を設定します。
与信枠は、代金未回収のリスクを抑えるため、取引先の支払い能力に応じて制定することが大切です。なお、取引先の経営状況は変化するため、与信枠は定期的に見直すことをおすすめします。
4. 取引開始
取引可能と判断がなされたら、請求書払いを検討している取引先と、取引に必要な条件を取り決めて契約を結びます。取引内容や納品日、支払金額、支払方法などを具体的に決めましょう。
5. 請求書発行・送付
与信枠を設定して取引を開始し、商品やサービスの納品が完了したら、請求金額を確定させて請求書を発行します。トラブル防止のため、請求書の記載内容は間違いのないようにしてください。
請求書を受領した取引先は、支払期日までに支払いをします。企業間の支払いの手段は「銀行振込」が多いです。他にも「コンビニ決済」「クレジット決済」「バーコード決済」などの手段があります。
6. 入金確認と入金消込
請求書の送付後は、支払期日がきたら入金確認と入金消込を行います。入金消込とは、請求情報と入金情報を照合して入金予定額を消していくことです。請求書に記載した支払期日に予定どおり入金されているかを、会社の口座情報を見て確認してください。
7. 督促(入金が確認できなかった場合)
消し込めなかった請求があった場合、まずは、自社内で請求忘れや発送漏れなどの間違いがなかったかを確認します。そのうえで、営業担当から取引先の担当者に連絡します。自社が原因の場合は、請求をする旨をあらためて伝えて、支払ってもらえる日を確認します。また、相手方の支払い忘れや請求書の紛失が原因であれば、多くの場合すぐに入金してもらえます。支払い忘れの詳しい対応方法については後述します。
しかし、経営が悪化して支払いが難しい場合や、相手方の都合で入金を拒まれた場合には、督促するなどの対応が必要です。なぜなら、民法により売掛金は、5年経過すると消滅時効にかかります。支払いの督促などをせず滞納を放置したまま5年間が過ぎると相手方は消滅時効を援用して、請求を断れるようになってしまうのです。なお、相手方に対し、裁判所を通じた支払督促などの手続きをとれば、またその時点から時効が始まります。
【無料でお試し】クラウド請求書作成ソフト「Misoca」でかんたんキレイに請求書作成!
支払い忘れへの対処法
請求書払いでは、支払い忘れが起きる可能性があります。もし支払い忘れが起きた場合は、請求する側と支払う側それぞれに対応が求められます。
請求する側は、代金未回収について自社に非がないかを確認し、電話や催促状・督促状を通じて支払いを求めることとなります。それでも支払われない場合、最終的には法的措置を視野に入れなければならないかもしれません。
一方の支払う側は、支払い忘れに気づいた時点で取引先に連絡を入れる必要があります。連絡後はすみやかに支払い手続きを進めます。
弥生のクラウド請求書作成ソフト「Misoca」には、回収保証があります。「Misoca」で発行した請求書に、売掛金の回収保証を付与できるサービスです。回収保証の付与された請求書に対して、支払いの遅延や取引先の倒産などによって売掛金の回収ができなくなった場合に損害を補填します。
代金の未回収リスクの心強い備えとなるため、請求書払いを導入予定の場合は、ぜひ検討してみてください。
【無料でお試し】クラウド請求書作成ソフト「Misoca」でかんたんキレイに請求書作成!
請求する側も支払う側も、請求書払いを理解し効率的に活用しよう
請求書払いにはメリットが多い一方で、注意すべきデメリットもあるため、請求する側も支払う側も、その仕組みや注意点をよく理解したうえで活用することが大切です。
また、2023年10月からはインボイス制度がスタートしています。適格請求書(インボイス)は必ず記載しなければいけない記載項目があります。そして、適格請求書発行事業者は、適格請求書の保存方法などについてもルールがありますので、正しく理解して対応してください。
また、電子帳簿保存法の「電子取引のデータ保存」が2024年1月1日以後の取引から完全義務化になります。「電子取引のデータ保存」についても請求書を電子発行する際に該当します。仕組みや制度を正確に理解することで、請求書払いを効率的に活用できるようになります。
請求業務を効率化したい場合は、弥生のクラウド請求書ソフト「Misoca」の導入がおすすめです。請求書や見積書、納品書を効率的に作成でき、まとめて管理することもできます。もちろん、インボイス制度・電子帳簿保存法の電子取引のデータ保存も対応しています。経理業務の正確性を高め、負担軽減にもつながるでしょう。
適格請求書、電子帳簿保存法については下記の記事をご覧ください。
【無料でお試し】クラウド請求書作成ソフト「Misoca」でかんたんキレイに請求書作成!
クラウド見積・納品・請求書サービスなら、請求業務をラクにできる
クラウド請求書作成ソフトを使うことで、毎月発生する請求業務をラクにできます。
今すぐに始められて、初心者でも簡単に使えるクラウド見積・納品・請求書サービス「Misoca」の主な機能をご紹介します。
「Misoca」は月10枚までの請求書作成ならずっと無料、月11枚以上の請求書作成の有償プランも1年間0円で使用できるため、気軽にお試しすることができます。
見積書・納品書・請求書をテンプレートでキレイに作成

Misocaは見積書 ・納品書・請求書・領収書・検収書の作成が可能です。取引先・品目・税率などをテンプレートの入力フォームに記入・選択するだけで、かんたんにキレイな帳票ができます。
各種帳票の変換・請求書の自動作成で入力の手間を削減

見積書から納品書・請求書への変換や、請求書から領収書・検収書の作成もクリック操作でスムーズにできます。固定の取引は、請求書の自動作成・自動メール機能を使えば、作成から送付までの手間を省くことが可能です。
インボイス制度(発行・保存)・電子帳簿保存法に対応だから”あんしん”

Misocaは、インボイス制度に必要な適格請求書の発行に対応しています。さらに発行した請求書は「スマート証憑管理」との連携で、インボイス制度・電子帳簿保存法の要件を満たす形で電子保存・管理することが可能です。
確定申告ソフトとの連携で請求業務から記帳までを効率化

Misocaで作成した請求書データは、弥生の確定申告ソフト「やよいの青色申告 オンライン」に連携することが可能です。請求データを申告ソフトへ自動取込・自動仕訳できるため、取引データの2重入力や入力ミスを削減し、効率的な業務を実現できます。
会計業務はもちろん、請求書発行、経費精算、証憑管理業務もできる!
法人向けクラウド会計ソフト「弥生会計 Next」では、請求書作成ソフト・経費精算ソフト・証憑管理ソフトがセットで利用できます。自動的にデータが連携されるため、バックオフィス業務を幅広く効率化できます。

「弥生会計 Next」で、会計業務を「できるだけやりたくないもの」から「事業を成長させるうえで欠かせないもの」へ。まずは、「弥生会計 Next」をぜひお試しください。
無料【クラウド請求書作成ソフト「Misoca」がよくわかる資料】をダウンロードする
この記事の監修者小林祐士(税理士法人フォース)
東京都町田市にある東京税理士会法人登録NO.1
税理士法人フォース 代表社員
お客様にとって必要な税理士とはどのようなものか。私たちは、事業者様のちょっとした疑問点や困りごと、相談事などに真剣に耳を傾け、AIなどの機械化では生み出せない安心感と信頼感を生み出し、関与させていただく事業者様の事業発展の「ちから=フォース」になる。これが私たちの法人が追い求める姿です。










