請求書とは?見積書や領収書との違い、作成時の項目を簡単に解説
監修者: 高崎文秀(税理士)
更新
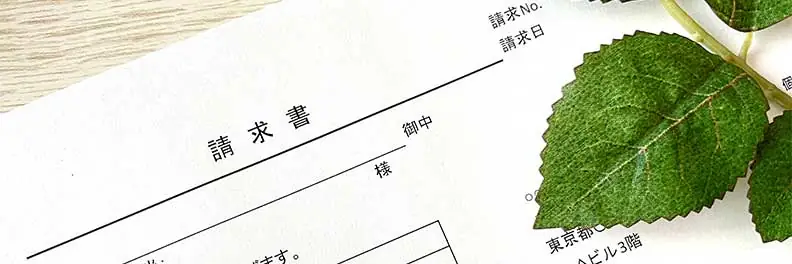
企業間で商品・サービスの取引をする際は、多くの場合、売手側が証憑書類として請求書を発行します。証憑書類には領収書や納品書など複数の種類がありますが、請求書にはどのような特徴があるのでしょうか。
本記事では、請求書の概要や記載項目、作成・発行・受領の流れなどをわかりやすく解説します。また、実務でよくある質問についてもQ&A方式で記載しました。請求書に関する基礎知識を整理するためにご活用ください。
無料【クラウド請求書作成ソフト「Misoca」がよくわかる資料】をダウンロードする
請求書とは商品やサービスの対価を受け取るために発行する書類のこと
請求書とは、商品・サービスの売手側が、買手側に代金を請求するために発行する書類のことです。2025年現在、請求書の形式は、インボイス制度の施行により「適格請求書(インボイス)」と「区分記載請求書」の2種類に大別されます。
適格請求書とは、2023年10月にスタートしたインボイス制度(適格請求書等保存方式)に対応した請求書です。これに対し、区分記載請求書は、2019年10月の軽減税率導入後から使用されている請求書を指します。基本的に、課税事業者で登録が済んでいる「適格請求書発行事業者」は適格請求書を、その他の消費税の納税義務がない免税事業者や未対応の課税事業者は、区分記載請求書を発行します。
請求書の発行は必ずしも義務ではありません。ただし、適格請求書発行事業者は、買手側から要求された場合、求めに応じて適格請求書を交付することがインボイス制度で定められています。また、請求書の授受は商習慣としても定着しているため、実質的には、請求書発行体制の整備が不可欠です。
請求書は、取引が行われた事実やその内容を証明する「証憑書類」の一種であり、税務上の資料としても重要なものです。証憑書類には、請求書の他に領収書や注文書、納品書などがあります。
なお、証憑書類について詳しくは、以下の解説記事を参考にしてください。
請求書と見積書の違い
見積書とは、商品・サービスの発注・契約前に、価格や数量、納期などの取引条件を提示するために売手側が発行する書類です。買手側は見積書の情報に基づいて、取引の可否を判断します。これに対して請求書は、取引(契約)が成立し、商品・サービスを提供した後に代金を請求する目的で発行される書類を指します。
見積書について詳しくは、以下の解説記事もご一読ください。
請求書と領収書の違い
領収書とは、商品・サービスの代金が支払われた後に、実際に金銭の授受があったことを証明するために、売手側が買手側に発行する書類です。税務申告においては、支払いの事実を証明する証憑書類としての役割を持ちます。これに対して請求書は、代金の支払いが行われる前に、請求金額や振込先など、支払いに必要な情報を提示するために発行される点が大きな違いです。
なお、医療機関の窓口のように請求と支払いが同時に行われる場合は、「請求書兼領収書」として1枚にまとめて発行されることもあります。領収書および請求書兼領収書について詳しくは、以下の記事を参考にしてください。
請求書と注文書(発注書)の違い
取引に係る書類として注文書(発注書)があります。注文書(発注書)とは、取引に際して希望する商品・サービスの内容を明記し、発注の意思を伝えるために取引前に買手側(発注者)が発行する書類です。これに対して請求書は、取引(契約)の成立後に、代金を請求するために売手側が発行します。ただし、注文は口頭やメールといった書面以外の方法で行われることも多いため、注文書(発注書)が存在しない取引も珍しくありません。
請求書と納品書の違い
納品書とは、商品・サービスを実際に提供したことを示すために売手側が発行する書類です。それに対して請求書は、納品物の代金を買手側に請求するための書類であり、それぞれ発行する目的が異なります。なお、単発の取引や、取引ごとに請求を行う形式などで納品書と請求書の発行タイミングが同時になる場合は、「納品書兼請求書」として1枚にまとめて発行されることもあります。
納品書および納品書兼請求書について詳しくは、以下の記事も参考にしてください。
【無料でお試し】クラウド請求書作成ソフト「Misoca」でかんたんキレイに請求書作成!
請求書を作成する際に記載する項目・内容
請求書を発行する際は、買手側がスムーズに支払いを済ませられるよう、必要な情報を正確に記載することが求められます。また、適格請求書発行事業者の場合は、インボイス制度に基づく必須の記載項目があるため、記載漏れのないようにご注意ください。
請求書の記載項目や書き方については、以下の記事で詳しく解説しています。ぜひ参考にしてください。
必ず記載する項目
まずは、適格請求書発行事業者が発行する適格請求書の必須項目を確認しておきましょう。
適格請求書発行事業者の場合、2023年10月に施行されたインボイス制度により、買手側の求めに応じて、適格請求書を発行することが義務付けられました。適格請求書に記載する必須項目は以下のとおりです。
-
-
①書類作成者の氏名または名称および登録番号
-
②取引年月日
-
③取引内容(軽減税率の対象品目である旨)
-
④税率ごとに区分して合計した税込対価(又は税抜対価)の額及び適用税率
-
⑤税率ごとに区分した消費税額等
-
⑥書類の交付を受ける事業者の氏名または名称
-
-
引用:国税庁「No.6625 適格請求書等の記載事項
」
また、適格請求書および区分記載請求書の両方に記載が必要な項目は以下のとおりです。
-
- 請求書の宛先
- 請求金額
- 発行者の氏名または名称
- 取引年月日
- 取引内容(品名、単価、数量、軽減税率の対象品目である旨)
- 税率ごとに区分して合計した税込の対価
つまり、インボイス(適格請求書)を発行する際は、区分記載請求書の内容に加えて、「登録番号」「適用税率」「税率ごとの消費税額」の3項目の記載が必要です。請求書のフォーマットに決まりは特にありませんが、上記の必須項目については記載漏れがないように注意しましょう。
記載しておくとよい項目
以下の項目は必須ではありませんが、代金の支払いや事務負担の円滑化を図るために記載しておくことを推奨します。
-
- 支払期日
- 振込先の情報(銀行名・支店名・口座番号・口座種別・名義)
- 請求書番号
- 請求書発行日
- 備考
備考欄には、「振込手数料をどちらが負担するのか」といった、実務に必要な情報を記載するのが一般的です。振込手数料の処理について詳しくは、以下の記事をご覧ください。
【無料でお試し】クラウド請求書作成ソフト「Misoca」でかんたんキレイに請求書作成!
請求書を発行する場合の流れ
請求書は、対価の支払いを受けるために必要な書類です。また、その後の経理処理や税務申告にも必要になるため、内容を正確に記載し、適切なタイミングで発行することが求められます。請求書発行業務の一般的な流れを解説します。
1.取引先ごとに請求金額を確定させる
まずは実際の取引内容に基づき、取引先(買手側)ごとの請求金額を正確に算出します。企業間取引の場合、取引ごとに請求書を発行する「都度方式」の他に、月単位など期間の売上をまとめて一括請求する「掛売方式(締め請求)」も一般的です。特に掛売方式(締め請求)の場合、複数の取引をまとめて記載することになるため、漏れのないように注意しましょう。
なお、もしも見積書の金額と実際の請求金額が異なる場合は、事前に買手側にその旨を伝えておくことが重要です。できれば受注時点、遅くとも納品時には、実際の請求額について買手側の了承を得るようにしましょう。事前申告なしに見積金額や発注金額を超える代金を請求すると、取引先との信頼関係を損ない、トラブルにつながる可能性があるため、事前に認識をすり合わせておくことが重要です。
2.請求書を作成して送付する
請求書を作成したら、郵送やメール添付などの方法で請求先へ送付します。PDFなどのデジタルデータで作成した請求書をメールに添付して送付する場合は、事前に先方から了承を得ておきましょう。特に、普段やりとりしているものとは異なるメールアドレスから送信する場合は、事前にその旨を伝えておかないと、迷惑メールとして処理されてしまうリスクがあります。
また、PDFなどのデータで請求書をやり取りする場合は、電子帳簿保存法の「電子取引」に該当します。発行者側も法令が定める要件に則って、請求書のデータを保存する必要があります。郵送する場合も、送付した請求書の控えを紙またはデータなどの形式で保存しておかなければなりません。
請求書の保存期間は、事業者や請求書の種類によって異なります。青色申告法人の場合、原則として7年間です。ただし、欠損金が生じた事業年度は10年間の保存が必要です。個人事業主の場合は原則5年間の保存義務があります。なお、適格請求書発行事業者は、法人・個人事業主を問わず適格請求書を7年間保存する必要があります。
請求書の送付方法や保存期間、電子帳簿保存法に則した保存方法については、以下の記事を参考にしてください。
3.買手側からの入金を確認する
支払期日になったら、買手側からの入金を確認し、請求書の内容と照らし合わせて消込を行います。消込とは、請求金額と実際の入金額を照合し、債権や債務の残高を消す作業のことです。つまり、請求金額が入金済みであることを経理上で明確にする処理のことを指します。消込を適切に行わないと、未入金を見落としたり、二重請求が発生したりする可能性があるため、正確に処理することが重要です。
消込については、以下の記事で詳しく解説しています。
4.入金がなければ必要に応じて支払いを促す
支払期日になっても入金がない場合は、相手(買手側)に連絡をする前に、まずは自分(売手側)に請求ミスがないかどうかを確認しましょう。
発行側(売手側)のミスを確認するためにチェックすべき項目は次のとおりです。
-
- 請求書は確実に送付したか
- 請求書の宛先に間違いはないか
- 請求書の到着日が買手側の請求締め日を過ぎていないか
- 支払期日に間違いがないか
発行側(売手側)にミスがあった場合は、先方に謝罪をしたうえで改めて請求書を送付します。
発行側(売手側)にミスがないようであれば、買手側に連絡をして、まずは請求書が届いているかどうかを確認しましょう。そのうえで未入金になっていることを伝え、先方の現状確認をします。
買手側のミスで入金されていない場合は、以下のようなパターンが考えられます。
-
- 支払日の失念や誤認
- 請求書の紛失や経理担当者への渡しそびれ
ここまでの時点で未入金の原因が判明し、入金があれば問題ありませんが、場合によっては支払いに応じてもらえないケースもあります。その際は、「請求書の再発行」「催促状の送付」「督促状の送付」と段階的に対応を強化していきましょう。それでも支払いがない場合は、取引停止や法的措置も検討する必要があります。
未入金を連絡する際のコツについて詳しくは、以下の記事を参考にしてください。
【無料でお試し】クラウド請求書作成ソフト「Misoca」でかんたんキレイに請求書作成!
請求書を受領する場合の流れ
買手側として請求書を受領する場合は、以下の流れで支払処理を行います。
1.受領した請求書を確認する
売手側から請求書が届いたら、まずは内容に誤りがないか確認します。請求書がメールで届いた場合は、受領した旨を返信しましょう。もしも内容に誤りがあった場合は、受領の連絡と併せて伝えます。
特に適格請求書に記載漏れや誤記がある場合は、制度上の要件を満たすよう、発行側に修正してもらう必要があります。なお、メールで請求書を受領した場合は、電子帳簿保存法における「電子取引」に該当するため、同法の「電子取引のデータ保存」に則った保存が必要です。
請求書の受領および訂正の連絡方法や、電子帳簿保存法に則った保存方法については以下の記事を参考にしてください。
2.支払期日までに入金する
請求書の内容に間違いがなければ、支払期日までに指定の方法で入金します。もし請求書に誤りがあった場合は、早めに発行者へ連絡し、修正した請求書を再発行してもらう必要があります。特に適格請求書の場合は、原則として買手側による追記や修正が認められていません。そのため、交付側(売手側)で、修正・再発行をしてもらう必要があります。
なお、受領した請求書は、支払完了後も一定期間保存しておくことが義務付けられています。保存期間は原則として法人が7年間、個人事業主が5年間、適格請求書事業者で、適格請求書に該当する書類は法人、個人を問わず7年間です(受領側が、簡易課税制度を選択している場合を除く)。
【無料でお試し】クラウド請求書作成ソフト「Misoca」でかんたんキレイに請求書作成!
請求業務を効率化する方法
請求書にミスがあると、経理業務が滞るだけでなく、取引先との信頼関係にも悪影響を及ぼしかねません。頻度が高い請求書発行業務を正確にこなすには、効率化することが重要です。請求業務を効率化する方法を解説します。
電子化を促進する
紙の請求書をやめて電子化(データ化)することで、印刷・宛名書き・封入・切手貼りなどの作業をする必要がなくなり、請求業務の効率化が可能です。電子化された請求書であればメールで送付できるため、封筒代や郵送代などが不要になり、コストカットにも役立ちます。
また、紙の請求書を保存する場合は、ファイリングの手間がかかるうえ、保管スペースも確保しなければなりません。電子データであれば、物理的なスペースの確保が不要となり、ペーパーレス化の促進にもつながります。適切なデータ管理体制を構築すれば、高い検索性も確保できます。
請求書の電子化について詳しくは、以下の記事を参考にしてください。
アウトソーシングを活用する
請求業務の効率化には、外部の代行会社にアウトソーシングするのも1つの方法です。外注すれば、必要なデータを用意して依頼するだけでよく、請求業務の負担を大きく軽減できます。アウトソーシングには費用がかかりますが、社内で担当者を確保する場合と比べてコストを抑えられるケースもあります。社内に経理業務に長けた人材が不足している場合は、業務品質の改善にも有効です。
請求業務のアウトソーシングについて詳しくは、以下の記事も参考にしてください。
請求書作成サービスを導入する
自社内での請求書発行業務を効率化するには、請求書作成サービスを導入するという方法もあります。請求書作成サービスを使うと、品目や単価、数量といった必要項目を入力するだけで請求書を作成でき、請求金額も自動で計算されるため、ミスの削減と効率化が可能です。作成した請求書をPDFで発行・送付すれば、電子化やペーパーレス化にもつながります。
例えば、弥生のクラウド請求書作成ソフト「Misoca」では、インボイス制度や電子帳簿保存法にも対応した請求書を簡単に作成可能です。便利な請求書作成サービスを活用し、請求業務の効率化に役立てましょう。
【無料でお試し】クラウド請求書作成ソフト「Misoca」でかんたんキレイに請求書作成!
【Q&A】請求書に関するよくある質問
最後に、請求書に関してよくある質問にお答えします。
請求書を発行するタイミングはいつ?
請求書を発行するタイミングは「都度方式」と「掛売方式(締め請求)」で異なります。都度方式では取引ごとに請求書を発行するのに対し、掛売方式(締め請求)では規定の締め日に一定期間内の取引分をまとめる形で請求書を発行します。
掛売方式(締め請求)の場合、取引をまとめ金額を確定させたらなるべく早い段階で請求書を送付するようにします。
請求書の発行タイミングについて詳しくは、以下の記事でご確認ください。
請求書の再発行を依頼されたときはどう対処すればいい?
請求書を再発行すること自体に問題はありません。ただし、二重請求にならないように注意が必要です。一例として、「再発行である旨を記載する」「請求書番号をオリジナルの番号と一致させ、枝番を付ける」などの対策をとりましょう。
請求書の再発行について詳しくは、以下の記事を参考にしてください。
請求書には印紙が必要?
原則として、請求書に収入印紙を貼る必要はありません。収入印紙は、所定の金額を超える額の「代金を受け取った際」に領収書などの証憑に貼るものであり、請求書の発行タイミングは「代金の受け取り前」だからです。ただし、「請求書兼領収書」を発行する際は、収入印紙の貼付が必要になる場合もあります。
収入印紙が必要な書類や金額の要件などについては、以下の記事を参考にしてください。
請求書には印鑑が必要?
請求書への押印は必須ではありません。ただし、商習慣上、企業間取引の請求書には押印するのが一般的です。印鑑を押すことで偽造防止にもつながるため、先方から希望された場合はできるだけ応じましょう。電子印鑑を利用すれば、手作業で押印する手間を省けます。
請求書の印鑑について詳しくは、以下の記事を参考にしてください。
【無料でお試し】クラウド請求書作成ソフト「Misoca」でかんたんキレイに請求書作成!
請求業務の効率化にはクラウド請求書作成ソフトが便利
請求書とは、取引の代金を請求するために、売手側が買手側に発行する証憑書類です。スムーズに取引を完結させ、双方が滞りなく経理・税務処理を進めるには、適切なタイミングで正確な請求書を発行する必要があります。
請求書の発行業務を効率化するには、弥生のクラウド請求書作成ソフト「Misoca」を活用するのがおすすめです。「Misoca」を使えば、請求書の作成・発行・送付のプロセスを電子化・自動化でき、手間なく迅速に請求書発行業務を行えます。電子帳簿保存法やインボイス制度といった法令にも対応しているため、法令遵守の面からも安心してご利用いただけます。ぜひ導入をご検討ください。
【無料でお試し】クラウド請求書作成ソフト「Misoca」でかんたんキレイに請求書作成!
クラウド見積・納品・請求書サービスなら、請求業務をラクにできる
クラウド請求書作成ソフトを使うことで、毎月発生する請求業務をラクにできます。
今すぐに始められて、初心者でも簡単に使えるクラウド見積・納品・請求書サービス「Misoca」の主な機能をご紹介します。
「Misoca」は月10枚までの請求書作成ならずっと無料、月11枚以上の請求書作成の有償プランも1年間0円で使用できるため、気軽にお試しすることができます。
見積書・納品書・請求書をテンプレートでキレイに作成

Misocaは見積書 ・納品書・請求書・領収書・検収書の作成が可能です。取引先・品目・税率などをテンプレートの入力フォームに記入・選択するだけで、かんたんにキレイな帳票ができます。
各種帳票の変換・請求書の自動作成で入力の手間を削減

見積書から納品書・請求書への変換や、請求書から領収書・検収書の作成もクリック操作でスムーズにできます。固定の取引は、請求書の自動作成・自動メール機能を使えば、作成から送付までの手間を省くことが可能です。
インボイス制度(発行・保存)・電子帳簿保存法に対応だから”あんしん”

Misocaは、インボイス制度に必要な適格請求書の発行に対応しています。さらに発行した請求書は「スマート証憑管理」との連携で、インボイス制度・電子帳簿保存法の要件を満たす形で電子保存・管理することが可能です。
確定申告ソフトとの連携で請求業務から記帳までを効率化

Misocaで作成した請求書データは、弥生の確定申告ソフト「やよいの青色申告 オンライン」に連携することが可能です。請求データを申告ソフトへ自動取込・自動仕訳できるため、取引データの2重入力や入力ミスを削減し、効率的な業務を実現できます。
会計業務はもちろん、請求書発行、経費精算、証憑管理業務もできる!
法人向けクラウド会計ソフト「弥生会計 Next」では、請求書作成ソフト・経費精算ソフト・証憑管理ソフトがセットで利用できます。自動的にデータが連携されるため、バックオフィス業務を幅広く効率化できます。

「弥生会計 Next」で、会計業務を「できるだけやりたくないもの」から「事業を成長させるうえで欠かせないもの」へ。まずは、「弥生会計 Next」をぜひお試しください。
無料【クラウド請求書作成ソフト「Misoca」がよくわかる資料】をダウンロードする
この記事の監修者高崎文秀(税理士)
高崎文秀税理士事務所 代表税理士/株式会社マネーリンク 代表取締役
早稲田大学理工学部応用化学科卒
都内税理士事務所に税理士として勤務し、さまざまな規模の法人・個人のお客様を幅広く担当。2019年に独立開業し、現在は法人・個人事業者の税務顧問・節税サポート、個人の税務相談・サポート、企業買収支援、税務記事の監修など幅広く活動中。また通常の税理士業務の他、一般社団法人CSVOICE協会の認定経営支援責任者として、業績に悩む顧問先の経営改善を積極的に行っている。










