所得控除とは?控除額の計算方法や種類を一覧でわかりやすく解説
監修者: 齋藤一生(税理士)
更新
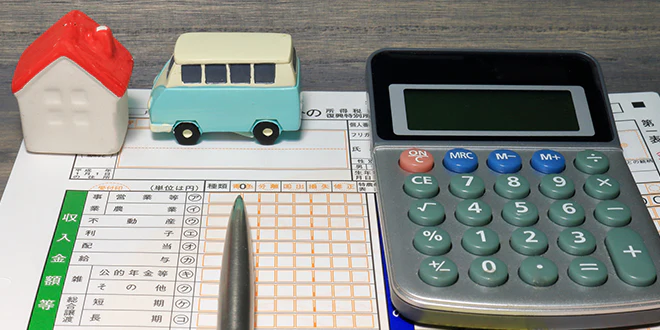
所得控除とは、税額計算のベースになる所得から一定の金額を差し引ける制度ですが、自動では適用されないため、確定申告や年末調整で申告する必要があります。所得控除の適用を受けることができれば、その分、課税される所得金額が減るため、所得税や住民税の負担を減らすことができます。
しかし、所得控除の種類や適用される要件などについて、詳しく知っている方は少ないかもしれません。
ここでは、所得控除の種類や計算方法、適用を受けるための要件などについて、詳しく解説していきます。節税のためには、利用できる所得控除を見落とさずに申告することが必要です。
なお、本記事は、令和7年度税制改正での2025年(令和7年)12月1日施行の内容を前提に記載をしています。また、この改正は原則として、2025年(令和7年)分以後の所得税について適用されます。
ただし、2025年(令和7年)11月までの給与及び公的年金等の源泉徴収事務に変更は生じません。
日付や金額などを入力するだけで、確定申告に必要な帳簿や申告書類が完成します
初年度無料ですべての機能が使用できます。
e-Taxも製品から直接できるので、自宅からかんたんに確定申告が可能です

所得控除とは所得金額から一定の金額を差し引ける制度
所得控除とは、個々の納税者の事情に合わせて、所得から一定の金額を差し引ける制度のことです。
所得税は、個人の所得に応じて課税されます。所得とは、収入から必要経費を差し引いた金額です。所得控除が適用されれば税金を計算する基となる所得から一定の金額が差し引かれるため、税負担を軽減できます。
所得控除は全部で16種類あり、それぞれに適用要件や計算方法が定められています。ただし、適用要件に該当したとしても、自動的に適用されるわけではありません。所得控除の適用を受けるためには、確定申告または年末調整で、自ら申告する必要があります。
なお、所得税の計算にかかわる控除には、所得控除の他に税額控除もあります。所得控除が税金を計算する前の所得から差し引くことができる制度であるのに対して、税額控除は計算した所得税額から直接一定額を差し引くことができる制度という点が両者の違いです。どちらも節税につながるという点では同じですが、控除のプロセスが異なります。
税額控除については、以下の記事で詳しく解説していますので参考にしてください。
所得税の計算方法
所得税は、1年間の収入から必要経費や所得控除額を差し引いた課税所得に、所定の税率を掛けて求められます。
所得税の計算方法は、以下のとおりです。
所得税の計算式
所得税=課税所得×所得税率−控除額
税率や控除額は、課税所得の額によって異なるため、下の速算表を参考にしてください。
所得税の速算表
| 課税される所得金額 | 所得税率 | 控除額 |
|---|---|---|
| 1,000~194万9,000円 | 5% | 0円 |
| 195万~329万9,000円 | 10% | 9万7,500円 |
| 330万~694万9,000円 | 20% | 42万7,500円 |
| 695万~899万9,000円 | 23% | 63万6,000円 |
| 900万~1,799万9,000円 | 33% | 153万6,000円 |
| 1,800万~3999万9,000円まで | 40% | 279万6,000円 |
| 4,000万円以上 | 45% | 479万6,000円 |
- ※1,000円未満の端数金額は切り捨て
-
※国税庁「No.2260 所得税の税率
」
なお、会社員などの給与所得者には必要経費を差し引ける制度がない代わりに、給与所得控除という控除が用意されています。そのため、給与所得者の課税所得は、「年収−給与所得控除−各種所得控除」で求められます。この給与所得控除の額は、給与額に応じて決まります。
所得税については、以下の記事で詳しく解説していますので参考にしてください。
所得控除は16種類ある
所得控除は全部で16種類あります。令和7年度税制改正により、特定親族特別控除が新設され、2025年分から1つ増えました。
利用できる控除を見落とすことがないように、控除の種類を知っておきましょう。それぞれの控除の特徴や適用要件について、以下の表を参考にしてください。
所得控除一覧
| 控除の種類 | 主な適用要件 | 控除額 |
|---|---|---|
| 基礎控除 | 合計所得金額が2,500万円以下 | 合計所得金額に応じて、16万~95万円(2024年分までは16万~48万円) |
| 配偶者控除 | 控除対象となる配偶者の合計所得金額が58万円以下(2024年分までは48万円以下)、給与収入なら123万円以下(2024年分までは103万円以下)で、かつ、本人の所得が1,000万円以下 | 本人の所得や配偶者の年齢に応じて13万~48万円 |
| 配偶者特別控除 | 控除対象となる配偶者の合計所得金額が58万円超133万円以下(2024年分までは48万円超133万円以下)、給与収入なら123万円超201.6万円以下(2024年分までは103万円超201万6,000円未満)で、かつ、本人の所得が1,000万円以下 | 本人と配偶者の所得に応じて1万~38万円 |
| 扶養控除 | 所得税法上の控除対象扶養親族がいる場合(16歳未満の人は控除対象扶養親族とはなりません) | 扶養親族の年齢、同居の有無によって38万~63万円 |
| 特定親族特別控除 | 所得税法上の19歳以上23歳未満の控除対象扶養親族の合計所得金額が、58万円超123万円以下(給与所得のみで123万円超188万円以下) | 所得に応じて、6万~63万円 |
| 医療費控除 | 1年間に支払った医療費が一定額を超えた場合、医療費控除かセルフメディケーション税制(医療費控除の特例)のいずれかを適用できる(生計を一にする家庭単位) | <医療費控除の場合> ・支払った医療費-保険金など-10万円(総所得金額などが200万円未満の場合は総所得の5%) ・最大200万円まで <セルフメディケーション税制(医療費控除の特例)の場合> ・対象医薬品の購入費-1万2,000円 ・最大8万8,000円まで |
| 寄附金控除 | 国や地方公共団体などに対して特定寄附金を支出した場合 | 以下のうち低い方の金額−2,000円 ・特定寄附金の合計額 ・その年の総所得金額等の40%相当額 |
| 社会保険料控除 | 自分や生計を一にする家族・親族の社会保険料を支払った場合 | その年に支払った全額 |
| 生命保険料控除 | 民間の保険会社などに生命保険料、介護医療保険料および年金保険料を支払った場合 | 一定の方法で計算した金額 (最大12万円まで) |
| 地震保険料控除 | 民間の保険会社などに地震保険料を支払った場合 | 一定の方法で計算した金額 (最大5万円まで) |
| 小規模企業共済等掛金控除 | 小規模企業共済法に規定された共済契約に基づく掛金等を支払った場合(小規模企業共済掛金やiDeCoの掛金など) | 掛金の全額 |
| ひとり親控除 | 配偶者がおらず、生計を一にする子供がいて、所定の要件に該当する場合 | 35万円 |
| 寡婦控除 | 夫と離婚・死別した後婚姻していないなど、納税者本人が寡婦で、ひとり親に該当しない場合 | 27万円 |
| 勤労学生控除 | 納税者自身が控除対象となる勤労学生の場合 | 27万円 |
| 障害者控除 | 本人や生計を一にする配偶者または扶養親族が、所得税法上の障害者に当てはまる場合 | 対象の状況や障害の重さ、同居の有無に応じて、27万円、40万円、75万円のいずれか |
| 雑損控除 | 災害や盗難、横領によって、対象の資産に損害を受けた場合 | 以下のうち多い方の金額 ・(損失金額+災害等関連支出の金額-保険金等の額)-総所得金額など×10% ・(災害関連支出の金額-保険金等の額)-5万円 |
これらの所得控除を適用するには、確定申告または年末調整での申告が必要です。ただし、上記のうち、医療費控除・寄附金控除・雑損控除の3つについては、年末調整では対応できません。
会社員などの給与所得者がこの3つの控除を適用したい場合は、勤務先で年末調整を受けていたとしても、自分で確定申告を行う必要があります。
なお、給与所得者のふるさと納税による寄附金控除は、「ふるさと納税ワンストップ特例制度」を選択しているなら、年末調整をすれば確定申告は不要です。ただし、給与所得者が医療費控除や副業の雑所得があるなど、何らかの理由で確定申告をする場合、ふるさと納税ワンストップ特例制度は無効になります。その場合は、ふるさと納税分も含めて、確定申告をする必要があるので注意しましょう。
一方、確定申告では、すべての控除を申告することができます。ここからは、それぞれの所得控除について詳しく説明していきます。
年末調整と確定申告の違いについては、以下の記事で詳しく解説していますので参考にしてください。
【損してない?】青色申告でいくら安くなる?売上・経費を入れて今すぐ比較!
基礎控除
年間の所得の合計額が2,500万円以下なら誰でも適用できるのが、基礎控除です。
令和7年度税制改正により、基礎控除額が変更になりました。年間所得が2,350万円以下なら、控除額は58万円です。合計所得金額2,350万円超の場合の基礎控除額に改正はありません。
基礎控除額(改正された範囲)
| 年間の合計所得金額 (収入が給与だけの場合※注3) |
改正後(※注1) | 改正前(2024年分まで) | |
|---|---|---|---|
| 2025年分・2026年分 | 2027年分以降 | ||
| 132万円以下 (200万3,999円以下) |
95万円(※注2) | 48万円 | |
| 132万円超336万円以下 (200万3,999円超475万1,999円以下) |
88万円(※注2) | 58万円 | |
| 336万円超489万円以下 (475万1,999円超665万5,556円以下) |
68万円(※注2) | ||
| 489万円超655万円以下 (665万5,556円超850万以下) |
63万円(※注2) | ||
| 655万円超2,350万円以下 (850万円超2,545万円以下) |
58万円(※注2) | ||
-
※国税庁:令和7年度税制改正による 所得税の基礎控除の見直し等について(源泉所得税関係)
-
(注)1: 改正後の所得税法第86条の規定による基礎控除額58万円に、改正後の租税特別措置法第41条の16の2の規定による加算 額を加算した額となります。
2: 58万円にそれぞれ37万円、30万円、10万円、5万円を加算した金額となります。なお、この加算は、居住者についてのみ適用があります。
3: 特定支出控除や所得金額調整控除の適用がある場合には、表の金額とは異なります。
基礎控除について詳しくは、以下の記事をあわせてご覧ください。
配偶者控除
配偶者控除は、生計を一にする配偶者の所得額が58万円(2024年分までは48万円)以下の場合に適用できる控除です。パート・アルバイトなどの給与収入だけの場合には、適用となる所得額は年収123万円以下(2024年分までは103万円)になります。ただし、納税者本人の合計所得金額が1,000万円以下でなければいけません。
控除額は、納税者本人の合計所得金額や配偶者の年齢によって決まります。例えば、本人の合計所得金額900万円以下で、かつ、配偶者の年齢が70歳未満だった場合には、控除額は38万円です。
配偶者控除については、以下の記事で詳しく解説していますので参考にしてください。
配偶者特別控除
配偶者の年間所得額により、配偶者控除の対象外になったとしても、133万円以下であれば配偶者特別控除の対象になる可能性があります。パート・アルバイトなどの給与収入のみの場合には、123万円超201.6万円以下(2024年分までは103万円超201.6万円以下)で適用対象になります。なお、配偶者控除と同様に、納税者本人の合計所得金額が1,000万円を超えると適用できません。
控除額は、納税者本人と配偶者の合計所得金額によって、細かく定められています。例えば、本人の年間所得が900万円以下で、配偶者の所得が48万円超95万円以下なら38万円、配偶者の所得が95万円超100万円以下になると36万円が控除されます。
配偶者特別控除については、以下の記事で詳しく解説していますので参考にしてください。
扶養控除
扶養控除は、所得税法上の控除対象扶養親族がいる場合に適用できます。控除額は、扶養親族の年齢や同居の有無などによって、以下のように定められています。
扶養控除の金額
| 区分 | 控除額 | |
|---|---|---|
| 一般の控除対象扶養親族(年齢が16歳以上) | 38万円 | |
| 特定扶養親族(年齢が19歳以上23歳未満) | 63万円 | |
| 老人扶養親族 (年齢が70歳以上) |
同居老親等以外 | 48万円 |
| 同居老親 | 58万円 | |
-
※国税庁「No.1180 扶養控除
」
扶養控除については、以下の記事で詳しく解説していますので参考にしてください。
特定親族特別控除
令和7年度税制改正により新設された控除で、2025年分から適用になります。
特定扶養親族(19歳以上23歳未満)の年間所得が58万円(給与所得のみで123万円)を超えて、扶養控除の対象外となったとしても、123万円(給与所得のみで188万円)以下であれば、特定親族特別控除の対象になる可能性があります。この場合も、納税者本人の合計所得金額が1,000万円以下でなければいけません。
控除額は所得(収入)に応じて、3万~63万円です。
医療費控除
医療費控除は、1年間の医療費が10万円を超えた際に適用を受けられます。総所得金額が200万円未満の場合は、総所得金額の5%を超過した金額に適用可能です。
医療費控除の計算にあたっては、納税者以外にも生計を一にする配偶者やその他親族にかかわる医療費も対象となります。また、対象となる医療費は治療費だけでなく、通院にかかった交通費や、出産育児一時金を差し引いた分娩費用なども含まれます。
ただし、保険金などが支払われた場合には、その給付の目的となった医療費の金額を限度として、差し引いて計算します。また、予防接種や健康診断など予防にかかる費用や美容整形を行う費用などは対象外のため、申告する際には対象となる費用をあらかじめ把握しておいてください。なお、例外的に重大な病気が見つかって治療に移行した場合の健康診断の料金は医療費控除の対象となります。
なお、2026年12月31日までは、通常の医療費控除に代えて、「セルフメディケーション税制(医療費控除の特例)」を利用することも可能です。この税制は、適用を受けようとする年分に 健康診断受診や予防接種といった健康促進のための一定の取り組みを行っている納税者が申告できます。納税者やその家族が、薬局などで特定一般用医薬品を年間1万2,000円を超える金額分を購入した場合に対象となります。
医療費控除とセルフメディケーション税制はどちらか一方しか適用できないため、より控除額の大きい方を選択して申告するようにしましょう。
医療費控除については、以下の記事で詳しく解説していますので参考にしてください。
寄附金控除
国や地方公共団体、認定NPO法人などに寄附をした場合は、寄附金控除が利用できます。また、ふるさと納税の制度を利用しても、寄附金控除の適用を受けることができます。ふるさと納税が「自己負担2,000円で返礼品を受け取れる」などと言われているのは、寄附金額から2,000円を引いた金額が寄附金控除の適用を受けることにより、所得税や住民税の減税につながる仕組みだからです。
寄附金控除を利用するには、寄附をした証明書が必要です。寄附をした団体などが寄附金控除の対象になるかどうかは、その団体のWebページなどに記載されているため確認してみましょう。
なお、国税庁長官が指定した特定事業者(例:さとふるやふるさとチョイス、楽天ふるさと納税などのふるさと納税サイト運営会社)が発行する年間寄附額を記載した「寄附金控除に関する証明書」を添付することでも申告できます。
また、e-Taxで申告を行う人は、ふるさと納税の「寄附金控除に関する証明書」の内容を入力して送信することで、証明書類の提出を省略できます。ただし、これらの証明書類は5年間の保存義務がありますので、紛失しないように適切に保存しておきましょう。
寄附金控除については、以下の記事で詳しく解説していますので参考にしてください。
社会保険料控除
納税者が自己または、自己と生計を一にする配偶者やその他の親族の負担すべき社会保険料を支払った場合は、社会保険料控除の適用対象になります。例えば、生計を一にする子供の国民年金を親が代わりに支払っている場合には、その分も併せて申告できます。
例えば、学生納付猶予の特例を使って猶予していた場合、追納しないと将来受け取れる年金額が減ってしまいます。追納分も社会保険料控除の対象になります。ほかにも学生納付猶予の特例を使わずに親が学生の子どもの年金を代わりに払っているなら、親の社会保険料控除として申告できます。親は節税になり、子どもは年金を満額受給できますので、お得です。
また、2年分の国民年金保険料を前納した場合は、対象年ごとに社会保険料控除をするか2年分まとめて社会保険料控除をするかを選択できます。一度に申告した方がよいか分けた方がよいか判断したうえで、漏れなく申告を行えるようにしましょう。
一方、扶養している配偶者の公的年金から控除されている介護保険料がある場合には、納税者が支払っているとはいえないため、社会保険料控除の適用を受けられません。
社会保険料控除の対象となる社会保険料は、以下のとおりです。
対象となる主な社会保険料の範囲
- 国民健康保険料(税)
- 健康保険料
- 後期高齢者医療制度の保険料
- 国民年金保険料
- 厚生年金保険料
- 雇用保険料
- 船員保険料
- 介護保険料
- 国民年金基金の掛金
これらの社会保険料のうち、国民年金保険料と国民年金基金の掛金への適用については、確定申告や年末調整の際に控除証明書の添付が必要になります。それ以外の健康保険料などは、控除証明書の添付は不要ですが、金額を明記して申告する必要があるため、どの保険料をいくら支払ったのかわかるようにしておきましょう。
社会保険控除については、以下の記事で詳しく解説していますので参考にしてください。
生命保険料控除
生命保険料控除は、民間の生命保険に加入している場合に適用できる控除です。1年間に支払った保険料のうち、一定の額が生命保険料控除の対象になります。
生命保険料控除は保険契約を結んだ時期によって異なり、2012年1月1日以降に締結された「新制度」と、2011年12月31日以前に締結された「旧制度」に分かれます。さらに、保険の種類によって、一般生命保険料控除や介護保険料控除(新制度のみ)、個人年金保険料控除の3つに分けられ、それぞれを計算した後に合算して控除額を求めます。
具体的な計算方法は以下のとおりです。
新制度
| 区分 | 年間の支払保険料等 | 控除額 |
|---|---|---|
| ・一般生命保険料控除 ・介護保険料控除 ・個人年金保険料控除 |
2万円以下 | 支払保険料等の全額 |
| 2万円超4万円以下 | 支払保険料等×1/2+1万円 | |
| 4万円超8万円以下 | 支払保険料等×1/4+2万円 | |
| 8万円超 | 一律4万円 |
旧制度
| 区分 | 年間の支払保険料等 | 控除額 |
|---|---|---|
| ・一般生命保険料控除 ・個人年金保険料控除 |
2万5,000円以下 | 支払保険料等の全額 |
| 2万5,000円超5万円以下 | 支払保険料等×1/2+1万2,500円 | |
| 5万円超10万円以下 | 支払保険料等×1/4+2万5,000円 | |
| 10万円超 | 一律5万円 |
生命保険料控除は、家族名義であっても納税者本人が支払っていれば申告できますが、保険金の受取人は申告をする本人か配偶者、親族に限られます。ただし、個人年金保険料については、配偶者を除く親族が保険金の受取人の場合は控除を適用できません。
また、生命保険料控除を申告する際には、生命保険会社が発行した生命保険料控除証明書か、電磁的記録印刷書面の添付が必要です。電磁的記録印刷書面とは、電子証明書等に記録された情報の内容と、その内容が記録された2次元バーコードが付された出力書面のことを指します。
ただし、旧制度で年間保険料が9,000円以下である場合と年末調整の際に控除を受けた場合は、どちらの書面の添付も不要です。
e-Taxで確定申告を行う場合は、生命保険料控除証明書の提出を省略できますが、法定申告期限から5年間保管しなければなりません。
なお、令和7年度税制改正により、23歳未満の扶養親族がいる場合、所得税の一般生命保険料控除が4万円から6万円に引き上げられます。ただし、生命保険料控除全体の限度額12万円は変わりません。これは、2026年分のみ適用される1年限りの措置です。
生命保険控除については、以下の記事で詳しく解説していますので参考にしてください。
地震保険料控除
自宅などに地震保険を掛けている場合、地震保険料控除の適用を受けることが可能です。この控除制度では、地震保険料は地震保険料と旧長期損害保険料の2種類に分けられています。このうち、旧長期損害保険料は2006年12月31日以前に契約して、その後契約内容の変更をしていない場合に限られます。
控除額の計算方法は、以下のとおりです。
地震保険料控除の金額
| 区分 | 年間の支払保険料の合計 | 控除額 |
|---|---|---|
| 地震保険料 | 5万円以下 | 支払金額の全額 |
| 5万円超 | 一律5万円 | |
| 旧長期損害保険料 | 1万円以下 | 支払金額の全額 |
| 1万円超2万円以下 | 支払金額×1/2+5,000円 | |
| 2万円超 | 1万5,000円 | |
| 両方の保険料がある場合 | - | それぞれの方法で計算した金額の合計(最大5万円) |
生命保険料控除と同様に、地震保険料控除を利用するためには、保険会社から送られてくる地震保険料控除証明書か、電磁的記録印刷書面を添付する必要があります。
ただし、こちらも生命保険料控除と同じく、年末調整で控除された場合には、地震保険料控除証明書や電磁的記録印刷書面を添付する必要はありません。
なお、e-Taxで確定申告を行う場合は、控除証明書について提出は省略できますが、法定申告期限から5年間の保管が必要になります。
地震保険料控除については、以下の記事で詳しく解説していますので参考にしてください。
小規模企業共済等掛金控除
小規模企業共済等掛金控除は、納税者が小規模企業共済法で定められた共済契約に基づく掛金等を支払った場合に、その支払った金額について控除を受けられる制度です。下記のいずれかの掛金を支払った場合に適用できます。
小規模企業共済等掛金控除の対象
- 小規模企業共済
- 個人型確定拠出年金(iDeCo)
- 心身障害者扶養共済
対象となるのは、加入者本人の掛金などの支払いのみです。例えば、扶養している配偶者のiDeCoの掛金を、小規模企業共済等掛金控除として申告することはできません。また、上記のうち小規模企業共済は、小規模企業の経営者や役員、個人事業主などのための退職金制度であるため、基本的に会社員は加入することはできません。
小規模企業共済等掛金控除については、以下の記事で詳しく解説していますので参考にしてください。
ひとり親控除
ひとり親控除は、2020年に新設された所得控除です。他の人の扶養控除の対象になっていない生計を一にする子供がいて、子供の総所得金額が58万円以下(2024年分までは48万円)で、かつ、納税者本人の合計所得金額が500万円以下であれば、婚姻歴の有無や性別を問わずひとり親控除が適用できます。
なお、税制改正によって、2026年分から(住民税は2027年度分から)ひとり親控除が拡充される予定です。具体的には、控除額が35万円から38万円に、納税者本人(親)の所得要件が500万円以下から1,000万円以下になります。
ひとり親控除については、以下の記事で詳しく解説していますので参考にしてください。
寡婦控除
寡婦控除は、納税者自身が寡婦であるときに適用を受けることができる制度です。寡婦控除が適用されるのは、ひとり親控除に該当せず、下記のいずれかの要件に当てはまる女性です。
寡婦控除が適用される女性
- 夫と離婚した後婚姻をしておらず、扶養親族がいて合計所得金額が500万円以下の方
- 夫と死別した後に再婚しておらず(生死不明の場合を含む)、合計所得金額が500万円以下の方
つまり、離婚後婚姻していない場合には扶養親族がいることが要件となりますが、死別・生死不明であれば扶養親族の要件は不要です。混同しないように注意しましょう。
なお、2019年以前は、寡婦控除は一般の寡婦と、扶養親族である子供がいる特別の寡婦に区分されていました。また、妻と離婚または死別した男性で、扶養親族である子供のいる方を対象とした寡夫控除という制度がありました。
しかし、税制改正により2020年分以降は寡婦控除の区分がなくなり、寡夫控除が廃止されると同時に、ひとり親控除が新設されました。寡婦控除に該当しないシングルファーザーや、未婚の母といった婚姻歴がなく独身で子供を育てている方は、総所得金額などの要件を満たせば、ひとり親控除を適用できます。
寡婦控除については、以下の記事で詳しく解説していますので参考にしてください。
勤労学生控除
勤労学生控除は、申告をする本人が勤労学生の場合に利用できる控除です。対象になるのは、以下の要件にすべて当てはまる人です。
勤労学生控除が適用される対象者
- 高校、大学、高等専門学校、一定の要件を満たす専修学校など、特定の学校の学生、生徒
- 勤労による所得(給与所得など)がある
- 申告する年の所得額が85万円以下(2024年分までは75万円以下)、給与収入なら150万円以下(2024年分までは130万円以下)で、そのうち給与所得以外が10万円以下
勤労学生控除については、以下の記事で詳しく解説していますので参考にしてください。
障害者控除
納税者本人、生計を一にする配偶者、扶養親族が、所得税法上の障害者に当てはまる場合、障害者控除の適用を受けることが可能です。なお、扶養親族には、扶養控除が適用されない16歳未満の子供も含まれます。
控除額は、障害者・特別障害者・同居特別障害者のうち、どの区分に該当するかで異なります。障害者控除の対象となる人が複数いる場合には、それぞれの対象者に対し控除の適用を受けることが可能です。
障害者控除については、以下の記事で詳しく解説していますので参考にしてください。
雑損控除
雑損控除は、災害または盗難、横領のいずれかの理由で損害を受けた際に受けられる控除です。詐欺や恐喝は対象外です。
控除額は、以下の2つの計算結果のうち、高い方の金額となります。
雑損控除額の控除額(いずれか高い方)
- (損害金額+災害に関連して支出した金額-損害に対して受け取った保険金の額)-総所得金額等×10%
- (災害に関連して支出した金額のうち、盗難や横領被害の原状回復を除く費用-損害に対して受け取った保険金の額)-5万円
雑損控除の対象となる損害は、通常の生活に必要な資産への損害だけです。別荘のような娯楽用の不動産の損害や30万円を超える貴金属類・書画骨董などの損害、棚卸資産・事業用固定資産などに対する損害は含まれません。
また、損害額が大きくて1年では控除しきれない場合は、翌年以降3年間にわたって繰り越すことができます。
雑損控除については、以下の記事で詳しく解説していますので参考にしてください。
所得の種類などによって利用できるその他の控除もある
所得の種類によっては、上にあげた所得控除の他にも適用できる控除制度があります。ここからは、確定申告や年末調整で適用できる、所得控除以外の主な控除について紹介します。
青色申告特別控除
青色申告特別控除は、青色申告で確定申告をしている個人事業主が利用できる控除です。対象となる所得は、事業所得または不動産所得、山林所得のいずれかです。
青色申告特別控除の金額は、65万円、55万円、10万円の3種類あり、それぞれ適用要件が異なります。
まずは、青色申告特別控除で65万円控除を受けるための要件からご紹介します。
65万円の控除を受けるための要件
-
1事業所得、または事業的規模の不動産所得がある
-
21.の所得に関連する取引について、複式簿記で記帳している
-
32.に基づいて作成した青色申告決算書(貸借対照表と損益計算書)を添付して確定申告をする
-
4期限を守って確定申告を行う
-
5現金主義による所得計算の特例を選択していない
-
6e-Taxで確定申告を行うか、または、仕訳帳と総勘定元帳など対象帳簿について、電子帳簿保存法が定める「優良な電子帳簿」として保存している
- ※2027年分以降の確定申告では、「6」の要件に加えて、国税庁長官の定める基準に適合する特定電子計算機処理システムを使用して電磁的記録の授受・保存を行っている場合も追加
55万円控除は、上記の65万円の控除を受けるための要件のうち、「6.」以外のすべてを満たしている場合に適用を受けられます。
なお、10万円控除は、上記の65万円控除および55万円控除の要件を満たさない青色申告事業者が適用を受けられます。
青色申告特別控除で65万円もしくは55万円の控除を受けるには複式簿記での記帳が必要になるため、難しいと感じる方もいるかもしれません。しかし、「やよいの青色申告 オンライン」などの会計ソフトを活用すれば、簿記の知識がなくても複式簿記・発生主義での記帳が可能です。さらに、「やよいの青色申告 オンライン」なら、65万円控除が受けられるe-Taxも簡単に行えます。
なお、青色申告をするには、所定の期限内に「所得税の青色申告承認申請書」を税務署へ提出する必要があるため、忘れないように注意しましょう。
青色申告特別控除については、以下の記事で詳しく解説していますので参考にしてください。
給与所得控除
給与所得控除は、会社員やパート、アルバイトなど勤務先から給与を受け取っている方が適用できる控除です。特別な申告をしなくても、年末調整をすれば会社側で反映してくれます。
給与所得控除の額については、令和7年度(2025年度)税制改正により、最低保障額が55万円から65万円に引き上げられました。
給与所得控除額の区分(色枠内が改正範囲)
| 給与等の収入金額 | 給与所得控除額 | |
|---|---|---|
| 改正後(2025年分から) | 改正前(2024年分まで) | |
| 162万5,000円以下 | 65万円 | 55万円 |
| 162万5,000円超180万円以下 | 収入金額×40%-10万円 | |
| 180万円超190万円以下 | 収入金額×30%+8万円 | |
| 190万円超360万円以下 | 収入金額×30%+8万円 | 収入金額×30%+8万円 |
| 360万円超660万円以下 | 収入金額×20%+44万円 | 収入金額×20%+44万円 |
| 660万円超850万円以下 | 収入金額×10%+110万円 | 収入金額×10%+110万円 |
| 850万円超 | 195万円(上限) | 195万円(上限) |
給与所得控除については、以下の記事で詳しく解説していますので参考にしてください。
公的年金等控除
公的年金等控除は、国民年金や厚生年金、企業年金などの公的年金を受け取っている方が利用できる控除です。
控除額の計算方法は、年金を受け取る人の年齢や公的年金以外の所得の合計所得金額に応じて細かく決められています。計算が複雑なため、国税庁のWebページ「No.1600 公的年金等の課税関係」では、簡単に計算するための「公的年金等に係る雑所得の速算表」が用意されています。
利用できる所得控除がないか確認してみよう
所得控除の種類や適用要件は、社会の変化などに応じて変わる場合があります。令和7年度税制改正では、基礎控除や給与所得控除の見直し、特定親族特別控除の新設などがありました。
税にかかわる制度は、今後も頻繁に改正が行われる可能性があります。確定申告や年末調整の時期になったら、改めて最新の所得控除の種類を確認し、利用できる控除を見落とすことがないようにしましょう。
確定申告は「やよいの青色申告 オンライン」や「やよいの白色申告 オンライン」を活用すれば、簿記の知識がなくても手軽に行えます。「やよいの青色申告 オンライン」なら、青色申告特別控除の条件である複式簿記・発生主義での記帳が可能なうえ、65万円控除が受けられるe-Taxも簡単に行えます。
確定申告ソフトなら、簿記や会計の知識がなくても確定申告が可能
確定申告ソフトを使うことで、簿記や会計の知識がなくても確定申告ができます。
今すぐに始められて、初心者でも簡単に使える弥生のクラウド確定申告ソフト「やよいの白色申告 オンライン」とクラウド青色申告ソフト「やよいの青色申告 オンライン」から主な機能をご紹介します。
「やよいの白色申告 オンライン」は、ずっと無料、「やよいの青色申告 オンライン」は初年度無料です。両製品とも無料期間中もすべての機能が使用できますので、気軽にお試しいただけます。もちろん、確定申告やe-Taxでの申告が可能です!
【損してない?】青色申告でいくら安くなる?売上・経費を入れて今すぐ比較!
初心者にもわかりやすいシンプルなデザイン

弥生のクラウド確定申告ソフトは、初心者にもわかりやすいシンプルなデザインで、迷うことなく操作できます。日付や金額などを入力するだけで、確定申告に必要な帳簿や必要書類が作成できます。
取引データは自動取込&AIの自動仕訳で入力の手間を大幅に削減!

弥生のクラウド確定申告ソフトは、銀行・クレジットカードなどの金融機関の明細や電子マネー、POSレジ、請求書、経費精算等のサービスと連携すると日々の取り引きデータを自動で取得します。
自動取得した取引データはAIが自動で仕訳して帳簿に反映します。学習機能があるので、使えば使うほど仕訳の精度がアップします。紙のレシートは、スマホやスキャンで取り込めば、文字を認識してデータに変換し、自動で仕訳します。これにより入力の手間と時間が大幅に削減できます。
確定申告書類を自動作成。e-Tax対応で最大65万円の青色申告特別控除もスムーズに

弥生のクラウド確定申告ソフトは、画面の案内に沿って入力していくだけで、収支内訳書や青色申告決算書、所得税の確定申告書、消費税の確定申告書等の提出用書類が自動作成されます。
「やよいの青色申告 オンライン」なら、青色申告特別控除の最高65万円/55万円の要件を満たした資料の用意も簡単です。インターネットを使って直接申告するe-Tax(電子申告)にも対応し、最大65万円の青色申告特別控除もスムーズに受けられます。
自動集計されるレポートで経営状態がリアルタイムに把握できる

弥生のクラウド確定申告ソフトに日々の取引データを入力しておくだけで、レポートが自動で集計されます。経営状況やお金の流れをリアルタイムで確認できます。最新の経営状況を正確に把握することで、早めの判断ができるようになります。













